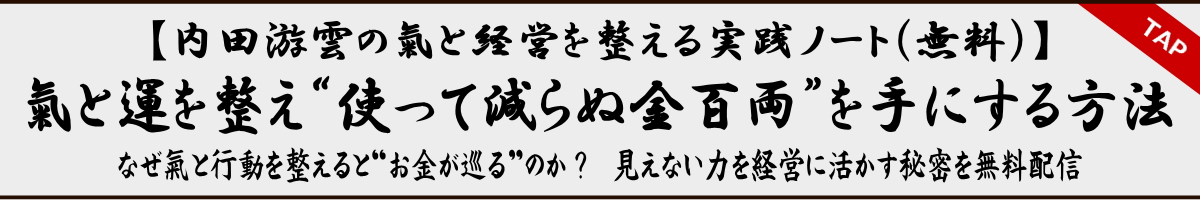資本主義の本質は、労働収入よりも資産収益が優位に拡大するというr>gの法則にある。努力だけでは豊かになれず、格差は構造的に広がる。日本の政策も株主や外国人投資家を富ませる仕組みに偏り、働く人の生活を潤さない。だからこそ50代以降の経営者や起業希望者は、資産形成を人生戦略の中心に据える必要がある。株式や投資信託を通じて資本の流れに参加し、自由で安心できる未来を自ら選び取ることが重要だ。
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(主にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。40年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供するメルマガ【氣と経営を整える実践ノート】も発行中(無料)
資本主義の本質を直視しなければ、私たちはいつまでも労働収入に縛られた人生から抜け出すことができない。
資本主義の本質を正しく見つめる
『見たくない現実にこそ、未来を変える答えがある』
かつては「努力すれば報われる」という言葉が、多くの人を励ましてきた。だが現実の資本主義の本質は、そのような美談だけでは説明できない冷徹な仕組みを持っている。資本主義社会では、まず何よりも金を稼ぐことが絶対条件だ。どんなに芸術を愛しても、自然と共に生きたいと願っても、生活のためにはお金が必要になる。これは経営者であれ労働者であれ、避けられない鉄則である。
しかし、社会を見渡すと、必死で働かなくても豊かに暮らす人たちがいる。彼らに共通しているのは、十分すぎる資産を持っているという事実だ。政治的には評価が低かった鳩山由起夫氏も、その一族は約400億円の資産を有していると言われる。仮にその資産を株式で運用すれば、年利3%で年間12億円。本人が何をしようがしまいが、ゴロゴロしているだけで毎月1億円が入る計算になる。庶民が宝くじに一縷の望みを託しても、この差は永遠に埋められない。
このように、資本主義は「働いた分だけ豊かになる」社会ではない。むしろ、資産を持つ人ほど何もしなくても豊かになり、持たない人ほど必死に働いても余裕が生まれにくい。しかも恐ろしいのは、資産が大きければ大きいほど、その増加スピードが加速するという点だ。何もしないほうが資産が勝手に膨らむという逆説的な現象さえ起きる。ここに資本主義の核心がある。
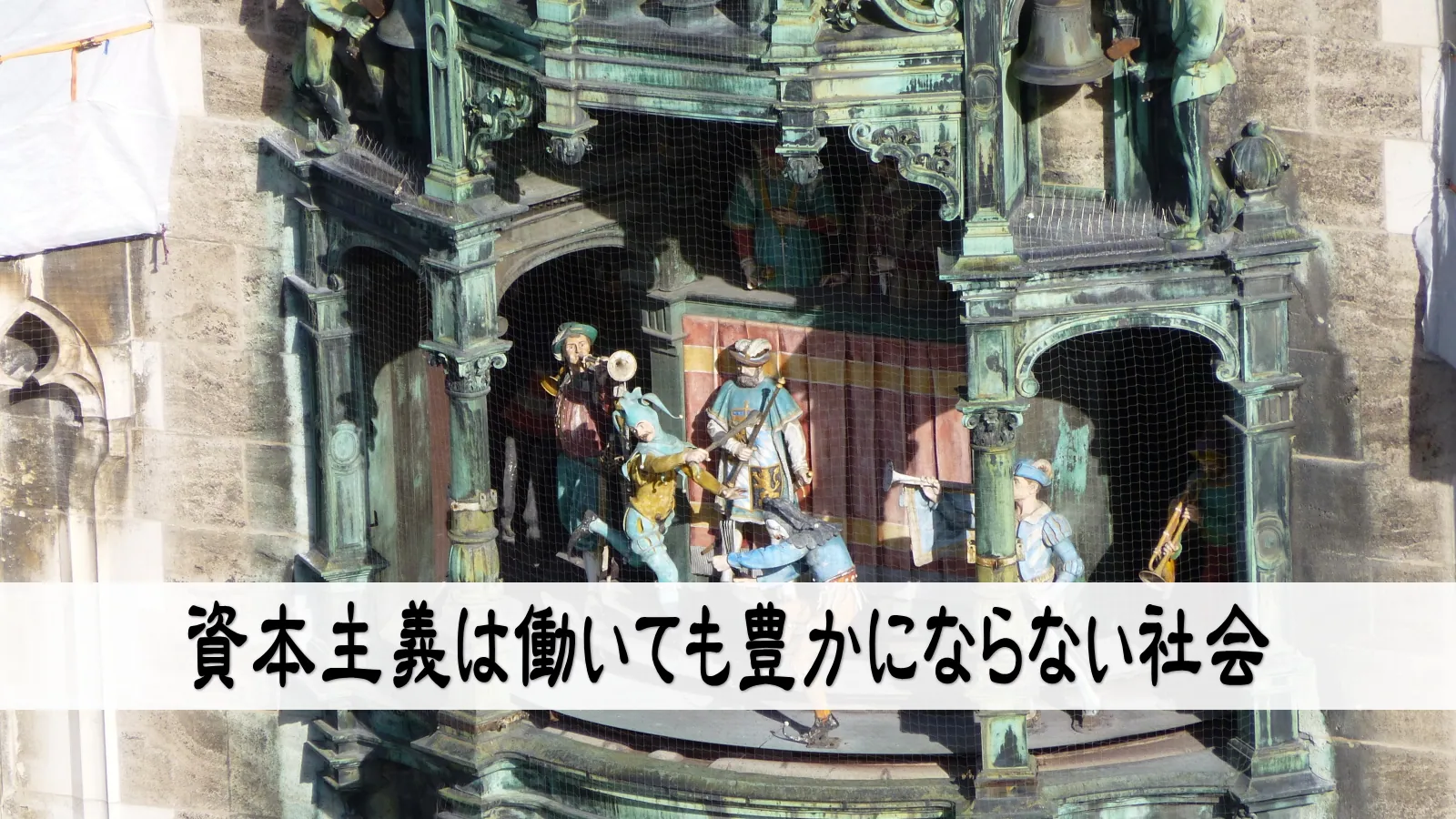
フランスの経済学者トマ・ピケティは、世界各国の税務統計を200年以上も調べ上げ、ひとつの公式を導き出した。それがr>gである。rとは資本収益率、gとは経済成長率を指す。つまり、資産から得られる収益は、労働で得られる収入よりも長期的に高くなり続けるという法則だ。仕事で得られる年収が平均2%しか伸びない一方、資産を持つ人は平均7%の成長を享受する。40年経てば、この差は天文学的な広がりを見せる。
この仕組みを理解せずに資本主義を語るのは、ルールを知らずにゲームに挑むようなものだ。資本主義を直視する勇気を持たなければ、働いても働いても報われないという現実に飲み込まれる。小さな会社を営む経営者や、これから起業しようとする人ほど、この真実を知らねばならない。なぜなら、労働に頼るだけの経営は、資本主義のルールの中では不利な立場に追い込まれるからだ。
もちろん、働くこと自体は尊い。そこにやりがいや誇りを見出すこともできる。しかし、「働けば報われる」という幻想にしがみついてしまうと、資本主義の構造そのものに振り回されてしまう。経営者であればなおさら、働くことと同時に、資産を持つことの意味を考える必要がある。
資産を持たない人が負け組になる
『働くだけでは抜け出せない不公平なルールがある』
資産形成の基本を理解せずに生きることは、労働収入と投資収入の違いを知らないまま、敗北が約束されたゲームに挑むようなものだ。
資本主義社会において最大の分かれ道は、資産を持つか持たないかに尽きる。どんなに努力しても、資産を持たない人は豊かさを手に入れにくい。なぜなら、労働による収入は経済成長率(g)とほぼ同じ速度でしか伸びないからだ。日本の過去数十年を見ても、平均年収の伸び率は年2%程度にとどまる。これでは物価上昇や税金の負担に追いつけない。
一方で、資産を持つ人々はまったく別のルールで生きている。株式や不動産を保有し、それを長期的に運用することで、平均して年5〜7%程度のリターンを得ることができる。仮に1000万円を投資に回して7%で運用すれば、10年後には約2000万円になる。対して労働収入だけで積み上げようとすれば、同じ金額を貯めるのに何倍もの時間がかかる。これが労働収入と投資収入の決定的な違いだ。
ここで重要なのは、経営者もまた例外ではないという点だ。中小企業の経営者の多くは「売上を伸ばすこと」ばかりに意識が向かうが、売上や利益は事業が順調である限りの話に過ぎない。病気や不況、顧客の離反があれば一瞬で崩れる。つまり、事業所得だけに依存することは、労働者と同じリスク構造にいるということだ。
トマ・ピケティが示した公式「r>g」を思い出してほしい。労働収入(g)が年2%伸びる世界にとどまる一方で、資本収益(r)は年5〜7%で増え続ける。仮に40年という時間軸で比較すると、労働者は小さな坂を上り続けるのに対し、資産家はエスカレーターに乗って上昇していくようなものだ。その差は、もはや努力や根性で埋められるものではない。
この法則を理解せずに「とにかく働けばなんとかなる」と信じ続けるのは、勝負が決まっている試合に挑むのと同じだ。経営者や起業家にとっては特に致命的である。なぜなら、せっかくの事業が黒字であっても、個人として資産形成を怠れば、結局は労働依存の生活から抜け出せないからだ。
大切なのは、早い段階で資産形成の基本に取り組むことだ。貯金だけでは資産は増えない。少額でも株式や投資信託に分散し、資本収益のサイクルに身を置くことが必要になる。経営者であれば、事業から得た利益の一部を事業拡大だけでなく、資産形成にも振り向ける視点が欠かせない。
資産を持たない人は、資本主義というゲームで不利な立場に置かれ続ける。だが逆に言えば、資産を持つ側に回ることができれば、その不公平なルールを味方につけられるのだ。資本主義を直視するとは、この「敗北の法則」を
格差拡大は資本主義の必然なのか
『富が流れる先を知る人だけが、豊かさを手にできる』
格差は偶然ではなく、r>g の法則によって必然的に広がる。資本収益率が労働収入を上回る社会構造を理解しなければ、未来を誤解することになる。
資本主義の社会では、「格差は努力不足の結果だ」とよく言われる。しかし実際にはそうではない。格差は資本主義の仕組みに組み込まれた必然であり、個人の勤勉さだけで覆せるものではない。
フランスの経済学者トマ・ピケティが提唱したr>g の法則が、その核心を示している。労働収入は経済成長率(g)と歩調を合わせるため、長期的に見ても平均2%程度の伸びにしかならない。一方で資本収益率(r)は5〜7%程度を維持し続ける。つまり、資産を持つ人は何もしなくても豊かになり、持たない人は懸命に働いても報われにくい。この不等式が続く限り、富は資産家に流れ続けるのだ。
実際、世界各国の統計を見ても格差は拡大している。アメリカでは富裕層上位1%が国民全体の資産の3割以上を保有している。日本でも、金融資産1億円以上を持つ富裕層の数は増え続けており、一方で預金しか持たない層は低金利のなかで資産を増やせず取り残されている。これは努力の差ではなく、構造的な格差が積み上がった結果に過ぎない。
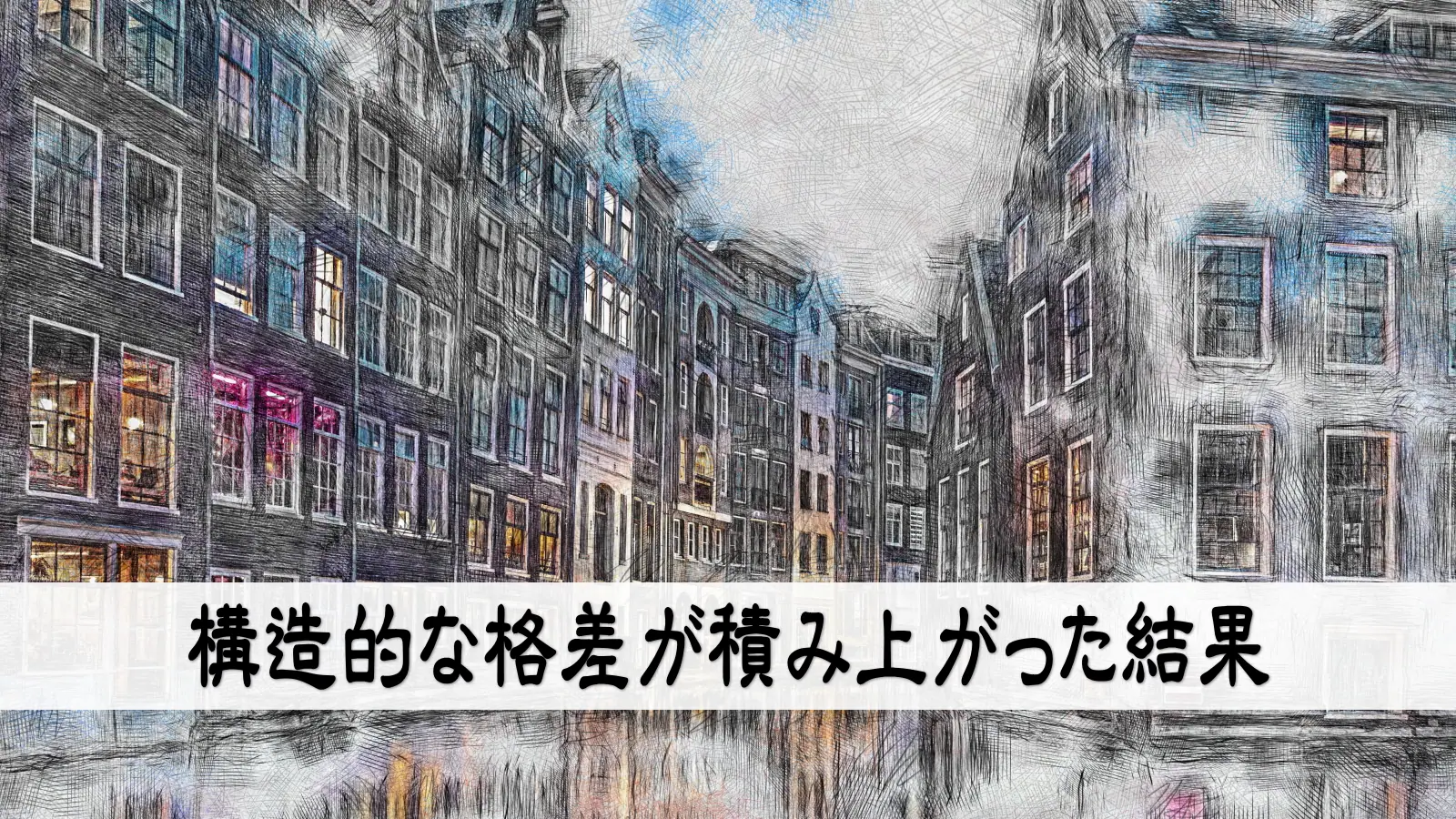
さらに、この格差は「時間」が経つほどに拡大していく。労働者が40年働いて得る収入の増加が2%であるのに対し、資産家は7%で増え続ける。たとえば年収が2倍になるのに40年かかる人がいる一方で、資産家は同じ期間に何倍もの富を積み上げる。これはもはや競争ですらなく、最初からルールが異なるゲームに参加しているようなものだ。
こうした現実を前に、「格差をなくそう」と掛け声をあげても簡単には解決しない。なぜなら、資本主義の根幹そのものが格差を生み出す仕組みだからだ。政策で一時的に緩和できても、資本の収益率が労働収入を上回る限り、再び格差は広がっていく。
ここで重要なのは、この仕組みを「不公平だから嫌だ」と拒絶することではない。むしろ、この必然を受け入れたうえで、どのように自分の立ち位置を変えていくかを考えることだ。資産形成を始めるという行動は、その第一歩になる。
経営者や起業家にとって、格差は外部環境の問題ではなく、自らの人生や事業に直結する課題である。富が流れる方向を知り、それに逆らわずに乗ることができるかどうか。そこに、今後の経営と人生の分岐点がある。
日本の政策が示す資本主義の現実
『誰のための経済か、その答えは株価に隠されている』
日本の家計資産の半分が現金預金に偏る現実のなかで、株価を中心とした経済政策の恩恵を受けるのは、国民ではなく株主と外国人投資家である。
日本の家計は金融資産を多く持っているが、その内訳を見れば驚くほどの偏りがある。約半分を現金・預金で保有しており、株式の割合はわずか14%程度にすぎない。対照的にアメリカの家計は、株式が40%を占め、預金は1割強しかない。つまり、同じ株価上昇でも、日本では家計が恩恵を受けにくいという構造が最初から存在している。
それにもかかわらず、2013年以降の日本の政策は「株価の引き上げ」に集中してきた。日銀は大量の国債を買い入れる量的緩和に加えて、ETFやREITといった株式や不動産関連の金融商品までも購入した。さらにGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は資産配分を見直し、国内株式の比率を一気に12%から25%に引き上げた。国の年金資金までもが「株価を支える」方向に動員されたのである。
政府はこうした政策を「ストック効果」と呼び、株価上昇が家計の資産価値を高め、消費意欲を刺激するのだと説明してきた。確かにアメリカでは、株価上昇が家計の消費を押し上げる力を持つ。しかし日本の場合、株式比率が低すぎるため、その効果はアメリカの3分の1程度にとどまる。つまり、株価を上げても国民の財布はほとんど潤わない。
では誰が潤ったのか。答えは明白である。外国人投資家と株主だ。日銀の緩和で円安が進めば、日本株は割安となり、海外投資家にとって格好の買い場になる。取引全体の6割を占める彼らが買えば株価は上がり、売れば下がる。株価の実態は、もはや日本国民の消費や所得とは関係が薄く、海外マネーの動きに左右されている。
この現実を直視すれば、2013年以降の政策が「デフレ脱却のための対策」と説明されてきたのは表向きに過ぎないことがわかる。実際には、株主を富ませるための仕組みが整えられただけだ。働く人々の所得が増えないまま株価だけを持ち上げても、消費が広がるはずがない。
「働くことは尊い」というレトリックは確かに美しい。しかし、現実の政策は働く人のためではなく、資本を持つ人のために設計されている。ここに資本主義の現実がある。経営者や起業家であれば、この構造を理解したうえで、自分の資産をどう守り、どう育てるかを考える必要がある。そうしなければ、自分の努力が見事に空回りしてしまうだろう。
資本主義を直視し生き方を選ぶ
『自分で選び取る覚悟が、安心できる未来をつくる』
人生100年時代の資産戦略を描くためには、社会が隠してきた資本主義の本質を直視し、自由な生き方と安心できる未来づくりを自ら選択するしかない。
「汗水たらして働けば必ず報われる」
長らく信じられてきたこの言葉は、もはや資本主義の現実とは乖離している。努力は確かに価値がある。だが努力だけで豊かになれる時代は終わった。資産を持たないまま働き続ければ、r>g の法則に押し流され、格差の下層に固定されてしまう。これが私たちが直視すべき現実である。
では、どうすればよいのか。第一歩は、資産形成を人生設計の中心に置くことだ。50代を迎える経営者や起業希望者にとって、これは避けて通れないテーマになる。事業の成否にかかわらず、資産からの収入を得られる仕組みを整えておくことで、老後の不安を軽減し、自由に生きる選択肢を広げることができる。
そのために必要なのは、壮大な一攫千金の夢ではない。小さくても確実に投資収入を育てることだ。株式や投資信託など、自分に合った形で資本の流れに参加する。事業から得た利益の一部を資産に回す。それだけで、未来の安心度はまるで違ってくる。
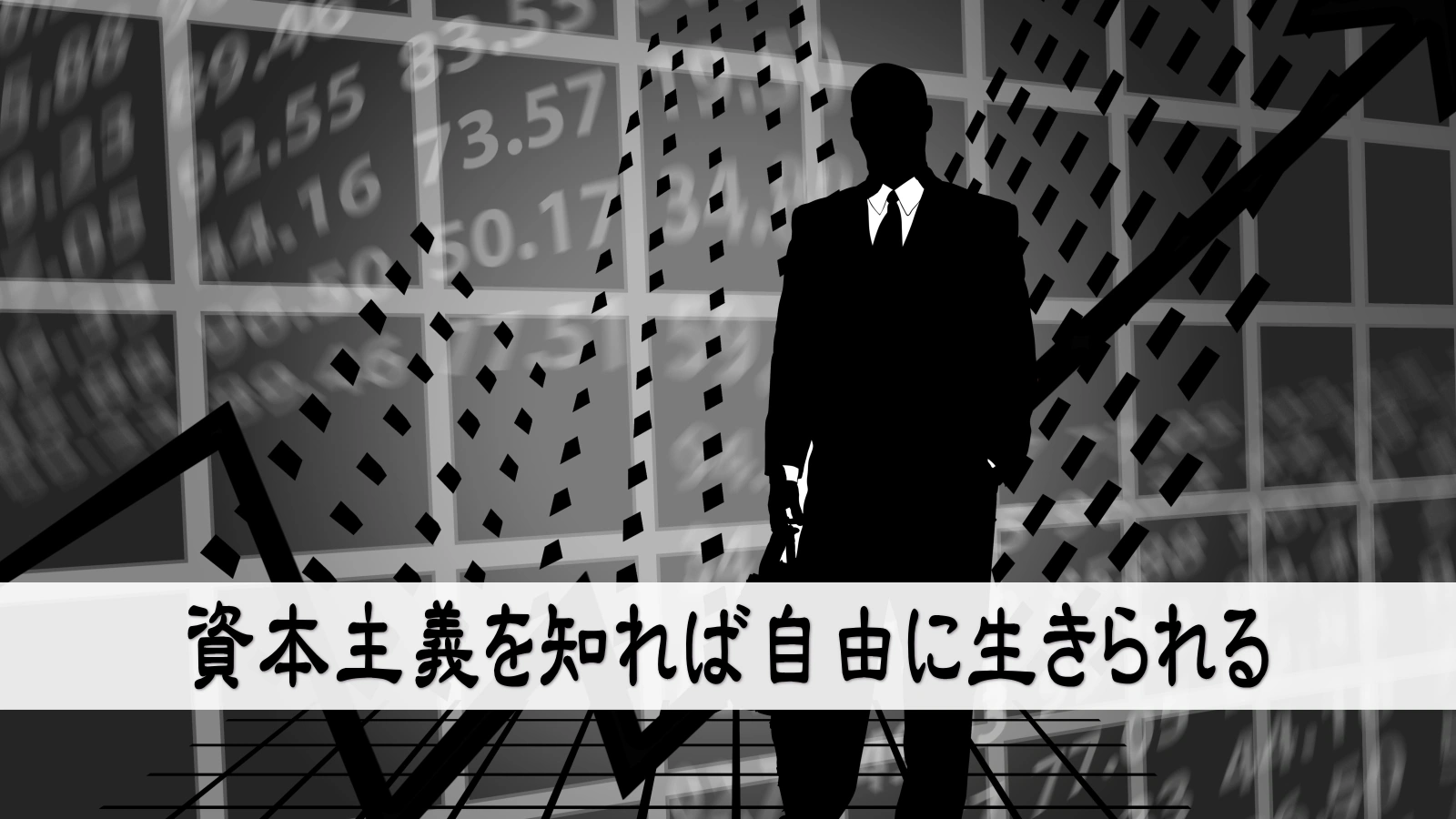
また、資本主義のルールを理解することは、単なるお金の話にとどまらない。自由な生き方を選ぶ基盤を整えることに直結する。働かなくても暮らせる状態が整えば、仕事は「生活のための義務」ではなく、「やりたいからやること」へと変わる。ここに人生の大きな転換がある。
さらに、資産を持つことは「安心」をもたらす。人生100年時代、私たちは想定以上に長い時間を生きる。健康の問題、家族の問題、社会の変化・・・。予測できない出来事が次々に訪れる。だからこそ、資産から得られる安定した収入は、嵐の中で舟を守る錨のような存在になる。
最後に強調したいのは、この選択を誰も代わりにしてくれないということだ。政府の政策は株主を守るために動き、会社は永遠に存続する保証がない。だからこそ、自分の未来は自分で決めるしかない。資本主義を直視する勇気を持ち、自分の手で自由と安心を選び取ること。その覚悟こそが、これからの人生に本当の豊かさをもたらす。
結局のところ、資本主義の社会をどう生きるかは「働き続けるか」「資産を育てるか」の二者択一ではなく、その両方をどう組み合わせるかにかかっている。労働で人生を支えつつ資産を積み上げ、資産がやがて人生を支える段階へと移行する。この流れを意識した者だけが、長い人生の後半を安心と自由のうちに歩むことができるのである。