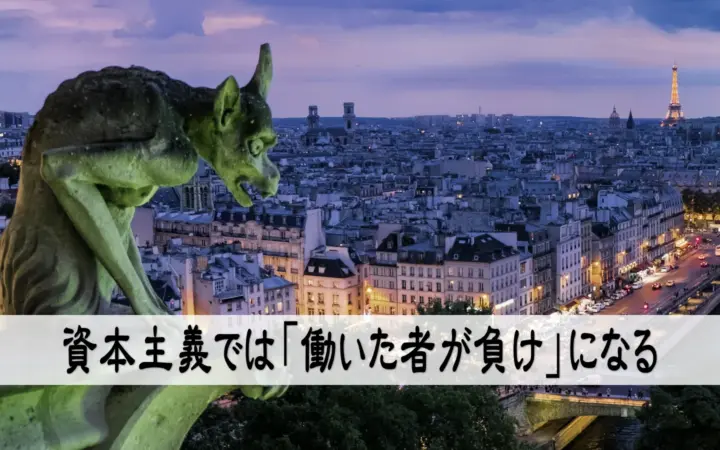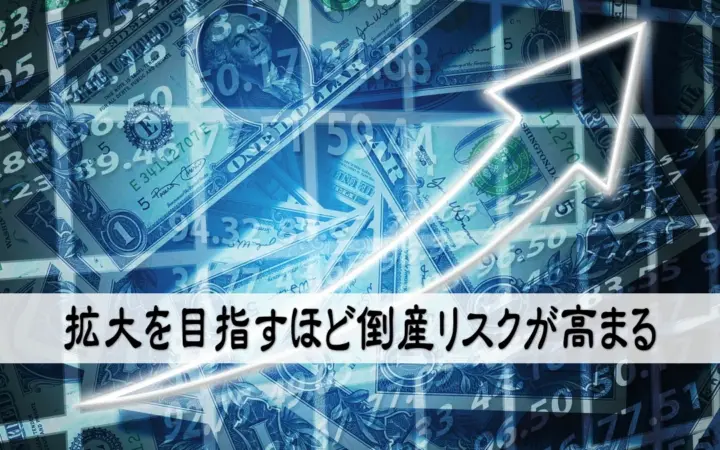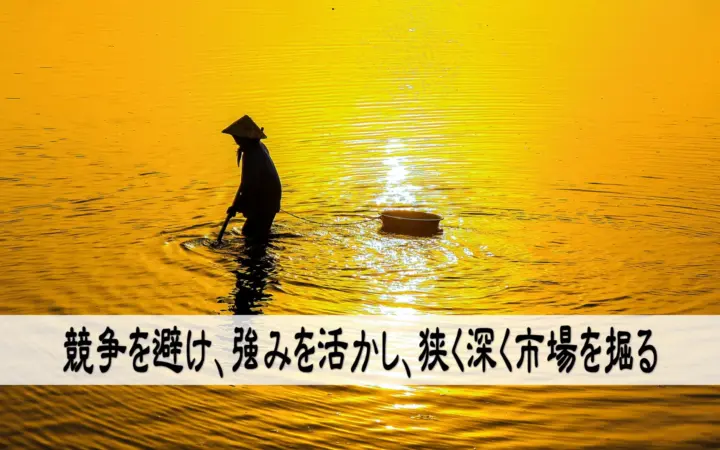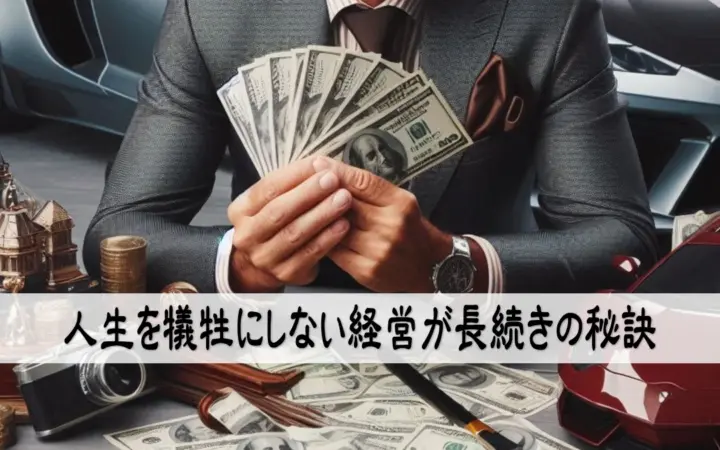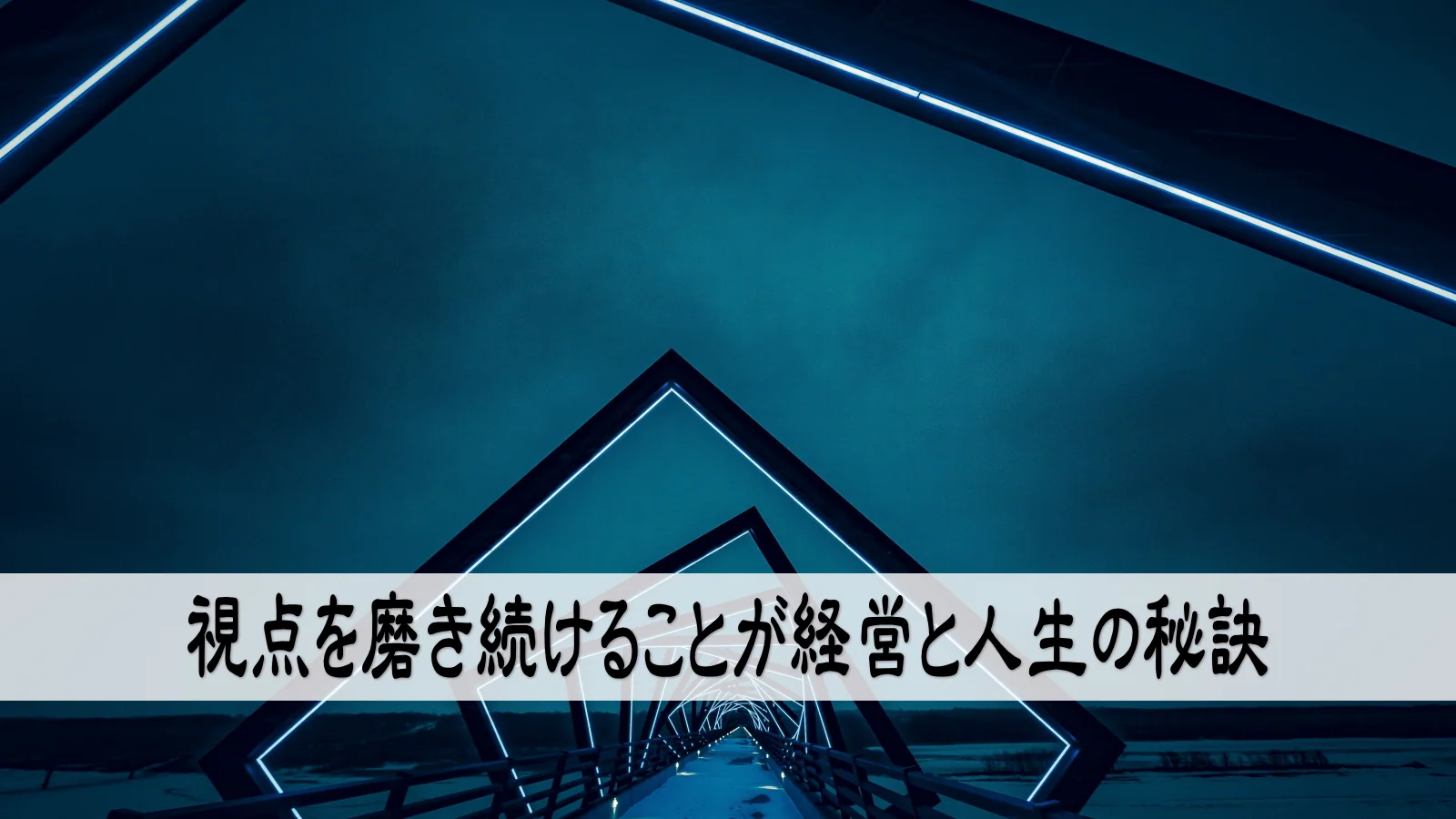
経営には「視点」が欠かせない。自分視点だけでなく、相手視点、第三者視点、俯瞰視点、時間軸視点の五つを行き来できる柔軟さが、経営をうまく回す鍵となる。これらの視点を使いこなせば、無理なく顧客と良好な関係を築き、長期的な資産形成が可能になる。特に50歳を超えた起業家にとっては、人生とビジネスを一致させ、焦らず着実に進むための土台となる。視点を磨き続けることこそが、豊かな経営と人生の秘訣である。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
経営というと、ビジネスモデルや資金繰り、販路の確保といった話が先に出てくるが、それらは手段にすぎない。もっと根本的なものがある。それが“視点”だ。50歳を過ぎて起業を考えるなら、まずこの視点を持つことから始めた方がいい。なぜなら、これまでの経験や常識が、時として今の市場では通用しないからだ。
経営するならまず視点を持て
人はどうしても、自分の考えを中心に物事を見てしまう。これが第一の視点、つまり自分視点だ。自分の価値観、自分の過去、自分の正しさ。だが、商売は相手がいて初めて成り立つ。にもかかわらず、自分の都合だけで進めてしまうと、どうなるか。お客は離れ、仲間は疲れ、商売は空回りする。
ではどうするか。視点をずらすのである。まずは自分視点を持ちつつも、それに固執しないこと。世の中を眺め、客観的に見る力。自分というフィルターを通さず、ありのままに物事を観察する習慣が必要だ。
そのために必要なのが、視点を階層的に捉える思考法だ。視点には5つの段階がある。この視点をを採用すれば、起業における判断力と柔軟性が一気に増す。これは道楽として起業をする人にも、経済的自立を目指す人にも共通する武器になる。
まずは、自分が何をどう見ているかを自覚すること。次に、それ以外の見方があることを理解すること。そして、それを実践に移すこと。視点を持つというのは、実はとても実践的な技術なのだ。
経営に必要な五つの視点とは
第一の視点は、自分視点。これはほとんどの人が常に使っている。だが、これだけではビジネスは成立しない。次に必要なのが、第二の視点。相手視点だ。お客の目で自分を見ること、自社を見ること。商売がうまくいかないのは、たいていこの視点が欠けているからだ。
第三の視点は、いわば裁判官の視点。自分と相手の両方を冷静に見て、どちらが正しいかではなく、どうすればうまくいくかを判断する。この視点があれば、衝突は減り、合意点が見つけやすくなる。
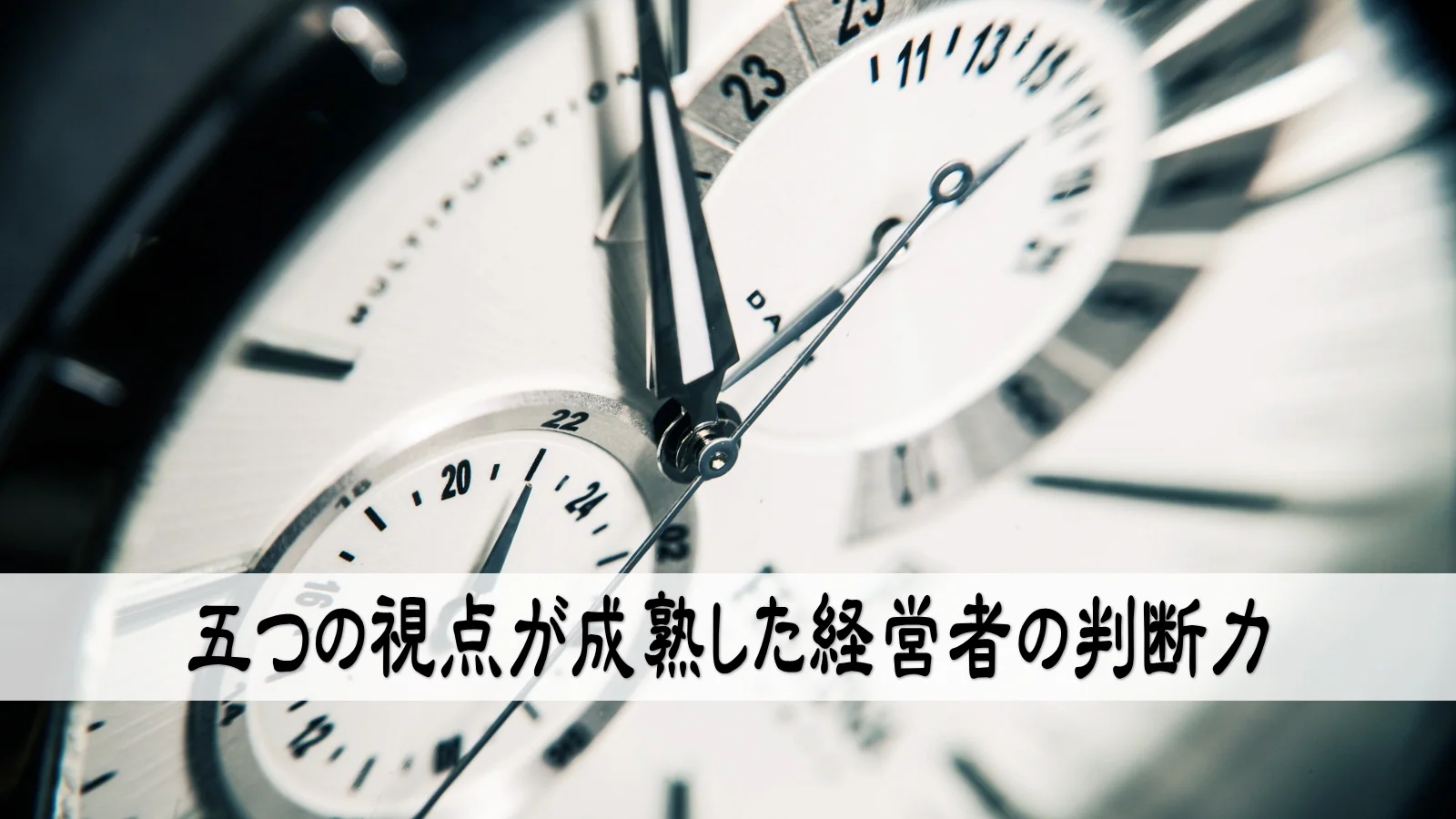
第四の視点になると、ぐっと抽象度が上がる。これは上空から全体を眺めるような感覚だ。業界全体の流れ、社会のトレンド、自分と相手が置かれている環境。それらを俯瞰して捉える視点である。これがあると、今やるべきことと、今やらない方がいいことの区別がつくようになる。
そして第五の視点。これは時間軸の視点である。つまり、過去から未来に至る流れの中で、今何をすべきかを判断する視点だ。さらに言えば、“流れ”を読む力ともいえる。これをやり過ぎるとスピリチュアルな話に突入する危険があるが、要は時間の経過を意識した思考法だ。
起業においては、第三から第四の視点を日常的に使えるようになることがひとつの目標になる。そして、必要に応じて第五の視点を取り入れる。それが成熟した経営者の判断力につながっていく。
衝突と葛藤を防ぐ視点の使い方
人間関係のトラブルの多くは、視点の欠如から生まれる。特にビジネスの場では、自分の都合と相手の都合が食い違うことが日常茶飯事だ。50代を超えた経営者は、経験が豊富な分だけ自己視点に偏りやすい。
第一の視点だけで動くと、自分の思い込みで相手を裁くようになる。相手視点を持つことで、相手の欲求や立場を理解できるが、今度は自分を押し殺すことになりがちだ。結果、ストレスが溜まり、続かなくなる。
そこで必要になるのが、第三の視点だ。自分と相手のやり取りを横から見る、つまり“観察者”としての自分を育てること。裁判官のように両者の主張を聞き、どちらかに肩入れせずに判断する。このスタンスがあると、交渉も、組織運営も、人間関係も、すべてが滑らかになる。
また、感情に巻き込まれずに問題を処理できるという点でも、この第三の視点は起業家にとって強力なツールだ。特に家族経営や地域密着型ビジネスでは、感情的な対立を避ける技術として不可欠である。
加えて、第三の視点を持つことは、不要な争いを未然に防ぐだけでなく、互いのニーズを尊重しながら合意形成する力を育てる。これは単なる“話し合い”とは違う。双方の立場と背景を正しく把握し、冷静に落としどころを探す行為である。交渉とは感情の勝負ではない。理性と視点の勝負なのだ。
この視点が身につくと、相手の反論や要求も冷静に聞けるようになる。むしろ反論があるからこそ、相手が何を本当に欲しているのかが見えてくる。衝突を恐れるのではなく、衝突を分析することで次の一手が生まれる。だから第三の視点は、衝突を避けるのではなく、衝突を利用する視点でもある。
さらに、これは対外的な交渉だけでなく、自分自身の内面との交渉にも役立つ。葛藤を抱えたとき、心の中で“第三者”として自分と向き合うことができれば、感情に流されずに道を選べるようになる。第三の視点とは、外との交渉技術であると同時に、自分との対話を深めるための技法でもある。この視点を持てば、経営も人生もブレにくくなる。
経営者の俯瞰力と思考整理法
第三の視点までを使いこなせると、対人関係の衝突はかなり減る。しかし、それだけではまだ足りない。ビジネスの世界では、人と人の間だけでなく、業界や社会全体の動き、環境の変化まで考慮しなければならないからだ。そこで必要になるのが、第四の視点、つまり「俯瞰力」だ。
第四の視点とは、一言でいえば「空から見る力」である。個別の事象に巻き込まれず、一歩引いて全体を見渡す。自分と相手だけでなく、その関係が置かれている社会や業界の流れまで視野に入れる。この視点が身につくと、流行や時流に流されず、適切な判断ができるようになる。
たとえば、自分の商品やサービスをどこで、誰に、どのタイミングで提供するか。それを考えるときに、目の前の顧客だけでなく、世の中全体の変化を見ていなければならない。競合他社の動き、社会情勢、法律の改正、テクノロジーの進化。これらを俯瞰的に捉えることで、思わぬ落とし穴を回避できるし、新しいチャンスにも気づくことができる。
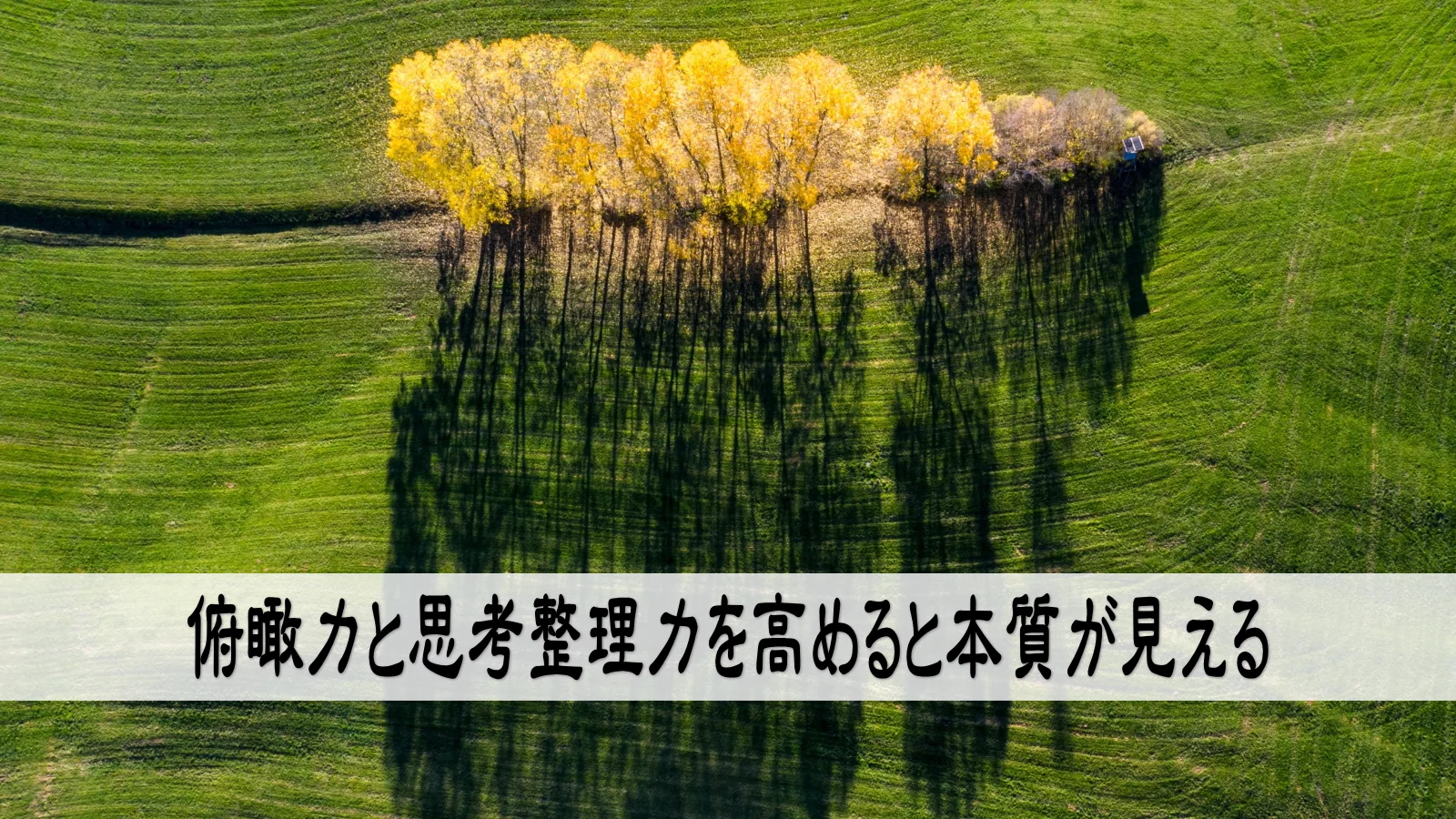
そして、この視点を支えるのが「思考整理力」だ。大量の情報をただ集めるのではなく、必要なものと不要なものを見極め、関係性を整理し、意味をつかむ力。これは単なるメモ術やノート術ではない。情報をどう分類し、どう判断材料に変えるかという思考の整理整頓である。
俯瞰力と思考整理力を高めると、やらなくていいことが明確になる。これは経営においてとても重要だ。やるべきことを決める以上に、やらないことを決めることが、事業を健全に保つポイントになるからだ。あれもこれもと手を出して、結果すべてが中途半端になってしまうのが、スモールビジネスが失敗する典型的なパターンである。
第四の視点を持てば、自分がどこに立ち、どこへ向かうべきかが見えてくる。俯瞰することで、流れを感じ取り、力を入れるべきところと抜くべきところのバランスが取れるようになる。これは無理をせず、長く続けるためにも必要な技術だ。
さらに、この視点は「本質を見る力」も育てる。表面的な数字や言葉に惑わされず、背景にある構造を理解する。だからこそ、流行り廃りに振り回されず、軸をぶらさずに経営を続けられるようになる。ビジネスを道楽化し、楽しく続けていくための土台は、実はこの第四の視点にあるといってもいい。
時間軸を加えると商売は深くなる
第四の視点までは空間的な広がりだったが、第五の視点は時間軸が加わる。これは非常にパワフルな視点で、うまく使えば長期的な戦略が立てられるようになる。
人間は「今」を中心に考えるが、商売は過去から現在、そして未来へと続く流れの中にある。この時間軸を無視して今だけを見て判断すると、短期的な成功に飛びついて大きな損失を生むこともある。
第五の視点では、今の行動が将来どんな影響を及ぼすかを考える。これは、売上ではなく資産に目を向ける考え方にも通じる。短期的な売上を追うより、長期的な信頼関係や資産形成に重きを置くのが、この視点の使い方だ。
ただし、注意点もある。時間軸にばかり目を向けると、今をおろそかにしがちになる。さらに、未来の予測に振り回されて地に足がつかなくなるリスクもある。商売においては、第五の視点は補助的に使うのが望ましい。
この視点を実践するうえで役立つのが「逆算思考」だ。5年後、10年後にどうなっていたいのか。そのために3年後はどうなっているべきか。1年後は? 今月は? 今日の行動は? これを積み重ねていくと、無理なく未来が形になっていく。
時間軸を持った経営は、派手さはないが底力がある。急拡大よりも、じわじわと効いてくる強さ。売上よりも信用を、スピードよりも確実性を大切にする。この視点を身につけた経営者は、多少の荒波ではビクともしない。むしろ波を利用して、悠々と航海を続けていくことができるのだ。
視点の活用が経営を一変させる
ここまで説明してきた五つの視点。この視点をただ知識として持っているだけでは意味がない。実際の経営にどう活かすか。もっと言えば、経営と人生をどう結びつけていくか。これこそが、この視点論の本当の目的だ。
経営とは、単に金を稼ぐ手段ではない。とりわけ50歳を超えてからの起業となればなおさらだ。これまで積み重ねてきた経験と知恵を活かしながら、自分らしく生きるための手段。その「生き方」と「商売」を無理なく一致させることが、成熟した経営者に求められる。
そのためには、第一の視点で自分自身の欲求と向き合い、第二の視点でお客の求めるものを理解し、第三の視点でそのバランスをとり、第四の視点で全体を俯瞰し、第五の視点で時間軸の流れを読む。この視点の積み重ねこそが、自然体で長く続けられるビジネスの基盤になる。
視点を磨くことで何が変わるのか。それは「無理をしなくなる」ということだ。無理をしないから続く。続くから育つ。育つから結果が出る。この好循環を作ることができれば、焦って売上を追いかける必要もなくなる。資産を育てるように、顧客との関係を育て、信用を積み重ねていけばいい。
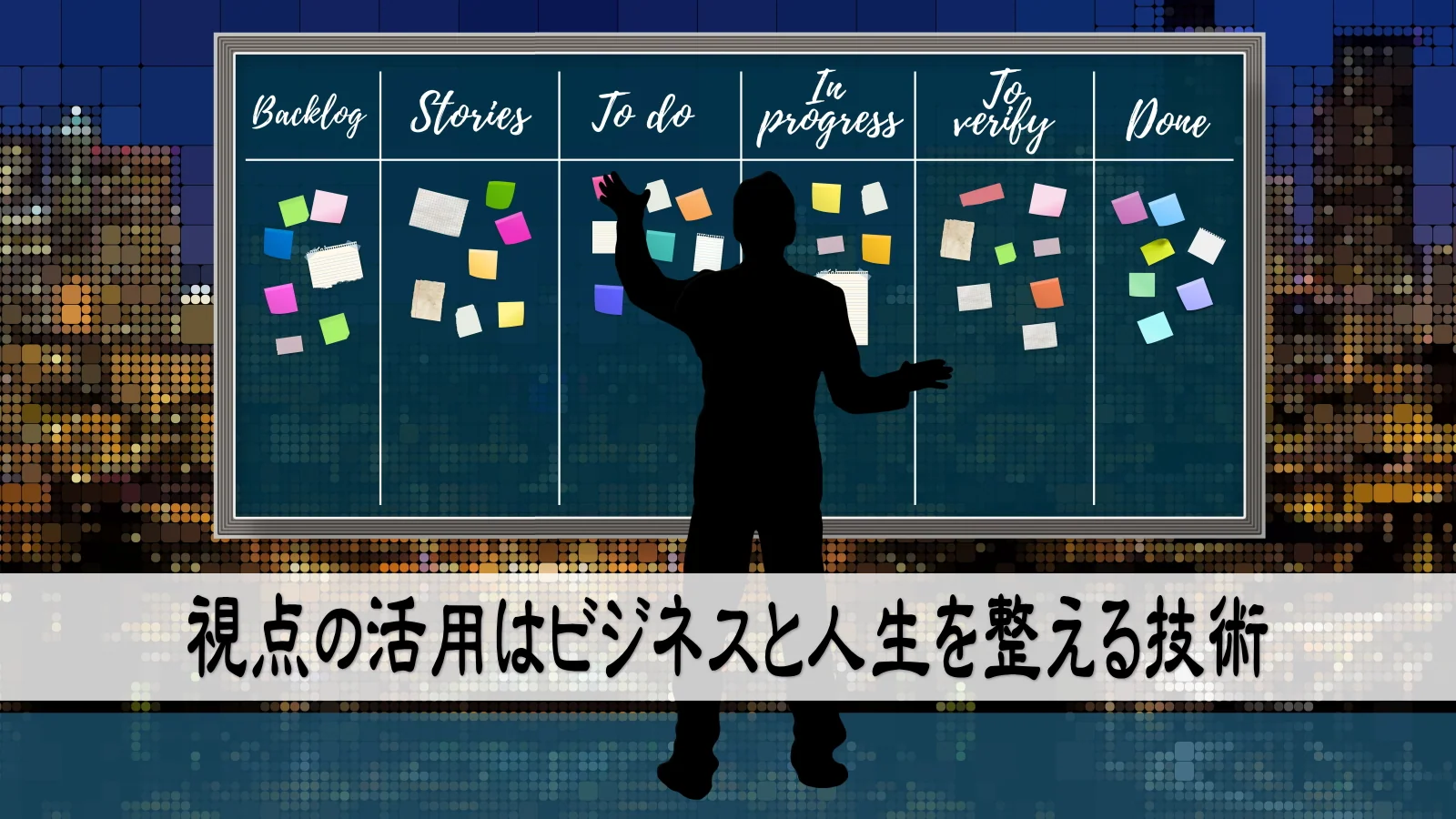
さらに、この視点の積み重ねは、人生の質そのものも高める。仕事に追われるのではなく、仕事を自分の生き方の一部として楽しめるようになる。朝起きて「今日は何をやろうか」とワクワクできる仕事。これこそが道楽化された仕事であり、天職の姿だ。
逆に言えば、視点が欠けていると、自分の欲求を押し付けたり、相手の顔色ばかりうかがったり、周囲に流されたり、未来ばかり夢見たりと、どこかに無理が生じる。そうするとビジネスも人生もどこかで歪みが出て、続かなくなる。だから視点は単なるビジネススキルではなく、人生を整える技法でもあるのだ。
視点を持つとは、すべてを俯瞰し、必要なタイミングで必要な視点に切り替える柔軟性を持つことだ。自分の立場を固定せず、相手にもなり、第三者にもなり、上空にも立ち、時間の流れにも身を置く。この切り替えの自在さが、成熟した起業家の強みになる。
そして何より大切なのは、視点を「持つ」ことではなく、「磨き続ける」ことだ。環境も人も、自分自身さえも変わっていく。その変化に応じて視点を柔らかく保ち、アップデートし続ける。そのしなやかさが、50歳を超えてもなお新しい挑戦ができる秘訣になる。
ビジネスは自分の生き方の一部であり、人生はビジネスの土台である。この二つが矛盾なく結びついたとき、起業は道楽となり、人生そのものが豊かになる。五つの視点は、そのための最良のコンパスなのだ。