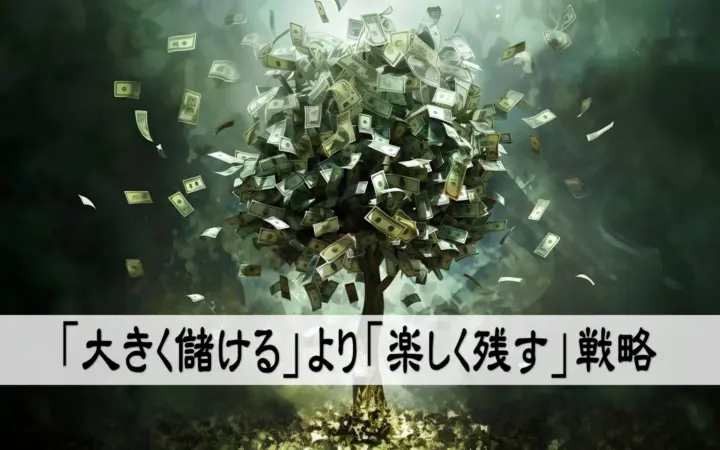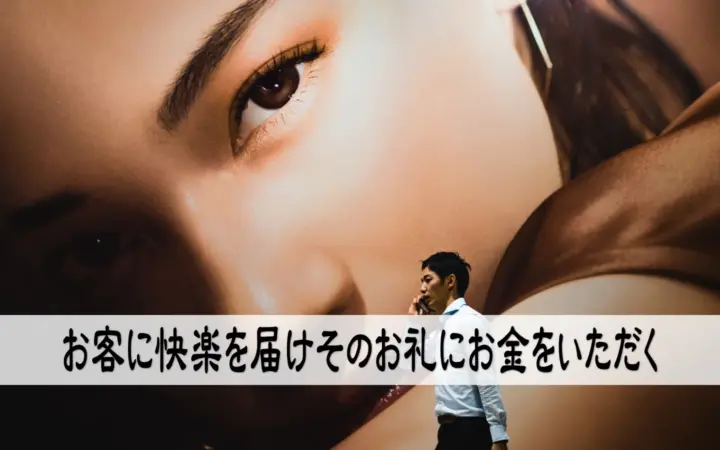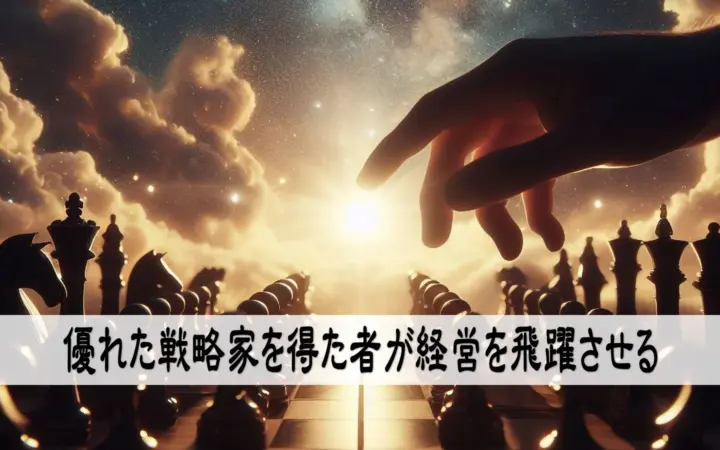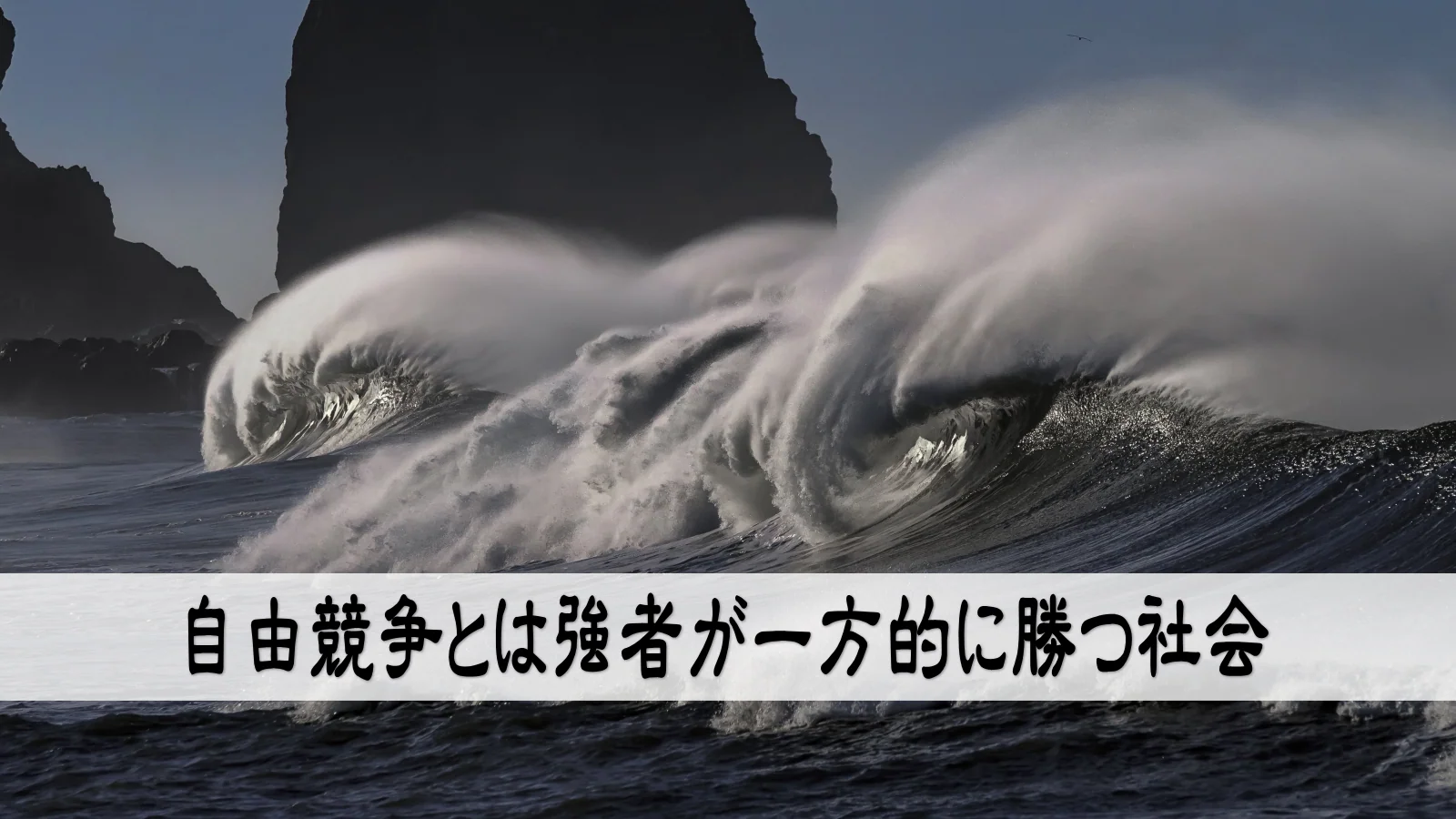
自由競争社会は平等ではなく、小さな会社が巨大資本と戦うのは圧倒的に不利である。スポーツやゲームのような公平なスタートはビジネスには存在せず、収奪がまかり通るのが現実だ。だからこそスモールビジネス経営では「戦わない戦略」が重要となる。ニッチ市場で勝負し、我を捨て流れに乗り、顧客と絆を育てながら資産を守ることが鍵だ。自由競争を逆手に取って生き残るには、拡大を求めず、人生の質を最優先にした経営が求められる。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
現代の日本は、資本主義が徹底している。資本主義社会の特徴である自由競争は、一見すると誰にとっても公平なチャンスが用意されているように思えるが、実際はまったく違う。巨大な権力や巨大な資本を持った企業や個人が圧倒的に有利であり、中小企業や個人事業者は勝ちにくい構造になっている。ビジネス経営が失敗しやすいのは、この自由競争社会という「甘く見てはいけない」環境が大きく影響している。
自由競争は「平等」ではないと知れ
世の中のすべてのゲーム、すべてのスポーツは、参加者全員が、まず最初に対等の状態になることからスタートする。カードゲームでは同じ枚数が配られるし、駒は同じ数の駒が配られる。スポーツでも対戦人数は同じ数で始められる。カードは、一方が30枚でもう一方が5枚のような、圧倒的な不平等でのゲームはあり得ない。将棋でも、一方が飛車角1枚ずつで、一方が飛車角が5枚あるというのもあり得ない。サッカーでも、一方が5人で一方が20人ということもありえない。
ところが、ビジネスの世界はまるで逆だ。平等なスタートなど用意されず、小さな資本で始めたばかりの事業者が、巨大企業と同じ土俵で戦わざるを得ないことがある。そこに公平な配慮はないし、フェアプレイを求める声も小さい。むしろ「競争」の名を借りた収奪が横行し、力ある者だけがうまみを奪い取ってしまうのがこの世界の現実だ。
もちろん、小さな企業がひらめきや行動力で大逆転を果たすドラマはときどき存在する。だが、それはごく稀な成功例であって、多くの場合は大資本に市場を奪われ踏み潰されて終わる。これこそが「自由競争は平等ではない」という厳しい真実だと認識する必要がある。特に50歳以上でスモールビジネス経営に取り組むならば、自由競争を無防備に信じるのではなく、最初からルールが不利に設定されていることを自覚しておきたい。
弱者が競争を生き抜く唯一の道
資本主義社会が自由競争で成り立っている以上、圧倒的に有利な立場にいる企業が勝ち続ける構造は変わりにくい。小さな会社や個人事業者は、頑張ったところで市場を大きく育てれば、やがて大手に食われてしまうリスクが常につきまとう。
これはいわば「競争」というより「収奪」に近い力関係だ。だからといって悲観的になって終わりではなく、大手が容易に手を出さない小さな市場を丁寧に攻略し、そこで生き残りを図るのが現実的な道となる。
弱者がこの苛烈な自由競争を生き抜くためには、むやみに大きな市場を狙ってはいけない。大きな利益が見込める場は、当然ながら大手も注目するからだ。勝ちやすい場所を探そうとすると、結局は「大手がまだ目を付けていないニッチを探す」行動に行き着く。

ニッチであれば規模は小さいが、そのぶん大手が大規模投資をするうま味が低く、しばらくは独自路線を貫きやすい。
ニッチを攻略するときに大切なのは、強みを発揮できる領域をしっかりと見極めることだ。大企業がやりたがらない隙間を的確に捉えれば、大きくはないが安定した収益を得る余地が見えてくる。
ただし、そのニッチを育てすぎると、いずれ大手が黙っていない。だからこそ「勝つ」よりも「負けない」ことに軸足を置く発想が大事になる。大手が本腰を入れた瞬間に市場を奪われる危険を考慮して、常に退路を用意しておく。あるいは「次のニッチ」を平行して模索しておく。
そうした動きこそが、自由競争の中で弱者が生き延びるための唯一の道なのだ。50歳を超えた経営者であれば、無理な拡大で体力を消耗するより、確実に負けない戦略を重視するほうがリスクも小さい。
戦わないスモールビジネス経営
自由競争に正面から挑むと、資本力や組織力で劣る小さな企業は打ちのめされやすい。そこで注目されるのが、戦わずして生き延びる「スモールビジネス経営」の発想だ。
大手と同じ土俵で真っ向勝負するのではなく、彼らが参入したがらない領域を見定め、小規模でも利益を確保できる運営に徹する。これによって身の丈にあった安定が得られるうえ、無用な大金や労力を費やさずに済む。
なぜスモールビジネス経営が強みを発揮するかといえば、無理をしない経営スタイルだからだ。拡大を急ぐと借金や投資額が膨れ上がり、競争の渦中で消耗し尽くす危険が増す。
一方、小規模ならば身の回りの資源や得意分野を活かしやすく、余計なリスクも抱えにくい。巨大企業が市場を荒らし回ったとしても、ほんの片隅でひっそりと利益を確保できるなら、それだけで十分に生き残れる。
スモールビジネス経営の神髄は「戦わない」という点にある。大手とガチンコ勝負をしようとしても、結局は深刻な体力勝負になってしまう。そうではなく、自分なりの得意分野に徹底して集中する。巨大資本が踏み込みにくい隙間を見つけて、そこでコツコツと顧客を獲得する。
規模が小さいということは、そこに大きな需要はないのかもしれないが、そのぶん大きな争いが起きにくい。ちょっと地味だが、長く続けていくにはこれが実にうまいやり方なのだ。
競争を避ける経営者の人生戦略
スモールビジネス経営の本質は、経営者自身の幸福を最優先に考えるところにある。拡大を志向して大金を追い求めると、終わりのない戦いに巻き込まれる。とりわけ50歳を過ぎてからの経営者は、体力も気力も無限ではない。
そこでもう一度、何のためにビジネスをしているのかを振り返る。結局、時間と心のゆとりこそが大切であり、経営で得た利益をどう増やし、どう使うかが勝負の分かれ目になる。
「使って減らぬ100両」という考え方は、無駄な散財を避け、必要最小限の投資や消費に抑えることで、資産を枯渇させない工夫を示唆している。
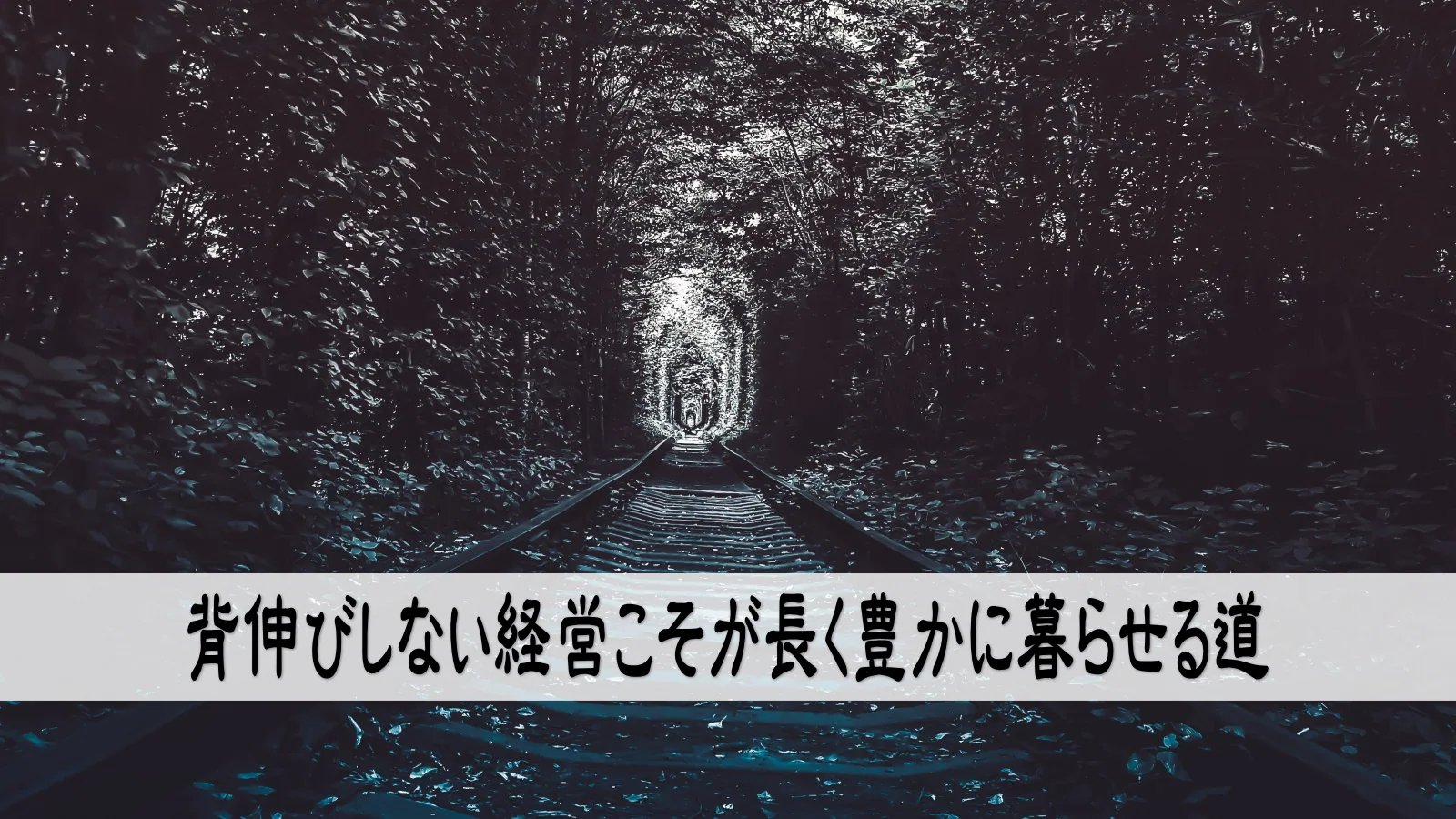
大金持ちにならなくとも、しぶとく持続可能なやり方で小さく稼ぎながら資産を増やすことは十分可能だ。外部に見栄を張らない、背伸びしない経営を続けるほうが、結局は長く豊かに暮らせる道へとつながる。
そして、好きなことを仕事にし、道楽のように楽しむ姿勢を持つのも有効だ。経営そのものを苦役と感じてしまうと、多少の資産があっても人生は疲弊しがちだ。自分が得意で、かつやっていて楽しいことならば、長期にわたってモチベーションを維持できる。
たとえ規模は小さくても、その分野のエキスパートになり、自分らしく働いて収益を上げられるなら、それこそが経営者の幸福へ直結する。利益を追いかけるよりも、自分の人生の質を守り高めることに注力するほうが、最終的には自由競争という荒波にも流されにくい。
「我」を捨て市場の流れをつかむ
スモールビジネス経営で自由競争の荒野を生き抜くには、自分のこだわりだけに固執せず、市場の変化を柔軟に捉える感覚が要になる。
世の中のトレンドや環境の動きを見て、自然に乗れる流れを見極めれば、最小限の力で利益を得られる。大きな波にうまく乗れば、個人が戦わずして大手と共存できる可能性も生まれる。
とにかく「我」を捨てて執着を手放すことが大切だ。自分の好きな領域が市場と合わなければ修正を加え、需要が盛り上がるタイミングを待つ。常に身の振り方を変えていく「変態」の精神こそ、しなやかに生き延びる鍵になる。
特に年齢を重ねた経営者ほど、新しい変化に対して尻込みしがちだが、変化を嫌えば不毛な競争に飲み込まれやすくなる。いっそ立ち位置を変えてみる度量を持てば、思わぬ方向からビジネスチャンスをつかめることもある。
大資本が参入してきたら、無理に対抗せずにさらりと退き、次の生き方を模索するほうが賢い選択になりやすい。戦わないスモールビジネス経営とは、本来そういう柔軟さを核に据えたスタイルだ。
50歳を超え、人生の本当の豊かさを知る年代だからこそ、よけいな我や競争心を捨て、市場の波を上手に活かす発想にたどり着きやすい。
顧客との絆が自由競争から守る
どんなに世の中が厳しい自由競争の場であっても、顧客との強い絆は中小企業を守る大きな壁となる。
大手の広告攻勢や値下げ攻勢には太刀打ちできなくても、個々の顧客との信頼関係がしっかりしていれば、簡単には崩されない。
むしろ顧客が応援してくれる存在になれば、大手が魅力的な条件を提示してきても、すぐに離れていくことは少ない。
ビジネスにはUSP(独自の強み)という考え方があるが、スモールビジネス経営では経営者自身の人間性が大きなUSPになることも多い。顔が見える形でのやりとりや、ほどよい距離感でのサービスの提供など、規模が小さいからこそできる温かみがある。

顧客をただの売上の数字として見るのではなく、本当に近しい仲間や友人のように育んでいけば、その関係性は長い年月をかけて深まっていく。これこそが、資本力に物を言わせるだけの企業には簡単に真似できないスモールビジネスの強みだ。
長期的な視点で経営者の人生を考えると、自分が年齢を重ねるほどに大事になるのは、金銭的な安定だけでなく、周囲との豊かな関係性である。
顧客と共に年をとり、共に成長していくような関係を育んでいけば、会社も自然に息の長い運営が可能になる。大手の真似をして急激に拡大を狙うより、少しずつ顧客との絆を重ねて守りを固めるほうが、最終的には自分の心を安定させる近道になる。
そうして築かれた事業は、いかに資本主義の荒波が激しくても簡単に揺らがない。まさに戦わずして勝ち続ける方法を体現できるのが、スモールビジネス経営の醍醐味である。