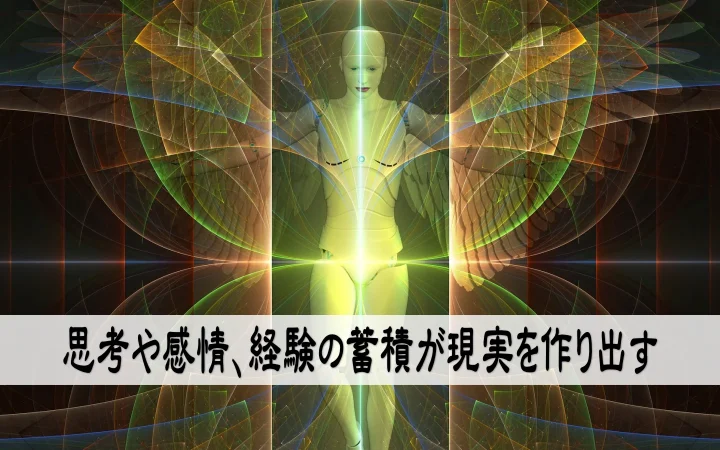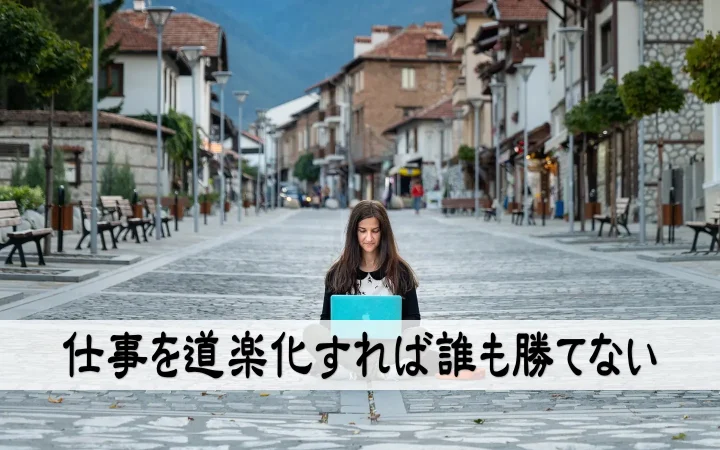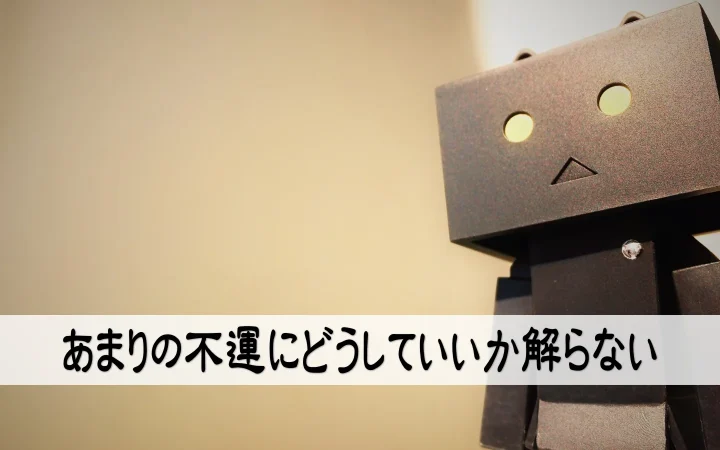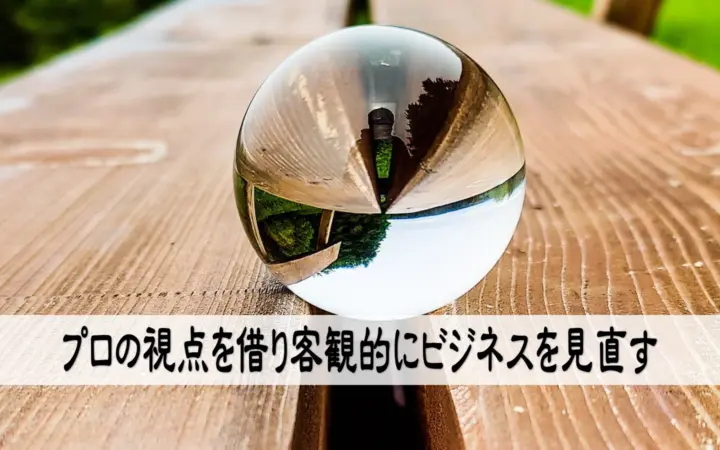世界は激しく変化し、日本企業も利益最優先で海外進出を続けてきた。しかし、その結果として技術流出や中国の軍事力拡大を助長し、日本の安全保障や経済に深刻な影響を与えている。こうした時代の変化において、小さな会社の経営者は利益追求だけでなく、地域や社会への責任を意識することが重要だ。雇用創出や納税、地元の発展に貢献する経営こそが、長期的に自社の安定につながる。単なる損得ではなく「善悪」を見極めながら、地域と共に共存共栄を目指す姿勢が、これからの時代に求められる経営の本質である。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
世界は大きく動いている。SNSを開けば海外の政治家の発言が瞬時に伝わり、それによって日本の企業が本社移転を検討し始めることも珍しくない。
そんな激動の時代の変化を目の当たりにすると、「経営はやはり利益優先で動くもの」という声が聞こえてくるかもしれない。
しかし、本当にそれだけでいいのだろうか。
時代の変化と日本企業の現実
世界を揺るがすニュースが連日飛び交い、政治・経済の潮目がめまぐるしく変わっていく時代だ。
アメリカ大統領の一言で、日本の大企業が「本社を移すか、それとも国内に留まるか」と右往左往する事態も決して珍しくない。
もともとグローバル展開は企業の自由だが、その判断があまりに短絡的だと、かえって日本企業全体の基盤を脆くする恐れもある。
たとえば、かつて多くの日本企業が「巨大マーケットがある」「安価な労働力を確保できる」といった理由で中国へ続々と進出した時代があった。
たしかに、そこで得た収益は莫大なものだったかもしれない。
しかし、一方で技術移転や資金提供が進み、中国の経済・軍事力は急速に拡大した。
その結果が尖閣問題をはじめとした日中の領土・海洋摩擦につながり、南シナ海では軍事拠点が次々と整備される事態を招いた。
もちろん、日本企業だけに責任があるわけではない。
アメリカだって隣国メキシコに同様のことをやってきた。
しかし、中国とメキシコの決定的な違いは、中国が「法治国家」ではなく「人治国家」、つまり共産党一党支配のもとで政策が大きく左右される独裁体制だという点にある。
利益を求めて進出した結果、日本側が技術や投資を惜しみなく提供し、最終的には軍事力強化の片棒を担がされてしまったと言っても過言ではない。
こうした時代の変化は、大企業だけでなく、私たち小さな会社にも影響を及ぼす。
輸入品が急増して価格競争が激化すれば、国内の中小企業は大きな打撃を受ける。
海外投資や政治的リスクのしわ寄せは、往々にして弱い立場の企業や地域に押し寄せるのだ。
「時代の変化」を単にグローバル化と受け止めるだけでなく、その背景に潜むリスクもしっかり見据える必要がある。
経営の本質と社会への責任
では、そうした世界情勢の激流の中で、小さな会社の経営者は何を目指せばいいのだろうか。
まずは「経営の本質」について改めて考えてみたい。
経営とは、言うまでもなく「儲ける」ことが大事だ。
利益を出してこそ、従業員に給料を支払えたり、設備投資ができたりする。
しかし、儲けることだけを目的とすると、いつか歪みが生まれる。
大きな利益を得たら、まず経営者自身が贅沢をしてもいい。
頑張った結果なのだから、それは正当な報酬だろう。
ただ、それを超えた余裕が生まれたときに考えてほしいのが、納税や地域投資といった「社会への責任」だ。
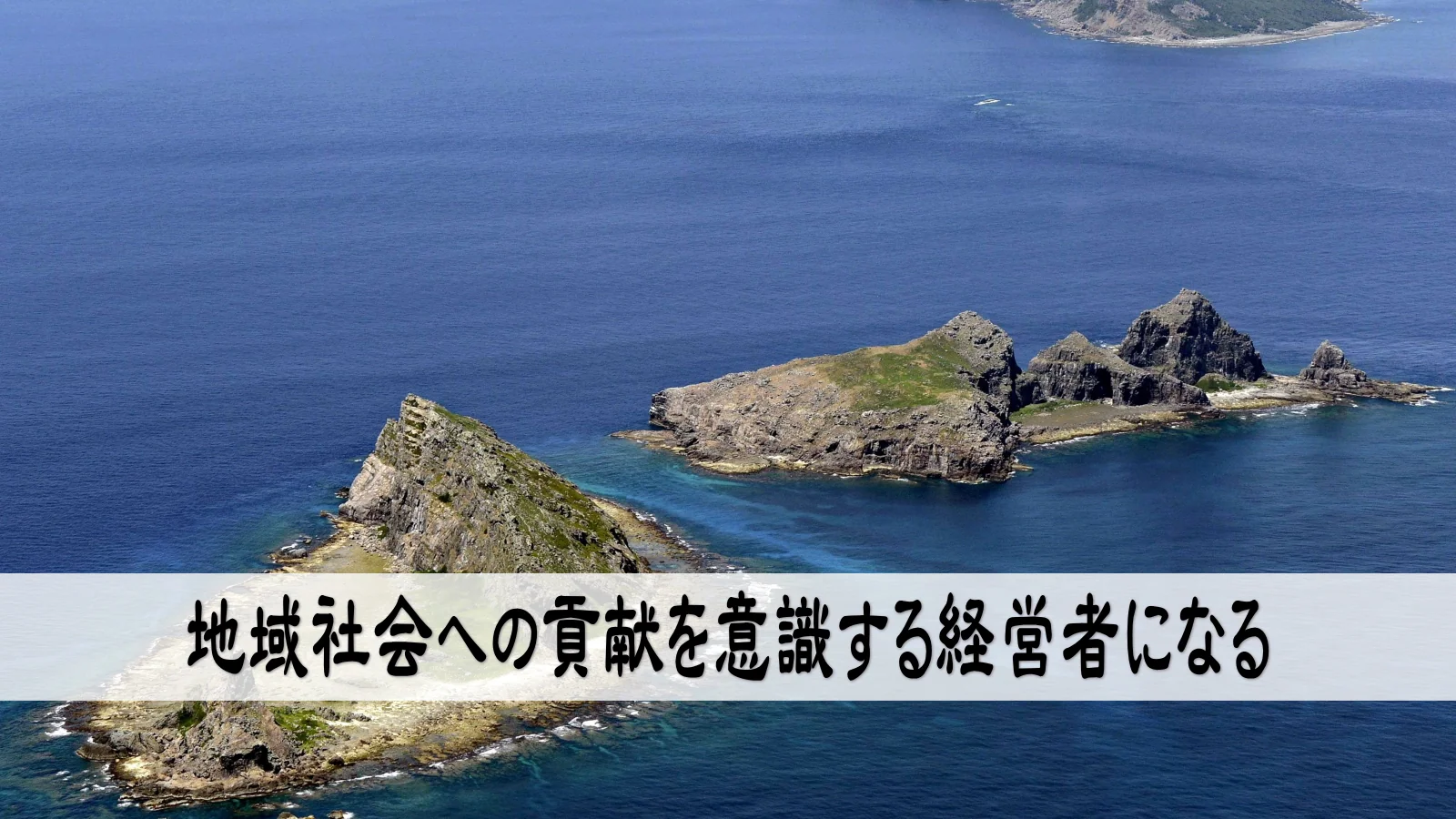
最近は大企業の中にもタックスヘイブンを利用して節税を図るところがあるが、そうした動きが加速すれば、日本国内の税収は減り、インフラ整備や教育、福祉への投資が滞ってしまう。
結果的に地域社会の衰退を招き、長期的には企業自身の成長も制限されてしまう。
一方、地域社会への貢献を意識する経営者は、雇用を生み、地元に税金を落とし、地元のイベントや活動に協力するなど、多面的に「持ちつ持たれつ」の関係を築く。
すると地元の人々の信頼を得て、長く安定して事業を続けられる可能性が高まるのだ。
たとえば大企業が撤退しても、自社のサービスや商品をこよなく愛してくれるお客さんが地域に残っていれば、小さくても力強い商売を続けられる。
経営における損得と善悪を読み解く
ビジネスにおいて「損得勘定」は切り離せない。
だが、そこに「善悪」という視点が加わると、経営の舵取りはまるで違う景色を見せる。
儲かるのであれば何でもやる。
誰にでも技術を渡す。
税金は可能な限り逃れる。
それが短期的に見て得策であっても、本当に「善い」行動とはいえない場合がある。
前述の中国との問題などは、その好例だ。
もちろん尖閣問題や南シナ海の軍事拠点化は、日中双方の政治的思惑も絡んでいる。
ただ、日本企業があまり先を考えずに技術移転や資金提供を続けたことも、中国の軍事力を事実上後押ししてしまったといえる。
巨大市場に魅了されて「損得勘定」を優先した結果、長期的には「自国の安全保障」が脅かされる事態を招いているのだ。
これは一種の自業自得でもあり、改めて「善悪」の視点を無視したツケと考えられる。
もちろん小さな会社が、直接中国の軍備拡大をどうこうできるわけではない。
だが、「自分たちが属する社会にどんな影響を与えるか」を常に考える姿勢は、経営者として必要不可欠だ。
地域を守るために、自社でできる範囲の取り組みを続ける。
従業員にも地域を大切にするマインドを植え付ける。
そうした“小さな誠意”が積み重なって、やがては大きな成果を生むかもしれない。
経営者としての基本を理解する
経営書やMBAの世界では「社長学」と呼ばれる知識やジャンルが注目されることがある。
組織を動かすリーダーシップ論や戦略論、財務やマーケティングに関するノウハウなど、その内容は多岐にわたる。
しかし、小さな会社を切り盛りするうえで本当に大切なのは、実はもっと日々の現場に根ざした“総合力”だろう。
たとえば従業員とのコミュニケーションで行き詰まったら、自ら頭を下げたり、互いの気持ちを聞き合う場を率先して設ける。
地元商店街の行事があれば、先頭に立って盛り上げる。
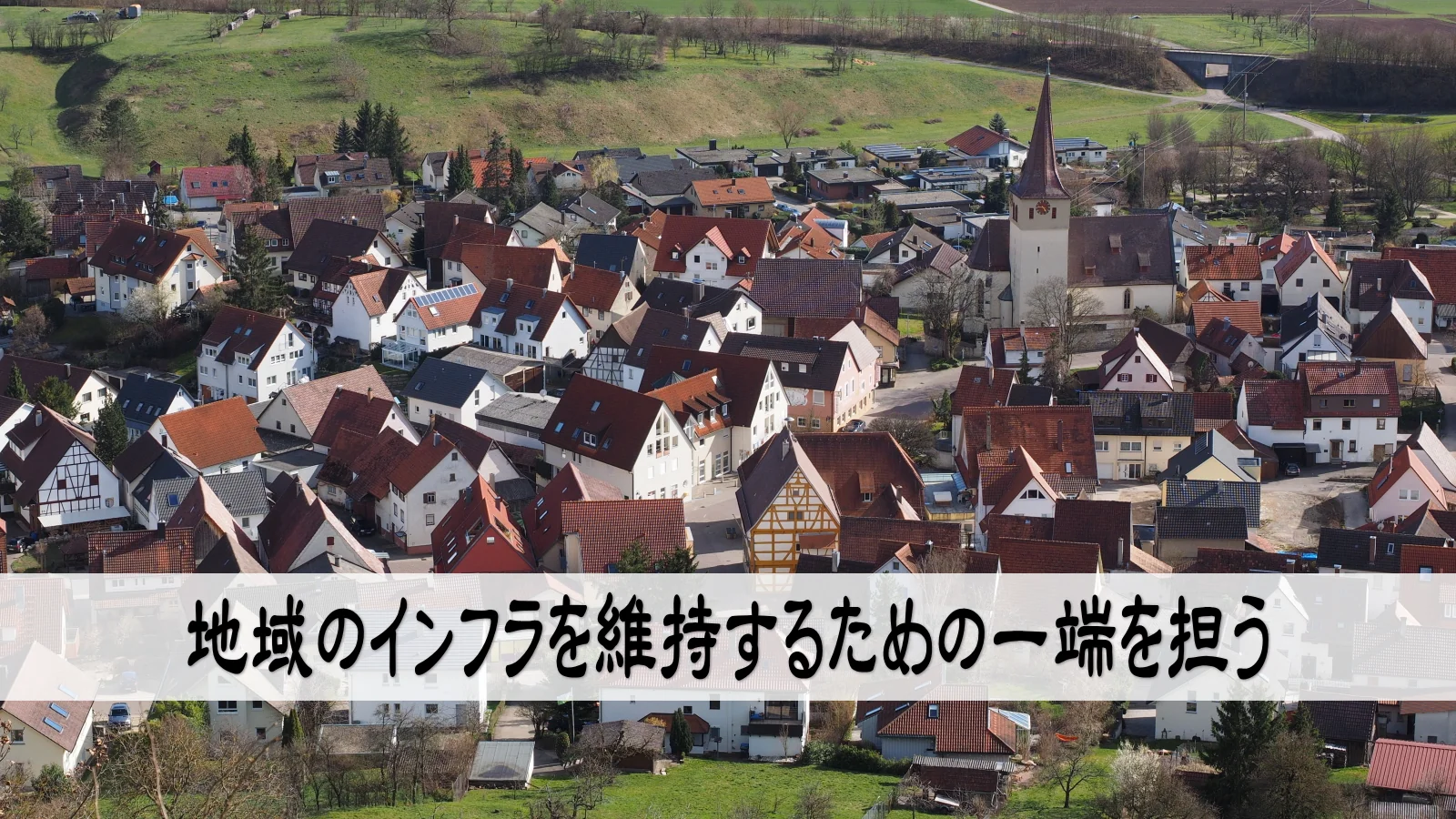
税金の支払いに関しては逃げずにきちんと対応して、地域のインフラを維持するための一端を担う。
こうした“小さな行動”が、結果として会社の信用を高め、ビジネスにも好循環をもたらすのだ。
言い換えれば、社長学は大学で学ぶ経営理論や海外ビジネスの成功事例だけで成り立つものではない。
むしろ、その会社が拠点を置く地域で培われる人間関係や、肌感覚で積み重ねてきた経験のほうが大きい。
自分の会社が地域にどういう役割を果たし、どうすればみんなが幸せになるのか?
そう考え続ける姿勢こそが、真の社長学の本領といえる。
地域と共に歩む小さな会社の戦略
世の中には「中小企業が国のためにできることなど限られている」という声もある。
しかし、何も国レベルで巨額の投資を行ったり、外交問題を直接どうにかしたりする必要はない。
自分たちが住み、働いている地域を少しでも良くすることこそが、身近で具体的な社会貢献だ。
たとえば、小さな会社でも地元のイベントや商工会議所の取り組みに参加し、まちおこしに協力することは可能だ。
地元の若者を積極的に雇い、職場でしっかり育成することも立派な地域貢献になる。
こうした姿勢は、人材確保にもつながりやすい。
結局のところ、人は「誇りを持って働ける会社」であればこそ長く働きたいと思うものだ。
また、地域での経済循環を意識するなら、仕入れをできるだけ地元の業者から行う工夫をしてみてもいい。
コストは多少かかるかもしれないが、その分が地元の売上になれば、やがては地元住民の購買力を高める。
こうした“循環”が広がれば、会社にとっても決して損にはならない。
むしろ、長い目で見れば大きな得になるはずだ。
損得を越えた共存共栄へ
最後に、消費者としての立場も忘れてはならない。
ただ「安いから」とネット通販ばかりを利用すれば、近所のお店は成り立たなくなる。
特に車が運転できなくなる高齢者が増えている今、自宅から歩いて行ける商店や病院、スーパーの存在は切実な問題だ。
地域に必要な店を守るには、地元で買い物をする意識が不可欠となる。
ビジネスは「損得勘定」が欠かせないが、それだけで判断してしまうと、いずれは多くの人が損をする事態に陥りかねない。
「善悪」を見極めながら「経営の本質」を追求し、自分が住む町や国を健全にする行動を取り続けることが、実は小さな会社が時代の変化の中で生き残るための最善策でもある。

中国のような巨大市場に惹かれて、安易に技術や資金を流出させると、あとから莫大なリスクが帰ってくることもある。
大企業ならまだしも、小さな会社が無理に海外投資に走って痛手を負えば、一気に事業継続が難しくなってしまう。
そうしたときこそ、足元を見直し、地域や国内に目を向ける経営スタイルが再評価されるはずだ。
激変する国際情勢のただ中にあっても、小さな会社は「自分たちの地域を大切にする」という基本姿勢を失わないこと。
その地道な積み重ねが、大きなうねりを生み、地域、ひいては国全体を少しずつ支えていく。
そんな“粋”で“しなやかな”経営こそ、これからの時代に求められる「社長学」の姿なのではないだろうか。
地域と共存共栄の道を模索する
国際情勢は複雑化し、経済や政治の動きも読みづらい。
しかし、その大波に飲まれながらも、自分の足元である地域をしっかりと支える事業者の存在は、いつの時代も貴重だ。
大企業が海外に飛び立つのもいいだろう。
だが、小さな会社は小さな会社なりに、地域と共存共栄の道を模索できる。
損得だけを追うのではなく、善悪や社会への責任まで見据える“経営の本質”こそが、長期的に自分たちをも豊かにしてくれるはずだ。
尖閣問題や南シナ海の情勢など、国際的なニュースを見れば不安になるかもしれないが、そんなときこそ「じゃあ自分は何をできるだろうか」と考えてみる。
地域で愛される会社を目指す。
地元の雇用を生み出し、地元で消費し、地元に納税する。
それこそが「時代の変化」に翻弄されない、粋な生き方ではないか。
大きな嵐の中でも、足元をしっかりと照らす明かりとなる。
そんな“小さな会社”が、この国を支える大きな力になるに違いない。