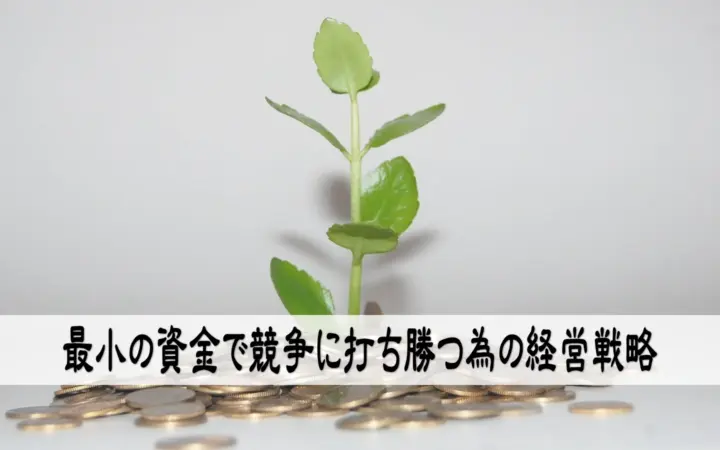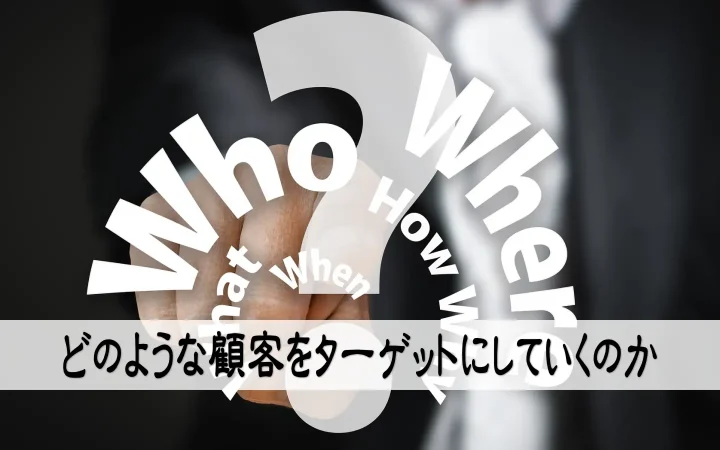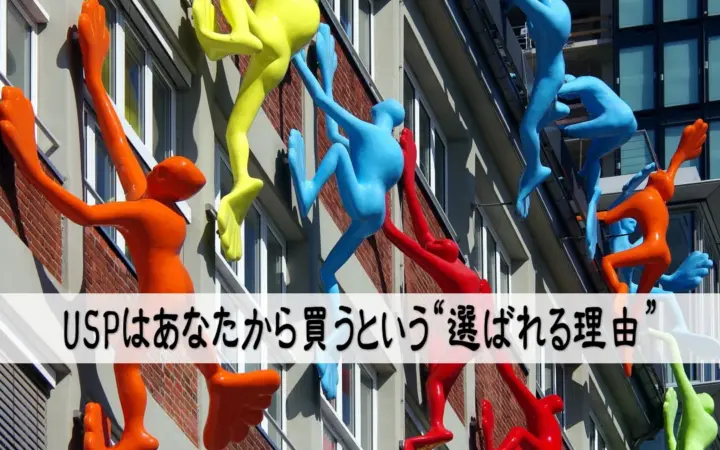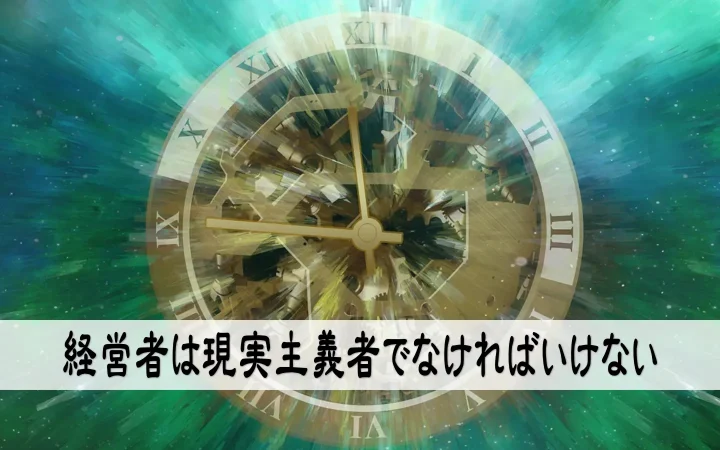小さな会社は、限られた資源を最大限に活かすために「戦略」に重点を置くべきである。戦略とは「どこで、誰に、何を売るか」を決めることであり、戦術(広告や営業)はその戦略に基づいて実行されるべきものだ。やみくもな戦術では成果が出にくく、経営資源を浪費するだけになる。一点突破で勝てる市場を見極め、戦略を軸に戦術を展開することが重要である。また、環境変化に応じて戦略を見直し、継続的に磨き続けることで、長期的な成功へとつながる。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
小さな会社を経営は、どうしても日々の売上や顧客対応に追われがちになる。
焦るあまり、手当たり次第に広告を打ったり、営業をかけたりしてしまうことも多い。
しかし、まず大事なのは“どこで誰に何を売るか”という軸を定めることだ。
これがいわゆる戦略の部分であり、実際の販促やセールスなどの戦術を支える根幹となる。
小さな会社はなぜ戦略が重要か
ビジネスには「戦略と戦術」がある。
戦略とは、どの市場で勝負するか、どうやって自社の強みを打ち出すかといった設計図のようなもので、戦術とはその設計図を具体的に実行する手段だ。
大企業であれば複数の手段を同時進行できるかもしれないが、小さな会社の場合、リソースは限られている。
だからこそ、しっかりと戦略を練り上げることで、最小限のコストで最大限の効果を狙える。
戦略なき戦術は、方向感のないまま突っ走るようなものだ。
やみくもに広告を出しても、肝心のお客が望む商品やサービスを提供できなければ意味がない。
逆に、戦略を固めてから戦術を選べば、たとえ予算が少なくても効果的な仕掛けが打てる。
もし戦略を明確化しないまま動いてしまえば、せっかくの行動力も空回りしがちになる。
小さな会社の戦略においては、まずゴールと方向性を定め、そこに全力投球することが肝心なのだ。
限られた資源を一点に集中せよ
小さな会社の社長なら、資金や人材が潤沢にあるわけではないことを痛感しているだろう。
どんな市場でも競合は存在し、常に厳しい戦いが繰り広げられている。
だからこそ、限られた経営資源をどう配分するかが勝負の分かれ目になる。
やたらと手を広げてしまえば、一つひとつに十分な力が注げず、結局はどれも中途半端に終わってしまうリスクが高い。
では、具体的にどうすればいいのか。
その答えが一点突破だ。たとえニッチな市場でも、自分の強みが活かせる場所で全力を注げば、大手が手を出しにくい分野で存在感を発揮できるチャンスが生まれる。
たとえば、地元密着型のサービスや特定の業界向けコンサルティングなど、競合が少ないところにフォーカスするとよい。

この一点突破こそが小さな会社の戦略の肝だ。
無理に背伸びして大手と同じ土俵で戦うのではなく、“自分にしかできないこと”を深掘りする。
そして、その分野でリーダーシップを握ることができれば、多少の景気変動にも耐えられる強いビジネスに育つ。
一歩ずつ着実に足元を固めながら、確実に勝てる勝負をするのが小さな会社に求められる姿勢なのだ。
まずは経営資源を一点に集中し、小さくても確かな成功体験を積むこと。
それが今後の事業拡大や新展開の土台となり、長く安定した成長をもたらす。
戦略を定める:どこで誰に何を
戦略を考えるうえで最初に決めるべきは、“どの市場で、どのような顧客に、どんな価値を提供するか”という点だ。
これはビジネスの設計図とも呼べる重要なステップであり、ここが曖昧だと後々の戦術もブレてしまう。
市場選びを間違えると、自社の強みを活かせずに埋もれてしまうし、顧客ターゲットを誤解していると、販促に力を入れても成果は上がらない。
たとえば地域密着型の飲食店なら、その地域に住む家族連れか、ビジネスパーソンか、あるいは観光客か、メインとなる客層を具体的にイメージする。
そして、その客層が求めるものは何かを深堀りして、自社が提供できる独自の強みを明確にするのだ。
大事なのは“自分たちの魅力”をしっかり言語化し、それを狙った客層にどう届けるかを考えること。
このプロセスこそが小さな会社の経営戦略の基盤となる。
やみくもに
「とりあえず幅広くアピールしよう」
という姿勢では、小さな会社が大手と対等に渡り合うのは難しい。
まずは自社のビジョンを定め、そこに合った市場と顧客を選び抜く。
そうすることで、自分たちの存在感を際立たせることができる。
どこで誰に何を売るのか。
この問いに正面から向き合い、具体的な答えを出すことが、“売れる仕組み”を作る第一歩だ。
戦術を組む:売る手段を考える
戦略が固まったら、次は戦術を組み立てる出番だ。
戦術とは、具体的にどんな広告を打つか、どんな営業方法を取るかなどの実行策を指す。
たとえばターゲットが若い女性なら、SNSを積極的に活用し、口コミを増やすのが効果的かもしれない。
逆に、企業相手のBtoBビジネスなら、直接の訪問営業や専門誌への広告が力を発揮することもある。
大切なのは、戦略と戦術がきちんと噛み合っているかどうかだ。
戦略で
「地元の家族連れをメイン顧客にする」
と決めたのに、高級レストランのような演出や高額商品ばかりを押し出していてはチグハグになる。

戦術はあくまで戦略に沿った形で選び、実践する必要がある。
また、実際に戦術を試したら、効果測定を忘れないこと。
SNSでの反応や問い合わせ数、実際の売上などをチェックし、うまくいかなければ別の手段に切り替える。
小さな会社なら、素早く軌道修正ができる点が強みだ。
場当たり的な営業ではなく、戦略を土台に一貫性ある戦術を展開することで、少ないリソースでも大きな成果を狙えるのが小さな会社の醍醐味である。
行動の前に考え、行動しながら検証し、さらに考える。この繰り返しこそが、戦術を育て、事業を伸ばす鍵となる。
戦略不在の戦術が招く落とし穴
ありがちな失敗例として、売上が落ち込むと目先の売上を取り戻そうと広告費を増やしたり、大幅な値引きキャンペーンを乱発したりするケースがある。
しかし、戦略が定まっていない状態でいくら戦術を積み上げても、大きな効果は望めない。
結果として広告費だけがかさみ、在庫や販促コストばかりが膨らむ悪循環に陥ってしまう。
こうした状態では、会社のイメージもブレやすく、顧客の心にも響きにくい。
たとえば高級志向のブランドが、突然ディスカウント路線に走ってばかりいると、本来狙いたい富裕層の顧客を逃す危険がある。
これはまさに戦略と戦術の不一致が引き起こす悲劇だ。
大きな軸がないままの戦術は、方向感を失っているため、投資対効果が期待しにくい。
一方、しっかりと戦略を立ててから戦術を選ぶ会社は、どの施策にも
「なぜこれをやるのか」
という明確な理由がある。
顧客が望むものと自社が提供する価値が噛み合っているからこそ、余計な出費や混乱を最低限に抑えられるのだ。
戦略不在の戦術は、地図を持たずに走り回るようなもの。
目的地が見えなければ、どんなに走ってもゴールには近づけない。
だからこそ、まずは全体像を見据えた戦略づくりが欠かせない。
戦略は磨き続けることで光る
経営環境は日々変化し、新しい競合やテクノロジーも次々に登場する。
だからこそ、一度決めた戦略も定期的に見直し、改善していくことが必要だ。
たとえば景気や社会情勢が変われば、顧客が求める価値も変化する。
そんなとき、戦術レベルだけでなく戦略そのものを再検討することで、新しい状況に合った勝ち筋を見つけられるかもしれない。
戦略は立てるだけで終わらない。
実行を通して得られたフィードバックをもとに、精度を高めていくのが理想だ。
いわゆるPDCAサイクルを回しながら、売上や顧客満足度などの指標をチェックし、狙い通りに成果が出ているかを確認する。
もし期待した結果が得られないなら、戦術はもちろん、戦略そのものの方向修正も視野に入れるべきだ。
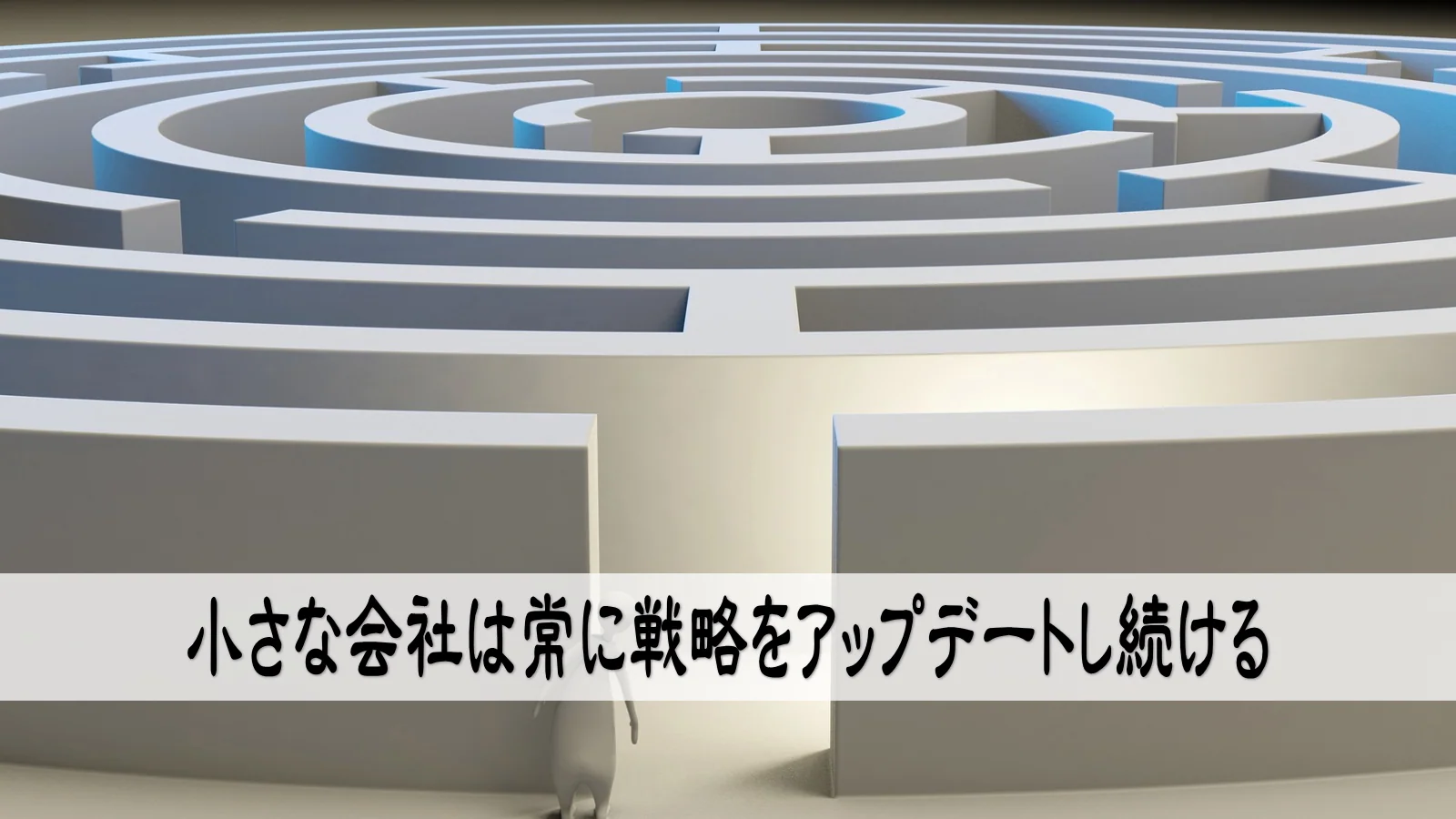
小さな会社ほど、市場の変化に柔軟に対応しやすい。
それは大手にはない大きな強みと言える。
社長自らの判断で素早く舵を切り替えられるからこそ、時代の波を巧みに乗りこなせる。
小さな会社の真髄は、常に戦略をアップデートし続けることにある。
そうすれば、たとえ環境が変わっても、“自分たちはどの市場で誰に何を提供するか”という軸がブレにくく、長期的に安定した成果を得られるはずだ。
戦略を磨き続ければ、その光はやがて多くの顧客の心を照らし、あなたのビジネスをいっそう輝かせるだろう。