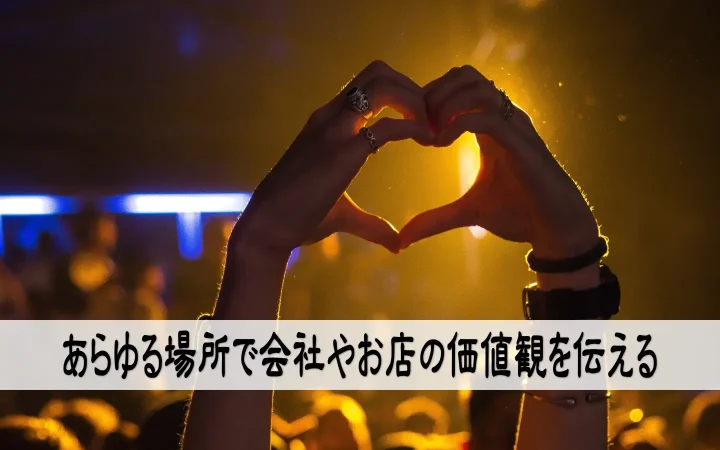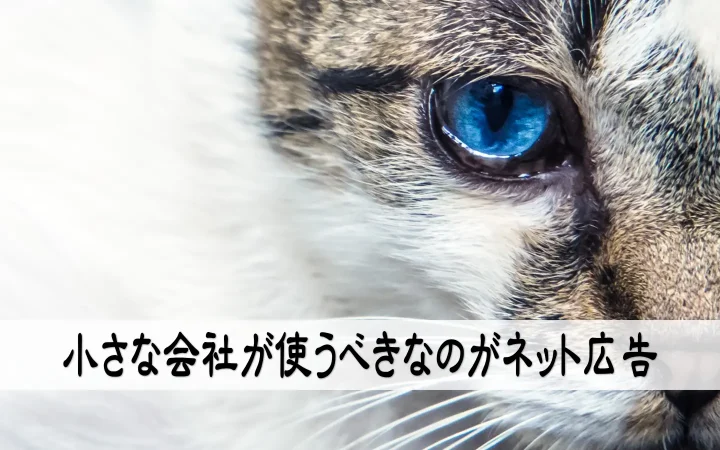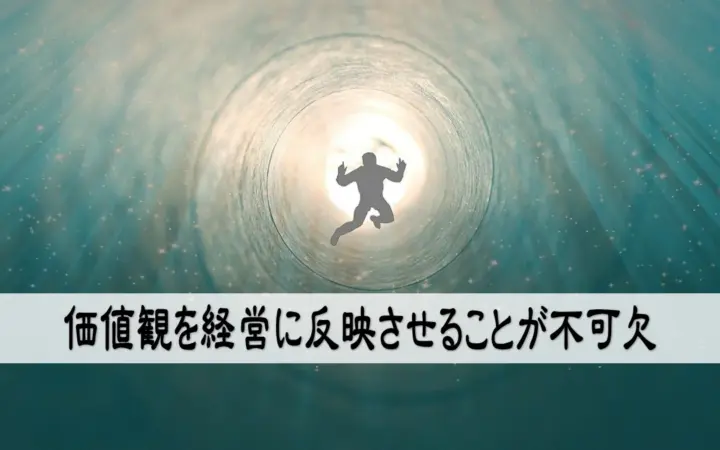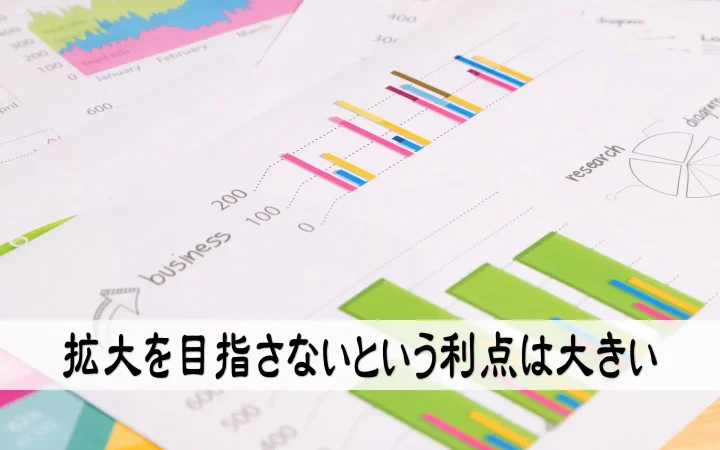中小企業や個人事業主が商品を売る際に直面する問題は、セールスに対する誤解に起因する。多くは「売る」ことを「売り込む」ことと混同し、抵抗感を持つが、実際はお客の問題を解決する提案が大切だ。「売ること」とは、顧客が欲しいものを提供することであり、「売り込む」こととは異なる。また、商品やサービスは顧客の悩みを解決する手段であり、その価値を適切に伝えることで、セールスが自然に進む。最終的には、マーケティングとセールスを通じて、顧客に必要な解決策を提供し、売れる仕組みを作ることが重要だ。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
小さな会社や個人事業の経営者が抱える悩みでよくあるのが、「商品はいいのに売れない」という現象だ。
技術には自信がある、品質は自慢できる、でもなぜか売れ行きが伸びない。
こうした経験はないだろうか。
なぜ自分の会社の商品は売れない?
実は、優れた商品を作っただけでは売れないのが現実だ。
いわゆる
「いい商品なら売れる」
というのは、多くの場合、幻想に過ぎない。
売れる商品には「売れる仕組」が必要になる。
仕組とは、欲しい人が見つけやすく、欲しくなり、そして買いやすい流れを作ることだ。
しかし多くの小さな会社はこの仕組作りを後回しにしてしまう。
なぜなら、「セールス」に対する抵抗感を抱えているからだ。
ペコペコ頭を下げて押し売りするのは嫌だ、そんなイメージが先行して、営業やマーケティングを敬遠してしまう。
結果として「売ること」と「売り込むこと」の区別が曖昧になり、「セールスは悪だ」という誤解に陥る。
しかし本来、セールスとはお客にとって必要な価値を提供する行為であって、決して悪ではない。
お客に役立つ商品を届けるのは、むしろ経営者としての責任ともいえる。
ここで押さえておきたいのは、セールスが苦手だと思うのは「売り込み」ばかりを想像してしまうからだということだ。
実際にはお客が「欲しい」と思う状態を作って売るのが正しい方法であり、それが「売れる仕組」づくりでもある。
「売る」ことと「売り込む」ことの差
人は「セールス」と聞くと、強引な押し売りのイメージを抱きがちだ。
上辺だけの笑顔で相手を騙し、無理やり商品を買わせる
そんな“悪徳商法”を想像してしまい、「売るのは悪いことだ」と感じてしまう。
しかし、「売る」ことと、「売り込む」ことは違う。
ここを理解するだけで、セールスに対する抵抗感は大きく和らぐ。
「売る」とは、お客が本当に望んでいるものを的確に提供することだ。
お客が買いたいと思い、自ら財布を開きたくなるような価値を示す行為である。
一方、「売り込む」とは、お客が望んでいないものを無理やり押し付けて買わせようとする行為だ。
同じ商品を提案しているとしても、お客の視点やタイミングを無視して押し通すやり方は「売り込み」になってしまう。

小さな会社や個人事業の経営者が陥りやすいのは、お客が嫌がるパターンの売り方だ。
見境なく電話をかけたり、SNSでしつこくメッセージを送ったりと、
「欲しくもないのに買わされる」
という空気を作ってしまう。
しかし、お客がいま必要と感じているときにサッと商品を差し出してあげるのは喜ばれる行為だ。
タイミングやお客の状態を無視した強引なアプローチこそが「売り込み」であり、お客の望みに寄り添うのが「売る」という行為なのである。
ではどうすれば“正しいセールス”ができるのか。
答えは単純で、
「お客が欲しいと思う状態を先に作る」
ことだ。
つまりマーケティングをしっかり行い、自社の商品がどんな価値を提供するのかをきちんと伝え、興味を持ってもらう。
それを実行すれば、頭を下げる必要も、無理に押し込む必要もなくなる。
売れる仕組を作る4つのステップ
多くの経営者は「いい商品」があれば、それだけで売れると考える。
しかし実際には、「商品」だけでなく
「集客」
「教育」
「セールス(クロージング)」
という段階をきちんと踏む必要がある。
言い換えれば、この要素を整えてはじめて「売れる仕組」ができあがる。
1つめは「商品」だ。
良い商品を作ることは大前提だが、そもそもお客の問題を解決するものでなければならない。
2つめは「集客」である。
いくらいい商品を持っていても、それを必要とするお客を集められなければ何も始まらない。
広告やSNSなどを活用し、見込み客をしっかり呼び込む施策を考える必要がある。
3つめは「教育」だ。
ここでの教育とは、難しい専門知識を教えることではなく、
「この商品が自分の問題解決に役立つ」
という納得感を育むことを指す。
ブログやメルマガ、動画などを通して、お客が「これなら自分にもメリットがある」と理解できるようにサポートする段階である。
4つめは「セールス(クロージング)」。
ここでようやく、
「ではどうでしょう? 買いませんか?」
と提案する。
この4つのステップをしっかり踏めば、自然とお客が手を挙げてくれる状態になる。
そうすれば、「売り込み」ではなく「売る」形で商品が動く。
マーケティングがしっかりしていれば、あとは背中を少し押すだけで買ってもらえるのだ。
セールスが苦手だと感じる経営者は、実はこの仕組づくりが弱い可能性が高い。正しくステップを踏むほど、最後のクロージング段階で苦労しなくなる。
売れないのは問題解決視点の欠如
商品がなかなか売れないと嘆く多くの経営者に共通しているのは、
「お客は商品そのものを欲しがっている」
という思い込みだ。
だが実際には、お客は「問題解決」を求めている。
ここを見誤ると、せっかくの良い商品も
「単なる機能説明の羅列」
に終わってしまい、購入意欲はかき立てられない。
例えば、「ハイパワーなトースターです!」と機能面を強調しても、お客からすると「だから何?」という印象になりがちだ。
大切なのは、
「忙しい朝にパンをサッとおいしく焼き上げたい」
という悩みや、
「冷凍ピザがまるでお店の石窯みたいにカリッと焼けます」
というメリットを示すこと。
こうした具体的な「問題解決」のイメージこそが購入動機を作り出す。
この視点を持たないまま「売れない・・・」と嘆いていても、何も状況は変わらない。
むしろ、
「うちの商品は性能が高いのに、お客はそれを理解してくれない」
と不満を抱え続けることになるだろう。
そうではなく、
「お客がどんな問題を抱えているか」
を理解し、それに対応する解決策を提案するのが真のセールスだ。

すべての商品やサービスは、お客の「困った」を解決するために存在する。
冷凍ピザを美味しく焼きたい、時間をかけずに食パンをサクサクにしたい、朝のバタバタを減らしたい
そういう「問題」を解決できるからこそ、トースターに価値が生まれる。
ところが作り手側は、機能のスペックや技術的な優位性ばかりをアピールしがちだ。
遠赤外線ヒーターがどうだとか、熱伝導率がどうだとか、専門的な数字を並べても、一般のお客はピンとこない。
お客が本当に知りたいのは
「これまで上手く焼けなかったピザが、たった数分でプロ級に仕上がる」
という成果だ。
専門用語を並べるだけではなく、
「あなたの問題をこうやって解決できる」
という視点で情報を提示することが大切である。
問題解決の視点を持つかどうかで、同じ商品でも売れ行きが変わる。
もし自社商品が売れずに困っているなら、
「この商品は、お客のどんな悩みや不便を解決するのか?」
を今一度洗い出してみることをおすすめする。
意外と、お客が求めている問題解決の本質をまだ掴みきれていないかもしれない。
商品が売れない本当の理由は、「商品そのもの」ではなく、「問題解決視点」が抜け落ちていることにある。
どんなに性能が高いトースターでも、どんなにデザインが優れた家具でも、お客の具体的な悩みを解消するものでなければ興味を引くことは難しい。
お客が求める悩み解決の見つけ方
ここで鍵になるのは、お客が抱えている問題をしっかり把握するリサーチ力だ。
多くの場合、経営者は自分の業界や商品のことばかり考えてしまい、本来はお客にフォーカスする必要があるのに、それをおろそかにしてしまう。
どんな悩みを持った人たちがこの商品を必要としているのか、どの程度の温度感で困っているのか、そういった具体的な姿をイメージすることが重要だ。
さらに、お客自身が気づいていない潜在的な問題を引き出すことも大事だ。
例えば
「朝はパンを焼く余裕がないから食べない」
と思い込んでいる人でも、実際には
「時間がかからずに美味しく焼けるなら、やっぱり朝食を楽しみたい」
と感じているかもしれない。
こうした気づきを与えるためには、お客が抱える日常の不便を想像し、
「こんなに簡単に解消できる方法がある」
と伝えることで顕在化させる。
悩みが明確になれば、あとはそれをどう解決できるかを具体的に伝えるだけだ。
「問題解決の手段」
として商品を見せることで、初めてお客は
「自分に必要なものだ」
と納得する。
広告文やセールストークの中で「解決策」を示すことこそが、小さな会社にとって最も効果的なアピール方法になる。
セールス力=問題解決力を磨く
結局のところ、セールスが苦手だと感じてしまうのは、商品を「売る」前に「売り込む」イメージを抱いてしまうからだ。
それを解消するには、
「問題解決力を高める」
という視点でセールスを捉え直すことが近道である。
お客の悩みを理解し、その解決策として商品やサービスを提供する
これがセールスの本質だ。
セールスはスキルなので、誰でも訓練で上達できる。
練習の際に意識したいのは、お客の立場に立って質問することだ。
お客はどんな場面で困っているか、どのくらいの頻度でその困りごとが起きるか、実際にそれを解決することでどう変わるのか。
こうした点を深掘りし、その結果として
「この商品があれば悩みが消える」
と思ってもらえるように導く。
このプロセス自体が「問題解決力」の向上につながる。
また、お客が抱える問題をリアルにイメージできるストーリーを交えると、より心を動かしやすい。
たとえば
「朝は何かと忙しく、ついパンを焦がしてしまう」
あるいは
「冷凍ピザを焼くのが面倒で、あきらめてしまう」
といった具体的なシーンを物語風に語ると、お客は自分を重ねて考えやすくなる。
そうすれば自然と
「この商品なら自分の悩みを解決できる」
と納得し、積極的に買う気になる。

「売る」ことと「売り込む」ことは違う。
優れた商品を必要な人に届けるのは正しい行為だ。
むしろ、お客が悩んでいるのに解決策を提案しないほうが不親切といえる。
小さな会社が生き残り、発展していくためには、セールス力を「問題解決力」と捉え直し、訓練によって着実に磨いていくことが必須だ。
セールスに苦手意識を持つ経営者が多いという現実はある。
しかし、マーケティングとセールスの本質を理解し、「問題解決」に基づいて商品を提供すれば、押し売りの後ろめたさを感じる必要などない。
むしろ
「あなたの悩みを解決できる方法がここにある」
という視点で、お客に寄り添う姿勢をアピールすれば、それ自体がお客からの信頼につながる。
売れる仕組を作りたいと考えるなら、まずは「問題解決力」を鍛える。
それこそが、小さな会社が飛躍するための最短ルートだ。
商品の魅力を押し付けるのではなく、相手の悩みや願望をどうすれば満たせるかを考え、わかりやすく伝える
その先にこそ
「売り込まなくても売れる」
世界が待っている。