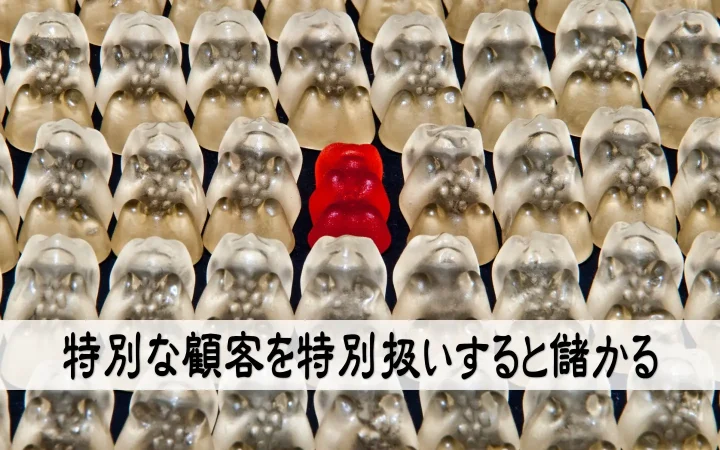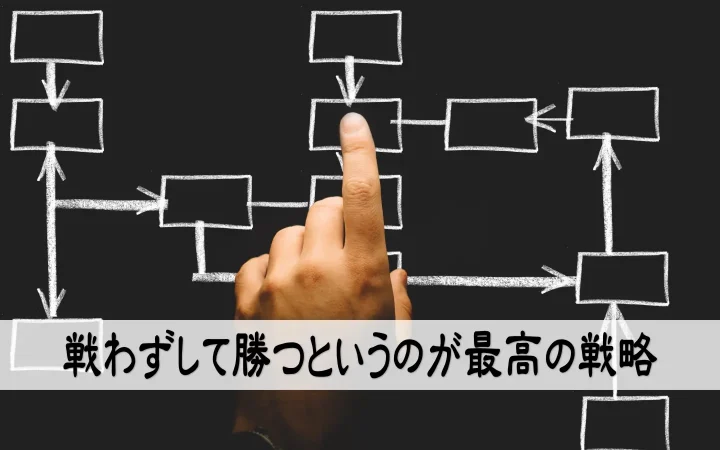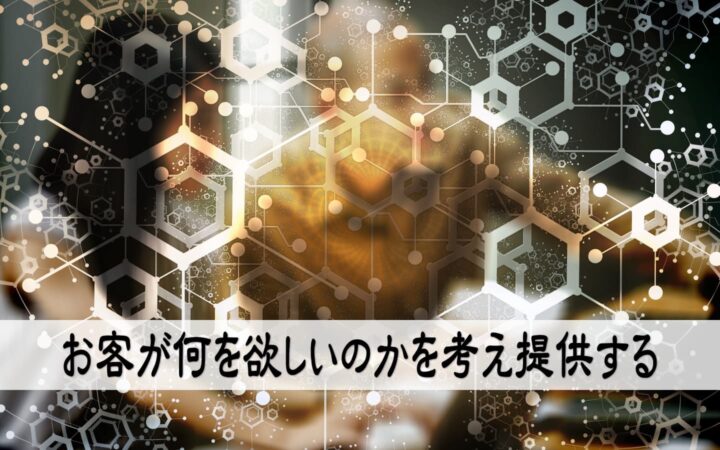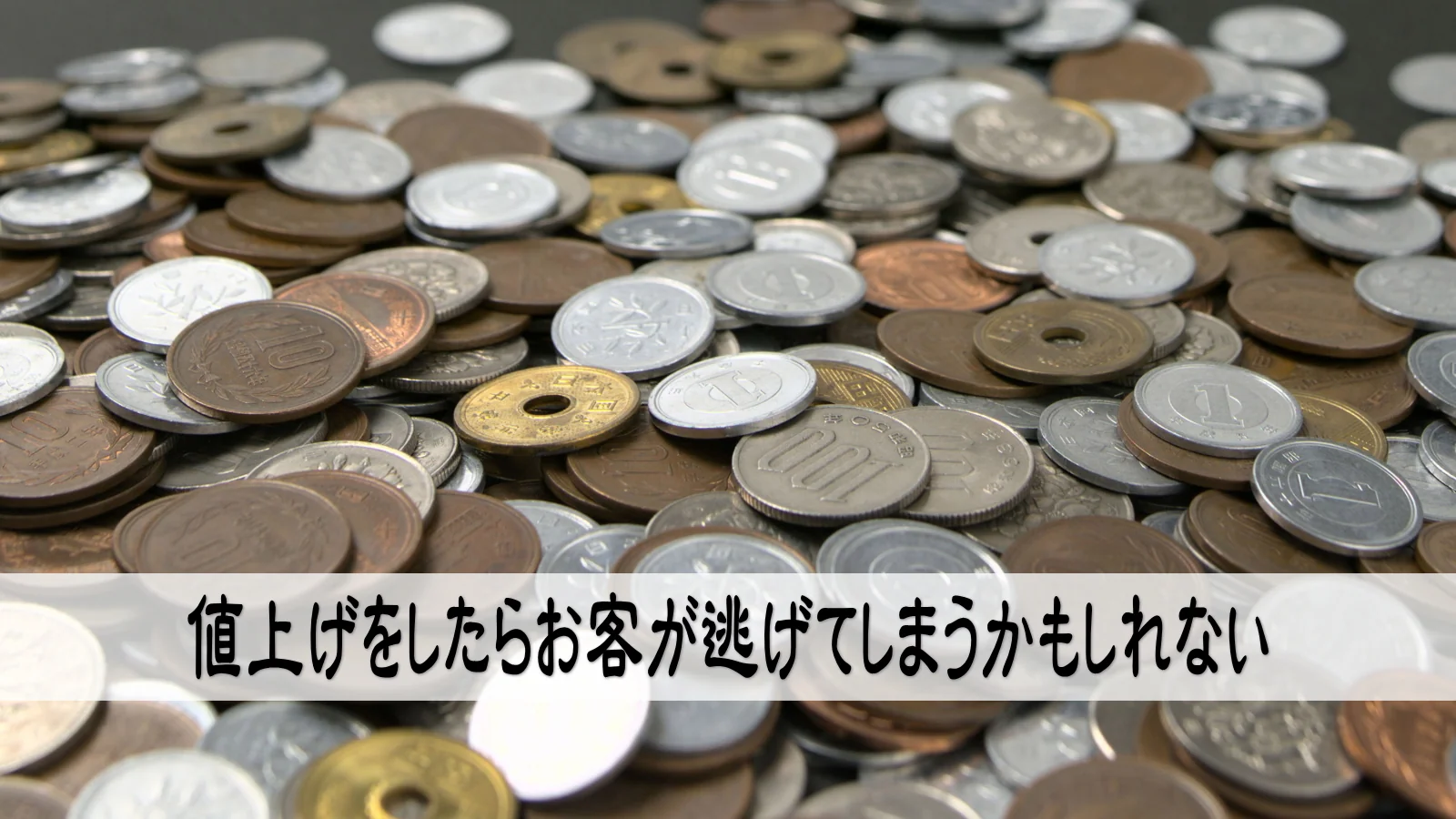
値上げは倒産の原因ではなく、むしろ安売りが企業を苦しめる。コスト上昇を無視し価格を据え置けば、利益が圧迫され、品質が低下し、顧客が離れていく。小さな会社ほど適正な価格戦略が必要だ。値上げを成功させるには、①お客様に納得してもらう説明、②品質向上やサービス強化、③リスク管理とフォローを徹底することが重要。適切な値上げを行い、価値提供型の企業へと進化すれば、価格競争に巻き込まれず、お客様に選ばれ続ける会社になれる。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
いざ値上げをしよう考えると、
「お客が逃げてしまうのではないか」
と心配になる人は多い。
とくに小さな会社では、日頃からお客との距離が近いぶん、その不安はなおさらだ。
小さな会社に値上げが必要な理由
結論から言えば、値段を据え置くことが必ずしも正解とは限らない。
昨今の日本経済は、大企業に優しく中小企業に厳しいと言われている。
円安による原材料費の高騰、人手不足や増税など、あらゆるコストが上がり続ける環境だ。
すると小さな会社ほど利益が圧迫され、自分の生活を守るだけでも苦しくなってしまう。
そのまま無理をして安売りを続ければ、利益率が下がる。
結果的に商品やサービスの質まで落ち、お客にとって魅力のないビジネスへと転落する危険がある。
実は、
「値上げをするから潰れるのではなく、安売りをするから倒産する」
のだ。
必要なタイミングでの適切な値上げは会社の存続にとって欠かせない手段なのだ。
「たった数%上げただけで離れてしまうお客なら、本当に必要な顧客なのか?」
こうした考え方もできる。
もし値上げがきっかけで離脱するお客が多いのであれば、それまであなたの会社が提供してきた価値に対して、十分に理解や共感を得られていない可能性が高い。
つまり、本来のファンやリピーターではなかったかもしれないのだ。
もちろん、値上げをすれば、お客への説明責任が生まれる。
特に小さな会社はブランド力やネームバリューで価格設定がしにくいため、どのように伝えるかがカギになる。
しかし、環境が変わり、コストが上がっているのに価格を変えずにいることは、長い目で見れば会社にとってもお客にとっても不幸な結末を招きかねない。
「値上げするのは悪」
という思い込みをまずは捨て、なぜ値上げが必要なのかを冷静に見つめ直すことが肝要だ。
値上げは、あくまでも会社を健全に運営し、より良い商品やサービスを届けるための選択肢のひとつである。
むしろコスト上昇の煽りをまともに受けながら安売りを続けていれば、いずれ倒産に追い込まれるかもしれない。
だからこそ、小さな会社でも積極的に「価格戦略」を練り上げ、必然性のある値上げを検討することが重要になってくるのだ。
値上げを恐れなくていい理由
値上げを考えると真っ先に浮かぶのが、
「お客の反発」
だろう。
誰しも
「もっと安くしてほしい」
という心理を持っているので、値上げのアナウンスを聞いて喜ぶ人は少ない。
しかし、本当に怖いのは「値上げ」そのものではなく、
「値上げ後のコミュニケーション不足」
にある。
お客が納得できるだけの説明や価値提供がなければ、不満が高まって離脱してしまうのは自然な流れだ。
逆に言えば、納得感さえ得られれば、数%の値上げであれば多くのお客はそこまで強く拒絶しない。
特に日頃からあなたの会社や商品を愛用しているファンやリピーターであれば、
「きちんと理由を説明してくれるなら応援したい」
と思ってくれる可能性は十分にある。
値上げを恐れるのではなく、
「お客がなぜ自社の商品やサービスを選んでいるのか」
を改めて把握するチャンスと捉えるべきだ。

さらに、安売りやサービス過剰を続けることの弊害は深刻だ。
値段を下げるほど自分の首を絞め、結果的にモチベーションやサービスの質も下げてしまう。
お客への対応が雑になったり、仕入れコストを削るために品質を落としたりすれば、顧客満足度も一気に落ち込む。
そうなると悪循環に陥り、結局はさらなる値下げに追い込まれるという、負のスパイラルが待っている。
「値上げ=悪」
という固定観念を捨てることが大切だ。
価格はビジネスにおける重要な武器であり、適正に設定することが生き残りの鍵になる。
そもそも小さな会社ほど、大企業のように大量生産や大規模仕入れによるコストダウンは難しい。
だからこそ、その差を埋めるために値上げを検討し、収益を確保していく必要がある。
大切なのは、むやみに値上げをするのではなく、筋の通った「価格戦略」を打ち立てることにある。
値上げ前に準備を整えておく
値上げを成功させるには、事前準備が欠かせない。
まずは自社の商品やサービスの価値を再確認することだ。
小さな会社ならではの強みは何か、既存のお客から支持されているポイントはどこにあるかを洗い出す。
これがしっかり言語化できていれば、価格の妥当性を説明しやすくなる。
加えて、品質向上やサービス強化の検討も必要だ。
たとえば、材料費の見直しや新しい仕入れ先の開拓、スタッフ教育への投資など、
「値上げ後はこれまでよりもさらに良いサービスを届けられる」
という姿勢を示すことが大事になる。
具体的な行動が伴わなければ、お客にとっては
「ただ値上げするだけ」
に見えてしまい、納得感を得るのは難しい。
準備段階では「情報共有」を怠らないこともポイントだ。
値上げは経営者だけで決めるのではなく、スタッフ全員が同じ認識を持ち、適切に説明できるようにする必要がある。
小さな会社ほど、一人ひとりのスタッフがお客との接点を持っているケースが多い。
そこでスタッフ全員が違う説明をしてしまうと混乱を招く。
経営者は
「なぜ値上げが必要なのか」
「どうして今なのか」
「値上げをすることでどんな価値が生まれるのか」
を徹底的に共有しよう。
さらに、競合や業界の動向も調べておくと安心だ。
他社も同じように原材料費や人件費の上昇を受けて値上げをしているのであれば、お客に
「うちだけ特別に高くするわけではない」
という説得材料になる。
小さな会社だからこそ、世の中の流れをしっかりつかみつつ、自社の価値を見失わないよう準備を重ねていくことが、値上げ成功の第一歩になる。
お客を納得させる値上げの伝え方
値上げの最大のハードルは、お客がどう受け止めるかにある。
ここでは、値上げを案内するときに押さえたいポイントをまとめる。
まず大前提として、お客に対する「納得感」を醸成する必要がある。
そのために、以下の三つを軸に説明するのがおすすめだ。
一つ目は、
「むやみに利益を増やそうとして値上げをしているのではない」
という点を伝えること。
原材料費の高騰や人件費の上昇など、やむを得ない事情がある場合は正直に伝える。
二つ目は、
「本来もっと値上げが必要なところを、お客の負担を抑えるために最小限にとどめている」
という努力を示すこと。
ここに会社としての誠意が表れる。
三つ目は、
「自社だけが特別に値上げしているわけではない」
という事実を示すこと。
業界全体の流れであることを伝えれば、
「そこまで非常識な話ではない」
と思ってもらいやすい。
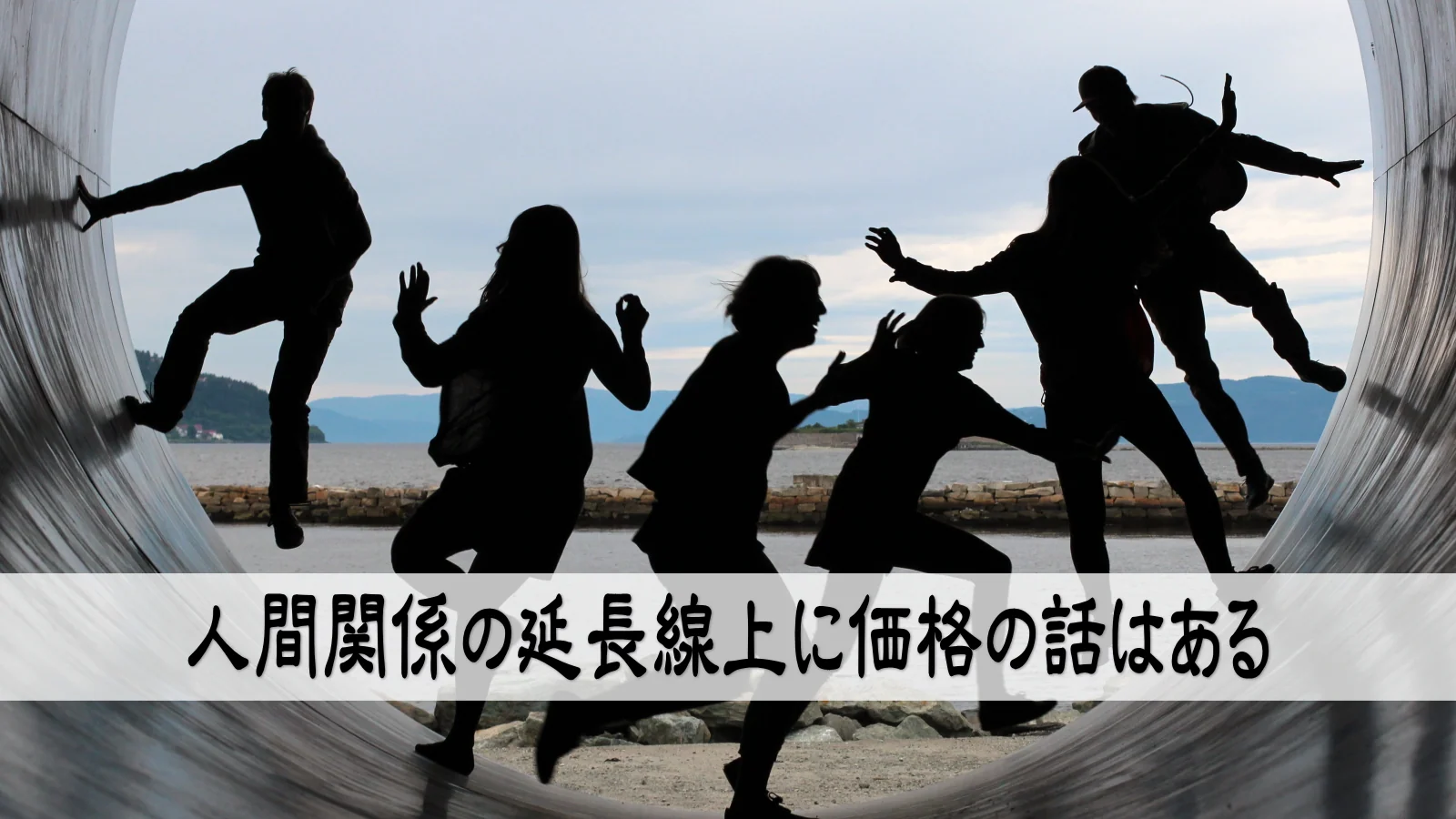
さらに、
「それでも負担が増える分、今後はより高品質なサービスや商品を届けます」
という未来への約束もセットにすると効果的だ。
ただ価格が上がるだけではお客はデメリットしか感じない。
ところが、その先にプラスアルファの価値があると分かれば、納得してくれるお客は多い。
具体的には
「新しい設備を導入する」
「アフターサービスを充実させる」
など、わかりやすい形で示すのがコツだ。
そしてもう一つ大事なのが、コミュニケーションの頻度だ。
普段からお客との接触が少ない会社だと、急に値上げを告げられたときに驚きも反発も大きくなる。
逆に日頃から挨拶やサービス案内を丁寧に行い、何かあれば顔を出して説明しているような関係性であれば、値上げの報告をしても
「あなたが言うなら仕方ないね」
と理解を得やすい。
要は、人間関係の延長線上に価格の話があるというわけだ。
小さな会社値上げ後のリスク対策
値上げを実施した後は、
「本当にお客が離れないか」
「クレームが増えないか」
が気になるところだ。
そこで重要になるのがリスク対策とフォローアップである。
まず値上げ直後はお客の反応を敏感にチェックしよう。
もしクレームがあれば、真摯に耳を傾けて、誤解を解くための説明をすぐに行う。
小さな会社だからこそ、一人ひとりのお客に対してきめ細やかなフォローが可能だ。
また、値上げに伴って離れていくお客もゼロではないかもしれない。
しかし、それはある意味で仕方のないことだ。
コストが上がっている状況で、全員を安価でキープし続けるのは不可能に近い。
むしろ値上げによって生まれた余力を使い、残ってくれたお客により手厚いサービスを提供することに注力するのが得策だ。
値上げ後にやるべきもうひとつの大切なことは、
「継続的な価値提供の見直し」
である。
価格を上げたのだから、今後どんな付加価値をつけていくかを常に考える必要がある。
たとえばイベントを開催して直接意見を聞く、メールやSNSで積極的に情報を発信するなど、定期的なコミュニケーションでお客の満足度を高めていく施策を続けていくとよい。
ここに手を抜くと、
「値上げしておきながら何も変わらないじゃないか」
と不満を持たれるリスクが高まる。
もちろん値上げ直後は不安定な時期だが、だからこそリスク管理を徹底することで、会社の信頼度が格段にアップする。
もしこの時期を乗り越えることができれば、
「この会社は誠実だし、価格が上がってもその分だけの価値を提供してくれる」
とお客に認められるようになる。
つまりリスク対策とフォローアップこそ、値上げを成功に導く大きなカギなのだ。
価値提供型企業を目指す
最終的には
「値上げ後も選ばれ続ける会社」
にならなければ意味がない。
そこで注目したいのが「価値提供型企業」への進化だ。
値段だけで勝負するのではなく、独自の価値をしっかり打ち出し、お客に
「ここじゃなきゃダメだよね」
と思ってもらうことがゴールになる。
価格競争に巻き込まれて安売りを続ける会社が多い中、あえて値上げをすることは、お客にとって
「この会社は何か違う」
「ちゃんと自分たちを大切にしてくれる」
という印象を与えるチャンスでもある。
ただし、そのためには日頃のコミュニケーションや品質管理が欠かせない。
特に小さな会社ほど経営者の顔が見えやすいぶん、人間関係の距離が近い。
その特性を活かして、お客の声に耳を傾け、一緒に商品やサービスを育てていく姿勢を示すとよい。

値上げには、会社をしっかり支えるための「価格戦略」という側面だけでなく、企業が持つ「価値観」をお客と共有するためのきっかけという一面もある。
「わが社は適正価格で最高の品質を提供したい。そのためにどうしてもこの価格にならざるを得ないんです」
という姿勢を真摯に伝えれば、共感してくれる人は必ずいる。
そして何より、無理なく安定的に利益を出せる仕組みを作ることで、サービス体制にも余裕が生まれる。
結局はその余裕がさらなる品質向上や顧客満足につながり、ポジティブな連鎖を生むのだ。
小さな会社であっても
「価値提供型企業」
を目指す姿勢があれば、値上げ後もお客に選ばれ続ける存在となる。
逆に安売りを続けて疲弊し、
「値上げをするから潰れるのではなく、安売りをするから倒産する」
という最悪のシナリオにはまり込まないためにも、一歩勇気を出して価格を見直すことが未来を変える鍵になるのだ。