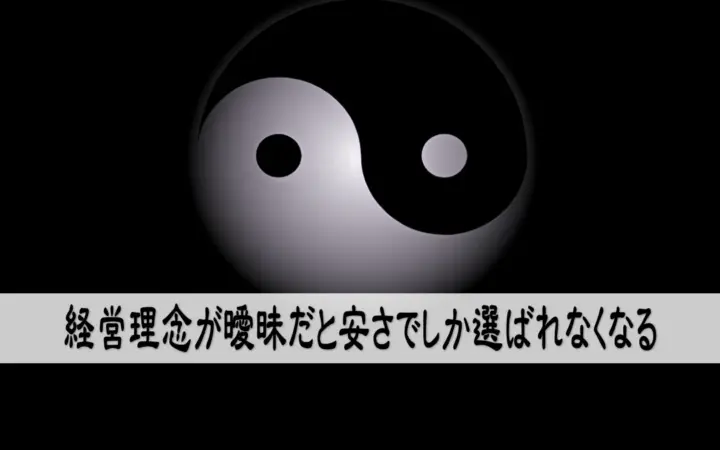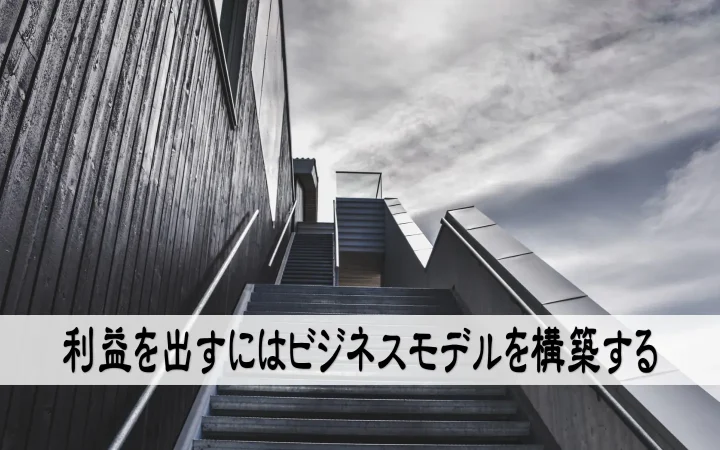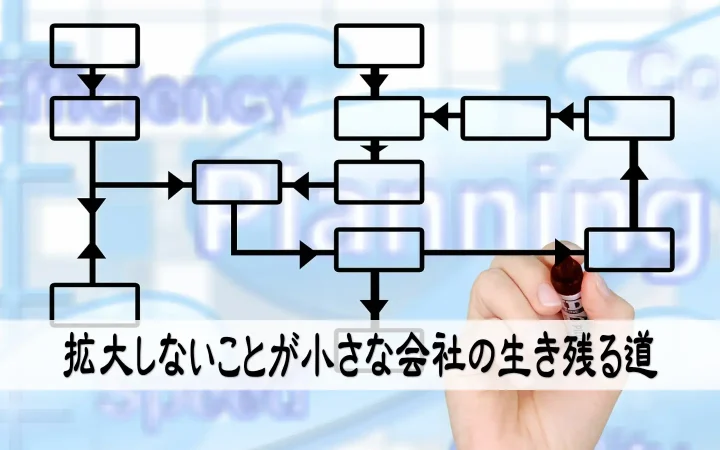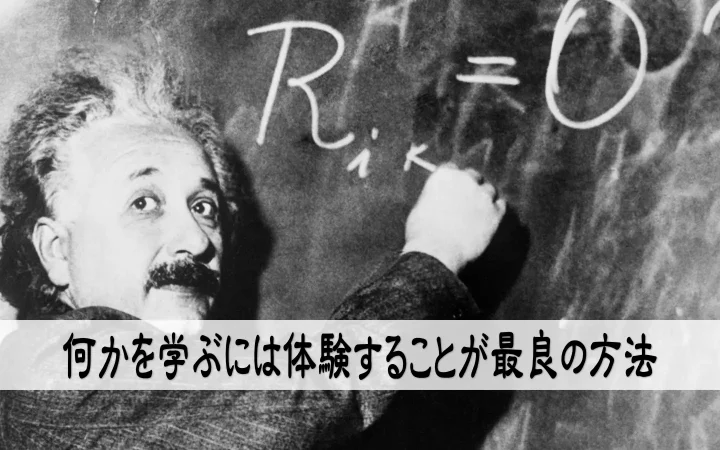「好きなこと」を仕事にするのは魅力的だが、現実との擦り合わせなしでは失敗しやすい。ラーメン屋と蕎麦屋を比較すると、蕎麦屋のほうが客単価が高く、原価やランニングコストも低いため失敗しにくい。中高年の起業には、体力・資金・競争環境を踏まえた「失敗しない選択」が重要だ。理想だけでなく数字で現実を見ることで、スモールビジネスは成功に近づく。経営とは、やりたいことと現実を丁寧に擦り合わせる技術なのである。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
「好きなこと」を商売にするのは素敵に聞こえる。しかし、実際には好きだけで突き進むと痛い目を見る。特に50歳以上の中高年がスモールビジネスを始める場合は、より一層の注意が必要だ。若いころのように体力任せでやれるわけではなく、やみくもにリスクを取ることも難しい。だからこそ、やりたいことと現実の状況をきちんと擦り合わせる作業が欠かせない。
“好き”を仕事にする落とし穴
私自身、セミナーやコンサルティングを通じて多くの会社の起業や再生に関わってきた。その経験からも、「私は○○が好きだから○○業をやりたい」という経営者が意外に多いと感じる。もちろん好きであることは大きな強みだ。好きだからこそ情熱が湧き、たとえしんどいときでも踏ん張れる。だが、それだけでは商売は成り立たない。商売には利益が必要であり、利益を生み出すには顧客ニーズや市場規模という現実を無視できないからだ。
たとえば、「大のラーメン好きだからラーメン店を開く」という発想は自然だが、本当に儲かるかどうかは別問題だ。好きなことをやるだけなら趣味で終わってしまう。ビジネスとして継続するには失敗しないための戦略が重要になる。特に飲食業は厳しい世界。日々の仕込みや原材料費、競合店との価格競争など、思った以上にハードルが高い要素がそろっている。
理想と現実は時に大きくかけ離れる。やりたいことを実現しつつ、どうすれば失敗を回避できるか。そこを考え抜くことこそ、中高年の起業で最も大切なポイントだ。いわば、「好き」を生かすためには「数字」と「戦略」をしっかり押さえなければならない。好きなことをただの道楽に終わらせず、しっかりした商売にするにはどうすればいいか。まずは、その落とし穴がどこにあるかを冷静に見つめるところからスタートしよう。
蕎麦屋とラーメン屋の損得勘定
飲食業、とりわけ「ラーメン屋か蕎麦屋か」という選択は、よくあるテーマだ。多くの場合、単純に「ラーメンが好き」「蕎麦が好き」で決めがちだが、損得勘定で見ると意外なほど差がつく。そこで、まずは客単価の違いに注目してみたい。
ラーメン屋を想像してみると、ラーメン一杯は800円前後から始まり、少し上乗せして餃子やビールを注文しても一人あたり1500円に届くかどうか。一方、蕎麦屋の場合は、手打ち蕎麦そのものに高級感があるため、軽く1000円は超える。天ぷらや日本酒を合わせれば2000円ぐらいになることも珍しくない。たかが数百円の差かもしれないが、この積み重ねはビジネスにとって大きい。

さらに、ラーメン屋の厳しさは仕込みコストに表れる。豚骨スープをじっくり煮込むならば、その時間と光熱費は馬鹿にならない。油が飛び散るために掃除が大変で、業務用換気設備も高コスト。しかも、参入障壁がそれほど高くないため、周囲にもライバル店が増えがちだ。価格競争が激化する中、客単価を上げようにも競合店が安い価格で勝負してくるのでなかなか難しい。
蕎麦屋の場合はどうだろう。山の中の古民家で蕎麦を打つ光景を思い浮かべる人は多いだろうが、実際それが集客の強みになり得る。土地や家賃の負担が都会ほどかからず、自然の雰囲気も一種のブランドとなる。清掃の負担もラーメン店ほどはないし、設備コストも低め。しかも単価が高めで利益率もそこそこ良い。こうした数値的根拠からしても、蕎麦屋のほうが失敗しにくいのは頷ける話だ。
飲食業の失敗要因を見極める
飲食業で大切なのは、いかに失敗しないかを真っ先に考えることだ。やりたいことを実現するのは素晴らしいが、潰れてしまっては元も子もない。特にラーメン屋は「あと4~500円高く売れないと利益が出にくい」といわれるほど、コストに対して価格設定が追いついていない。これはスープの仕込みや光熱費の高さ、油汚れの対策などが直接響いてくるためだ。
しかも、ラーメン屋は競合が多い分だけ、味の工夫や特別なサービスだけではカバーしきれない要素がある。価格を上げると「高い」と言われ、下げると利益が出ない。市場原理がシビアに働くのがラーメン業界の怖いところだ。結局、高い原価率と熾烈な価格競争の板挟みになるため、一定以上の利益を維持するのが難しい。
一方で、蕎麦屋は比較的コストを抑えつつ、客単価を高めに設定しやすい。なぜなら、蕎麦は「風味や喉越しを味わう高級食」のイメージがあるからだ。山奥にある古民家蕎麦屋など、観光地化した場所も少なくない。むしろ、そうした立地が強みになり、初期投資も抑えられて一石二鳥だ。こうした「現実」を冷静に見極めず、「好き」の勢いだけで突き進むと危険極まりない。
飲食業は、ただでさえ準備段階でお金がかかる。店舗物件の契約や内装工事、厨房設備、さらには人件費も先に支払わねばならない。そこに追い打ちをかけるように、仕込みや清掃などのランニングコストが重くのしかかる業態を選んだら、薄氷の経営になりかねない。「好きだからやりたい」は大事だが、まずは失敗要因を取り除く努力が欠かせない。
中高年にこそ蕎麦屋が適する訳
蕎麦屋は、50歳以上のスモールビジネス経営者にこそ向いているといえる。理由はいくつもあるが、まず挙げたいのは体力面だ。ラーメン屋は仕込みが激務でハードな作業が多い。一方で、蕎麦屋は丁寧にそばを打つ作業こそあるものの、スープを長時間煮込むなどの過酷な工程は少ない。清掃の手間や油汚れの対応も少なく、比較的落ち着いた環境で営業しやすい。
また、地域の古い物件や空き家を活用できるのも蕎麦屋の魅力。山あいの静かな立地で「わざわざ行きたい店」を演出するのは、蕎麦屋ならではのブランド力がある。田舎や郊外の空き家を安価で借り受け、古民家風に改装すれば、都会では得られない風情が生まれる。地代や家賃を抑えられれば、ランニングコストも自ずと少なくなる。

しかも、蕎麦屋は客単価が高いため、無理に大量のお客さんを捌かなくても成り立つビジネスになりやすい。ゆったりとした店の雰囲気で少し値段が張るメニューを提供し、そこに日本酒や天ぷらをプラスすれば客単価は2000円前後まで上昇する。中高年経営者にとって、無茶な拡大路線に走らずとも安定した収益を確保できるのは大きな魅力だ。
ラーメン屋はファーストフード的な要素も強く、回転率が勝負になることが多い。しかし、中高年で起業するなら、ゆったりとした空間を提供しながら適切な価格を設定し、少ないお客さんでも十分にやっていけるスタイルを確立したほうが体にも心にも優しい。そうした点で、蕎麦屋は「やりたいこと」と「現実」とを両立しやすい飲食業態といえる。
理想と現実を丁寧に擦り合わせる
経営とは、理想と現実のギャップをどう埋めるかが勝負どころだ。やりたいことを思いっきりやるのは気持ちがいいが、現実の資金や市場のニーズと噛み合わないと失敗の確率が一気に上がる。「好き」を形にするために必要な仕入れコスト、人件費、売上予想を冷静にシミュレーションすることが肝心だ。
飲食業であれば、店の立地、客層、価格帯、さらにはライバルの存在を調査しないまま開業すると、痛い目を見る可能性が高い。思い込みだけで「ここならいける」と賭けに出てしまう人が多いのも事実。特に50歳以上で初めて起業するケースでは、勢いがありすぎても考えすぎてもバランスを崩しやすい。だからこそ、専門家や先輩経営者に相談し、数字で検証するプロセスが大切になる。
実際に起業前に試算してみると、「理想よりもずっと初期費用がかかる」「想定より客単価が低い」といった現実が出てくることも少なくない。そこで軌道修正できればいいが、「やりたい気持ち」が強すぎると、つい見通しを甘くして突き進んでしまう。商売が上手くいくコツは、何より「どうすれば失敗しないか」を合わせて考えることだ。
趣味とビジネスは似て非なるもの。とはいえ、まったく好きでもないことを仕事にしては続かない。「好き」という燃料と「現実」という地図をうまく照合し、失敗しにくい道筋を選ぶ。そうすれば、飲食業でも安定したスモールビジネス経営が見えてくる。最終的に長く続けるためには、理想と現実を丁寧に擦り合わせる技術が欠かせないのだ。
失敗しない起業こそ成功への近道
多くの人は「成功するために起業する」と考える。しかし本当に大事なのは、「どうすれば失敗を回避できるか」を突き詰めることだ。失敗をしないということは、そのまま成功の確率を高めることにつながる。特に飲食業、そして中高年のスモールビジネス経営においては、余計な遠回りをせずに堅実な道を選ぶほうがいい。
たとえば、ラーメン屋か蕎麦屋かで悩むのであれば、蕎麦屋のほうがコスト面でも客単価面でも安定していることが明らかだ。それなら、まずは失敗しにくい蕎麦屋という選択肢を検討し、「どうすればうまくいくだろうか」とプラスに考えるほうが賢い。日本酒や天ぷら、地元産の野菜や山菜などをうまく組み合わせ、「ここだけの味」を演出すれば、価格を下げなくても十分に支持される店づくりが可能だ。

もちろん、すべての人が蕎麦屋をやればいいという話ではない。大切なのは、やりたいことと市場のリアルをすり合わせ、失敗リスクを最小限に抑える視点を持つこと。仮にラーメン屋を選ぶなら、明確な差別化や効率的な仕組みづくりが必要になるし、他店との差を徹底的にアピールする工夫が欠かせない。いずれにせよ、「これなら勝負できる」と確信できる材料が欲しい。
最後に強調したいのは、「失敗しない」ことが決して消極的な姿勢ではないという点だ。むしろ「攻めるための守り」こそが成功の近道である。年齢を重ねた経営者なら、人生経験や人脈を活かして、より慎重かつ粋に商売を育てることが可能だ。しっかり稼ぎつつ自分らしく楽しめる道を選べば、仕事を道楽のように感じる瞬間さえ訪れるだろう。
結局、商売が上手くいくコツは、やりたいことをやるだけではなく、どうすれば失敗しないかを合わせて考えることにある。失敗を避けるということは、そのまま成功の確率を上げる。中高年であっても遅すぎることはない。しっかりと数字を把握し、周囲の声に耳を傾け、堅実なスタートを切る。そうして失敗のリスクを抑えることこそ、結果的に長く続けられる商売、そして人生の質を高める経営につながるのだ。