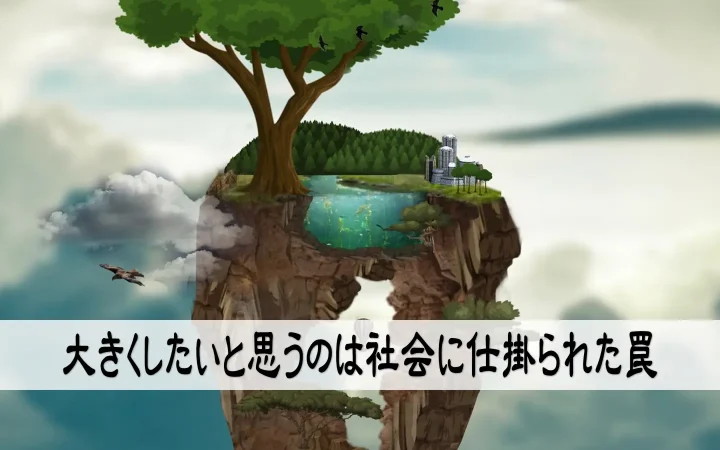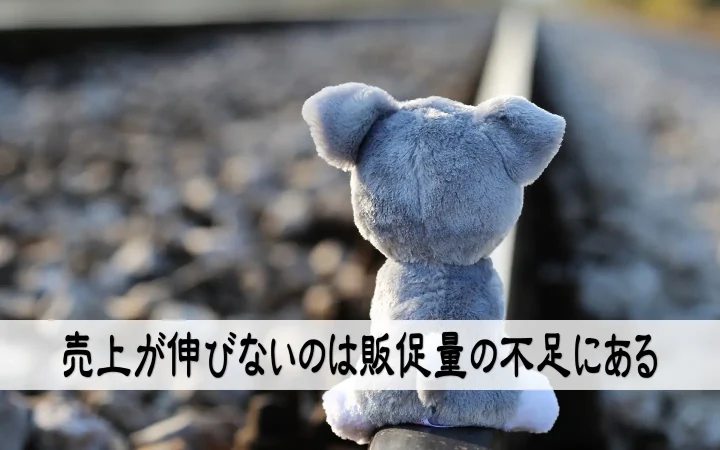スモールビジネスが値引きに走るのは客数を増やしたいからだが、実際には利益が減り、常連客が離れ、サービスも低下する「負のスパイラル」に陥りやすい。値引きは一時的な効果しかなく、価格目当ての客は定着しにくい。長く安定した経営には、安さでなく「価値」で勝負することが重要。自社ならではの魅力を磨き、価格競争から抜け出すことで、忙しくても儲からない状況を脱却し、無理なく繁盛するビジネスを目指すべきである。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
値引きで「一時的に客数を増やす」という発想は、多くのスモールビジネス経営者にとって魅力的に映る。特に50歳以上の方の中には「昔から安売りがいちばん手っ取り早い」と言い聞かせてきた経験もあるだろう。実際、キャンペーンを打ったり、チラシやDMをばらまいたりして値段を下げると、新規のお客さんが増えるケースは少なくない。
値引きが生む落とし穴を見抜く
だが、安易に値引きに走ると、売上や利益が思ったほど伸びず、逆に「忙しいのに儲からない」という事態に陥るのが実情だ。たとえば、4,000円の商品を3,000円に下げて売ってみると、「客数は増えたのに、トータルの売上は意外に伸びない」という現象が起こりやすい。この種の失敗は経営者の年齢を問わず頻発するが、長年の勘や経験に頼る50代以上の方こそ、改めて数字で検証する姿勢が大切になってくる。
実は、値引きによる売上の増加は単純には比例しない。「客数が2倍になれば売上が2倍になる」と思い込みやすいが、値段を下げた時点で客単価が落ちてしまう。すると、定価のときと同じ額を稼ごうとするなら、従来以上に多くの客数を集めなければならない。これは利益面ではさらに顕著だ。原価2,000円の商品を4,000円で売れば2,000円の儲けだが、3,000円に下げると儲けは1,000円しか残らない。単純計算でも2倍売ってようやく同じ利益になるのだから、よほどの集客力がなければ追いつかない。
それでも値引きの罠にはまりやすいのは、「すぐにお客さんが増えた」という手応えを得やすいからだろう。だが、その一時的な盛り上がりを過信しすぎると、実は大きな落とし穴が待ち受けている。とりわけ、長く商売を続けてきた人ほど「いつものやり方」に固執してしまいがちだが、そこにこそ大きなリスクが潜んでいるのだ。
数字が示す値引きの残念な現実
「値引きで増えるのは客数だけかもしれない」。この事実を知るには、少しばかりの数字の裏付けが必要になる。たとえば先ほどの例で、4,000円の商品を3,000円に値下げしたとき、単価が1,000円落ちるわけだ。客数が2倍に増えたとしても、3,000円×2で売上は6,000円。定価で1名に売ったときの4,000円とは違って、2倍の数売っても単純に2倍の売上になるわけではない。
さらに恐ろしいのは利益だ。原価が2,000円なら、4,000円で売ると利益2,000円。3,000円で売ると1,000円しか残らないから、利益が半減してしまう。同じ利益を得るためには、最低でも2倍の客を呼び込まなくてはならなくなる。もし「今までより2倍儲けたい」と欲をかけば、4倍もの客数増が必要となる計算になる。
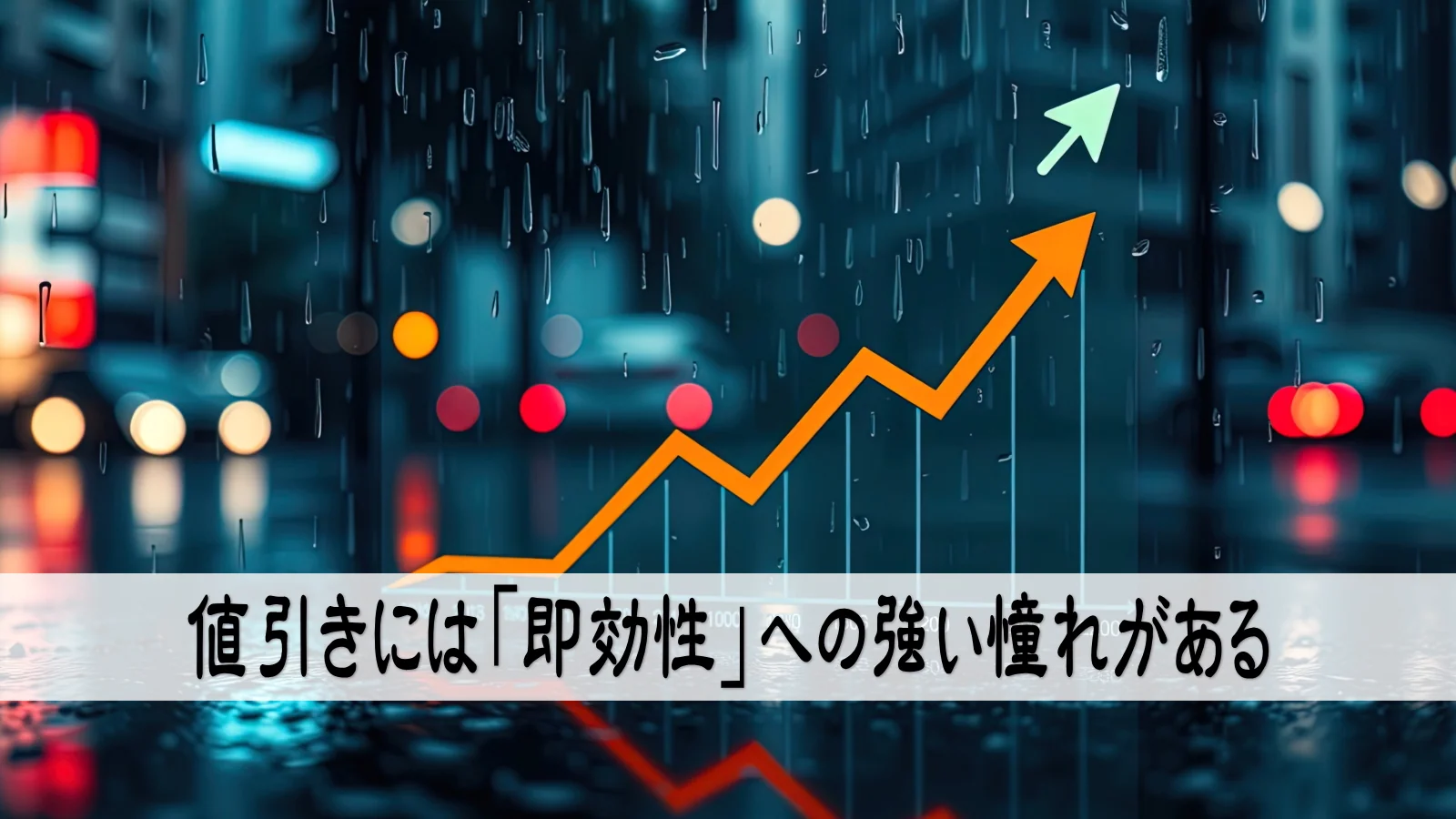
多くの経営者は「いや、そこまで客が増えるとは思えないけど・・・」と内心でわかっているのかもしれない。にもかかわらず「でも安売りすれば、そこそこ来るはず」と期待を寄せてしまう。その根底には「即効性」への強い憧れがあるのだろう。「売上が落ちてきたら、とりあえず値段を下げる」というやり方は確かに手っ取り早い。しかし、それは「短期決戦」には強いが、「長期戦」に弱い打ち手でもある。
しかも、値引きした商品ばかりが目立つようになると、「安く買いたい」という層が集まり始める。一時的に売上が上がっても、リピーターにならないまま去っていく可能性が高いのが、値段だけを求めるお客さんの特徴だ。そうなると「また値引きしなければ集客できない」ループに陥りやすい。これが長く続けば、経営者自身のメンタルにも大きな負担がかかる。
客数を追うと失う大切なもの
値引きが呼び寄せるのは、客数だけではない。実は、客の「質」にも変化が起こる。たとえば、従来の常連さんは「こだわりの商品がある」「ゆっくりくつろげる雰囲気が好き」といった理由で店を選んでいたかもしれない。ところが、値段を下げて客数を増やすと、お店や会社の雰囲気が一変する恐れがある。
安さに惹かれて新しいお客さんが殺到すると、店内はにぎわって「何だか活気がある」と一見は見える。だが、売価が下がって利益が減れば、そのぶん多くの商品やサービスを提供しなければ同じ利益をキープできない。店側はてんてこ舞いになることもあり、常連客への対応にしわ寄せがいく。
「いつもよりスタッフが忙しそうで、居心地が悪かった」「少し高くてもここは落ち着けるのが魅力だったのに・・・」といった声が上がると、常連は徐々に離れていく。しかも、常連の客単価は高めで、口コミ力もある。そうした大切な存在を失うリスクを見過ごしたまま、目の前の“お手軽な売上”を追ってしまうのが、値引き戦略の怖いところだ。
さらに、短期的な増客に浮かれた結果、お店全体のサービスレベルが低下すれば、せっかく来店した新規客も「思ったより居心地が悪い」と感じてリピートしないケースが多い。こうして「客数を増やしたはずなのに、なぜか売上が安定しない」と悩むようになり、気がつけば経営者自身も疲弊する。
負の連鎖が襲うスモールビジネス
値引きには、いわゆる負のスパイラルがつきまとう。「値下げして集客→一時的に忙しくなる→利益は思ったほど増えない→常連が離れる→売上が下がる→さらに値下げで集客…」といった連鎖は、企業規模に関係なく起こりうる。スモールビジネスの場合、資金力も人員も潤沢でないことが多いため、この連鎖にはとくに注意が必要だ。
値引きで集まるお客さんは「安いから買う」というモチベーションが強い。そのため、もっと安い店やサービスがあればそちらに移るリスクが高い。固定客になりづらいお客さんばかりを集めても、中長期的には利益に結びつかないのだ。

また、値引きキャンペーンを継続すると「いつも割引しているイメージ」が定着してしまい、正規の価格に戻した途端にお客さんが離れるケースも少なくない。そうなると「また割引券を配らないと誰も来ない」という状態に追い込まれがちだ。
一時的な売上アップを目的とした「値引きDM」「割引クーポン」は、確かに効果を実感しやすい。しかし、それが常態化すると、「値下げ合戦」に参加するしか選択肢がなくなる。すると経営者は自社の強み(USP)やサービス品質の向上に投資できなくなり、事業全体の魅力が薄れていく。
最悪の場合、「客数はそこそこなのに利益が出ない」というまま資金が枯渇し、倒産してしまうことさえある。目先の客数にとらわれ過ぎると、気づいたときには「もう後戻りできない」状態になりかねない。
値引きに頼らない集客のカギ
それでも「値引きは絶対だめ」とは言い切れないのが現実だ。経営者としては、資金繰りに苦しむ緊急事態では応急処置が必要になるし、在庫処分などで一時的に値下げをする場面もある。だからこそ「値引きを使うなら最小限に」を徹底する工夫が大事になる。
たとえば、値下げだけでなく「商品やサービスの価値をしっかり伝える」アプローチを取り入れるのは有効だ。「ここでしか手に入らない」「職人がこだわり抜いて作っている」「特別な体験ができる」といった情報を丁寧に発信する。こうした背景を知れば「少しくらい高くても、ここがいい」と思う人は必ず存在する。特に50歳以上の経営者は豊富な経験や人脈を持っているケースが多い。それを活かして、自社や自店ならではの魅力を再定義してみてほしい。
また、「背中を押す最後の手段」として、限定的な値引きを提案するのも一つの方法だ。たとえば初回限定のお試し価格や、リピートしたくなるような特典の付与など、条件や期間をしっかり絞って「価値を感じてもらうための導入」として活用する。そうすることで、お客さんは「安いから行く」ではなく「試してみてよかったから通う」という意識に変わりやすい。
さらに重要なのは、値引きではなく「お客さんへの細やかな配慮やサービス強化」に力を注ぐことだ。人手が足りないと感じるなら、数を追うよりも顧客満足度を上げる施策に時間と予算を振り向ける。そうした取り組みが評判を呼び、少しずつ安定した売上につながるという好循環を生み出す。
価格競争を脱し商品価値で勝つ
「価格で勝負するのではなく、価値で勝つ」という姿勢が、スモールビジネスが長く繁盛するうえで欠かせない。特に50歳以上の経営者には、人生経験や業界の知恵が蓄積されている。これを最大限に活かし、「ここは値段云々ではなく、○○がすごい」と言われる存在感をつくることが大切だ。
価格競争から抜け出すために、まず「なぜ自分の店や会社を選んでほしいのか」を言語化してみよう。お客さんが本当に求めているのは「安さ」だけではない。たとえば「落ち着ける空間」や「信頼できる専門知識」「心地よいコミュニケーション」「気軽に相談できる雰囲気」など、値段以外の理由で来店・利用を決める人は多い。

「値引きゼロでも売れる企業なんてあるの?」と疑問に思うかもしれないが、現実には値引き無しで繁盛している小規模店舗は存在する。そこでは「自社だけの価値づくり」が徹底されているのだ。もちろん地道な努力が必要だが、「気がつけば常連客が増えていて、無理なく利益が出る状態」が理想的なゴールになるだろう。
スモールビジネスで長く安定した経営を続けるには、「値段の安さ」ではなく「ここにしかない価値」を育てることが肝心だ。値引きに走るのは一瞬でできるが、その先に待っているのは「忙しいのに儲からない」もどかしさかもしれない。50歳以上の経営者こそ、これまで培ってきた人生経験や強みを活かし、お客さんとの絆を深めるビジネスを目指してほしい。数ある選択肢の中でも「ここじゃなきゃダメなんだ」と思ってもらうための磨き上げこそが、長期的に経営を安定させる最大のポイントになる。
値引きは確かに即効性がある。しかし、長い視点で見れば、価格競争に振り回され続けるのはリスキーだ。売上アップを目指すだけでなく、利益を確保しながらお客さんとの良い関係を築いていくには、「価値で勝負する」という発想が欠かせない。50歳を超えた今だからこそ、自身の人生の質を優先しつつ、仕事をもっと楽しみ、無理なく長く続けていくためにも、値引きだけに頼らない戦略を考えてみてはどうだろうか。