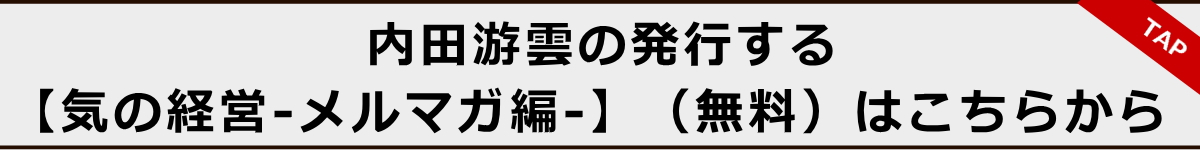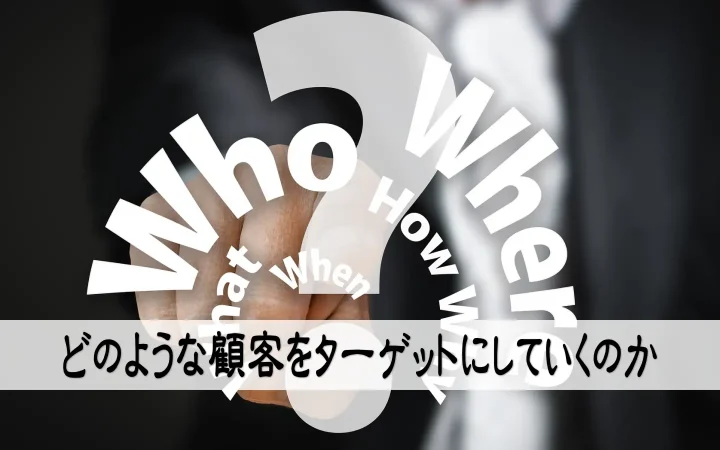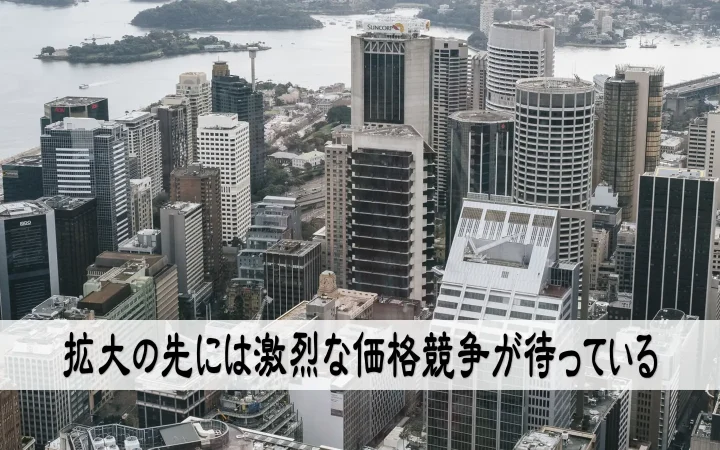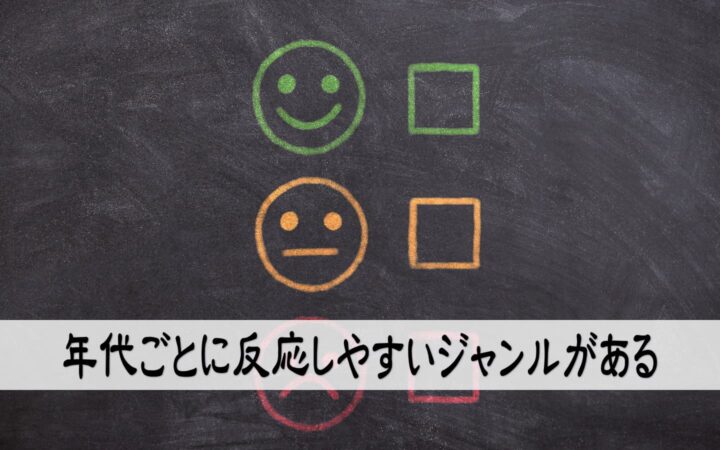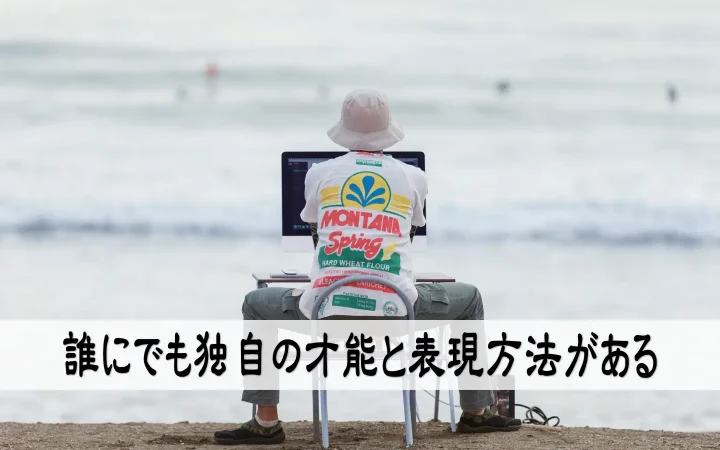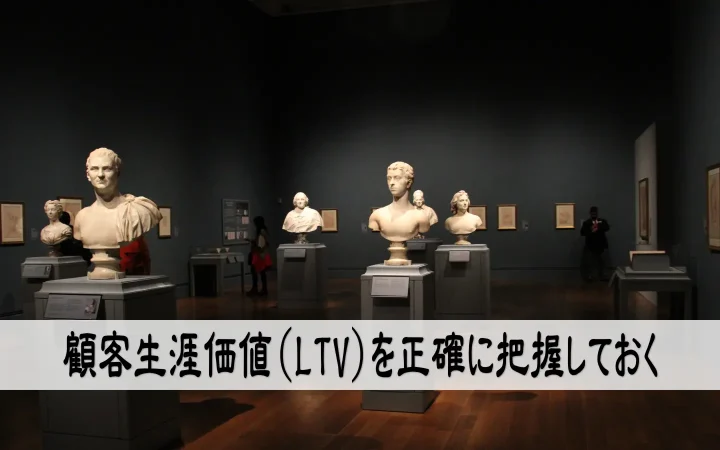儲かる会社には、共通するシンプルな仕組みがある。商売の目的は「長期的利益」であり、ターゲットを明確にし、やるべき順番を間違えずに経営を丁寧に整えること。この3つが揃えば、小さな会社でも無理なく利益体質をつくることができる。反対に、目的を見失い、集客や広告を優先して順番を飛ばせば、売れても残らず、疲弊する経営になる。才能や時流に頼らず、基本を地道に積み上げた会社だけが、最後に“ちゃんと儲かる”のである。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
商売の目的を見誤った会社は、どれだけ集客しても長期的利益にはつながらない。
儲からない会社の共通点とは
『努力しているのに報われないのは、“経営の目的”を見失っているからだ』
本気でやっているのに、なぜか儲からない。
SNSも毎日更新し、チラシも丁寧につくり、接客も手を抜いていない。それなのに、口座残高は一向に増えず、経費の引き落としだけが正確に働く。こういう経営者の多くが見落としているのは、「自分の商売の目的が何なのか?」という問いだ。
商売とは、売ることではない。集めることでもない。残すことだ。
売上から原価を引き、経費を差し引いて、それでも残った“利益”こそが目的であり、そこからしか事業は続かない。そしてこの「利益」という目的を長期的に積み重ねること。これが商売の王道である。
だが、目先の売上を追いすぎると、集客が目的になってしまう。とにかく人を呼ぼう、反応を増やそう、PVを稼ごう。気づけば、売る相手も、売る理由も曖昧になり、「人は来るのに売れない」「売ってるのに儲からない」というミステリーが始まる。
実はミステリーでもなんでもなく、原因はシンプルだ。手段が目的化しているのである。目的地を忘れた旅人は、どんなに早足でも遠ざかるだけ。経営もまったく同じで、どこへ向かっているのかが曖昧なままでは、利益というゴールにたどり着けない。
広告を出す。SNSを頑張る。接客を磨く。どれも悪くない。ただし、その行動が「何のためなのか」を忘れたら意味がなくなる。手段は手段として、利益を残すために選び取るべきだ。そこに意識があるかどうかで、結果が大きく分かれる。
儲かっている会社は、実に静かで堅実だ。派手さはなくても、やることはブレない。
やらなくていいことをやらないし、やるべきことをきっちりやる。理由はただひとつ、すべての判断基準が「長期的な利益」に結びついているからである。
商売の基本は、目的を見失わないこと。まずはここから立て直すだけで、経営はしっかりと“残る道”を歩み始める。
どれだけ動いても儲からないときは、順番と構造に原因があることが多い。どれだけ動いても儲からないときは、順番と構造に原因があることが多い。経営の土台が整えば、商売の無駄が減り、利益が自然と残りはじめる。まず整えるべき視点はこちら。▶「経営の土台づくり」
儲かる会社は順番を間違えない
『何から手をつけるかで、会社の未来は9割決まる。順番こそが最強の経営戦略である』
儲かる会社の特徴は、すべての経営活動に優先順位をつけ、長期的利益に向けて整えている点にある。
商売において、やるべきことは山ほどある。商品を磨く。チラシを撒く。ブログを書く。ホームページを整える。SNSを動かす。お客様にDMを送る。どれも大切だが、「全部やろう」とすると、たいてい何一つ成果につながらない。
儲かる会社がやっているのは、全部ではない。「いま、これをやるべきだ」という順番が明確で、それに沿って動いているだけだ。
逆に、うまくいっていない会社ほど、「とりあえず目立とう」「広告を出せば売れるだろう」と、順番を飛ばして華やかな手段に走る。だが、経営は料理と同じで、いきなり火にかけても、下ごしらえができていなければ台無しになる。
まず整えるべきは、お客の動線と利益の構造である。どんなお客に、どの商品を、どんな価格で、どう届けるか。それが見えていないのに「アクセス数」や「フォロワー数」ばかり気にしても、結局お金が残らない。
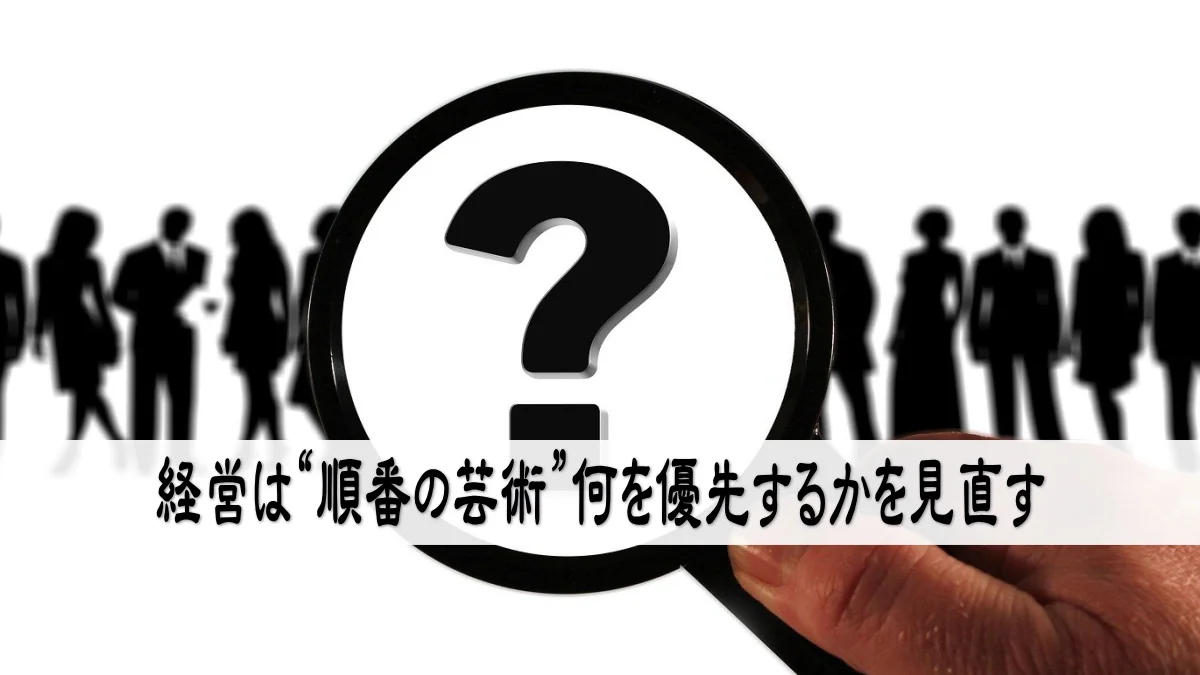
「売上が減ってきたから、とにかく集客を」と考えた瞬間から、順番は崩れる。先にやるべきは“売れない理由”の分析と、構造の見直しだ。たとえば、売っても利益が出ない価格設定になっていないか。来てほしくない層にばかりアプローチしていないか。根本的なズレに気づかないまま集客を強化しても、苦しさは増すばかりだ。
儲かっている会社ほど、すべてに段取りがある。いきなり「売ろう」としない。まずは整え、磨き、届ける準備をしてから、一手ずつ積み上げていく。見た目は地味でも、利益はしっかりついてくる。
経営は“順番の芸術”である。焦るときほど、何を優先すべきかを見直すことで、逆にスピードが上がる。やみくもに動くより、順序を整えて動くほうが、結果は早く、深く、確実に出る。
「まず集める」では儲からない。集客の前に整えるべき順番と仕組みを見直すことで、ムダな動きが減り、利益につながる流れが生まれる。▶「集客の順番」
ターゲット不明では儲からない
『“誰のための商売か”を定めなければ、利益は確実に遠ざかる』
顧客ターゲットが明確でない経営は、的外れな集客と値引き競争に追われ、売れない理由から抜け出せない。
「うちは誰でも歓迎です」「とにかく人が来てくれれば」。この発想が、儲からない地獄の入口である。
本当に来てほしいのは誰か?その問いに答えられないままチラシを撒き、SNSを動かし、ブログを書いても、それは“誰にも刺さらない商売の独り言”になってしまう。
儲かる会社は、ターゲットが具体的である。性別、年齢、趣味嗜好、価値観、支払い能力、そして何より“どんな悩みを持っているか”を言語化している。そのうえで、「この人にこれを届けたい」と考えて商品や伝え方を設計しているから、自然と選ばれる。
反対にターゲットがぼやけた経営は、集客そのものがズレていく。たとえば、高品質な商品を安売りして「安さ」で来るお客を引き寄せれば、価格しか見ていない人ばかりになる。結果、値引きに依存し、利益が残らず、疲弊する商売が完成する。
理想の顧客は誰か。これは絞るほどラクになる問いだ。来てほしい人が見えれば、「その人はどこにいるか」「どれくらい払えるか」「何を魅力に感じるか」が明確になる。すると、発信の内容も、言葉のトーンも、価格設定もブレなくなり、無駄が消える。
売上が上がらないとき、「もっと集めよう」と考える前に、「今のお客は誰か」を見直すべきである。
その上で、「本当は誰に来てほしいのか」「その人に届く工夫をしているか」を確認すれば、集客のやり方も、販促の優先順位も自然に変わっていく。
なお、ターゲットを絞ることは“誰かを排除する”ことではない。“一番伝えたい人”を決めることだ。万人受けを狙ったメッセージは、誰の心にも届かない。言葉が刺さるのは、それを必要としている人に向けて話しかけているときだけである。
顧客ターゲットを明確にすることは、売上アップの戦術ではない。儲かる会社の戦略である。
誰に届けるかを定めるだけで、集客も発信も経営判断もすべてがシンプルになる。ターゲットが見えると、商売の言葉も価格も無理なく整いはじめる。▶「ターゲット設定」
儲かる順番と経営の整え方
『売る前に整える会社だけが、焦らず着実に利益を積み上げている』
儲かる仕組みをつくるには、集客や販売の前に「経営の順番」を正しく整えることが不可欠である。
「まずは売ることが先だ」と思っていないか。
商品がある。サービスができた。じゃあ次は売るしかない──そう考えるのは自然だが、実はこの“いきなり売る”という姿勢こそ、利益を遠ざける原因になる。
儲かる会社は、売る前に整えている。何を整えているかといえば、「誰に」「何を」「いくらで」「どんなふうに」売るのかという構造である。これを決めずに宣伝を打っても、反応は薄く、集客しても売れず、むしろ疲労と損失だけが増える。
たとえば、ランチ営業を始めた飲食店がチラシを出したが、クーポン目当ての安さだけで来た客ばかりが殺到し、原価と人件費が合わずに赤字になった。これは「整えずに売った」典型例である。誰に来てほしいか、いくらで利益が出るか、繰り返し来てもらうには何が必要か。その順番がないまま、売るだけを急いだ結果だ。
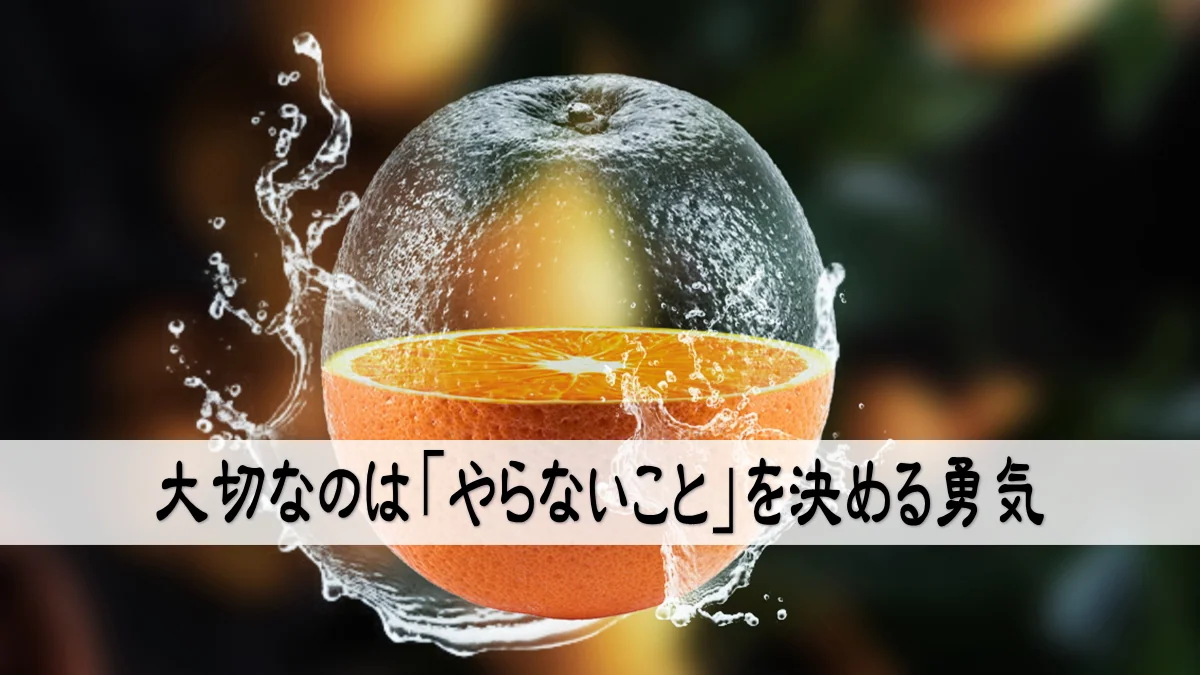
スモールビジネスでは、この“順番の設計”が命綱になる。リソースが限られているからこそ、やることを絞る。その際にまず見るべきは、売上ではなく“利益の構造”だ。商品ごとの粗利はどうか、時間あたりの生産性はどうか、無駄な工程はないか。こうした見直しなしに売ることを先行させると、儲かるどころか消耗が加速する。
さらに大切なのは、「やらないこと」を決める勇気だ。あれもこれもと手を出すと、整うものも整わない。SNSよりメニューの見直しが先かもしれない。広告より価格戦略の再設計が必要かもしれない。
順番を間違えれば、努力が逆効果になる。
焦らずに一つずつ整える。それができる会社は、無理なく利益が積み上がる。派手な動きより、的確な順序。それが経営における静かな力であり、儲かる仕組みの本質でもある。
経営の仕組みや順番を整えることで、商売は安定して利益を生み出せるようになる。派手な戦略より、堅実に儲かる構造を組み立てたい人は、こちらの視点から見直してみてほしい。▶「経営構造と戦略」
儲かる会社の条件は3つある
『儲かる会社には例外なく、成功を導く3つの条件がそろっている』
商売の目的が明確で、顧客ターゲットが絞られ、経営の優先順位が徹底された会社だけが、安定して長期的利益を出し続けている。
儲かる会社には、目に見えない共通点がある。それは「商売の目的がぶれていない」「誰に売るかが決まっている」「やるべき順番を守っている」という3つの条件だ。この3つが揃ってはじめて、経営は“儲かる構造”として安定しはじめる。
まず一つ目は、「商売の目的が長期的利益であること」。
短期的な売上や一時の話題に振り回される会社は、成長しない。反対に、毎月派手な成果が出なくても、着実に利益を残し続けている会社は、じわじわと強くなる。「今月いくら売れたか」より、「今期いくら残ったか」に意識を向けるだけで、経営判断の軸が変わってくる。
二つ目は、「顧客ターゲットが明確であること」。
誰に売るかが曖昧な会社は、どうしても言葉も価格もぼやける。すると、値引きで集めるか、流行りに乗って目立つしかなくなり、結局は短命で終わる。長く続いている商売は、見込み客の悩みや価値観に寄り添いながら、自社の“らしさ”を絞り込んで伝えている。
三つ目は、「経営の優先順位を間違えないこと」。
目の前の流行に踊らず、地味でもやるべきことから手をつける。整えるべきは内部の利益構造、価格設計、商品構成。SNSより、まずは帳簿とにらめっこする勇気がある会社が、最後には笑って残る。
この3つの条件は、特別なノウハウではない。派手な戦略でもない。むしろ、あまりに地味で、気づかれにくい。だが、この“地味な正解”を外さずに積み上げた会社だけが、商売の波に流されず、生き残る。
小さな会社こそ、この3つを大事にしたい。拡大を目指さなくても、安定した利益を出す道はある。長く商売を続けたいなら、売る前に整え、焦らず順番を守る。それだけで、経営の風向きは確実に変わっていく。
「誰に」「なぜ」「何を」で選ばれるか。その答えを言語化することで、価格競争に巻き込まれず、自社らしい商売が成立する。商売の強みを再確認したい人はこちらへ。▶「USPの設計」