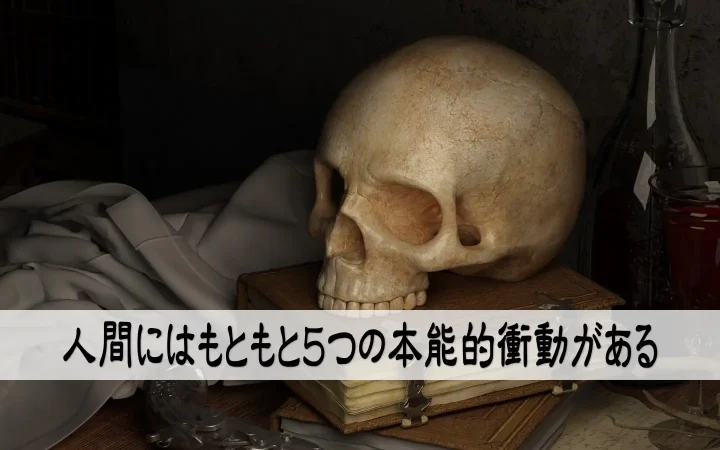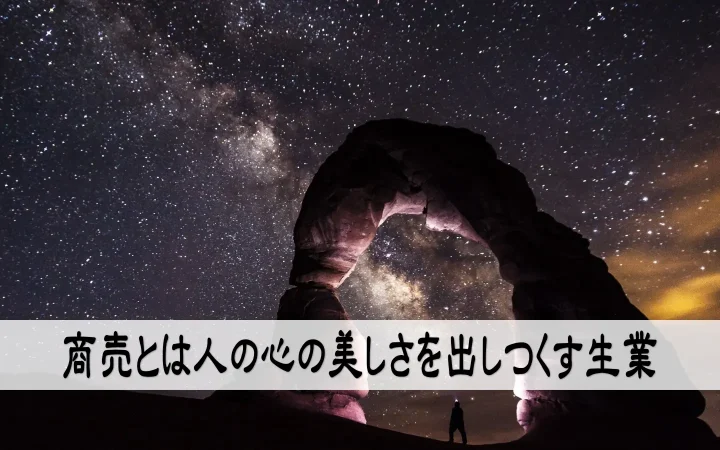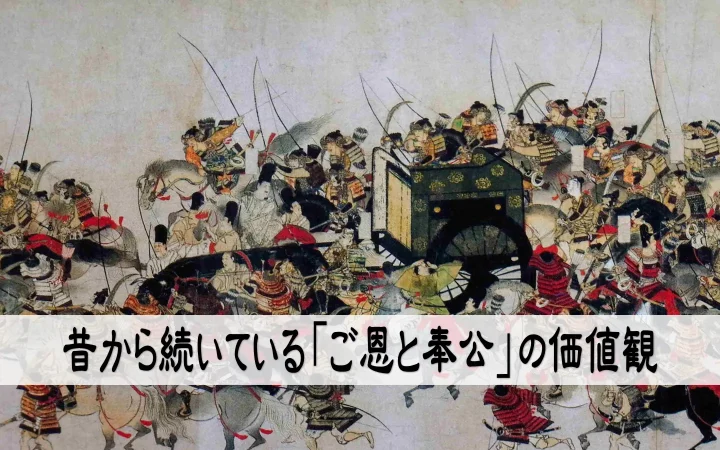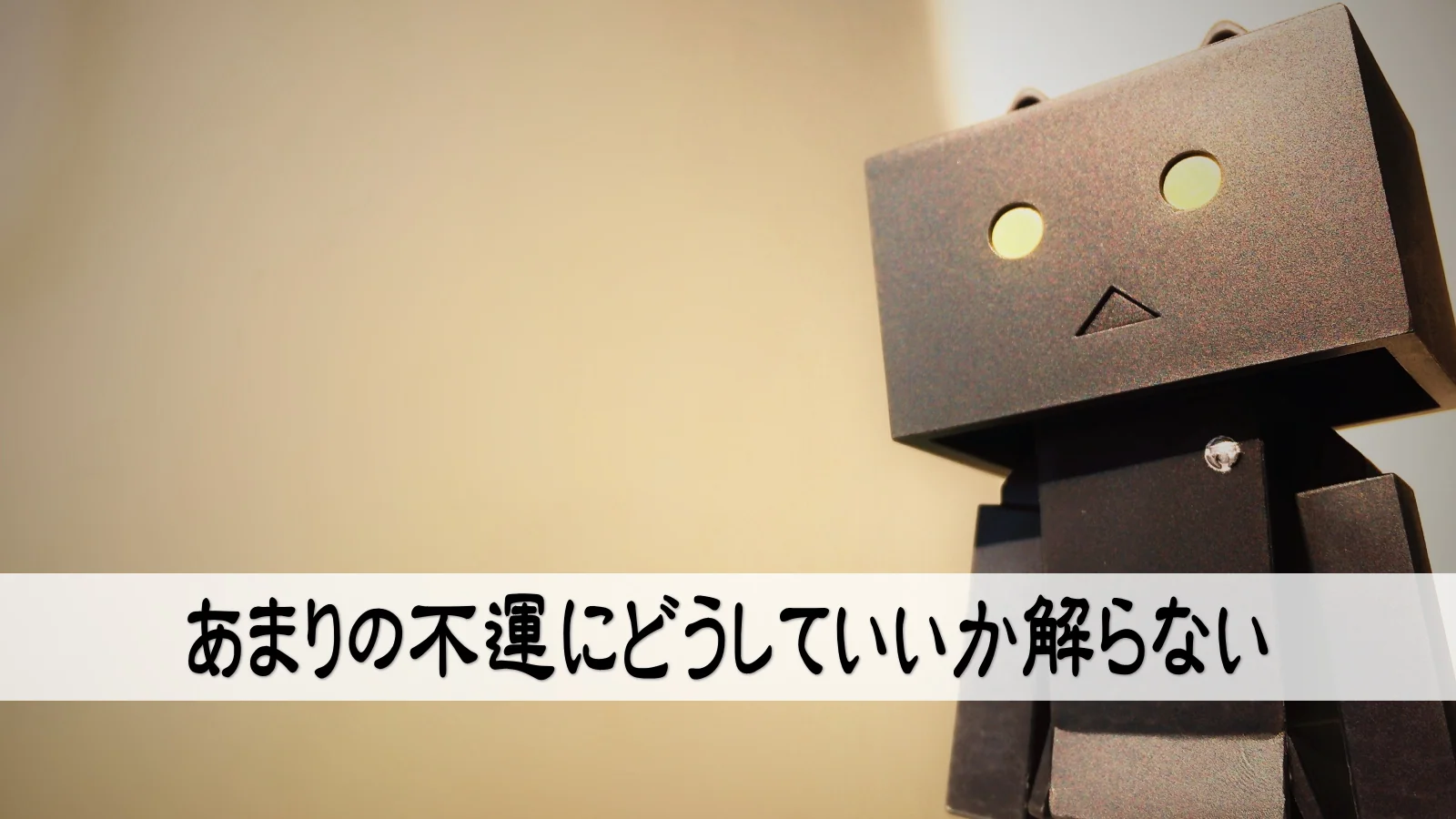
小さな会社の経営者にとって、問題は避けられないものだ。しかし、どんな問題にも必ず解決策はある。重要なのは、問題を外部のせいにせず、自ら向き合うことだ。「あまりの不運にどうしていいか解らない」と感じることもあるが、長期目線で捉え、自分の強み(USP)を活かしながら対処すれば道は開ける。ノート術を活用し問題を可視化し、社長学を学びながら柔軟に思考をアップデートすることで、経営の難問を乗り越える力が身につく。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
小さな会社を経営していると、なぜか次々に問題が起こる。
ときには人手不足、ときには予想外の出費、ときには自分の体調不良やスタッフ同士の対立など、まさに
「選り取りみどり」
といわんばかりに、多様なトラブルが一斉に襲来するものだ。
問題解決の鍵は逃げない姿勢
しかし、どれだけ優れた経営者であっても、問題とまったく無縁でいられる日はこない。
むしろ問題なく回っている期間のほうが短い可能性すらある。
だからこそ大切なのは、
「問題が起きるのは当たり前。必ず解決策がある」
と開き直ることだ。
なかには
「あまりの不運にどうしていいか解らない」
というほど追い詰められる時期もあるだろう。
しかし、そうした極端な不運に直面したとしても、問題を他人や環境のせいにしている限り、状況はまず好転しない。
最終的に事態を打開できるのは、自社の未来をどうするかを判断し行動する経営者自身だけなのだ。
ここで忘れてはならないのが
「経営者の人生の質を最優先する」
という視点である。
大きく拡大することよりも、まず自分自身が健康であり、仕事を道楽化して楽しみながら天職に生きることを意識したい。
そうすると、自然と無理をしない経営判断が身についてくる。
拡大を志向しすぎて心身をすり減らすより、自分が納得できるペースで会社を育てるほうが、長い目で見て結果的にプラスになることが多い。
この“逃げない姿勢”を支えるのが
「我を捨てて流れに乗る」
という発想だ。あれこれ悩んで足踏みを続けるより、問題が出てきたら
「やってみよう」
「まず動いてみよう」
と軽やかに行動に移す。
周囲の意見にも耳を傾け、状況に合わせて柔軟に対応する。
その柔軟性が、後々に続く問題解決のヒントをもたらすことも多い。
問題から逃げず、自分の人生の質を高めながら経営する。
まずはこの姿勢が、どんなに大きな難問でも解決に導くための第一歩となる。
あまりのの不運に直面したら
経営を続けていると
「どうしてこんなに不運が重なるのか」
と疑いたくなる状況がやってくる。
具体的には、予期せぬ取引先の倒産、大口案件の突然のキャンセル、信頼していたスタッフの退職が同時多発的に起きるようなシーンだ。
まさに、
「あまりの不運にどうしていいか解らない」
という言葉がぴったりの瞬間である。
こうした不運の連鎖は、実に厄介だ。
立て直しの糸口を探しても、何から手をつければいいのか見当がつかず、精神的にも追い詰められてしまう。
しかし、どんなに大きな問題やトラブルが起きても、基本的には
「解決できるからこそ起こる」
というのが経営の現実である。
なぜなら、問題の大きさは、その経営者の器以上のものはやってこないともいわれるからだ。
大きな問題に直面するということは、それだけ成長の余地が与えられている証拠ともいえる。
ここで耐え、自分の強み(USP)をさらに磨いていけば、同じような不運が再来したときでも、より冷静に対処できるようになる。
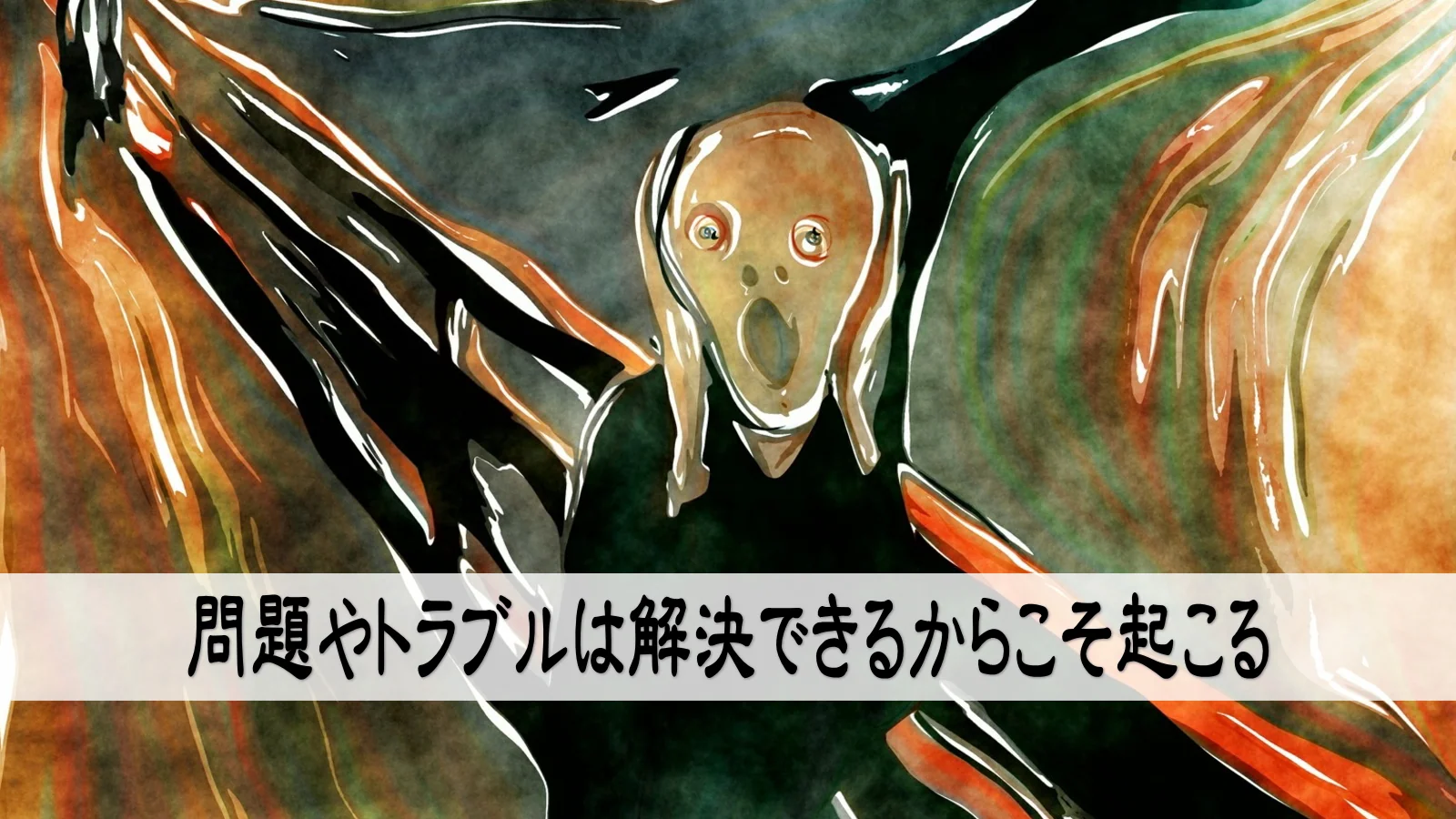
経営者としての視点を変えれば、
「売上増より資産増を目指す」
とか
「顧客と共に成長する」
などの長期的な考え方が自然と身についてくる。
短期的な売上だけに振り回されていれば、一時的な不運に翻弄され続けるかもしれない。
しかし、たとえ売上が下がっても、根本の資産価値(顧客との信頼関係やブランド力)が揺らがなければ、再び盛り返すチャンスは必ず来る。
不運を嘆いてばかりいては、前には進めない。
経営者はむしろ
「このピンチを糧にするにはどう動くか」
を考えながら、自分自身のマインドセットをアップデートしていく。
そうすることで、結果的に
「あのときは最悪だと思ったけれど、振り返ってみれば必要なステップだったな」
そう思える日がやってくるのだ。
ノート術で全体像を可視化する
そんな不運の波にのまれそうなときこそ、役に立つのが「ノート術」である。
これは、同時多発的に起こる問題を整理し、俯瞰してみるための手法だ。
人間の頭は同時にいくつもの課題を考えると混乱しやすいので、とにかく紙に書き出して整理する。
やり方はとてもシンプルだ。
まず、現状のありのままを書き出す。
たとえば
「取引先Aが倒産」
「スタッフBが退職」
「金銭的な余裕が薄い」
などをリストアップし、その横に
「これから起こりそうな問題」
も想定して追加していく。
ここで大切なのは、最初から問題をひとまとめにしないことだ。
いったんすべてを分解し、要素ごとに切り分けて書き出すことで、自分が直面している課題の“総量”と“個別の正体”をはっきりさせる。
全体像が見えたら、それぞれの問題に対して
「今すぐできること」
を同じノートに書き込む。
大それた解決策でなくてもいい。
「取引先Aの担当者に直接連絡を取る」
「スタッフBの引き継ぎ内容を確認する」
「銀行に条件変更の相談をする」
など、具体的で小さなアクションをガンガン書く。
色を変えたり、囲みをつけたりして視覚的にわかりやすくするのも手だ。
ノート術の最大の利点は、頭の中でグルグル回っていた悩みを客観視できるようになる点にある。
どれだけ問題が複雑に見えても、紙の上で切り分けてしまえば
「案外シンプルに解決できるかもしれない」
と気づく瞬間がある。
さらに、少しでも行動を起こせば前進した感覚が得られるため、ネガティブ思考から抜け出しやすくなる。
ノート術は、「社長学」の重要なスキルでもある。
自分の頭の中も会社の状況も可視化して整理していく。
経営者の人生の質を落とさないためにも、ノート術は強力な味方になる。
書いているうちに、自分の強み(USP)がどこにあるのかも再確認できるから不思議だ。
考え方を転換する社長学
問題のリストアップと簡単なアクションの準備ができたら、次は本格的な
「考え方の転換」
に取り組む。
なぜなら、多くの場合、問題の本質的な原因は経営者自身の思い込みや先入観にあることが多いからだ。
たとえば、
「これくらい売上がないと会社として恥ずかしい」
「もっと拡大しないと周囲にバカにされる」
など、外部の価値観を無意識に刷り込んでいるケースは少なくない。
しかし、拡大を志向しすぎるあまりに経営が苦しくなったり、急激な売上増で社内体制が追いつかずに混乱することも珍しくない。
そこでもう一度、売上増より資産増を目指す姿勢や、我を捨てて流れに乗る柔軟さを思い出してほしい。
さらに、顧客と共に成長するという意識を持てば、自社のサービスや商品の価値を本質的に高める活動へ自然と目が向く。
たとえ一時的に落ち込むことがあっても、長期目線で人生を経営するためには何を優先すべきかが見えてくる。

このように、社長学の真髄は
「まず自分が変わること」
にある。
目の前に起きる問題を通して、自分の経営観を更新し続けるのだ。
問題が起きたら
「これは自分の考え方を調整するチャンスだ」
と捉え、ノート術で洗い出した行動を実行しながら、ビジョンを少しずつ修正していく。
結果的に同じような問題が再発しても、以前とはまったく違うアプローチでスムーズに解決できるようになる。
もちろんそれで問題が減るわけではない。
しかし、自分自身の思考力と行動力が高まり、人生の質を大切にしながら会社を運営できるようになる。
これこそが考え方を転換する社長学の醍醐味である。
長期目線で人生を経営する
問題に直面すると、どうしても目先の数字や一時的な感情に振り回されがちになる。
しかし、長く会社を続けていくなら、長期目線で人生そのものを経営する視点が欠かせない。
単に売上を追いかけるのではなく、自分がどう生きたいのか、会社をどの方向に進めたいのかを明確にしながら、小さな一歩を積み重ねるのだ。
ここで思い出したいのが、
「経営者の人生の質を最優先する」
という姿勢である。
寝る間を惜しんで働き続けるだけが成功ではない。
むしろ自分が心身ともに疲弊してしまえば、結果的に会社全体がバランスを崩すことになりかねない。
道楽のように仕事を楽しみ、天職に生きる感覚を忘れないほうが、結局は高いパフォーマンスを発揮できるものだ。
同時に、
「強み(USP)に特化する」
ことも意識したい。
他社と同じ土俵で競い合うのではなく、自分たちだけが提供できる価値にフォーカスする。
そうすることで、顧客と共に成長するための具体的なプランが立てやすくなる。
いつしか拡大しないことが不安に感じなくなり、むしろ自分のペースで良質な資産を積み上げることが楽しくなってくる。
長期目線で経営を考えれば、一時的な不運に動じすぎる必要もなくなる。
たとえ
「あまりの不運にどうしていいか解らない」
と感じるときでも、
「これは会社と自分自身が次のステージに進むための転換期だ」
ととらえられる。
結果を急がず、今やるべきことを淡々とこなしていけば、やがて状況は好転する。
大きな波が来たときも柔軟にサーフィンするように乗りこなすイメージでいれば、ピンチをチャンスに変えることも夢ではない。
未来を拓くための行動指針
ここまでの内容を踏まえれば、経営の難問を解決するうえで大事なのは
「逃げずに現実を見つめ、行動する」
こととわかる。
実際にどう行動するかは会社や経営者ごとに異なるが、以下の指針を意識してみると役立つはずだ。
1. 問題は分解して書き出す
ノート術を活用し、現状や今後起こりそうな課題をすべて洗い出す。
頭の中で悩むより、紙に書くほうがはるかに楽になる。
2. すぐ動けることから着手する
問題解決の方法をあれこれ考えるよりも、とりあえずできる小さなアクションを実行する。
進み始めると、不思議と次のステップが見えてくる。
3. 考え方をこまめにアップデートする
「拡大しなくてはならない」
「売上こそが正義」
といった固定観念を疑ってみる。
長期目線で人生を経営し、経営者の人生の質を優先するほうが、中長期的には大きな成果を生む。
4. 顧客と共に成長する視点を忘れない
自分の強み(USP)を磨き、そこに価値を感じてくれる顧客と信頼関係を築く。
売上増より資産増を目指すことが、経営の安定にもつながる。
5. 我を捨てて流れに乗る
大きな問題ほど、すべてを自力でなんとかしようとするより、周囲の知恵や時流をうまく取り込むほうが得策な場合が多い。
柔軟に構えれば、新しい活路が開ける。

どんなに工夫しても、経営上の問題がゼロになることはない。
だが、問題解決のたびに社長としての力が磨かれ、自分自身が成長し、会社の底力も強まっていく。
そして何より、人生そのものを豊かにするきっかけとなる。
あまりの不運にどうしていいか解らないときこそ、逆に
「自分はこの局面を乗り越えられるだけの器がある」
そう信じ、思い切り行動してみてほしい。
結果的にそれが、長期的な目線での経営において、最も重要なターニングポイントになる可能性は高い。
経営者として、先の見えない状況でも一歩踏み出す勇気こそが未来を拓く鍵だ。
仕事を道楽化しながら天職に生き、人生の質を下げずに問題解決を楽しんでいけば、必ず会社も自分自身も次のステージへ進める。
どんな問題も逃げずに立ち向かい、ノート術で見える化し、経験と学びをアップデートし続けていけば、
「あまりの不運にどうしていいか解らない」
ような局面であっても、きっと道は開けてくるに違いない。