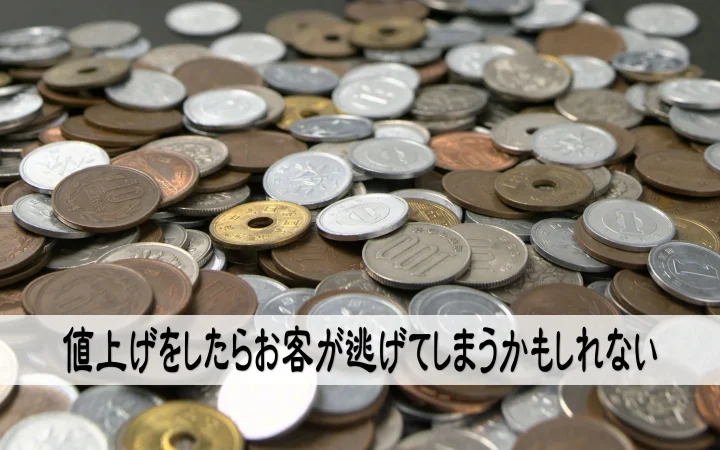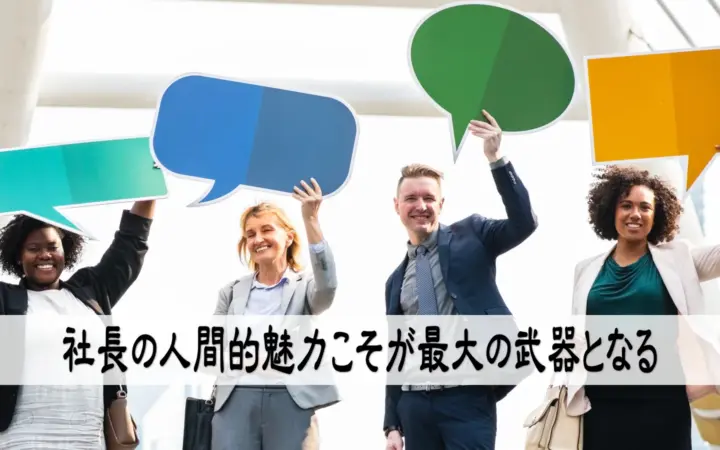ビジネスの利益は「需要と供給」のバランスで決まる。消費者は売り手の利益を嫌うため、利益を出すには供給を抑え、需要が上回る「売り手市場」を作る必要がある。機会損失を恐れて供給を増やせば、価格が下がり利益が減る。「限定」と「希少性」を活かし、安易な安売りを避けることで価値と利益を守る。スモールビジネスこそ、規模ではなく需給のコントロールで安定した経営を目指すべきである。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
世の中のほとんどのビジネスは、需要と供給のバランスによって最終的な価格や利益が決まる。これは中学生の教科書にも載っているほど当たり前の話だが、実際に商売をしていると忘れがちになる。特に、50歳以上でスモールビジネスを営んでいると、昔のやり方や経験に頼りきってしまい、肝心の「需要と供給」という原則を振り返ることを忘れてしまう。
需要と供給は商売の基本法則
たとえば、株価が上昇するのは買い手が殺到し、売り手を上回った時だ。商品やサービスの価格が上がるのも、同じように需要が高まった結果だと考えればわかりやすい。逆に供給が需要を上回れば、どんなに優れた商品でも安売りの流れに飲み込まれやすい。これは、中小企業やスモールビジネスにもまったく同じことがいえる。
経営において、「まず需要をきちんと見きわめる」「次に供給量をうまくコントロールする」という順番を徹底するだけで、大きなトラブルを回避できる。どれだけ素晴らしいセールストークを身に着けても、そもそも求める人が少なければ、儲けは生まれにくい。いちばん土台にくるのは、ほかでもない需給バランスだということを今一度思い出してほしい。
需要より供給が多い状態に陥ると、後戻りが難しくなるケースが多い。大量の在庫を抱えたり、値下げ競争に巻き込まれたりして、疲弊してしまうからだ。だからこそ、「儲けたかったら需要>供給の売り手市場を作る」というシンプルな原則を経営の中心に据えることが、スモールビジネスでも大きな差を生む。50歳を過ぎても稼ぎを伸ばしたいなら、まずはこの基本を押さえておこう。
お店の利益を嫌う消費者の本音
消費者は売り手の利益など気にかけない。これは厳しいようだが、じつは当たり前の話だ。自分自身が買う立場になったとき、「この店がいくら儲かっているか」よりも、「自分はできるだけ安く手に入れたい」「いい条件で買いたい」と考えるのが普通だろう。だからこそ、「こんな価格じゃ採算が合わないんです」と売り手が叫んでも、消費者は動じない。「なら安いうちにまとめ買いしよう」と思うだけなのだ。
結局、商売人が高い利益を得られるのは、ただひとつ。需要が供給を上回っているときだけだ。需要が旺盛なら、売り手が強気に価格を設定しても買い手がつく。ところが、供給過多の状態では、少しでも安いところへ人が流れてしまう。消費者はあくまで自分の懐を最優先に考えるから、値段が下がるのは大歓迎なのである。

この「利益を嫌う」という消費者心理を理解した上でとる方法が、売り手市場の確立だ。供給量をわざと抑えたり、商品を差別化したりして、「あれ、これ欲しいのに全部は行き渡らないぞ」という雰囲気を作るわけだ。消費者の購買意欲をくすぐり、じっと待っていても安くならないことを分からせれば、高い利益率を維持しやすい。
それでも、真面目な経営者ほど「お客様全員に届けたい」という思いを捨てきれないかもしれない。しかし、ビジネスは利益を出す行為だ。供給過多になれば値下げが進み、疲弊した結果、長く続けられなくなるという悪循環が待っている。消費者はあなたを助けてはくれない。だからこそ、自分の商売が潰れないように需給バランスを制御することが重要になる。
売り手市場をつくる経営の秘訣
売り手市場とは、需要が供給を上回っている状態のこと。たとえば、人気グルメ店で行列が絶えないのは、食べたい人の数が席数をはるかに超えているからだ。そうなると、「買えない(食べられない)人」が出るわけだが、その不便さこそが「人気がある証拠」としてさらに人を呼び、店側も利益を高めやすい仕組みにつながる。
この状況は、スモールビジネスでも十分に作り出せる。大企業のように大々的な宣伝や生産体制を整えるのではなく、自分の提供できる範囲を絞りつつ、商品の魅力を高めていく。そうすれば、数に限りがあるぶん「早く手に入れないと売り切れるかもしれない」という焦燥感を刺激できる。
大切なのは、自分が無理なく扱える供給量を把握することにある。そして、「欲しい人が全員買えるほど在庫を作らない」覚悟を持つことだ。こう聞くと、せっかくの売上を逃す「機会損失」に感じるかもしれない。しかし、すべての要望に応えようとして供給過多になると、あっという間に消費者は強気の値下げ交渉へと向かう。すると、利益はほとんど残らない。
少しもったいなく思うくらいが、結果的には高い利益率を保つポイントになる。もし供給量を増やすなら、間違いなく需要が伸び続けると確信できる段階まで待つことをおすすめする。闇雲に拡大すると、売り手市場はあっという間に崩れ去るので要注意だ。
「機会損失」という罠を避ける
スモールビジネスで売り手市場を狙うと、「欲しい人が買えないなんて、もったいない」「せっかくのチャンスを逃しているのでは」と心配の声が上がることがある。これが「機会損失」という言葉の甘い罠だ。もちろん、機会損失を軽視するのはよくないが、「すべての要望に応えれば儲かる」とは限らないのが現実である。
たとえば、「ここで供給を増やせば一時的には売上が上がる」と思っても、その後の相場が崩れ、商品価値が下がれば、取り返しのつかない損失に発展しかねない。スモールビジネスならなおさら、在庫リスクや固定費が重荷になる危険がある。たとえ短期的にお金が動いても、長期的に安値でしか売れなくなったら、ビジネスの継続が難しくなってしまう。
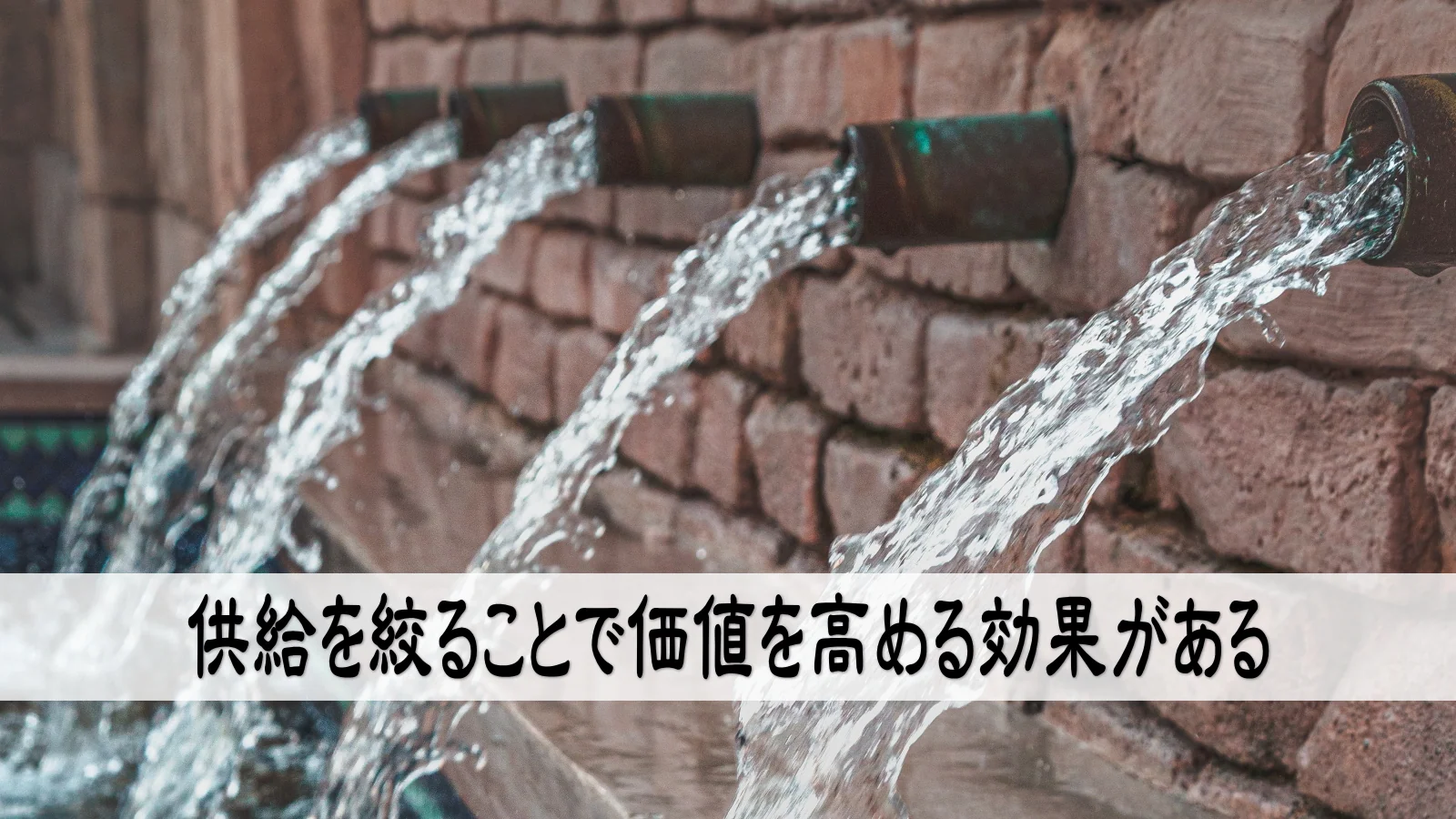
だからこそ、消費者が「機会損失」を嘆く状態を逆手に取ることが必要になる。「買おうと思ったのに売り切れていた」「もうちょっと早く決断しておけばよかった」といった悔しさは、次回の購買意欲を一段と高めてくれる。つまり、供給を絞ることで価値を高める効果が見込めるわけだ。
もちろん、むやみに売り逃すのがいいという話でもない。過度に抑えすぎると今度は知名度が広がらず、必要以上に顧客を遠ざける恐れもある。要は、自分の事業規模と照らし合わせて、ちょうどいい塩梅を探ることが大切だ。ときには「敢えて売り切る」という戦略が、長期的な利益を確保するカギになることを覚えておくことである。
安売りで失うものはかなり大きい
需要と供給のバランスを崩す最大の要因の一つが安売りだ。特に供給過多の状態に陥ると、売れ残りを恐れて「とにかく安く売るしかない」という発想が生まれやすい。しかし、「安くすれば売れる」というのは半分だけ正解で、半分は間違いでもある。
なぜなら、安売りしても、「そもそも欲しくない商品」なら誰も買わないし、本当に必要な人は「もっと下がるかも」と様子をうかがうかもしれない。さらに、安売りによってビジネスのブランドイメージまで下がってしまうと、長期的には高単価で売りづらくなる恐れがある。結果的に、利益がどんどん削られ、経営体力を失ってしまう。
スモールビジネスの場合、大企業と違って大量生産や広範囲な流通網を武器にするのは難しい。ならばこそ、「誰にどう売るか」をより慎重に考える必要がある。値段を下げても数がさばけなければ元も子もないし、「いつでも安い」という認識が広まると、もう高い価格での販売に戻すのは容易ではない。
利益を生み出すための最も重要なポイントは、「売り手市場を作り、需要が供給を上回る状況を保つこと」であり、その鍵を握るのが「利益を生むのは、『限定』と『希少性』」という視点だ。もし商品の存在感を高めたいなら、実は価格を下げるよりも「数を減らす」ほうが効果的な場合がある。買える人が限られているからこそ、高値でも欲しいと思う人が増えていく。
「限定」と「希少性」が生む利益
需要と供給がビジネスを左右するのは、結局のところ「限定」と「希少性」がカギになっている。どんな素晴らしい商品やサービスでも、供給量が余りすぎると値崩れが起きる。一方で、「数が限られている」「この機会を逃すと入手できない」と感じさせることで、人は強い購買意欲を持つ。
売り手市場を実現するために、あえて生産数や提供回数を絞るのは、大企業よりもスモールビジネスのほうがやりやすい。なぜなら、そもそも大量生産や大規模流通は向いていないからだ。独自の強みを活かしつつ、少数精鋭でやっていくスタイルのほうが、高い利益率を確保しやすい。そして、「欲しいのに買えない」という人が出るからこそ、「プレミアム感」が増していく。

もちろん、「限定」や「希少性」を狙うあまり、実際の顧客ニーズを見失っては本末転倒になる。きちんと売り先を把握し、適切な市場調査を行いつつ、自分のビジネスのキャパシティに合った供給量を設定することが大切だ。需要が増えていると確信できるなら、徐々に供給を増やしてもいい。ただし、その際は「安易に拡大しすぎない」姿勢を崩さないことがポイントになる。
50歳を超えて経営を続けるということは、すでに長年の経験や実績を積んできた証でもある。過去の成功体験や人脈を活かしながら、最適な需給バランスを模索してほしい。大事なのは、利益を生む基本法則を軽視せず、自分に合ったスケールで「売り手市場」を作り続けることだ。消費者はあなたの利益を気にしてくれない。だからこそ、自らが舵を取り、「需要>供給」の状態をキープする。その積み重ねが長い目で見て、安定した利益につながるはずだ。