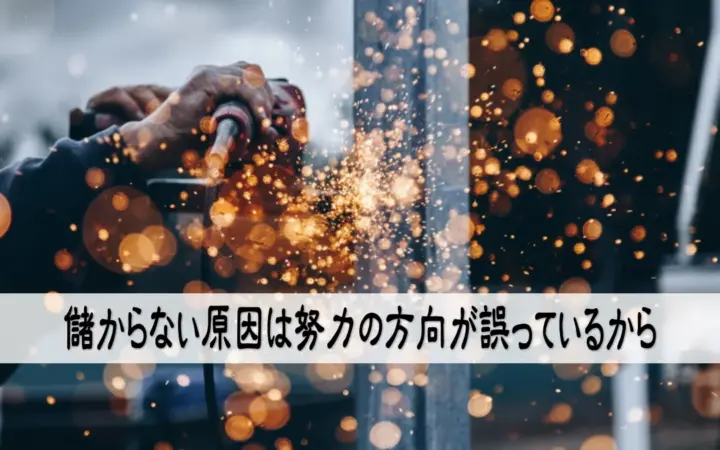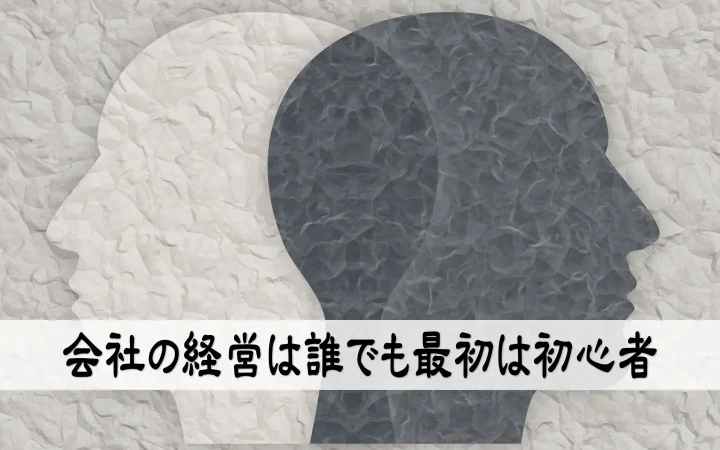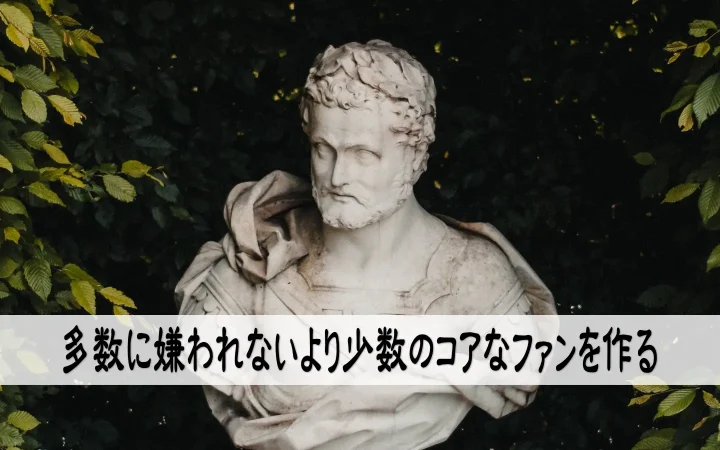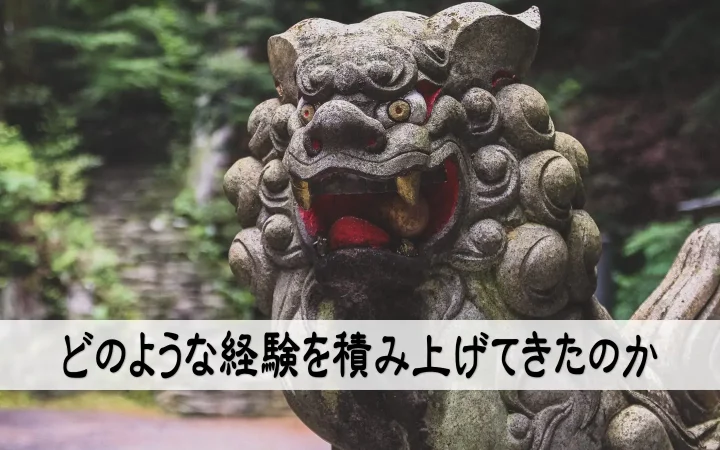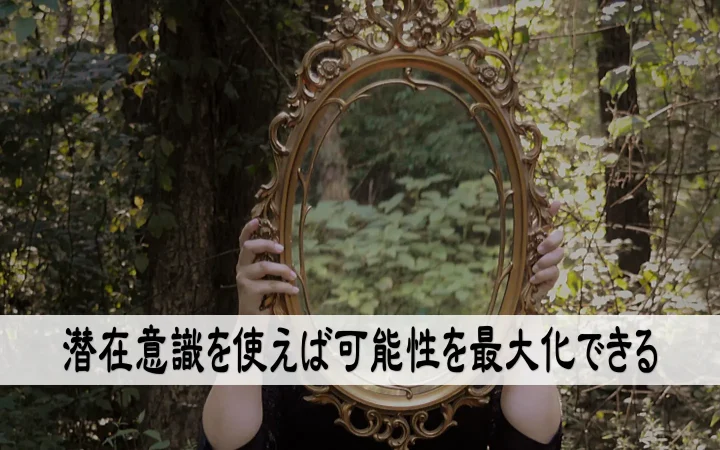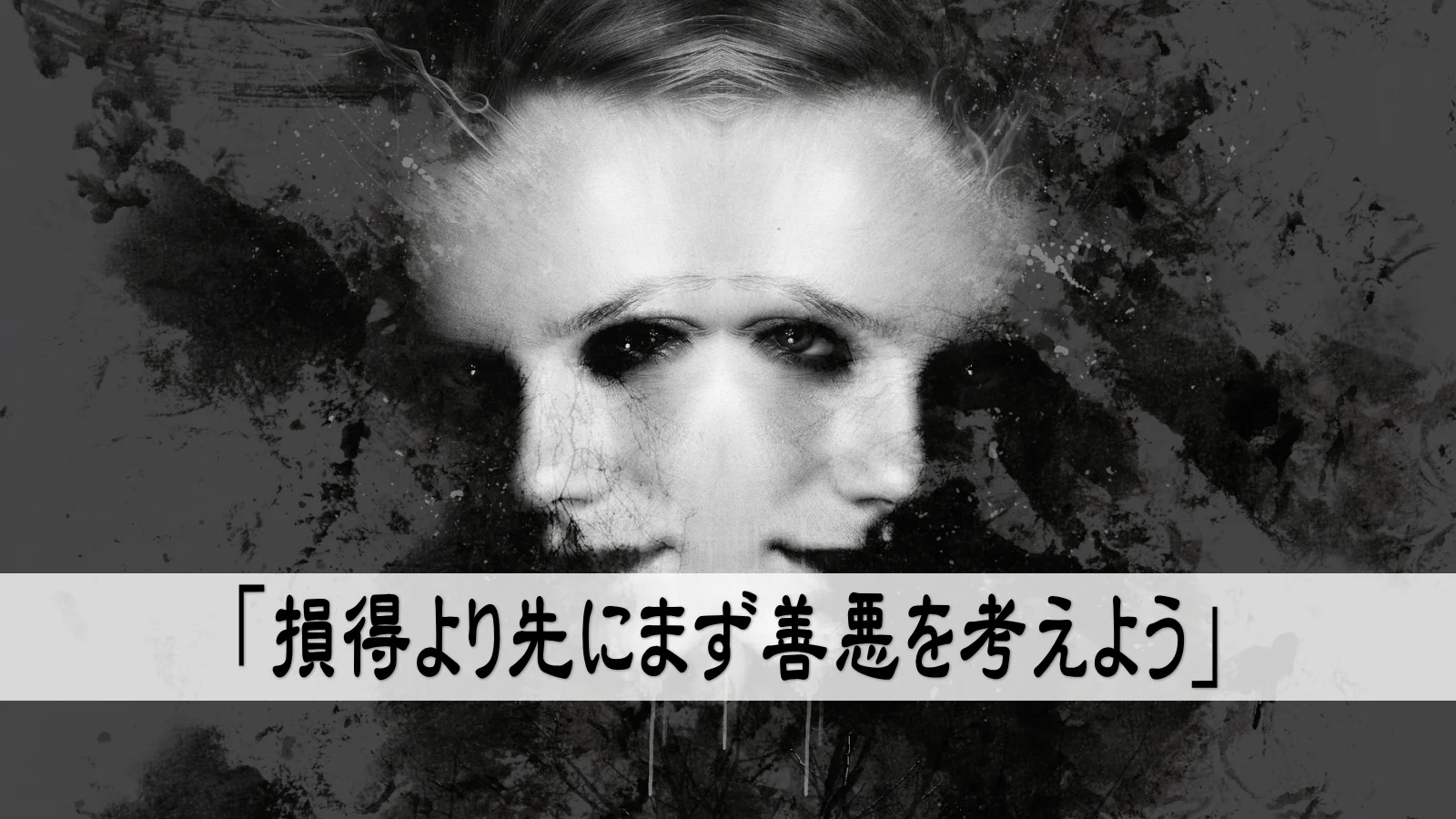
スモールビジネス経営において、「損得より先に善悪を考えよう」という姿勢が長期的な成功をもたらす。本来、商売の目的は顧客に幸福感を提供することであり、利益はその結果に過ぎない。目先の損得勘定にとらわれると信頼を失い、事業の持続性が揺らぐ。善悪の判断基準を持ち、小さな悪を見逃さないことが、経営者自身の誇りと信用を守る。善を軸とした経営は、顧客やスタッフとの強い絆を築き、最終的には最大の利益を生むのだ。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
損得勘定ばかりを最優先にすると、一時はうまくいくかのように見えるが、最後にしっぺ返しを受ける場面は少なくない。たとえば「少しくらい誤魔化しても問題ない」と考え、千円単位の不正を日常的に積み重ねていけば、いつしか大きな額をごまかすことに対しても罪悪感がなくなっていく。これは心が麻痺してしまう怖さであり、いつかは大きな代償を払わされる。
損得勘定がもたらす落とし穴
実際、商売十訓の筆頭には「損得より先に善悪を考えよう」という言葉が掲げられている。これは損得勘定を無視せよという極端な話ではない。ビジネスをするうえで利益が必要なのは当然だが、それを基準にすべてを決めると、周囲との信頼関係を損なう可能性が高まる。損得ばかりが頭を占めると、お客の本当のニーズを見落としたり、自分が何のために商いをしているのかを見失ったりする。
また「利を見てその真を忘れる」(荘子)という言葉があるように、目先の利益を追いかけすぎると、今自分が何をすべきかという本質を見失いやすい。小さな利益を優先した結果、信用を一気に失うケースも珍しくない。社長学の観点からも、経営者が目先の損得勘定だけで判断すると、社員やステークホルダーの士気が下がり、事業そのものが不安定になるリスクが高まる。いくら儲かったとしても、その基盤が揺らいでしまっては長続きしない。
もちろん、利益はなくてはならない大事なものだ。しかし利益は結果であり、目的にすべきではない。まずは自分も他人も喜ぶ行い、あるいは後悔しない行動を心がけることが重要になる。こうした考え方を身につけると、多少のトラブルや損失があっても、お客や取引先が助けてくれるようになる。そこにこそ、長期的な安定と成長のヒントが隠れている。
そして経営者は「損得より先に善悪を考えよう」という姿勢を社内外に示すことが大事になる。何か不正やトラブルが発生したときにも「これは善か悪か」を自問すれば、小さな悪や違和感を見過ごさずに済む。こうした姿勢がビジネス上の信用となり、ひいては豊かな顧客基盤と信頼関係を築く土台となる。
善悪の基準がつくる持続力
善悪とは一見すると曖昧な概念に思えるが、実は誰でも、自分の心に明確な基準を持っている。ただ、その基準を意識せずにいると、周囲の環境や状況に流されてしまいがちだ。だからこそ「自分が喜び、他人も喜ぶ」ことを第一に考え、「自分も他人も苦しむ」ことを避ける。そこに後悔するかどうかという観点も加わることで、自分ならではの善悪が明確になる。
たとえば、お客に幸福感を届けるのが仕事の目的だと理解していれば、目先の売上を上げるだけの行為や、顧客をだまして利益を得るような行為は自然と避けられる。もし、そういった短絡的手法に手を染めたら、いずれ自分も後悔するし、相手も嫌な思いをする結果になってしまう。善悪の基準をはっきりさせることで、迷ったときに踏みとどまる心の支柱ができる。
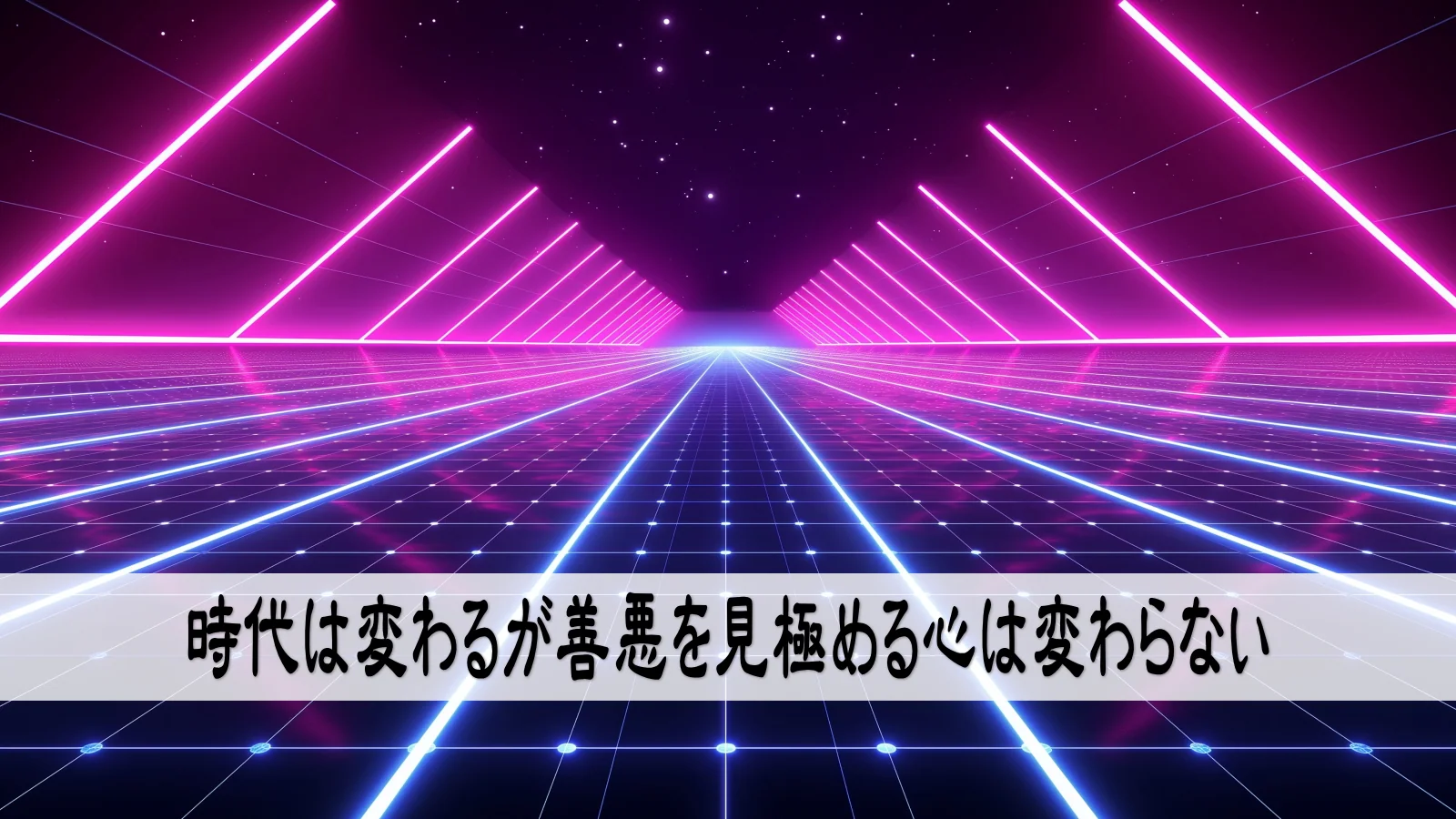
「いいこと」なのか「悪いこと」なのか、どちらかハッキリ言い切れないケースも多いだろう。たとえば「いいことではない」し「悪いことでもない」というグレーゾーンだ。しかし、自分の心に尋ねてみれば、本当にやるべきかどうか、意外と答えは明確だったりする。この自問を日々繰り返すことが、スモールビジネスでも長期的に高い信頼を勝ち取る秘訣である。
一方で、環境やトレンドに合わせて柔軟に動く必要もあるのがビジネスの常。ここで大切なのは「時代や状況は変わっても、善悪を見極める心は変わらない」という姿勢。情報は刻一刻と変わるが、根底にある自分の基準はブレない。これこそが持続力につながり、世間の流れに翻弄されず、着実に成果を積み上げていく源泉になる。
また小規模な事業ほど、経営者の人柄や人格がダイレクトに伝わる。そこに善悪の基準がしっかり根付いていれば、お客も自然に応援してくれる。利益だけを追い求める企業よりも「ここはちゃんといいことをしている」と思われる企業のほうが、人の心をつかみやすい。つまり善悪基準を大切にすることが、スモールビジネスにとっては最強のブランディングになるのだ。
自分の心にある“いいこと”
「損得より先に善悪を考えよう」というのは、ビジネスを離れた日常生活にも応用できる考え方だ。まずは「自分が喜び、他人も喜ぶ」ことを見つけるところから始める。たとえ小さなことでも、そこに自分のモチベーションや充実感が生まれれば、やがて周りもそれに共感してくれる。逆に、自分が嫌々取り組んでいたり、誰かを不快にさせていると、それはいつか必ず問題化する。
たとえば、あるスイーツショップの社長が、自分もワクワクしながら商品を試作し、お客に笑顔になってもらうことを何よりの喜びとしている。その結果、利益をあまり意識せずとも、口コミで評判が広がり売上も伸びていった。こうした姿はまさに「いいこと」を軸にした成功モデルだと言える。
自分の心が喜びを感じるポイントは、人それぞれ異なる。社会的に華々しいビジネスを望む人もいれば、地味でも安定した事業を好む人もいる。どちらにしても、自分が後悔しない選択をしているなら、それは善悪の基準に合った行動となる。ここで大切なのは、他人と比較して優劣を決めるのではなく、自分の心を満たしながら他人もハッピーにできるかどうかということだ。
また「悪いこと」はもちろん避けるとして、「いいことではない」行いも極力控える努力が必要だ。曖昧な気持ちで仕入れを増やしたり、根拠のない値上げをしたりすると、後々自分が苦しむだけでなく、取引先や顧客も納得しない。自分に不安や後ろめたさがあるなら、一度立ち止まって考えたほうがいい。「これって本当にいいことなのか?」という問いを投げかけるだけでも、軌道修正につながる。
さらに、良心に反する行動を重ねると心の癖になり、本当に悪いことでも平気でやってしまうようになる。小さな不正を見逃していると、それが当たり前に感じられてしまう。結果として、人間関係やビジネスの根幹を揺るがすような大問題に発展するリスクもある。だからこそ、自分の心にある“いいこと”を常に意識しながら進むことが重要だ。
商売十訓から学ぶ経営判断
昭和36年に倉本長治氏が発表した商売十訓の中でも、最初に掲げられた「損得より先に善悪を考えよう」という一文は、多くの経営者にとって普遍的なテーマだ。商売十訓は、昔ながらの道徳観や倫理観をビジネスに置き換えたようなもので、その根底には「商いは人のためにある」という考え方が流れている。
現代は時代も大きく変化し、ネットやSNSで個人が広く発信できるようになった。しかし、どれだけ世の中が便利になっても、人が求める本質的な価値、つまり「喜び」や「安心感」「幸福感」は昔から変わらない。だからこそ、商売十訓に書かれた理念は今でも色あせない。むしろスピードの早い時代だからこそ、古くからの知恵が引き立つ面もある。

たとえば損得勘定を優先しすぎると、お客が何を求めているのかを見誤りがちになる。売上や利益だけを見ていては、お客の心が離れた時点でビジネスが崩壊してしまう。ところが「善悪」に基づいて行動すれば、お客にとっての喜びを先に考えられるため、自然と自分も後悔しない選択ができる。理不尽な値上げや強引なセールスは避けられるし、何より自分自身も気持ちよく商いを続けられる。
また、商売十訓が示すのは、ビジネスと人間性が切り離せないという事実だ。どれほど優れた商品を持っていても、それを扱う人の心が曲がっていたら、いずれは問題が噴出する。逆に、飾り気のないシンプルなサービスでも、誠実さと善意が伴っていれば、多くの人に受け入れられる。ここには数値では測れない魅力が存在する。
スモールビジネスほど経営者の人柄や方針がダイレクトに影響する。社員が少なければ、社長の価値観がそのまま組織の空気感になる。だからこそ社長学の視点からも、リーダーはまず自ら善悪の軸を確立し、それを共有していく必要がある。口先だけで「うちはお客のためにやっている」と言っても、本心が損得勘定だとスタッフも気づいてしまう。最終的には何を基準に意思決定するか。その答えが「善悪を意識する」ことであれば、組織全体が肯定的に動き出す。
小さな悪も放置しておかない
「小さな誤魔化しだから問題ない」と考えるのは危険だ。千円程度の不正も、繰り返せば当人の心を麻痺させる。やがて何十万円、何百万円をごまかす行為も平気になるかもしれない。一度癖になると、そこから抜け出すのは相当に難しい。特にスモールビジネスの場合、経営者が自らこの悪循環にはまり込むと、事業全体に影響が出る。
たとえば、在庫管理で適当な処理をしてしまう。最初は「まあ、これくらいなら問題ないだろう」と思う程度のズレかもしれない。だが、それが常態化すれば、売上の把握も曖昧になり、仕入れや経費の管理もいい加減になる。そして気がつけば手に負えないほどのロスや負債を抱えているケースは珍しくない。
こうした悪い行為を「小さなことだから」と軽く見ていると、周囲の人間にも悪影響を及ぼす。たとえばスタッフが社長のずさんな管理を見習い、次第に会社の秩序や信用が失われていく。業者との付き合いでも「ここは誤魔化しても大丈夫」と思われると、相手側の対応も同じように雑になる。結果として顧客へのサービスの質が落ち、リピーターが離れ、評判が下降してしまう。
反対に、どんなに小さなことでも正直に対応し続ける企業は、周囲からの信用を勝ち取りやすい。クレーム対応でも誠実な姿勢を見せれば、トラブルが解決した後にむしろファンが増えることすらある。小さな善を積み重ねていくことで、信頼は雪だるま式に膨らむ。損得勘定ではなく、まずは善悪を意識して誠実に取り組むことが、長期的に見ると最大の得になる。
ここでも大切なのは「後悔しない」判断をすること。もし自分がその行動をしたあとで、何らかの罪悪感や言い訳が頭をよぎるなら、それは善悪でいえば「悪いこと」か「いいことではない」側だと考えられる。だからこそ、小さな悪を放置しない。その一歩一歩がビジネスの健全な発展に直結する。
社長学で磨く幸福感経営
スモールビジネス経営者が事業を通じて目指すべきは、単にお金を稼ぐことではなく、顧客に幸福感という価値を提供することだ。結果として利益が生まれるのは、その“おまけ”のようなもの。本来、仕事の存在意義は「お客にどれだけ役立つか」であり、「損得より先に善悪を考えよう」という姿勢こそが、その土台を支える。
経営者自身が自分のビジネスに喜びやワクワク感を感じ、同時にお客も喜んでいる状態が理想である。たとえば「これを使ってもらえれば、お客がこんなに幸せになるんじゃないか」と想像するだけで、自分も嬉しくなるような商品やサービスを作る。そういう純粋な気持ちは不思議と周りにも伝わり、売上とは別の形で経営者や従業員の人生を豊かにする。
そして、この考え方が社長学の要でもある。リーダーは常に会社全体の方向性を示す。もし社長が「とにかく儲けたい」という損得勘定を最優先していれば、社員も同じ姿勢をとるようになる。反対に「まず善悪を考えよう」「顧客の幸福感を大事にしよう」というリーダーがいる会社は、自然とスタッフも誠実に行動し、ファンやリピーターが着実に増えていく。
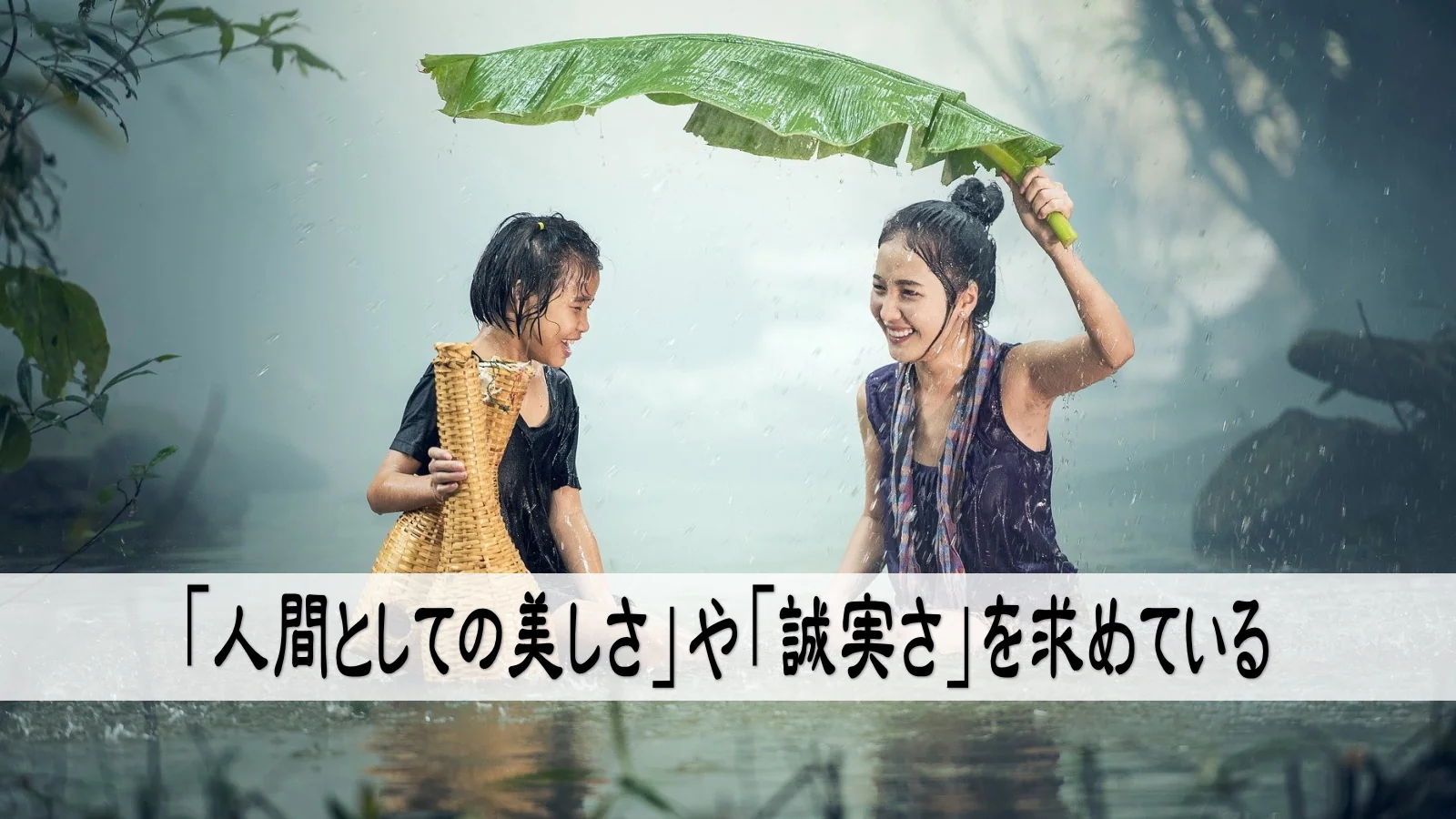
顧客はいつも買い物を通じて「人間としての美しさ」や「誠実さ」を求めている。そこに応える心があるからこそ、長く愛されるビジネスになる。最初は小さな商いであっても、時間が経つほどに信頼が大きく育ち、拡大志向よりも安定的かつ持続的な成長を実現できる。
結果的に売上も伸び、資産も増やせるかもしれないが、それはあくまで副次的なもの。本質は「お客の幸福感」である。自分も他人も苦しまない道を選んでいけば、「損得より先に善悪を考えよう」という言葉がまさに身体に染みついてくる。そこにこそ、商いを楽しむ心があり、軽妙酒脱な経営の日々が待っている。
スモールビジネスの世界だからこそ、このアットホームな幸福感経営が可能になる。大企業のような大規模システムに縛られず、経営者の思いや理念が即座に行動に反映される。好きなことを活かし、周囲と共に笑って過ごせる環境こそ、経営者にとっても最高のやりがいになる。ぜひ、日々の商いで「善悪」を軸に据え、誇り高く、そして粋にビジネスを楽しんでほしい。