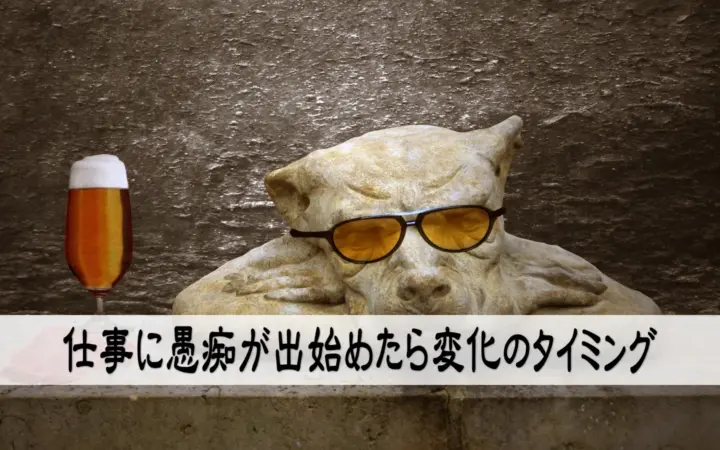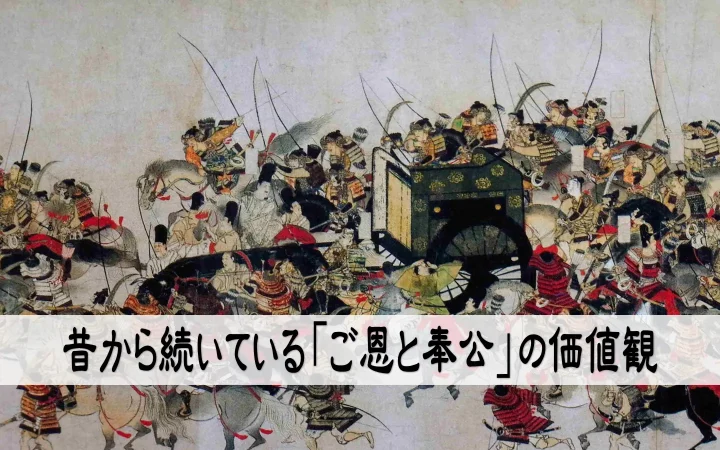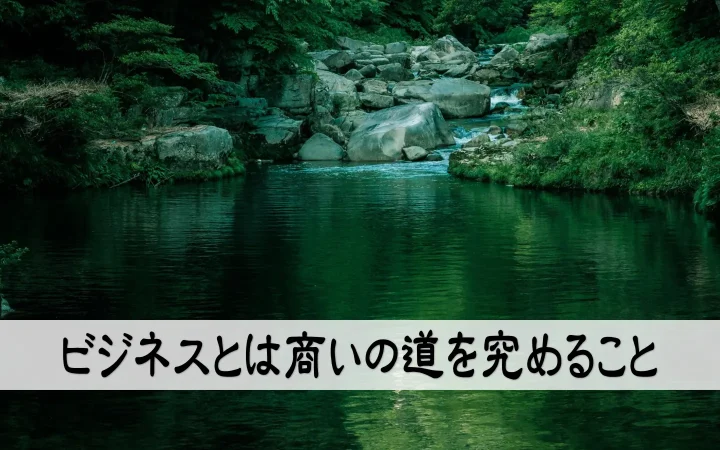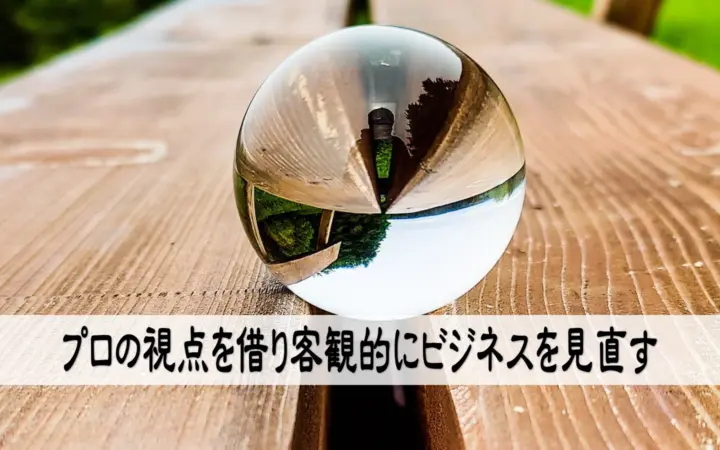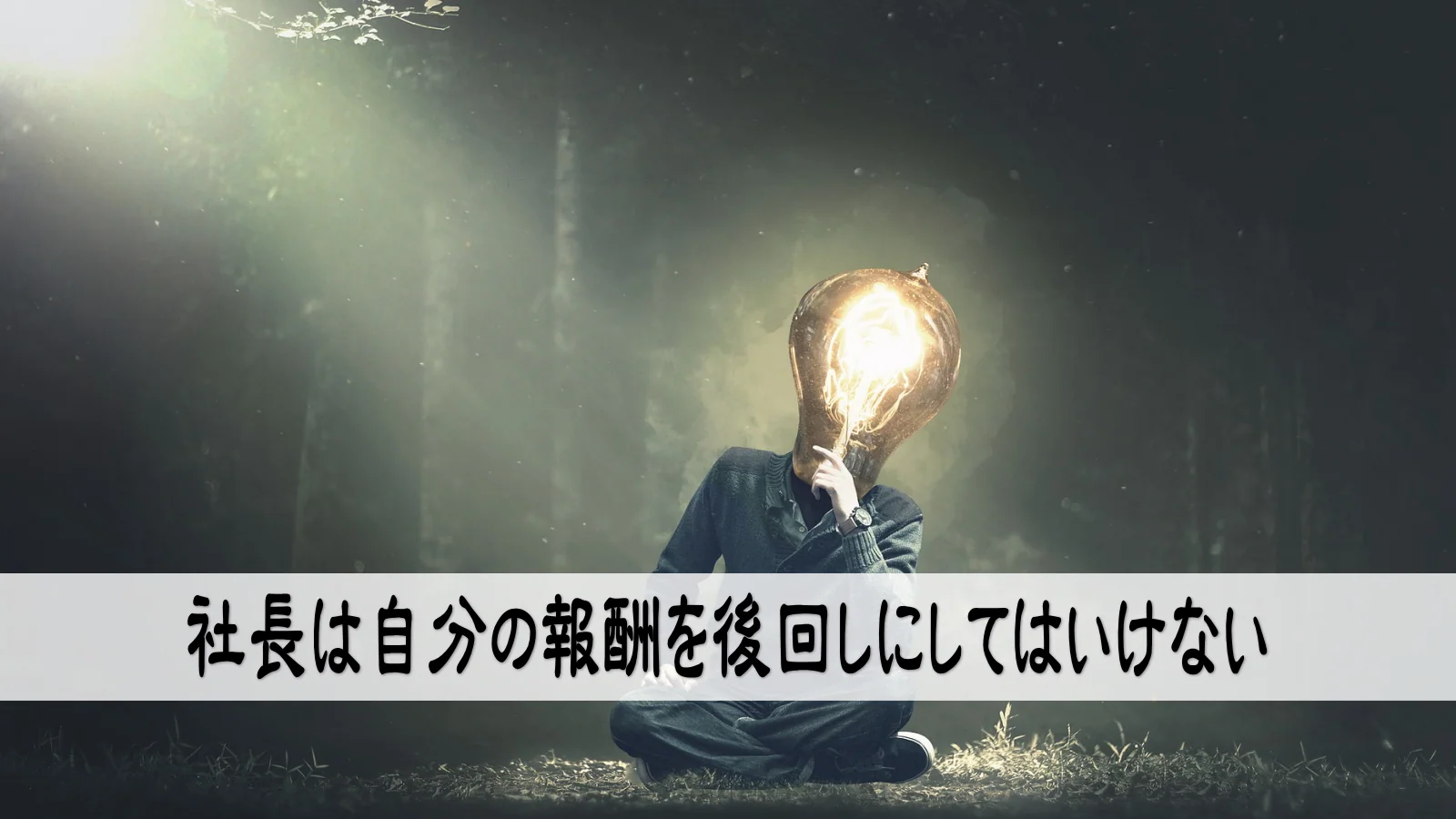
小さな会社では社長が最も重要な存在であり、最大の価値を生み出している。しかし、多くの社長が自分の貢献度を過小評価し、社員の給与や支払いを優先し、自分の報酬を後回しにしている。その結果、経営が不安定になり、社長のモチベーションも低下する。社長が適正な報酬を得ることは、会社の安定と成長に不可欠だ。不要な社員を抱え込まず、経営の本質を見極めることで、持続的な発展が可能となる。まずは「自分に最初に報酬を支払う」意識改革が重要である。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
小さな会社を経営するうえで、社長ほど重要な存在はない。
なぜなら、社長がいなければ事業は始まらず、また終わってしまうからだ。
大企業であれば、社長がいなくても役員や幹部が経営を引き継げるかもしれない。
しかし小さな会社の場合、社長本人の行動がそのまま業績や従業員の働き方に反映される。
いわば「社長=会社」といっても過言ではない。
社長が一番重要な存在である
それほど重要な立場であるにもかかわらず、
「社長としての貢献度を過小評価しているのではないか?」
と感じる社長は意外と多い。
社員や取引先に対して誠実に対応し、支払いも滞らないよう気を配るのは大切なことだ。
だが、その結果として社長自身の取り分がおざなりになっているケースは少なくない。
貢献度とは
「どれだけ会社の価値を高め、お客に喜ばれるか」
という指標であり、最終的には会社が生み出す利益の源泉をつくることに直結する。
小さな会社では、その源泉をつくるメインドライバーが社長自身であることがほとんどだ。
にもかかわらず、自分の貢献を十分に評価せず、経営の犠牲になっていると、会社にとっても社長にとっても良い結果にはつながりにくい。
社長が元気に働き、モチベーションを高く保つことは事業発展の要である。
誰よりも早く出勤し、誰よりも遅くまで働き、日夜考え抜いているからこそビジネスは回る。
その“要”が報われなければ、事業が停滞するのは自然な流れだ。
まずは
「社長がいちばん重要な存在である」
という認識をはっきりと持つことが、健全な経営と継続的な成長への第一歩となる。
貢献度の過小評価がもたらす罠
社長が自分の貢献度を過小評価したままでは、会社の方向性がゆがみやすい。
というのも、社長の意識が
「自分よりも社員や外部への支払いを優先しよう」
という方向に偏りすぎると、本来社長が得るべき報酬に手が回らず、結果的に経営全体が不安定になりがちだからだ。
実際、私も以前経営していた会社で、いつも自分の金を後回しにしていたことがある。ここでは、そのときの体験をそのまま紹介しよう。
「私が以前の会社をやっていた時、自分の金はいつも後回しにしていた。
これは、ほとんどの小さな会社の社長が経験することだと思うが、とにかく、支払いと社員への給料の支払いを最優先して怠らないようにしていたのだ。
そして、月末に残った僅かな額を自分の為に支払っていた。
その結果がどうだったかというと、結局、ずっと金銭的に苦労し、長時間一生懸命働いていたにも関わらず、私の収支は、常にぎりぎりセーフという感じだったのだ。
このギリギリセーフというところが、思い当たる人が多いのではないだろうか。」
このように社長が自分の給料を最後に回すと、
「利益は社員や外部への支払いに消えるものだ」
という誤った構図が定着してしまう。
社長が十分な報酬を得ていないと、自分のモチベーションや体力は損なわれる一方だ。
それが続くと結局、会社の業績が伸び悩んだり、ビジネス自体を続けるのが苦痛になってしまう。
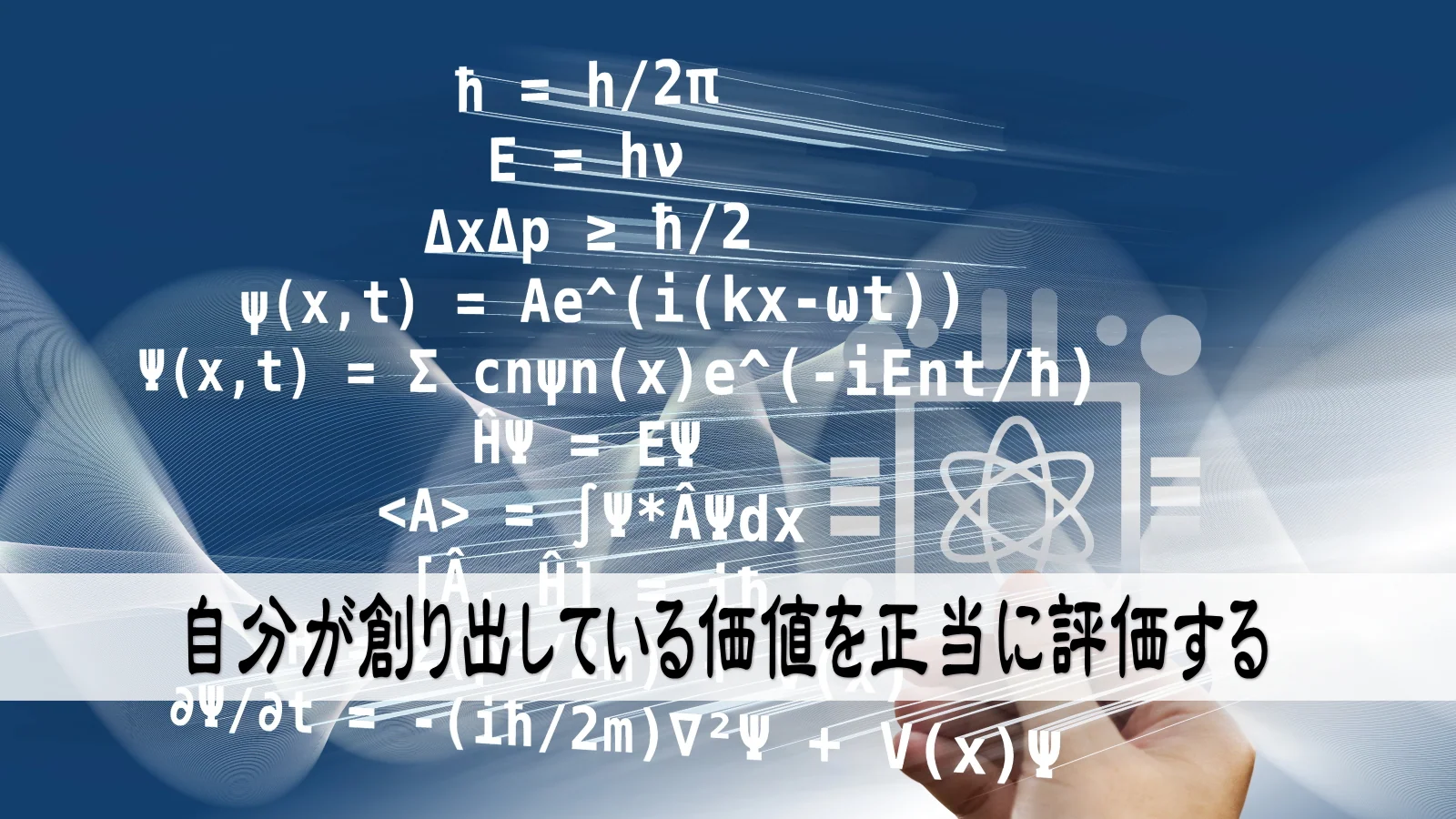
本来であれば、自分が創り出している価値を正当に評価することこそが社長学の基本だ。
貢献度の大きい人がふさわしい報酬を受け取るのは当然のこと。
しかし
「小さな会社だから」
「社員が大切だから」
そう理由をつけて、社長が自分を後回しにしていると、かえって社員にとっても良い環境ではなくなってしまう。
社長が疲弊してしまえば、事業を拡大する余裕も失われ、最終的には社員の安定的な雇用さえ危うくなるかもしれない。
つまり、自分の貢献度を過小評価しないことは、会社全体を守ることにもつながる。
まずは
「社長が適正な報酬を得るべきだ」
という当たり前の感覚を取り戻すことが重要になる。
自分の給料を最優先する意義
では、なぜ
「自分の給料を真っ先に確保する」
ことが大切なのか。
それは、社長がこの会社における最大の価値創造者だからである。
小さな会社では特に、社長の働きにより会社の命運が大きく左右される。
アイデアを出し、営業をかけ、トラブルに対処し、意思決定を行う。
これらすべてを行うのは社長であり、他の人が代わりを務めるのは難しい。
自分の給料を最優先するというと、
「社員に給料が行き渡らなくなったらどうするんだ」
と心配する声があるかもしれない。
しかし、それこそが
「社長の貢献度を軽視する罠」
である。
もし本当に社員に回すお金が足りないとすれば、それはその社員が生み出す価値が給与を賄うレベルに達していないということだ。
不要な社員を雇い続けることは、社長のモチベーションを下げるだけでなく、会社全体のバランスを崩しかねない。
もちろん、従業員の生活を支えたいという思いも大切だ。
しかし、それによって社長が自分の生活を圧迫し、貢献度に見合わない報酬で我慢しているようでは、本末転倒だ。
社長が長時間働いて疲れ切り、事業を続ける気力を失えば、従業員も安定した職場を失ってしまう。
まずは社長自身が
「自分のためにお金を使うのは必要な投資だ」
という認識を持つべきである。
社長学とは、会社をどう率いて成長させるかを学ぶ学問でもあるが、その第一歩は
「自分を大切にする」
ことにある。
社長が自身の貢献度を正しく評価し、相応の報酬を受け取ることで、会社運営に対する責任感ややりがいも格段に増す。
そうした前向きなモチベーションこそが、ビジネスをさらに伸ばす原動力となる。
不要な社員との向き合い方
「自分に最優先で給料を出す」
という考え方に抵抗を感じる社長は多い。
しかし、それによって社員への給料が払えなくなるとしたら、そもそもその社員は会社にとって必要な人材なのかを考え直す必要がある。
小さな会社であればあるほど、ひとりひとりの社員に対して
「本当にこの人は会社に貢献しているだろうか」
「この人がいることで会社の利益は増えているだろうか」
そう厳しく見極めるのが大事だ。
もし明らかに生み出す価値よりコストのほうが大きいなら、雇い続けるのはお互いにとって不幸な状況になりやすい。

もちろん、ただ数字だけを見て即断すればいいというものではない。
経験や人間関係、将来的なポテンシャルを考慮する余地はある。
しかし、社長が自分の給料をもらえないほど困窮しているのに、明らかに貢献度の低い社員をそのまま置いておくのは、会社の存続に関わる問題だ。
小さな会社での経営は、限られたリソースをいかにうまく使うかが肝要になる。
社員もそのリソースの一部であり、その存在が会社の成長を加速させるなら積極的に雇うべきだ。
一方、どうしてもコストに見合わない場合は、残念ながら早めの決断が必要になる。
社長が本来受け取るべき報酬を維持しつつ、会社の成長を目指すためには、そのような
「不要な社員を抱え込まない勇気」
も求められるのである。
モチベーションを高める社長学
社長が自分の給料を後回しにして、かろうじて回る経営を続けていると、いずれモチベーションが大きく下がる。
人間は
「報酬が得られる」
とわかっているからこそ、やる気が湧くし、困難にも立ち向かえる。
これは決して金銭欲だけの問題ではなく、
「自分の労力やアイデアが正しく評価されている」
という実感の問題だ。
この
「自分を評価している」
という感覚こそが、社長のモチベーションを支える土台となる。
モチベーションがあれば、難しい局面でも粘り強く戦う意欲が湧き、新しいアイデアを取り入れる柔軟性も生まれる。
逆に、十分な報酬が得られない状態が続けば、
「もうこれ以上頑張っても仕方がない」
という思考に陥りがちだ。
社長学の視点で見ると、社長が抱くモチベーションは会社の生命線といえる。
大企業ならば組織が大きいため、多少社長のやる気が下がっても周囲のサポート体制でカバーできるかもしれない。
しかし小さな会社であれば、社長が落ち込めば会社全体が暗くなるし、社長が前を向けば社員もついてくる。
だからこそ、まずは社長自身がしっかりと自分の貢献度を評価し、自分に投資していく必要があるのだ。
お金を受け取ることは悪ではない。
むしろ、
「自分を大切にする」
という態度を率先して示すのは社長の役目だといえる。
適正な報酬を得ている社長だからこそ、
「次のステップに向けて、もっと頑張ろう」
という前向きな姿勢を保てる。
そしてその姿勢が周囲にも伝わり、会社の空気を明るくする。
結果的に、社員にも良い影響が及ぶのである。
社長の意識改革で会社を伸ばす
最終的に、会社を伸ばす鍵は社長の意識改革にある。
いくら
「社長の貢献度は大きい」
「自分を大切にするべきだ」
と頭で理解していても、長年の習慣や周囲のプレッシャーから抜け出せないままでは行動は変えられない。
まずは
「自分に最初に給料を払う」
というシンプルな一歩を踏み出すことが、意識をガラリと変えるきっかけになる。
自分の報酬をしっかり確保してみると、不思議なことに視界が開けてくる。
経営者としての責任感も増し、
「自分を後回しにしなくていいのだ」
と思うことで、より冷静に会社の数字や社員の動きを見直す余裕が生まれる。
すると、これまで
「仕方ない」
と思って放置していたコストを削減できる案が見つかったり、本当に必要な人材の条件が明確になったりすることがある。

社長が自分に正当な対価を払うことで、会社の運営に無駄や甘えがあればそれが際立つ。
そこで勇気を持って改善を進めるのが、真の社長学といえるだろう。
そして改善が進むと、今度は社長自身のモチベーションがさらに上がり、好循環が生まれる。
社員も
「この社長のもとで働きたい」
と思えるようになり、人材の質が向上する可能性も広がる。
会社の規模や業種を問わず、貢献度を過小評価する社長は意外と多い。
だが、社長は会社の要であり、そのモチベーションこそが全体の未来を左右する。
まずは
「自分の働きにふさわしい報酬を受け取る」
という行為を当たり前のものとして受け入れ、意識を改革していく。
それが会社を大きく伸ばす原動力となり、持続的な成長へとつながるはずだ。