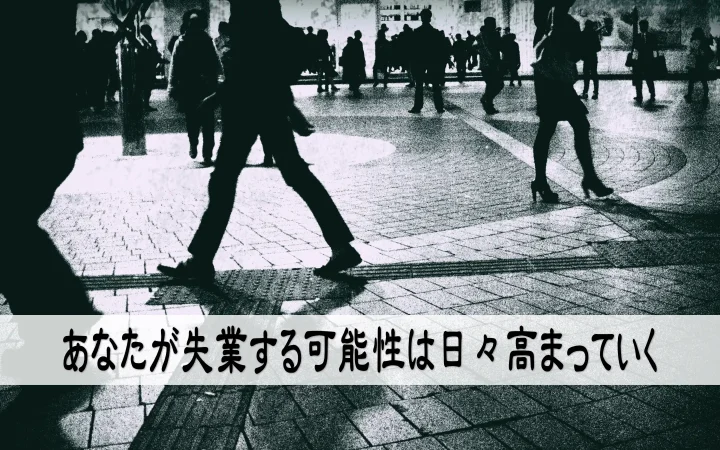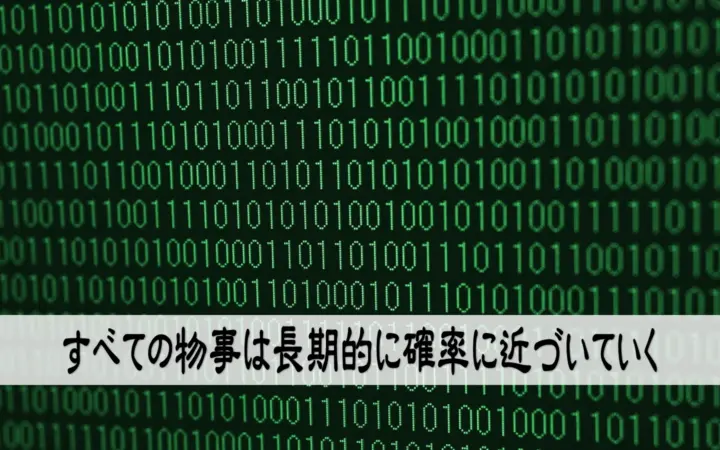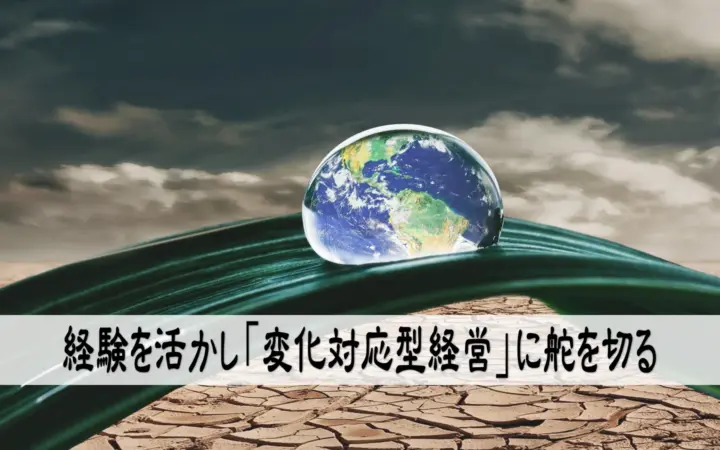令和の時代、日本社会の格差は拡大し、富裕層と貧困層の二極化が進んでいる。グローバリズムやAIの発展により、「組織の時代」から「個の時代」へ移行し、企業も個人の影響力を活用するようになった。特にAIを使いこなせるか否かが新たな格差要因となり、エヌビディアCEOの「AIを使いこなす人が淘汰を生き抜く」という言葉が象徴するように、学び続ける姿勢が重要だ。小さな会社が生き残るには、ネットを活用し、独自性を打ち出しながら、AIを取り入れる柔軟さが求められる。時代の変化に適応し、挑戦を続けることこそが、成功への鍵となる。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
令和になってから、「格差社会」というキーワードを耳にする機会が一段と増えている。
かつては「一億総中流」と呼ばれ、社会全体の所得が緩やかに分布していた日本も、いまや上下にはっきり二極化してきた。
富裕層は資産1億円以上を持つ人が200万人を超えるともいわれ、いっぽうで貧困層に沈み込む人々が急増しているのだ。
令和の格差拡大と小さな会社の生存戦略
この背景には、グローバリズムの台頭やIT革命など、さまざまな「時代の変化」がある。
日本のみならず世界全体がボーダーレス化して、企業活動はますます国境を越えるようになった。
その結果、安価な労働力や資源をどこからでも調達できるようになり、人件費の安い国との競争が国内の労働市場を圧迫している。
さらに企業は、利益を追求するために非正規雇用や派遣労働を増やし、人件費を抑えようとする。
こうした動きが、所得格差を拡大させてきた。
そして令和の時代に入り、グローバリズムへの批判が高まる場面もあったが、結局は資本主義の大きな潮流を止めることはできなかった。
コロナ禍やウクライナ戦争の影響でグローバル化が一時停止しているように見えても、その嵐が収束すれば「遅れ」を取り戻すかのように、再び急激にグローバル化が進むと予測される。
こうした流れのなか、小さな会社の経営者がどう生き残るかはまさに死活問題だ。
大企業ならではの体力やブランド力がない小規模事業者は、少しの経営判断の遅れが致命傷につながりかねない。
そこで必要なのは「個」の強みや独自性を活かし、時代に合わせて変化していく柔軟さだ。
格差の波に翻弄されるのではなく、波に乗るための知恵や戦略が求められる。
「組織」から「個」へと時代が移ろうなか、競争相手は国内の同業他社だけではない。
ネットを駆使し、海外を含めた広い市場でビジネスを展開できる小さな会社こそが、令和という荒波を乗り越えていく可能性を秘めているのである。
昭和・平成・令和のビジネス環境の変遷
まずは昭和から平成、そして令和へと、どのようにビジネス環境が変わってきたかを見てみよう。
昭和の時代は高度経済成長期で、工場やオフィスには大量の人材が同じような条件で集められ、同じような仕事を効率よくこなすことで日本全体が潤っていた。
終身雇用や年功序列が当たり前で、「組織の歯車」として働くことに安心感があったのだ。
しかし平成に入ると、バブル崩壊やグローバル化の波によって状況は一変する。
コスト削減や効率化を優先する企業は、必要不可欠と思われる一部の正社員しか守らず、残りを非正規雇用や派遣社員に切り替え始めた。
さらに、インターネットの普及が加速し、「人・モノ・金」が国境を越えて流動化。安価な労働力を求めて海外進出する企業も増え、日本国内の従業員は賃金の引き下げ競争を余儀なくされた。

そこに令和の時代が到来する。
AIやロボットなどのテクノロジーが飛躍的に進化し、またSNSや動画配信プラットフォームなどの普及によって、
「個人が世界を相手にビジネスをする」
ことが以前よりも簡単になった。
企業にとっては、社員を大量に雇うよりも、インフルエンサーやYouTuberなど少人数の「個」の力を活用する方が効率的という時代だ。
たとえば、100人の営業マンを雇ってコツコツ営業するより、一人の有力YouTuberに広告費を支払って配信してもらうほうが、あっさり大きな成果を上げる場合もある。
こうした時代の変化を受け、小さな会社は大手企業に負けない独自の戦略を立てることができるのかがポイントとなる。
すでに昭和のような大量生産のビジネスモデルは通用しない。
平成時代のように非正規雇用を増やして人件費を抑えるだけでは、経済全体のパイが広がらないなか苦しい戦いを強いられる。
令和の今こそ、新しいビジネス環境に合わせた発想の転換が必要なのである。
AIとネットが生み出す新しい格差
令和でさらに注目を集めるのが「AI」と「ネット」だ。
これらがもたらすメリットは計り知れないが、その一方で、新しい格差の要因にもなっている。
ひとつは
「AIを使いこなせる人」と「そうでない人」
の格差だ。
エヌビディアCEOジェンスン・フアンの言葉に
「AIが仕事を奪うのではなく、AIを使いこなす人たちによって淘汰される」
というものがある。
AIを上手に活用できる企業や個人は生産性が飛躍的に高まり、効率よく成果を出せるようになる。
一方でAIを毛嫌いして学ばない人は、短期間で大きく差をつけられてしまう可能性があるのだ。
もうひとつは、ネットを通じてビジネスを展開できるかどうか。
スマホが普及している現代では、誰もがネットにアクセスできるように見えるが、実はパソコンを使いこなし、仕組みを作れる人は少ない。
動画を見る側、SNSで受け取る側にまわる人は多いが、
「コンテンツを作る」
「ネットで集客する」
側に回れる人や会社は限られている。
その差がそのまま収益の差となり、所得格差を拡大させる。
つまり、
「AIとネットは便利」
だけで終わらせるのではなく、その波に乗れるかどうかで大きな勝負が決まる。
パソコンなんて古い、スマホで全部できると考えていると、コンテンツを生み出す力が身につかず、いつまでも「提供されるサービスを消費するだけ」の立場にとどまってしまう。
この構造は「格差社会」をさらに助長する大きな要因になり得る。
小さな会社だからこそ、この流れはチャンスにもなる。
大企業がAIの導入に時間をかけているうちに、小回りの利く企業や個人事業主が斬新なサービスや仕組みを作り上げ、急成長する例も出てきている。
時代の変化に素早く対応し、「AI」と「ネット」を自社のビジネスモデルに取り込むことで、格差をチャンスに変えていく余地は十分にあるのだ。
小さな会社の生存戦略―ネットの活用
小さな会社が令和の時代を生き抜くために、まず押さえておきたいのが「ネットを使う力」だ。
従来のように実店舗で商売をするだけでなく、ネット上に集客の仕組みを作り、顧客との接点を増やすことは避けて通れない。
ネットショップを開設したり、SNSやYouTubeを活用して商品やサービスをアピールしたりすることは、今や必須の経営戦略となっている。
たとえば、地域に根ざした小さな飲食店でも、SNSでの情報発信を続けることで遠方の人に知ってもらったり、特定のコミュニティでファンを増やしたりできる。
ネット上の評判が蓄積されれば、広告費をあまりかけなくても顧客が自然と集まる。
あるいは小さなメーカーでも、自社サイトで製品を販売しながらブログやメルマガで新製品やお得情報を発信していけば、リピーターを育てられる。
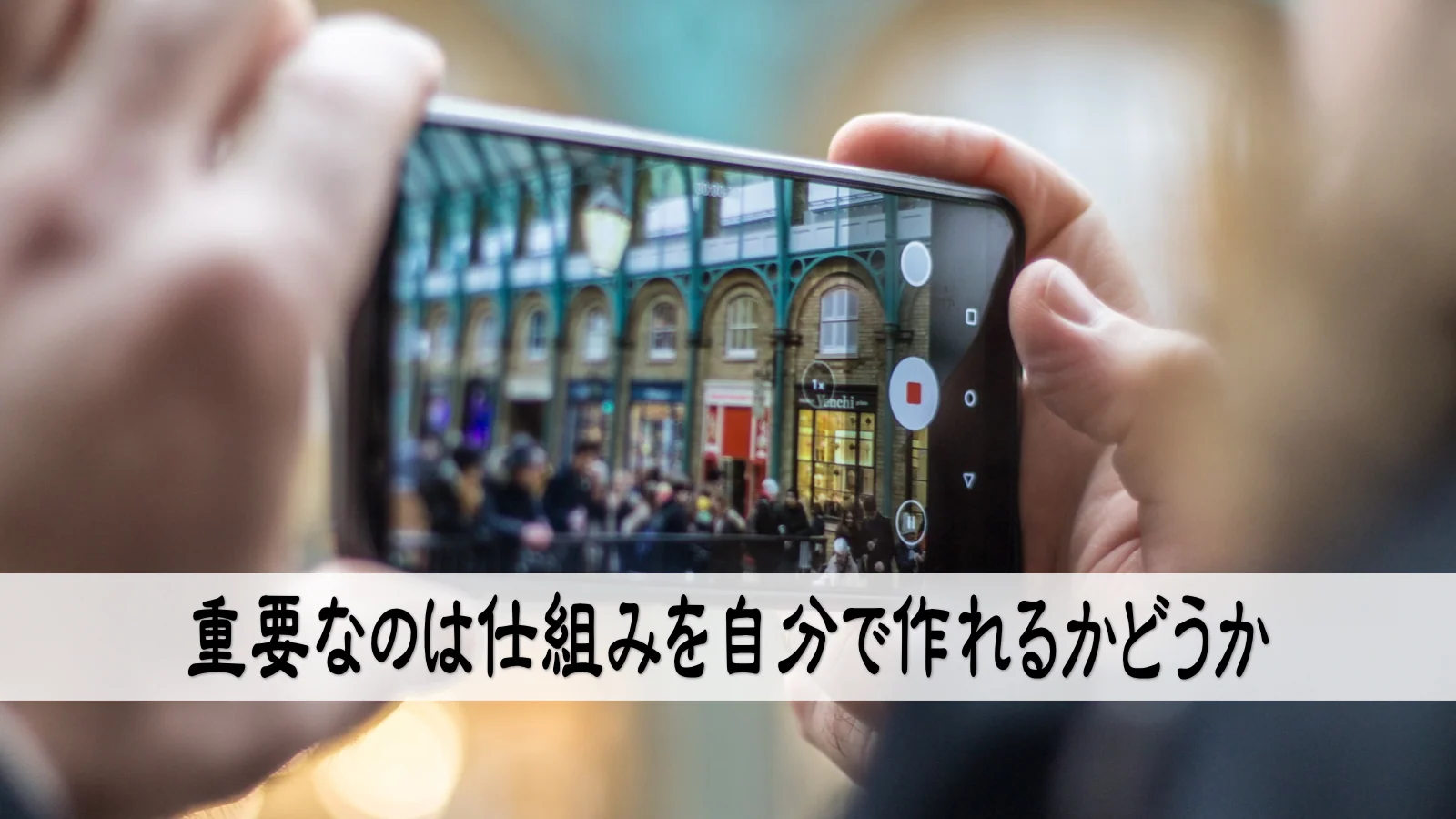
さらに重要なのは、単にネットを「使う」だけでなく、「仕組みを自分で作れる」かどうかだ。
外注して丸投げすると、どうしても費用がかさんだり、思うような成果が出なかったりするケースが多い。
最低限の知識を持っていれば、SEO対策やアクセス解析、広告の出し方などを学びながら試行錯誤できる。
小さな会社は大手のような潤沢な予算はないかもしれないが、アイデアとスピードを武器に、ネットを最大限活用すれば大きなチャンスをつかむことも可能だ。
AIを導入するハードルが高いと感じるなら、まずはネットマーケティングから始めるとよい。
SNSやブログ、動画配信などのツールは無料または低コストで始められる。
その上で実際に売上が伸びてきたら、自動化や分析ツールとしてAIを少しずつ導入していくのも手だ。
何よりも、やってみる勇気とチャレンジ精神が重要なのである。
社長はスーパーマンであるべきか
小さな会社の経営者は、しばしば
「スーパーマンじゃないとやっていけない」
と言われる。
マーケティング、営業、経理、労務管理など、会社を回すための多岐にわたる業務を、ほとんど一人でこなさなければならないからだ。
ネット上の仕組みづくりにしても同様で、外注を考えるにも設計図が描けないと話が進まない。
とはいえ、最初から何もかも完璧にこなせる経営者など存在しない。
大切なのは、
「とりあえず手を動かしてみる」
ことだ。
ネット集客やAI活用に苦手意識がある人でも、まずは小さくトライしてみると、不思議とハードルは下がる。
そこから少しずつ勉強を重ね、知識を蓄え、必要に応じて外注を上手に使えばいい。
さらに、近年はオンラインコミュニティや経営者向けの勉強会、SNS上の情報共有など、学ぶ手段が山ほどある。
成功事例やノウハウは探せばいくらでも見つかるが、情報を「取りに行く」姿勢がないと宝の持ち腐れになってしまう。
とくにAIやIT技術は日進月歩で進化するので、少しでも興味を持ったら積極的に情報をキャッチアップすることが大事だ。
「スーパーマンになるのは無理」
と嘆くより、
「できる範囲でまずやってみよう」
と一歩を踏み出すほうが建設的だ。
自分だけですべてをこなせなくても、友人や社外パートナーと連携すれば、よりスピーディに仕組みを整えられる場合もある。
要は、学びと行動を絶えず続ける経営者こそが、時代の変化に適応し生き残る可能性を高められるのだ。
今後10年で生き残るために必要なこと
これからの10年で小さな会社が生き残るには、「AI」「ネット」「独自性」という三つのキーワードを意識してほしい。
まずAIは、先述したように活用できるかどうかで生産性や競争力に大きな差がつく。エヌビディアCEOジェンスン・フアンの言葉どおり、
「AIそのものが仕事を奪うのではなく、AIを使いこなす人たちが使いこなせない人たちを淘汰する」
時代なのだ。
怖がるばかりではなく、どう使いこなして業務を効率化するかを考えよう。
次にネットは、ビジネス活動の中核になりつつある。
リアルの店舗や取引先だけに頼っていると、地理的・時間的な制約を超えにくい。ネット上に独自の仕組みを構築し、
SNSや動画、ブログなどを通じて自社のファンを獲得することで、安定した集客と売上が期待できる。
もしまだネットの活用が不十分なら、今すぐ始めても遅くはない。
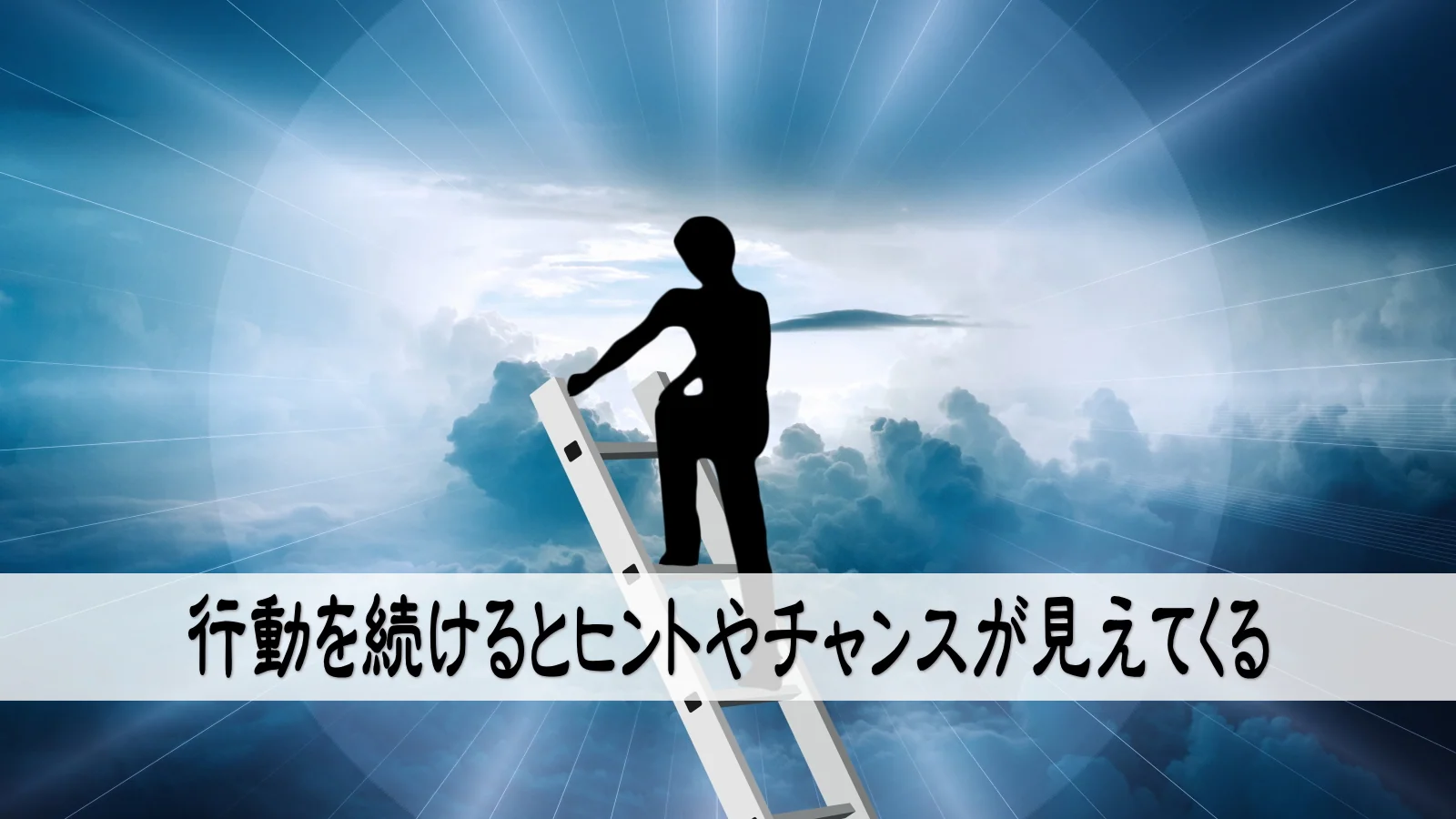
そして最後に「独自性」だ。
同じような商品やサービスを提供していては、大企業や他の競合と差別化できず価格競争に巻き込まれてしまう。
小さな会社こそ、自分たちにしかないストーリーや価値を打ち出すことが重要だ。
たとえば製造工程にこだわりがあるなら動画で公開し、職人技や社長自身の想いをアピールする。
あるいはユニークな販促企画を打ち出してSNSでバズを狙うなど、「この会社ならでは」を外に発信していく。
時代の変化はこれからも止まらない。
コロナ禍や世界情勢の影響など、先を見通すのが難しい状況が続くかもしれない。
それでも小さな会社の強みは、柔軟かつ迅速に戦略を変えられることだ。
失敗したらすぐ修正し、新しいチャレンジができる。
行動を続けるうちに必ずヒントやチャンスが見えてくる。
AI、ネット、そして自社ならではの強みを最大限に活かし、「格差社会」の荒波を突き抜けよう。
大企業にはないフットワークの軽さと創意工夫こそが、小さな会社の未来を切り開く最大の武器になるはずだ。