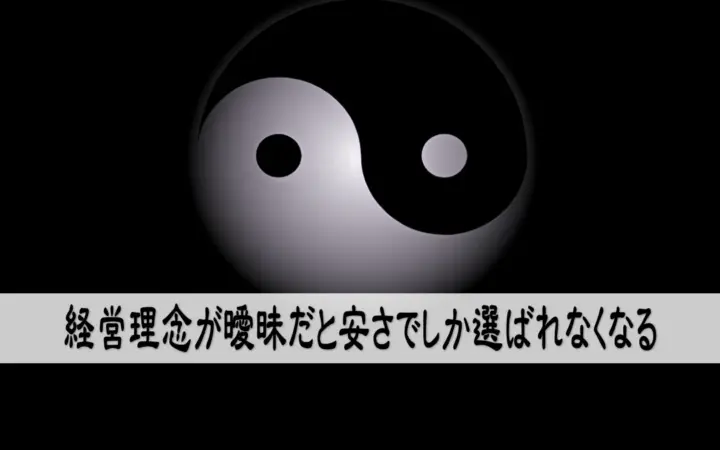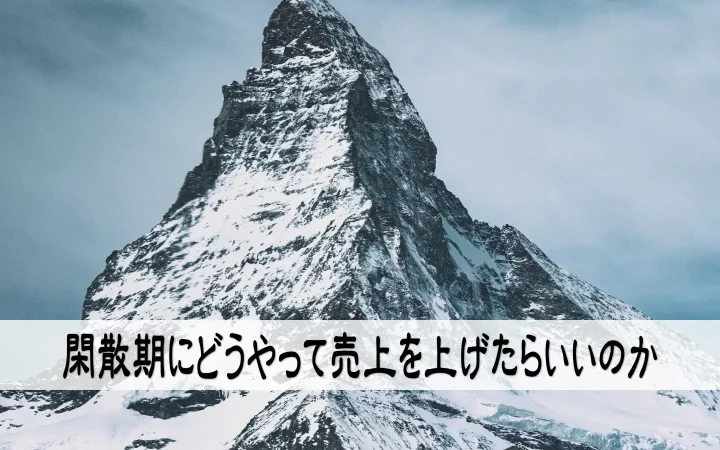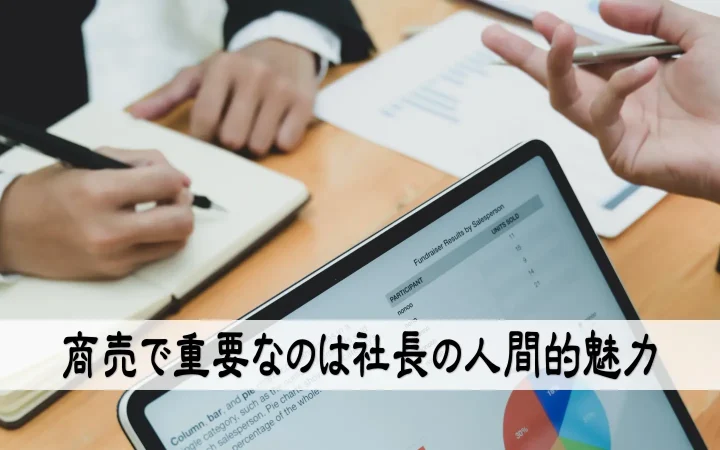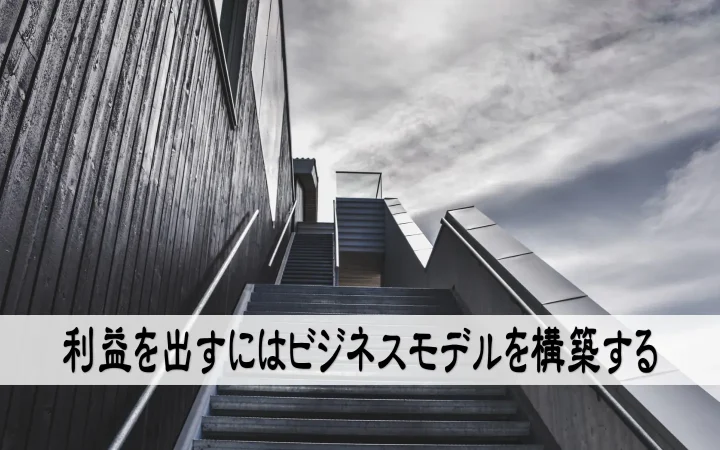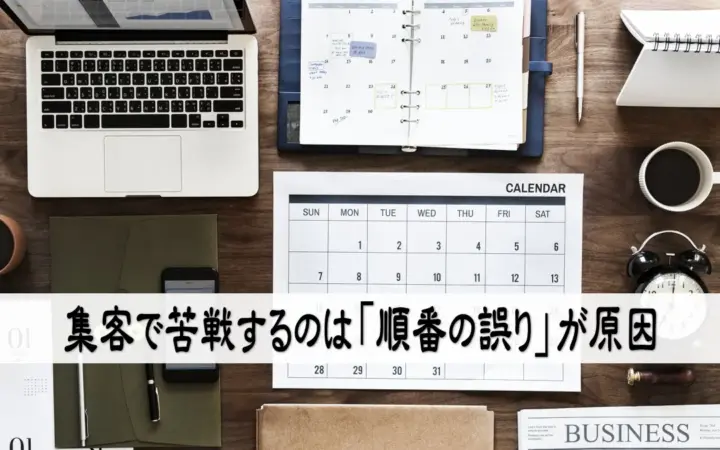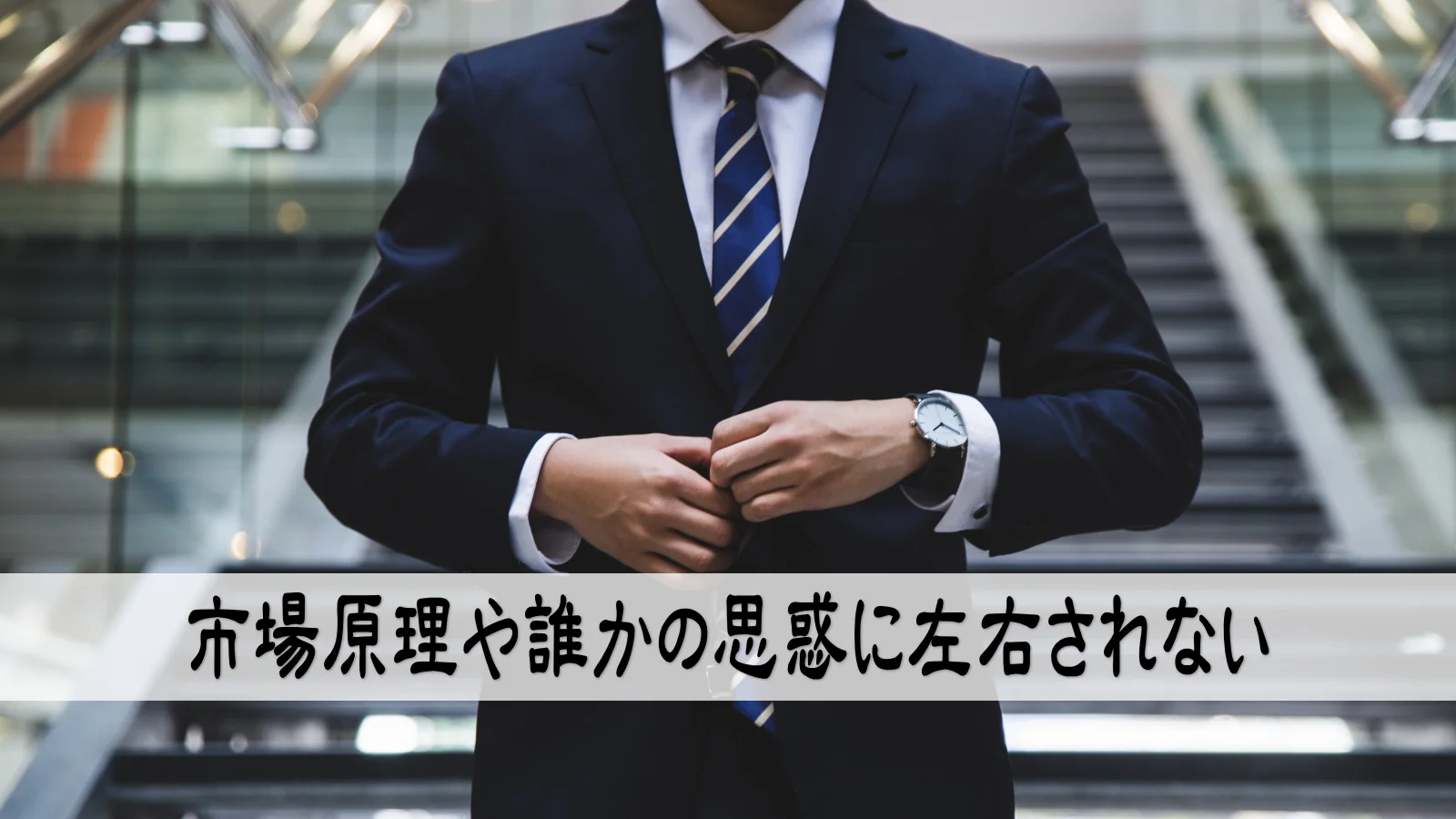
ビジネスの本質は、お客との一対一の関係にある。小さな会社は、社長のアイディア・情熱・信念を軸に、お客の声を直接受け止めながら柔軟に経営できる強みがある。しかし、規模を追いすぎると、経営者の自由が奪われ、利益率や意思決定のスピードも低下する。邱永漢氏は「小さな会社をいくつも持つほうがリスクが少なく、経営者も豊かになれる」と説いた。最終的に、たった一人のお客を大切にすることこそが、経営を成功へ導く本質である。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
ビジネスの本質は、お客と向き合う一対一の関係にこそ宿る。
どんな分野であれ、
「この人に喜んでもらいたい」
という思いが、商売のスタート地点だ。
ところが、会社を運営していると、いつのまにか売上や効率の数字ばかりを追いかけがちになる。
もちろん数字を意識することは大切だが、その前に
「このお客さんのために何ができるか?」
という一対一のつながりを見失っては、本末転倒だ。
ビジネスの原点は一対一にある
小さな会社の場合、経営者が直接お客とやり取りするため、相手の声や要望を肌で感じやすい。
要望や不満をすぐに知り、柔軟に対応できるからこそ、独自の価値を提供しやすい。
これは社長が遠い席に座り、現場の声が届きにくい大企業にはないメリットといえるだろう。
「とにかく規模を拡大しなければ生き残れない」
という考え方は根強い。
しかし、むやみに大きくすることで、
「そもそも何をしたかったのか?」
が見えなくなるケースは多い。
一対一の関係をおろそかにすると、商売の土台そのものが揺らいでしまうのだ。
商売の原点は、数字や効率を超えた“生身のお客さん”への気持ちにある。
小さな会社だからこそ、この一対一のつながりを大切にできるし、それが結果的には大きな強みを生む。
お客との密接な関係を基盤に、自分たちの魅力をしっかりと磨き上げる。
そこにこそ小さな会社の真価があるのではないだろうか。
社長の情熱と信念を軸に経営する
中小企業や個人事業は、社長自身のアイディア・情熱・信念によって回っていると言っていい。
戦後の日本を立て直した松下幸之助や本田宗一郎などの偉大な経営者たちは、まさに「思い」そのものをエンジンに事業を広げていった。
彼らの情熱や信念は強烈で、それが社員や取引先、お客を巻き込む原動力になっていたのだ。
しかし、会社が大きくなり、組織が複雑化すると、どうしても社長の想いが伝わりにくくなる。
組織の階層を経るうちに、メッセージは薄まり、場合によっては投資家や市場原理の都合が優先されてしまう。
売上や株価ばかり注目され、創業時に掲げたビジョンがどこかへ消えてしまうことも少なくない。
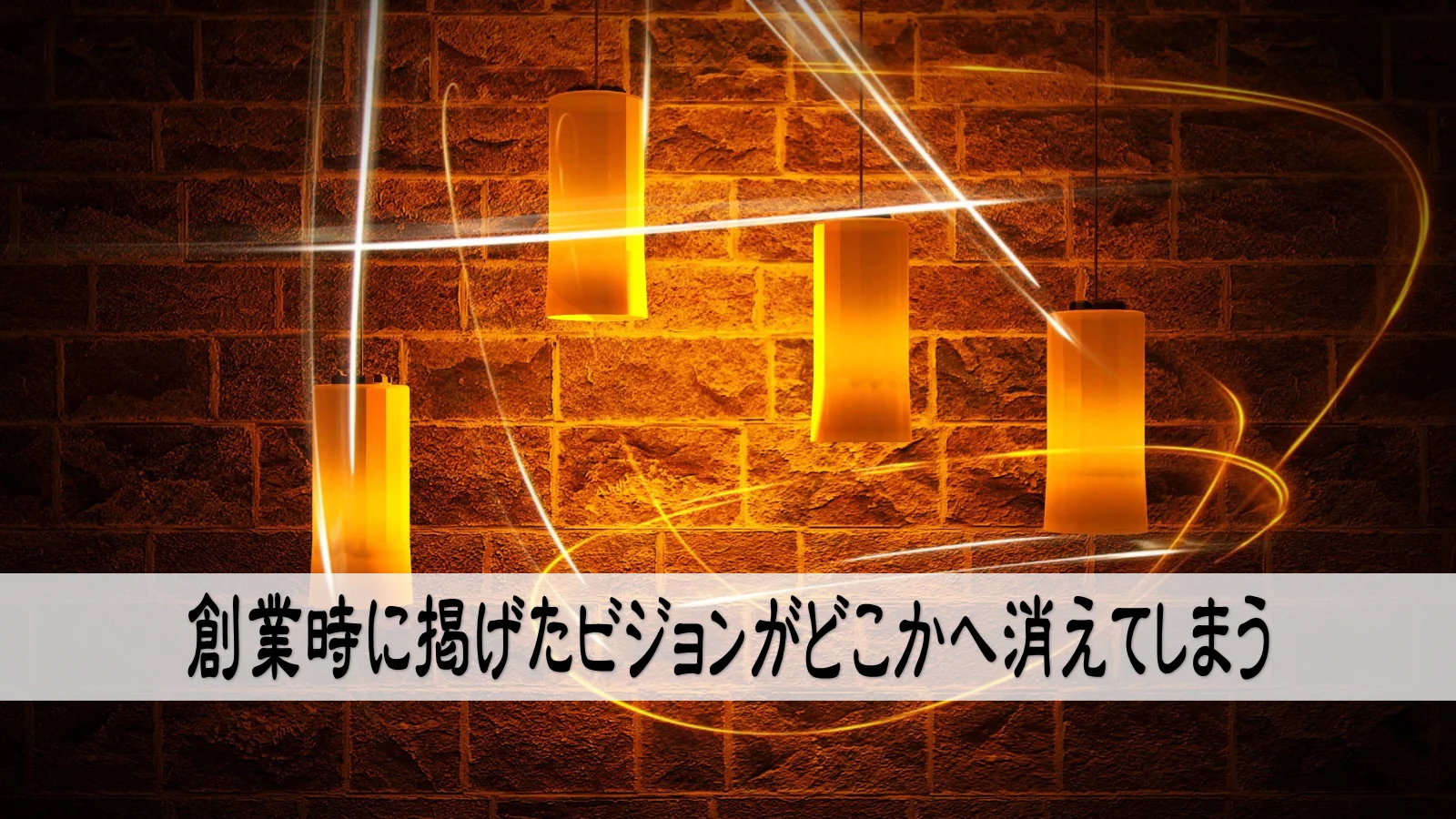
もちろん、大企業として大きく雇用を生み出し、社会的なインパクトを与える道を選ぶのも立派な戦略だ。
ただし、それがゴールだとは限らない。
自分ならではの経営哲学を貫き、小さくとも独自色を発揮したいと考える経営者は多い。
結局のところ、経営の方向性を決めるのは
「社長が何を望むか」
だ。
情熱と信念を注ぎ込んで、自分が理想とする事業を形にし続ける。
会社は小さくても、そこに社長の想いがしっかり根づいていれば、十分に生き生きと成長していくものだ。
大手と中小企業の残酷な現実
昔の大企業は、小さな町工場や家内制手工業からコツコツと積み上げて大きくなった。
松下幸之助が自宅の一室を工場代わりに電球ソケットを作り始めたり、本田宗一郎が小さなガレージでエンジンを磨いていた話は、今でも伝説として語り継がれている。
しかし、現代ではそうした
「小さいところから徐々に拡大する」
ルートが成功パターンではなくなった。
今の大手企業には、投資家や銀行から最初から大きな資金を集め、企画をまとめて一気に業界を塗り替えるケースが少なくない。
映画『ソーシャルネットワーク』で描かれたマーク・ザッカーバーグのように、ネットやSNSというインフラを活用し、短期間で巨大ビジネスを築く人たちもいる
しかし、大規模な投資を受けるということは、そのぶんリスクも高まる。
外部からの資金提供や社員の大量増員があると、経営者の自由度は減り、意思決定のスピードや質にも影響が出やすい。
加えて、売上や利益を最優先に考えねばならず、結果的に
「そもそも何のために商売をしているのか?」
がブレてしまうこともある。
実際、従業員1000人で売上高100億円の会社よりも、従業員10人で10億円を売り上げる会社のほうが利益率が高く、社長も社員も自由に稼いでいるなんて話はよくある。
規模を伸ばすだけが幸せに直結するとは限らないのだ。
たとえ小さくとも、しっかり利益を出して人を幸せにする経営をすれば、十分に豊かにやっていける時代になったといえる。
小さな会社を経営するための要点
小さな会社には、身軽さと柔軟性という大きな武器がある。
巨大組織のように複雑な手続きを踏む必要がなく、社長の
「やってみよう」
の一声ですぐに行動を起こせる。
顧客から寄せられた声にも素早く対応できるので、競合他社が追いつけないスピード感を発揮できるのだ。
こうした考え方を思い出すとき、昔、邱永漢氏(2012年没)と話したときの言葉が非常に印象的である。
彼はこう語っていた。
「お金持ちになりたかったら、 小さな会社をいくつも持つ方がいいよ
会社を大きくすると、リスクだけが大きくなるから。小さな会社は自分のお財布と同じだからね
でも、会社を大きくしてどんどん人が入ってくると自由にならなくなる。さらに、株式公開して、株価が上がって資産家になっても自社株は売れないから、しょせん絵に描いた餅と同じだよ。
そのうえ、死んだら相続税までがっぽり取られる。
だったら、小さな会社をたくさん持ちなさい」
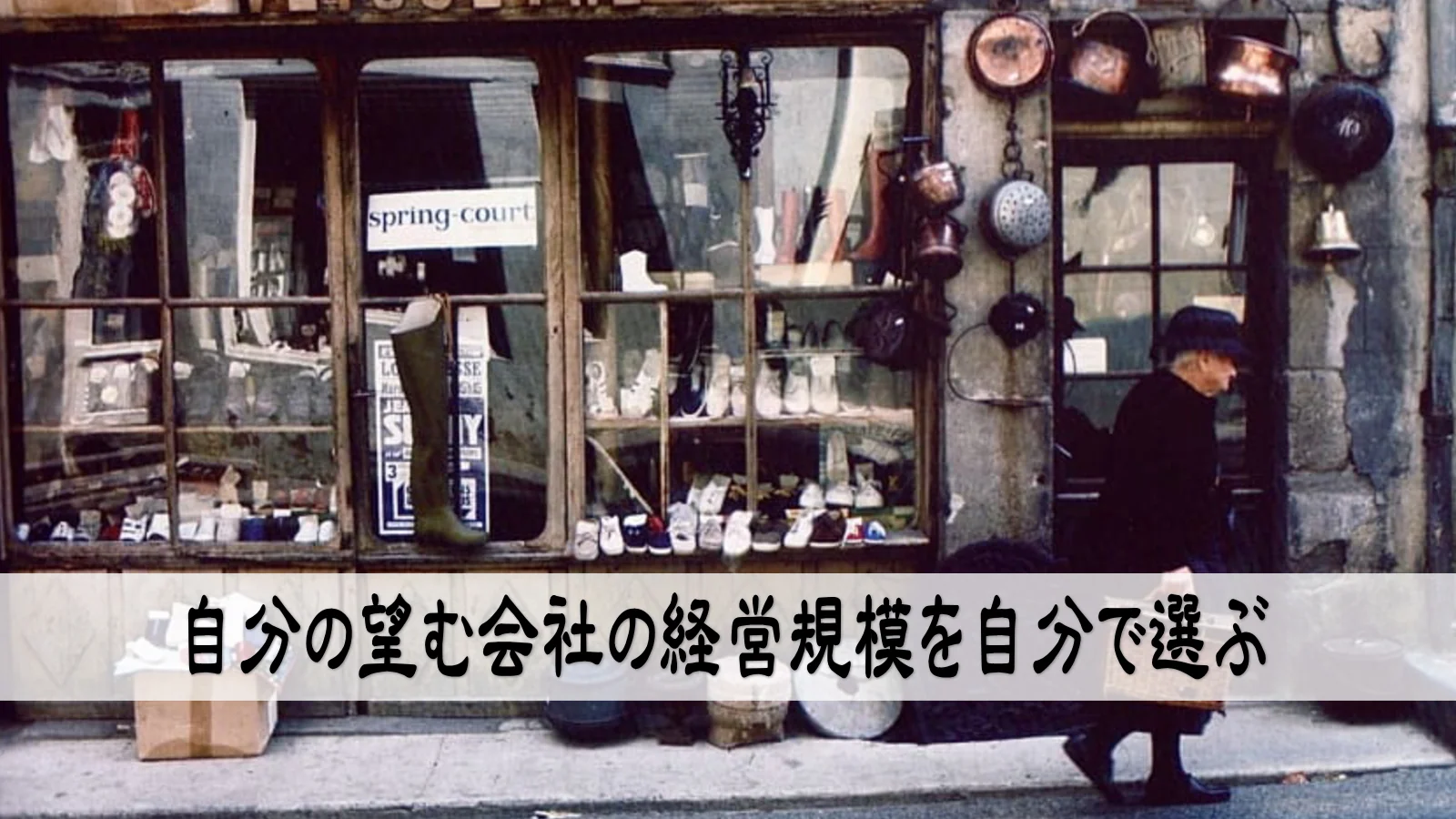
会社が大きくなるほど、責任とリスクも大きくなる。
株式公開して株価が跳ね上がったとしても、その株を自由に売るわけにはいかない。
しかも相続税まで重くのしかかる。
一方、小さな会社なら「自分の財布」感覚で自由に動かせるし、リスクが分散するメリットもある。
「社員五人で一億円の売上をいくつもつくるほうが、社員千人で百億円を目指すよりも、むしろ経営者も社員も楽しく豊かになる」
こうした考え方も、今の時代には現実味がある。
大きくなるばかりが正解ではないし、拡大のプレッシャーに追われて自分を見失う必要もない。
結局は、自分の望む規模を自分で選ぶことこそ、小さな会社を経営する要点といえるだろう。
小さな会社が未来を創る
そもそも商売とは、遠くにいる人とやりとりしたい、安心させたい、笑顔にしたい、そんな人間らしい気持ちがスタート地点にある。
IT分野であれば、通信速度や無料サービスなどを競い合う傾向が強いが、本来は
「人々の生活をどう豊かにするか?」
が核となるはずだ。
ここで、昔見たドラマで感動したワンシーンをシェアしたい。
(ちなみに、私は石原さとみさんの大ファンだ)
「ずーと考えていたんだ。」
「うさんくさい、信用できないと思われている会社で、いったい僕は何をするんだ?」
「IT というと、通信スピードが速いとか、情報量が多いとか、無料で使えるとか、そういうこと ばかりで競い合っているが…」
「そんなことはどうでもいいっ!」
「IT とは…人々の生活を豊かにするものだ。」
「パーソナルファイル だって そうだっ」
「グラハム・ベル という男は、ナゼ電話を作った?」
「事実はわからない。でも、僕はこう思う…」
「遠くにいる恋人の声が聞きたかった。それか、心配ばかりする母親に無事を知らせて安心させたかった。」
「メール に写真をつける技術だって同じだ。」
「離れている人と同じものを見て、一緒に笑ったり、喜んだりしたい…そう思ったから、作ったハズだっ.」
「ITの中心には…いつも人間がいるんだ。」
「僕らの仕事は、たぶん...大切な人を思うコト から始まるんだ。」
「君たちにも、そういう人がいるだろ。」
「だったら、その人の為に創ろう!」『リッチマン、プアウーマン』の最終話より
このセリフが示すように、ビジネスの真髄は
「大切な人を思うこと」
から始まる。
遠くにいる恋人の声を聞きたかったり、写真を共有して一緒に笑い合いたいという、ごく人間的な感情が技術を生み出す。
これはITに限らず、どんな業種にも通じる。
小さな会社であっても同じだ。
資本力や規模に左右されることなく、
「お客の生活をどう豊かにできるか?」
「いま自分にできることは何か?」
そう考え続けられるからこそ、スモールビジネスには大きな可能性がある。
大きな組織のルールや市場原理に縛られず、経営者が自分の感性を信じて動けるのは、まさに小規模ならではの強みだ。
小さな会社が取るべき経営戦略
最終的に、大きな組織を目指すか、小さな組織をいくつも持つかは経営者次第だ。
拡大を目指すことが悪いわけではないし、小さくまとめることがすべての正解でもない。
ただし、世の中には
「小さいほうが自分の思いを貫きやすい」
「大きくならないほうがみんなが幸せになれる」
というケースが確実に増えている。
なぜなら、ビジネスの本質は、お客との一対一の関係に凝縮されているからだ。
社長の情熱と信念を軸に、小さな会社だからこそ活きるスピード感と柔軟性、そして大切な人を喜ばせたいという人間的な気持ち
これらが組み合わさったとき、商売は驚くほど豊かに花開く。

実際、規模を追わなくても、安定した利益を生み出し、長期にわたって顧客と良好な関係を築いている中小企業は数多い。
大きさだけが経営戦略ではないのだ。
むしろ、一対一の距離感を大切にし、自分のやりたいことを形にしていくほうが、経営者も社員も心から満足できる結果につながりやすい。
最後に、商いの原点を思い起こさせる私の大好きな岡田徹の言葉を紹介して締めくくりたい。
生涯の願い
「私の生涯の願いは
タッタ一人でよい
この店は
私にとっては
だいじな店です
と
いってくださる
お客という名の
友人をつくること」『岡田徹詩集』より
———————————————-
岡田 徹
明治37(1904)年東京生まれ。
戦前から戦後にかけて活躍した商業指導家、経営思想家
この詩のなかにある「タッタ一人でよい」という言葉は、規模や効率に走らずとも、たった一人の“お客という名の友人”を大切にすることが商いの核心であると教えてくれる。
大きい会社を作ることだけが成功ではない。
お客との一対一の絆を重んじながら、自分なりの粋な経営スタイルを追求できるのが、小さな会社の醍醐味なのだ。
経営戦略とは、最終的には
「何のために商売をしているのか?」
という問いに答える行為でもある。
その答えが
「一対一の人間関係を大切にして、お客を喜ばせたい」
という原点に立ち返るのなら、それこそが社長にとって最高の戦略ではないだろうか。