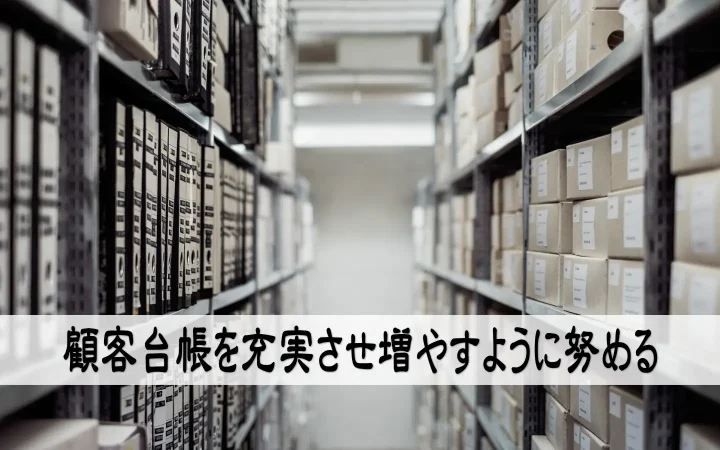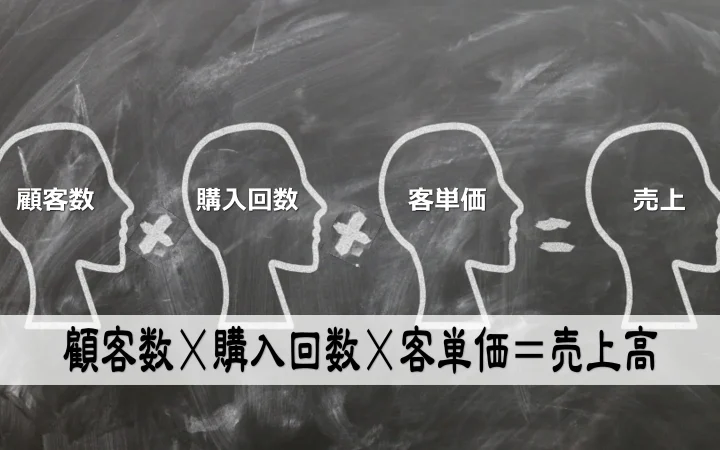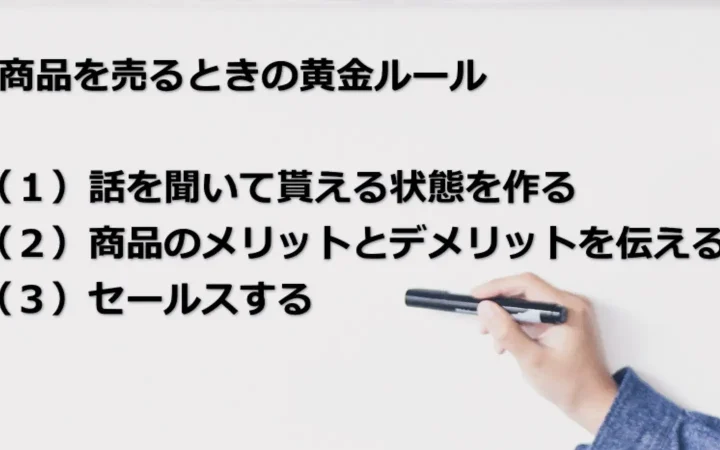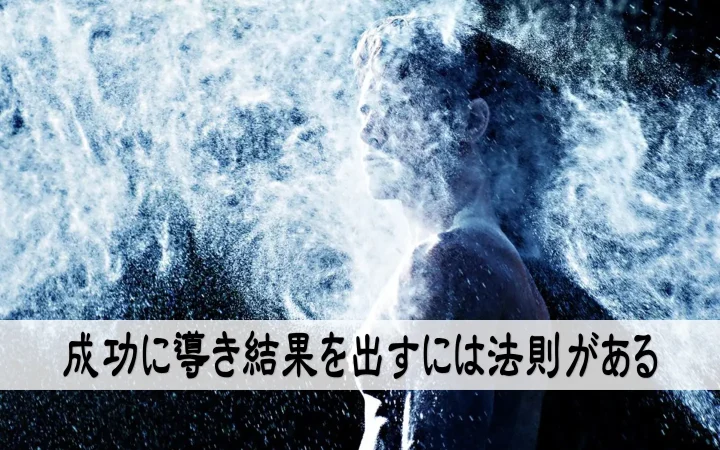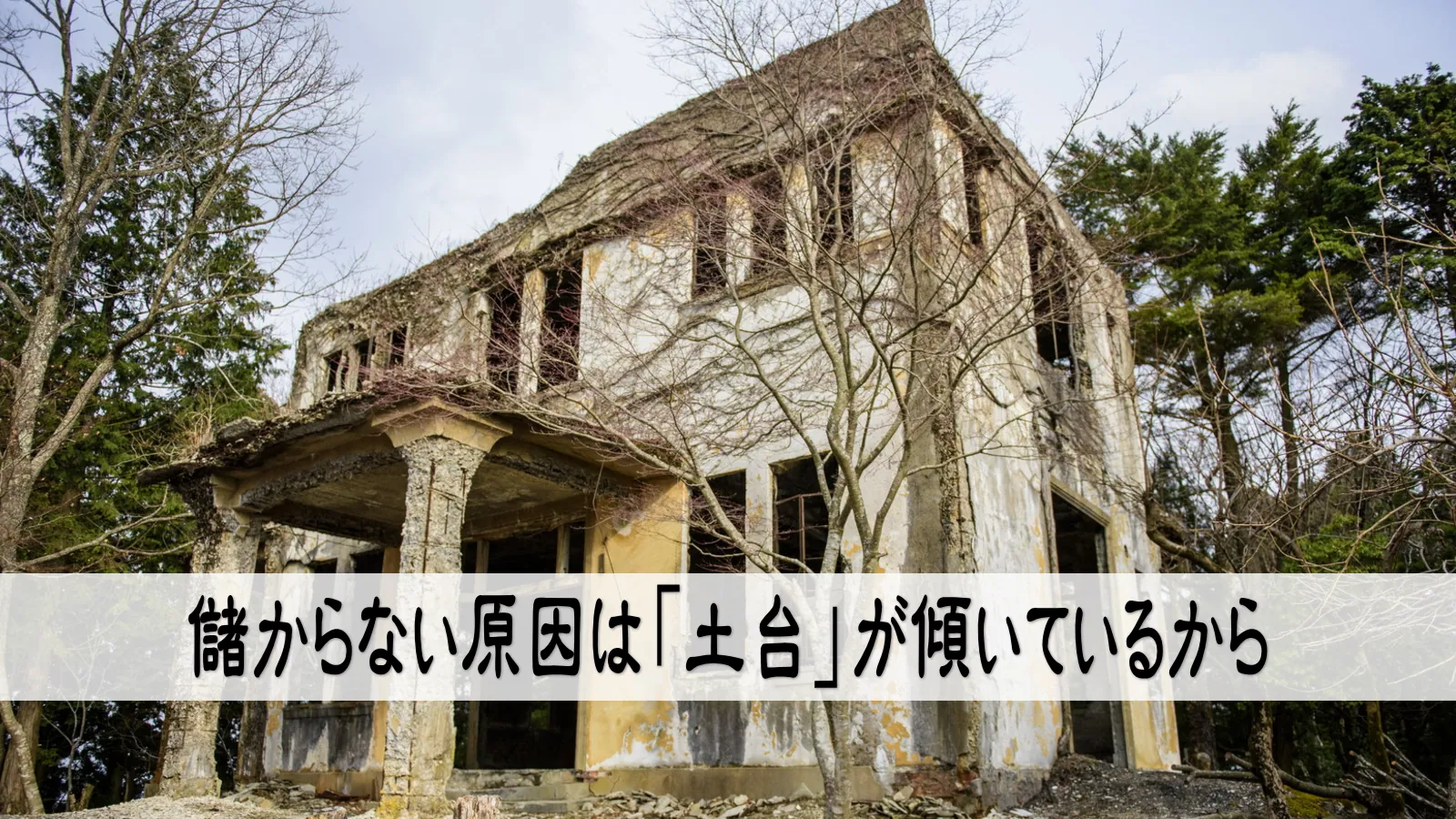
スモールビジネスが儲からない原因は、ビジネスの「土台」が傾いているからだ。多くの経営者は「誰に」「何を」「なぜ」提供するのかを明確にしないまま、集客やマーケティングに走り、無駄な努力を重ねている。「名前を知ったら解った気になる」錯覚を避け、ニッチ市場で独自性を発揮するためには、事業コンセプトを整理し、顧客の悩みに焦点を当てることが重要だ。土台を整えれば自然と利益が生まれ、シンプルなマーケティングで成果を出せる。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
「こんなに頑張っているのに、どうしてうちの会社は儲からないんだろう?」と首をかしげるスモールビジネスの社長は少なくない。勉強熱心な人ほど、セミナーへ足しげく通い、マーケティング手法を片っ端から試してみる。ところが、いざ実践しても思うように成果が上がらず、ただただ疲弊してしまうのだ。実はその背景には、「ビジネスの土台」が傾いたままの状態で、どれだけ集客や宣伝に力を注いでも無駄になってしまうという根本的な問題がある。言い換えれば、肝心要の部分を整備しないまま外側ばかりを飾っている状況だ。
土台が傾いていては儲からない
建物で例えれば、傾いた土台の上にいくら立派な外観を作っても、すぐにガタがきてしまう。そんな危うい状態を放置しておくと、いくら努力を重ねてもいつかは崩壊する。そこで本書では、スモールビジネスがしっかり利益を生むための「土台づくり」に焦点を当てる。土台といえば「誰に何を、なぜ提供するのか」という、まさに需要と供給の基礎の部分。ここがブレているとうまく儲からないのは当然の話だ。「あれだけ学んだのになぜ結果が出ないのか」という謎を解きほぐし、儲かるための堅実な道筋を見出してほしい。
スモールビジネスの現場でよくあるのが、「頑張っているのに利益が出ない」という嘆きだ。セミナーを渡り歩き、新しい集客テクニックを覚え、SNSも毎日更新しているのに、どうも売り上げが伸びない。それはまるで、傾いた土台に建物を無理やり建てているようなものだ。いくら意匠を凝らして美しい壁を塗り、最新の設備を詰め込んでも、土台そのものがしっかりしていないと建物は耐えきれずに崩れる。ビジネスにおいても同様で、土台が傾いているといずれ儲からない状態が続くことになる。
では、そもそも「土台」とは何だろうか。ズバリ、「誰に、何を提供するのか」という最も基本的な需要と供給の部分である。ここがおざなりになってしまうと、どれだけ派手な販促をしても空回りに終わる。実際、コンサルティングの場で「誰に何を提供しているんですか?」と尋ねると、「お客さんに商品を売っています」という漠然とした回答が返ってくることが多い。お客さんが「不特定多数」で、商品も「とにかく全部ウチで扱ってます」では、正直どこに向けてどう価値を伝えるのかが曖昧になってしまう。
この「土台」が傾いていると、どう頑張っても儲けの仕組みがうまく回らない。お客の悩みが曖昧ならば、商品やサービスが何を解決してくれるのかもぼんやりとしか伝わらないからだ。結果、集客しても満足に刺さらず、お金だけが出ていく展開に陥りがち。こうした「労多くして益少なし」の状態から抜け出すには、まず土台をしっかり整える必要がある。ここを無視して拡大だけを目指すと、やがて傾きが増してすべてが壊れてしまう。利益を生むための第一歩は、土台を正しく作り直すことなのだ。
誰に何をが曖昧では成果が出ない
スモールビジネスが成功するか否かは、突き詰めれば「誰に」「何を」提供するかの一点にかかっていると言っても過言ではない。ところが、多くの社長は「お客さん」を漠然とイメージし、「何を」も漠然とまとめてしまう。例えば「鈴木さんのような人に、○○という商品を提供しています」と言われた場合、いったい鈴木さんとはどんな背景を持った人なのか、○○という商品は具体的にどんな機能でどんな悩みを解決するのか、詳細を尋ねても答えが曖昧なケースが多い。
ここで陥りやすいのが、「名前を知ったら解った気になる」という錯覚だ。「鈴木さん」と名前をあげただけで相手の人物像を描いた気になり、「○○という商品名」を出しただけで特徴や価値まですべて把握した気になる。実はこの状態が、ビジネスの土台を傾かせる原因の一つになる。表面的な名称を覚えただけで満足していては、実際のニーズを満たすところまで落とし込むことができない。

さらに、スモールビジネスならではの強みとして「スモールビジネスはニッチ市場でこそ最大の力を発揮」する、という点を見逃してはならない。大手が手をつけづらい細かい市場や特定の悩みに特化することで、大企業以上に濃密なサービスを提供する余地がある。ところが「誰に」の部分を広げすぎると、ニッチな領域での強みがぼやけてしまうのだ。その結果、「結局どんな人に役立つビジネスなのか」が明確にならず、価値を正しく伝えられないまま集客が失敗に終わる。
ビジネスの土台をまっすぐ立てるためには、まず「誰」にフォーカスし、その人の悩みや願望を正確につかむこと。そして「何」を提供して、どのように悩みを解決するのかをしっかり言語化すること。曖昧さを取り払うことが、スモールビジネスで成果を出すための第一歩となる。
なぜを意識する事業コンセプト
「誰」に「何」を売るかが定まったら、次に考えるべきは「なぜ」その商品やサービスを提供するのか、という部分である。ここを明確に言語化したものが「事業コンセプト」と呼ばれる。別の言い方をすると、お客の悩みをどのように解決するかという価値の核となる部分だ。よく「5W1Hで整理しましょう」と言われるが、まさにビジネスにおいても同様に、「誰(Who)」「何(What)」「なぜ(Why)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「どのように(How)」を整理するのは極めて重要だ。
特にスモールビジネスは、経営資源が限られているからこそ、「なぜ自社がこの領域で勝負するのか」をはっきりさせないと、大手や他社との違いが埋没してしまう。自分たちならではのオリジナリティや得意分野を突き詰め、「ここならウチが断然頼りになる!」と思ってもらうための理由づけこそが「なぜ」にあたる。
ところが多くの経営者は、「商品やサービスの機能」ばかりを見せようとし、相手が「なぜ買うべきか」を理解する前に売り込みをしてしまう。例えば「うちの商品は高品質です」「プロが監修したから間違いありません」といったアピールは、いっけん説得力があるようで、実は抽象的すぎてお客にピンとこないことが多い。なぜなら、お客は「自分の抱えている悩みが解決されるかどうか」をもっと具体的に知りたいからだ。
この「なぜ買うべきか」を明確化する作業は、単に商品を並べるだけのビジネスから抜け出す手がかりになる。事業コンセプトがしっかりしていれば、お客は価格だけで比較するのではなく、「この会社だからこそ安心して頼める」という共感や信頼を感じやすい。そうなれば、自然と価格勝負から脱却し、適正な利益を確保しつつもリピーターを増やすことが可能になる。
スモールビジネスはニッチで勝負
スモールビジネスが大手と真っ向から競合しても、まず資金力や広告量、知名度などで圧倒的に不利になる。だからこそ、狙うべきはニッチ市場だ。先ほど触れたように、「スモールビジネスはニッチ市場で最大の力を発揮」するのが大前提だ。裏を返せば、大手が見逃している隙間や専門性の高い分野、特定の悩みや地域に集中することで、他では味わえない独自の価値を創り出せるというわけだ。
しかし、そのニッチ市場にアプローチする際にも、「誰に何を、なぜ提供するか」が重要になる。よくある失敗例として、「ニッチな分野を狙ったつもりが、実は誰にも響いていない」というパターンがある。せっかくマニアックな商品を扱っても、お客の需要を事前にリサーチしていないと的外れになってしまうことになる。
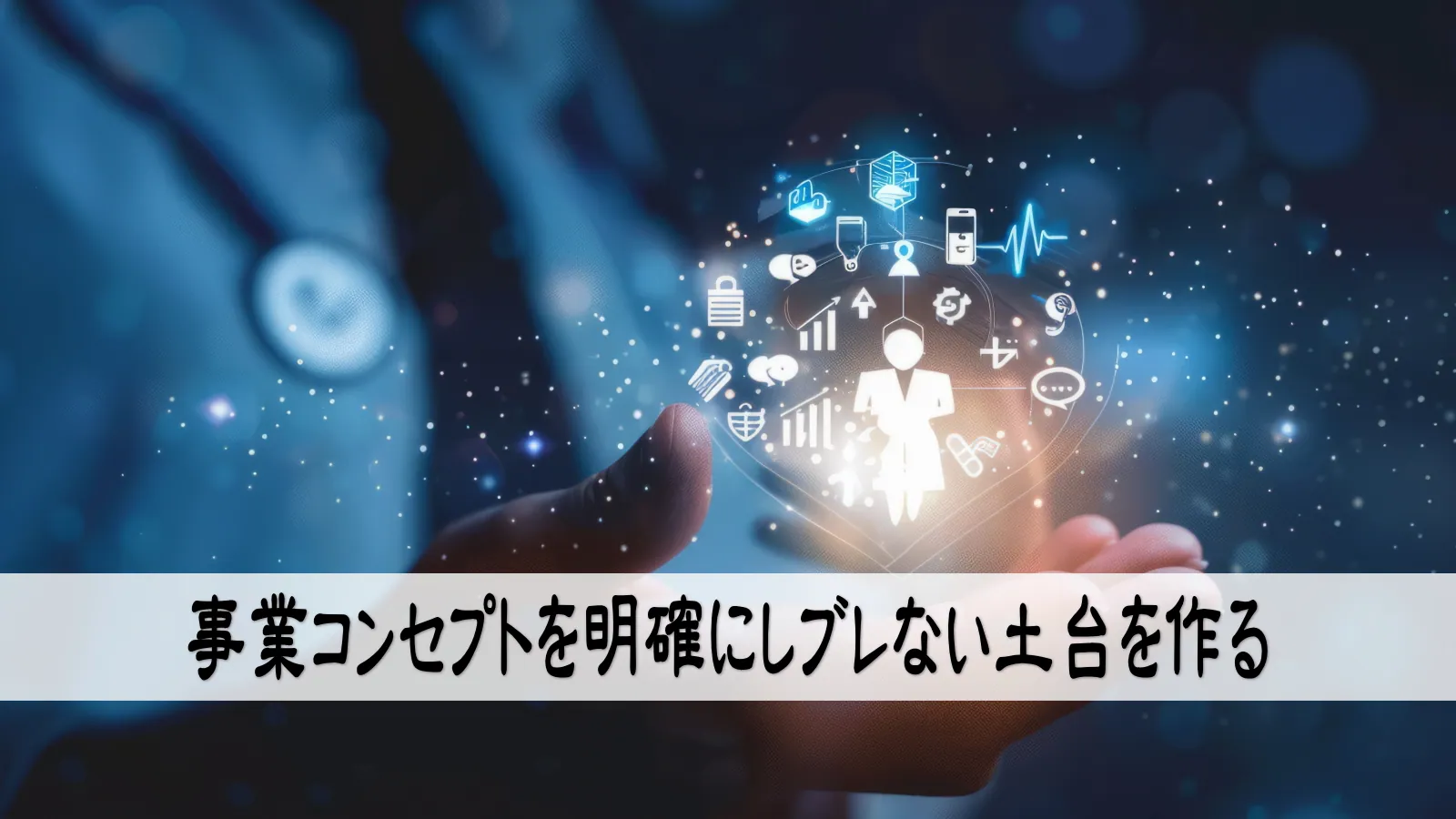
だからこそ、「需要と供給」のバランスを意識しながら、きちんとお客の悩みを把握する必要がある。単に「珍しい商品だからマニアが買ってくれるはず」などと短絡的に考えるのではなく、「このニッチ市場にはどういう背景の人が集まっていて、どんな困りごとを抱えているのか?」を徹底的に探る。そして、その悩みを解決するために「何をどう提供するのか」を細かく設計する。このプロセスが、スモールビジネスが強みを発揮するための基本になる。
ニッチ市場においてはお客との距離が近い分、口コミや評判がダイレクトに売り上げに反映される可能性が高い。そのため、うまくはまればリピーターが増え、安定した収益基盤を築ける。逆に土台が歪んだままだと、何をやっても中途半端に終わり、ただ貴重な時間と労力を消費するだけになってしまう。だからこそ、ニッチ市場を味方につけるためにも、事業コンセプトを明確にし、ブレない土台を構築することが大切だ。
名前を知ったら解った気になる
スモールビジネスの社長が陥りやすいもう一つの落とし穴が、「名前を知ったら解った気になる」現象だ。これはたとえば、「ペルソナを作りましょう」と言われて、ペルソナに“鈴木太郎、35歳、会社員”と名付けただけで、まるでターゲット像が完全に把握できたかのように錯覚してしまうパターンを指す。だが、実際にはそこからどんな不満や悩み、具体的な生活背景があるのか掘り下げないと、本当のペルソナ分析とは言えない。
同様に、商品名やサービス名を一生懸命考えるだけで、「中身が整理できた」と思い込むことも危険だ。確かにネーミングは大切だが、それだけでお客が抱える悩みが解決されるわけではない。結局、「誰に」「何を」「なぜ」を明確化しないまま名前を整えても、土台ができていないのだから意味がない。
例えば、あるダイエットサービスを提供しているとして、「ファイト!スリムプログラム」という名前を付けたとしよう。一見、元気が出そうなネーミングだが、それが誰のどんな悩みに応えているのかが不透明なままだと、お客は「このプログラムは本当に自分の体型や生活スタイルに合っているのだろうか?」と疑問を抱く。そして、疑問が解消されないままなら購入には踏み切らない。
この「名前先行」から脱却するには、改めてお客の「5W1H」を整理し、「どんな悩みを解決するためのプログラムなのか」を具体的に言葉にすることが必要だ。悩みの本質が見えれば、お客が自分の状況と結び付けて「これなら自分を変えられそうだ」と思える。すると「なぜ買うべきか」の理由が自然に伝わり、商品やサービスの価値がわかりやすくなる。
土台を整えれば自然と儲かる
ここまで、「土台が傾いていると儲からない」「誰に何を売るのかを明確にする」「なぜを意識した事業コンセプトの重要性」「ニッチ市場の強みを活かす」「名前を知ったら解った気になる罠」という流れで見てきた。最終的に言えるのは、ビジネスを成功に導くためには、いかにして土台をしっかり整えられるかという一点に尽きるということだ。土台さえ整えば、あとは自然に利益が回り始める。
なぜなら、一度「誰に」「何を」「なぜ」を明確に定義できれば、マーケティング戦略や商品開発、広報活動などの方向性が自ずと決まるからだ。例えば、ターゲットとなるお客の悩みがはっきりしていれば、それに合わせた商品の改良やサービス内容の改善もスピーディに行える。加えて、情報発信の際にも「うちの商品はこういう悩みを解決しますよ」という、的を射たメッセージが打ち出せる。
逆に、土台が曖昧だと「これは受けるかもしれないからやってみよう」「あっちのセミナーで学んだ新しいツールを導入しよう」と、あれこれ手を出しては消耗してしまう。その結果、「全然売れない」「コストばかりかかる」と負のループに陥りがちだ。
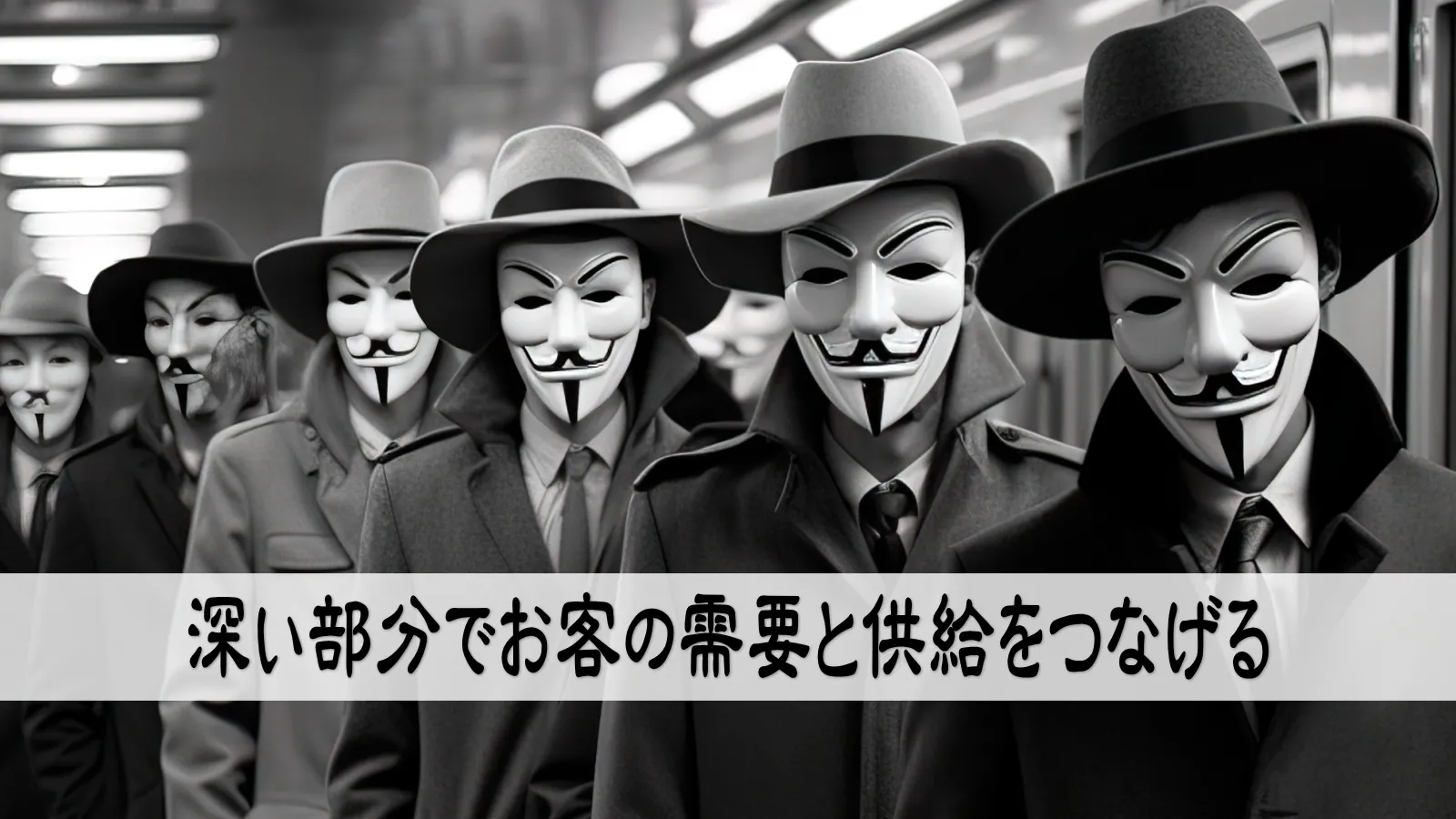
スモールビジネスにおいては、派手な拡大戦略よりも、まずは身の丈に合った堅実な基礎をつくることが大切だ。ニッチ市場でお客としっかり向き合い、事業コンセプトを明確化して「5W1H」を整理する。それだけでマーケティングはずいぶんシンプルになる。「名前を知ったら解った気になる」という上っ面だけの満足に留まらず、深い部分でお客の需要と供給をつなげることができれば、傾いた土台を立て直し、利益を継続的に生み出すビジネスを構築できるだろう。
こうした段階を踏むことで、スモールビジネスは大手にはマネできない独自性を発揮し、堅実に儲かる仕組みを作ることが可能になる。大切なのは、土台をしっかりと築き、ニッチ市場にフォーカスしつつ、明確な事業コンセプトを軸にお客と真摯に向き合うこと。これさえ揺らがなければ、例え小さな規模でも、十分に利益を生み、長く続けられるビジネスへと成長していける。なにより、大切な時間とお金を無駄にせず、自分のペースで着実に結果を出す感覚は何ものにも代えがたい。もし今、頑張っているわりに報われていないと感じているなら、ぜひもう一度、「誰に」「何を」「なぜ」を見直してみてほしい。それが傾いた土台を立て直す一番の近道となる。