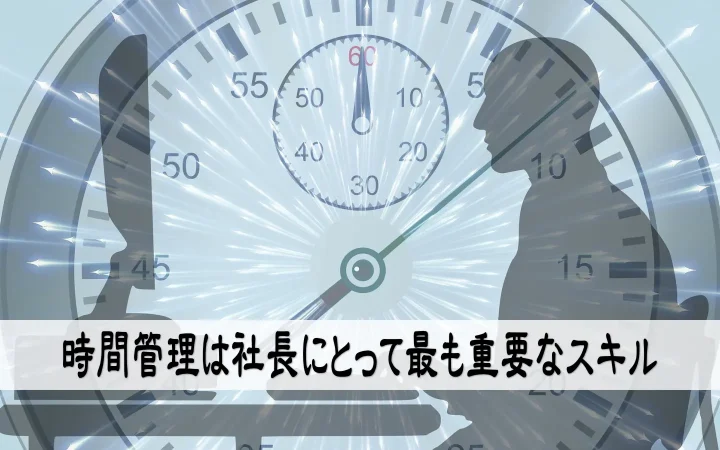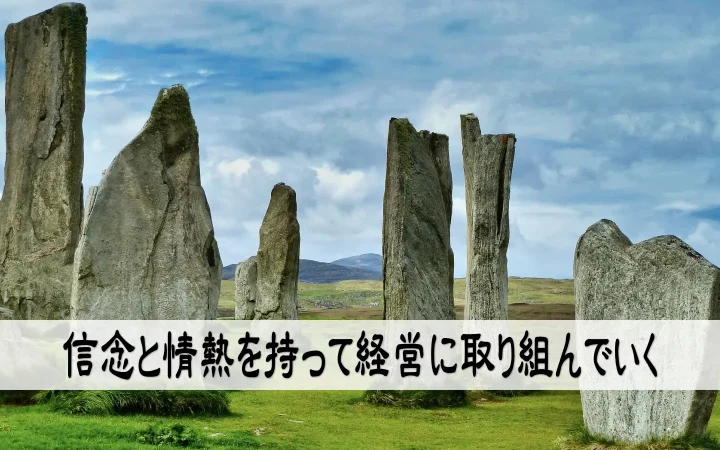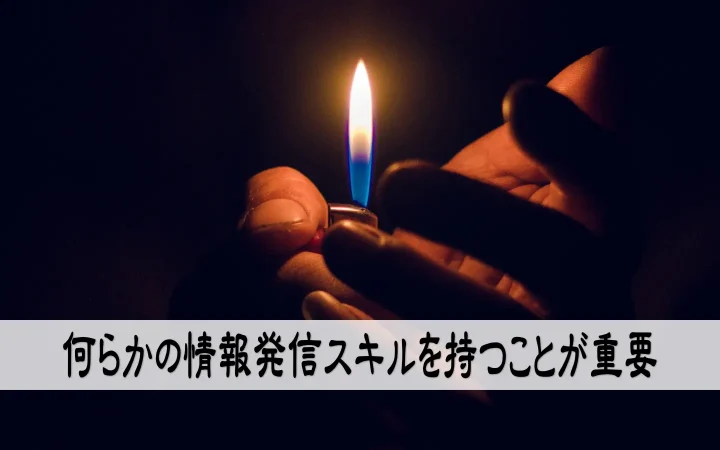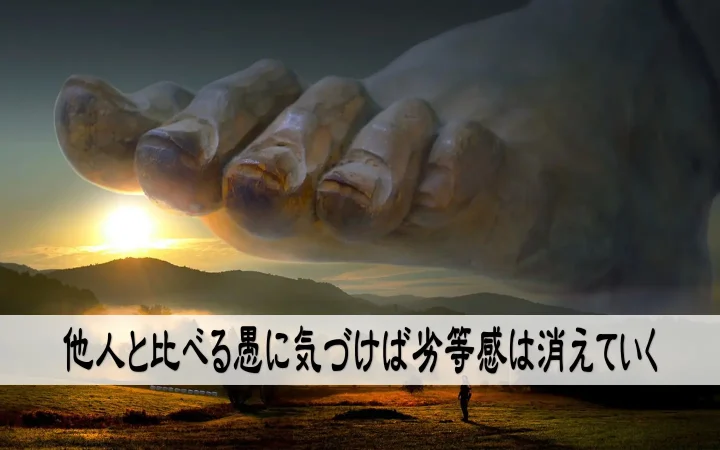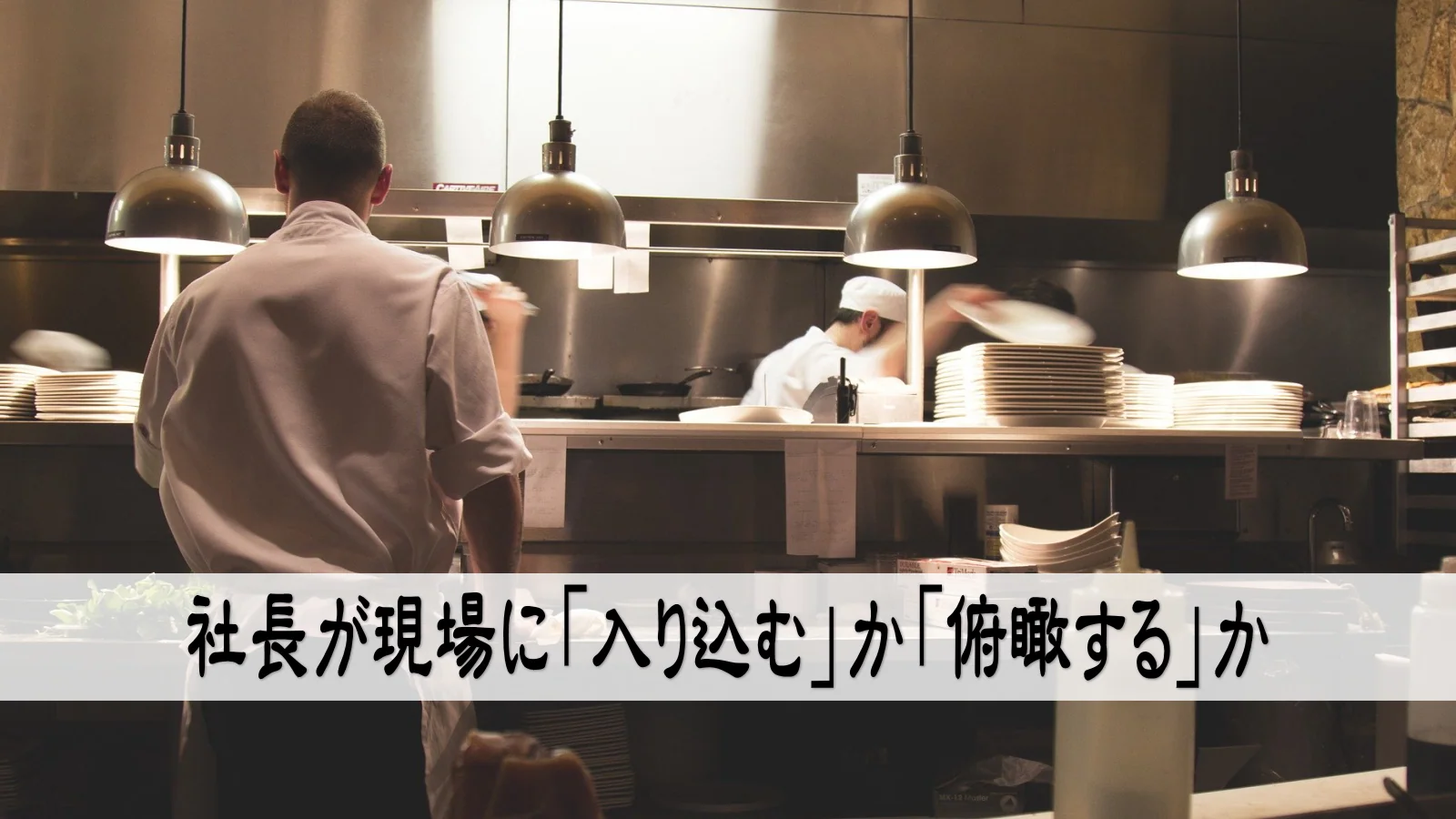
儲かる会社とそうでない会社の違いは、経営者が現場に「入り込む」か「俯瞰する」かにある。特に一人会社では、現場に追われ経営が後回しになりがちだが、本来の仕事は経営とマーケティングにある。経営者は「もう一人の自分」を意識の中に育て、客観視と学びを通じて経営力を高めるべきだ。学ぶ時間がないならコンサルの活用も有効。経営に投資することで善循環が生まれ、会社は長期的に安定成長する。経営とは経営をすることなのだ。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
儲かっている会社と、そうでない会社の差は想像以上に大きい。特にスモールビジネスでは、同じような商品やサービスを扱っていても結果は千差万別だ。最近よく耳にする「三現主義」――現場・現物・現実を直視する姿勢――は大切だが、実は経営者自身が現場に「入り込む」経営者ではなく「俯瞰する」経営者になることが、儲けを左右する決定打になる。
儲かる会社と儲からない会社
なぜ経営者が現場に深く入り込むと問題が起こるのか。端的に言えば、経営者の本来の仕事である「経営やマーケティングを考える時間」が削られてしまうからだ。お客を店や会社に連れてくることこそが経営者の役目だ。ところが、日々の雑務や接客に追われているうちに「社長学」を学ぶ時間も取れず、長期的なビジョンの構築もままならなくなる。結果として、「儲ける仕組み」を作る余裕がないまま時間だけが過ぎていき、いつまでも売上が頭打ちの状態に陥ってしまう。
一方、儲かっている会社の経営者は、あえて現場に立ちすぎないようにしているケースが多い。もちろん、現場の雰囲気を見極めるために立ち寄ることはあっても、あくまでマネジメントと方向性のチェックに徹する。従業員がいる場合はスタッフ教育に注力し、経営者が店にいなくても機能する体制を整えている。これが「現場はスタッフ、経営は自分」という役割分担であり、経営者が経営の仕事をしっかり行うからこそ、売上増だけでなく顧客満足度も高い状態を維持できるのだ。
実際に儲かっている店は、経営者がしっかりとマーケティングを考え、販促やブランディングを戦略的に行っている。そうやって経営に時間とエネルギーを使うからこそ、人が集まる環境が作られていく。現場を大切にしつつも依存しすぎないバランス感覚が、儲かる会社と儲からない会社の明確な違いを生むのである。
現場と経営を分けて未来を描く
スモールビジネスの現場では、「経営者が店頭に立ちっぱなし」という状況が頻繁に見られる。特に社員やスタッフが少ないと、経営者自らが接客から雑務までフル稼働しなければ回らないことも多い。しかし、この状態が続くと、会社の伸びしろは限られてしまう。なぜなら、経営者は会社の未来を描き、具体的な戦略を練るための時間を確保しにくくなるからだ。
現場から離れられない理由の一つに「マンパワー不足」が挙げられる。一人から数人の会社では、経営者が休むと誰も業務を回せなくなるという切実な状況がある。しかし、本来、経営の仕事は「先を見通す力」と「集客や販売戦略を組み立てる力」が要となる。ここをおろそかにすると、目の前の売上はともかく将来が不安定になり、いつまでも同じ問題に追われることになる。
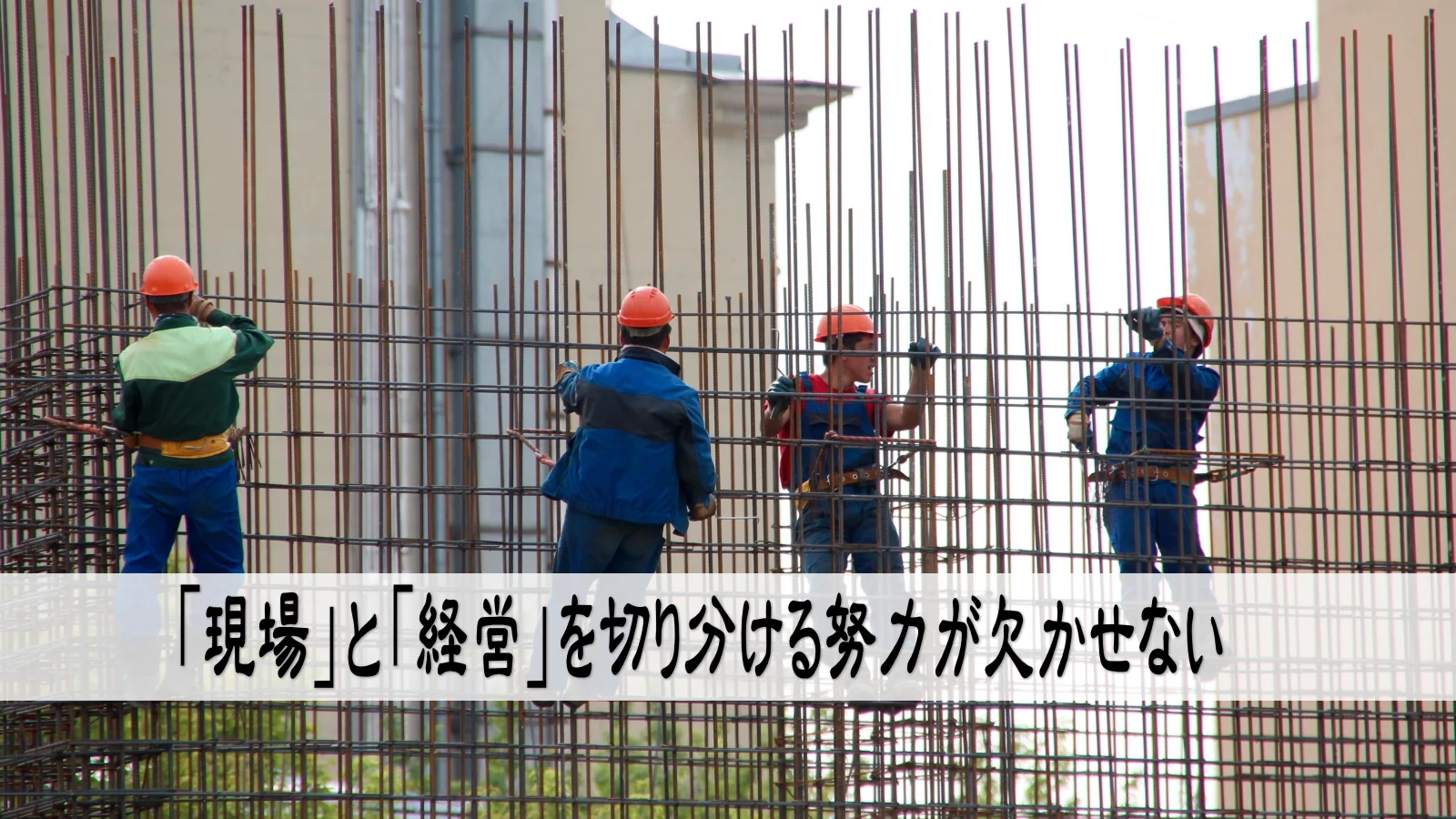
また、忙しさを理由に経営についてじっくり考えないと、気づかぬうちに大きな機会損失をしている可能性がある。日々の売上の確保に追われるだけでは、広い視野でのマーケティングや事業展開、新しいサービスや顧客へのアプローチ方法などを検討しづらい。その結果、競合に先を越されてしまったり、適切な投資のタイミングを逃すこともある。
だからこそ、「現場」と「経営」をきちんと切り分ける努力が欠かせない。もちろんまったく現場を見ないのはリスクがあるが、現場に入り込むのではなく俯瞰して問題を把握することが重要だ。経営者は店や会社の問題を客観的に把握し、改善策を示す役割を担う。それが会社全体の未来を左右する大きなポイントになる。
一人会社が直面する経営ジレンマ
特に悩ましいのが、一人会社のケースだ。一人しかいない以上、経営者が動かなければすべてが止まってしまう。「現場に入り込む」経営者にならざるを得ず、肝心の経営を考える時間を確保しづらい。業種によっては、経営と現場担当者の二役を同時にこなさなければならないため、日々の業務が終わる頃にはクタクタになってしまい、マーケティングや新規顧客獲得策などの検討は後回しになることもしばしばだ。
このような状況が続くと、当然ながら会社の成長は止まりがちになる。経営者としての視点を持つ余裕がないまま時間が過ぎ、結果として現場業務に追われるだけで利益を伸ばせない状態に陥る。しかも、忙しいわりに売上や利益が改善しないという負のスパイラルを生みやすい。
そんな一人会社にも解決策はある。一つは外部の力を上手に借りることだ。例えば必要に応じてアルバイトやパートタイマーを活用し、現場をサポートしてもらう。あるいは行政や商工会議所の無料相談を利用して、客観的視点を得る。大きく拡大を目指さなくてもよいが、「経営について考える時間をどう確保するか」という視点は不可欠だ。
もう一つ大事なのは、「社長学」を学ぶ姿勢を持つこと。一人会社だからこそ、売上だけでなく経営の仕組みを学ぶ必要がある。マンパワー不足は事実だが、その状況の中でどうやって経営者としての役割を果たすかが、長期的な成果を左右する。最初は少しずつでも良いので、経営の知識を身につけ、自分のビジネスを客観的に評価する視点を持つことが重要になる。
経営者としての「自分」を育てる
では、具体的にどうすれば「俯瞰する」経営者になれるのか。その鍵は「もう一人の自分」を頭の中に作ることだ。たとえ一人会社でも、意識の中に経営者としての自分と現場担当者の自分を分けて持ってみる。常に第三者の視点でビジネスを観察し、客観的に考えるクセをつけるのだ。
例えば、店頭で接客中でも「経営者の自分ならこの状況をどう評価するか?」と頭の片隅でシミュレーションする。人手が少なくても、どんな販促を打つべきか、どの顧客層を狙うべきかを常に考えておく。こうすることで、「入り込む」経営者ではなく「俯瞰する」経営者になる視点が磨かれていく。
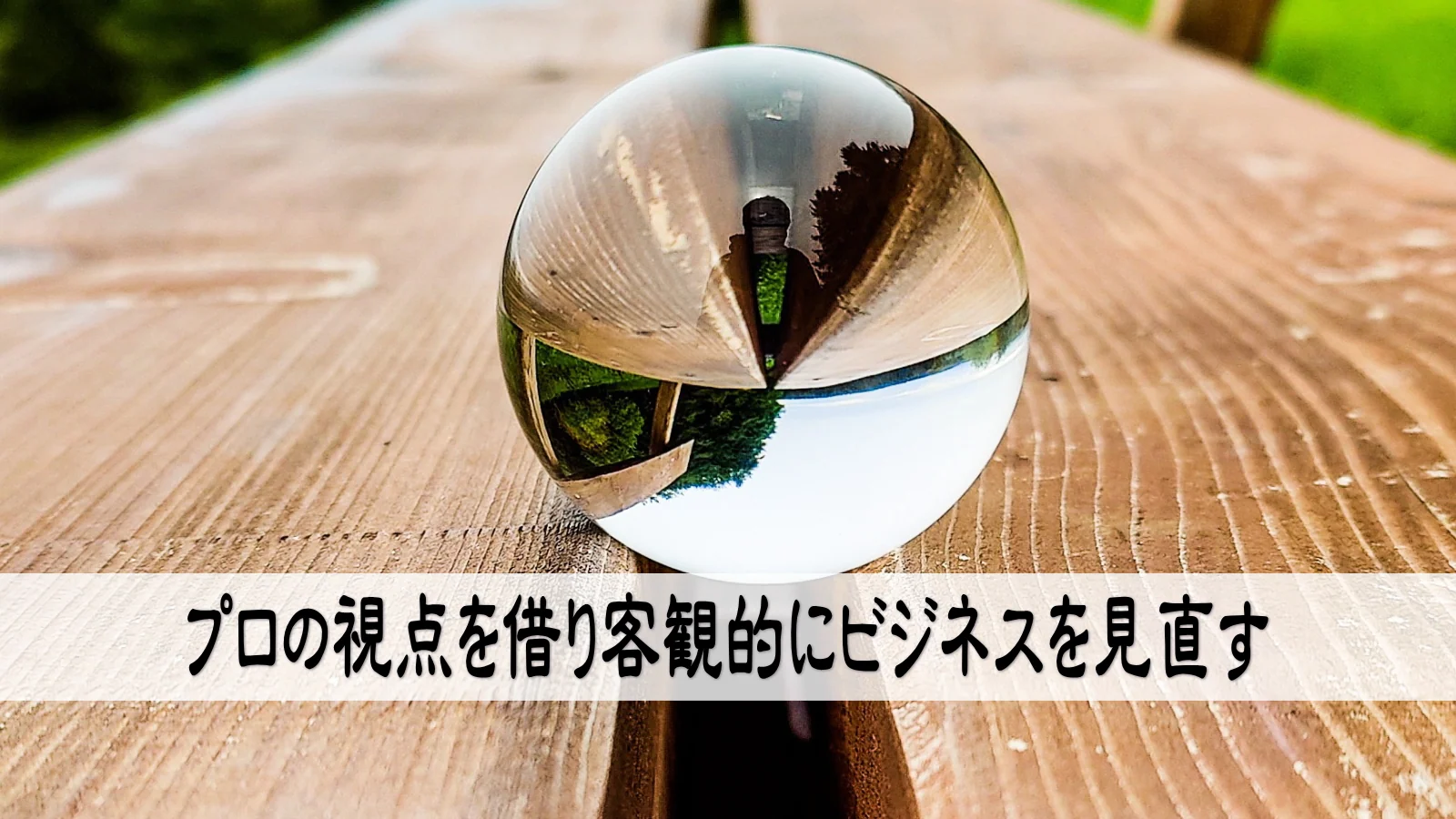
さらにマーケティングや経営の知識を学ぶことも大切だ。最初は本やセミナーで基礎を知るだけでも効果がある。特に50歳以上の経営者にとっては、これまでの経験の延長だけで走ってしまいがちだが、新しい知識を取り入れることは視野を一気に広げてくれる。何事も最初のうちは時間を要するが、3年ほど真剣に学べば誰でも一定のレベルに到達できる。
それでもなかなか時間が取れないなら、コンサルタントや専門家を活用するのも一手だ。プロの視点を借りて客観的にビジネスを見直すと、自分では気づかなかった改善点や新しいチャンスが見えてくる。人を増やすのではなく、まずは自分の頭の中に「もう一人の経営者」を育てる。そこから、ビジネスを大きく変えるヒントが生まれるはずだ。
経営を学ばないことによる大損失
経営者が現場にずっと張り付いてしまう理由の一つに、「経営を学ぶ時間がない」という声がある。しかし、これは本末転倒といえる。経営を考える時間を確保しないと、いつまで経っても現場の忙しさから抜け出せないからだ。
経営を学べば、売上を伸ばす具体的な方法や、コストを抑えながら利益を増やす手段が見えてくる。顧客ニーズのリサーチや、新しい集客チャネルの開拓など、現場業務とは違う視点を持つことで、ビジネス全体のパフォーマンスが向上する。学びを実践に落とし込めば、サービスの質も上がり、リピーターや口コミも増えやすくなる。
また、多くの50歳以上の経営者は、これまで蓄積してきた経験から「なんとかなる」と考えがちだ。しかし、時代の変化は予想以上に早く、常に最新の情報や手法をキャッチアップする姿勢が求められる。そこを怠ると、新しい顧客層やマーケットを取り込めず、結果として取り残されてしまう恐れがある。
だからこそ、経営の知識やマーケティングのスキルを習得することは最優先事項といえる。書籍やオンライン講座などを活用すれば、気軽に始められる。小さな一歩を積み重ねるだけでも、後々大きな差となって表れる。50歳を過ぎていても遅すぎることはない。自分の会社を冷静に分析し、マーケットのニーズを掴み、それを形にする力を身につけることが、長く続くビジネスを作る近道になる。
投資思考が生む善循環の秘訣
最後に、儲かる会社が意識している「善循環」について考えたい。実は、経営が下手な会社ほど、経営そのものに投資をしない傾向がある。広告費や人材育成、あるいは外部のコンサルタント費用などを「もったいない」と敬遠し、曖昧なネットシステムには大金をつぎ込んでしまう。結果として、売上向上や顧客満足に直結する取り組みには十分な資金を割かず、経営が停滞してしまうのだ。
一方、上手くいっている会社ほど「社長学」を学び、必要なところにお金と時間を惜しまず注ぎ込む。マーケティングの専門家を雇ったり、業務効率化の仕組みを導入したり、スタッフ教育を充実させたりと、未来につながる投資を厭わない。その結果、売上や利益がさらに増え、新たな投資が可能になるという好循環を生み出す。

こうした「善循環」を手に入れるためには、最初の勇気ある一歩が必要だ。余裕がないから投資しないのではなく、余裕を作るために投資するという発想が大事になる。特に経営を客観的に見るノウハウを持つコンサルタントの活用は、費用対効果が高い。店や会社がいま直面している課題を客観視し、解決策を示してもらうことで、新たなビジネスチャンスや収益源の発見につながるだろう。
これまで「現場に入り込み過ぎる」ことで手一杯だったとしても、今日から変えられる部分は必ずある。経営者が俯瞰の視点を持ち、経営に時間を使う。必要に応じて外部を活用する。この繰り返しこそが会社を安定軌道に乗せる秘訣だ。儲かる会社を目指すのであれば、まずは「経営者の仕事とは経営をすること」であるという当たり前の原則を、今一度しっかりと胸に刻んでほしい。