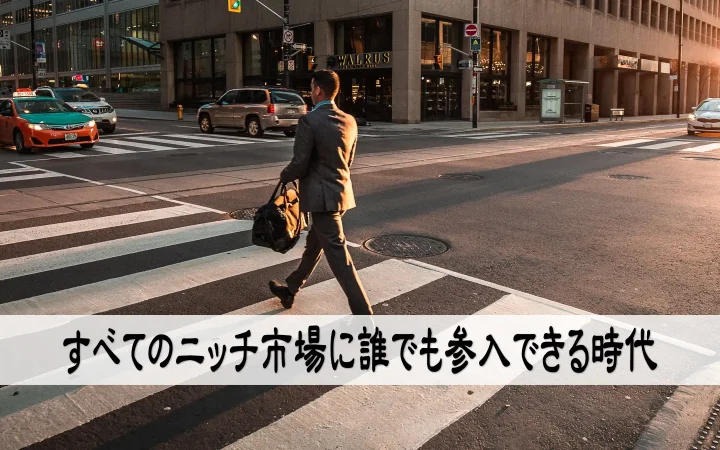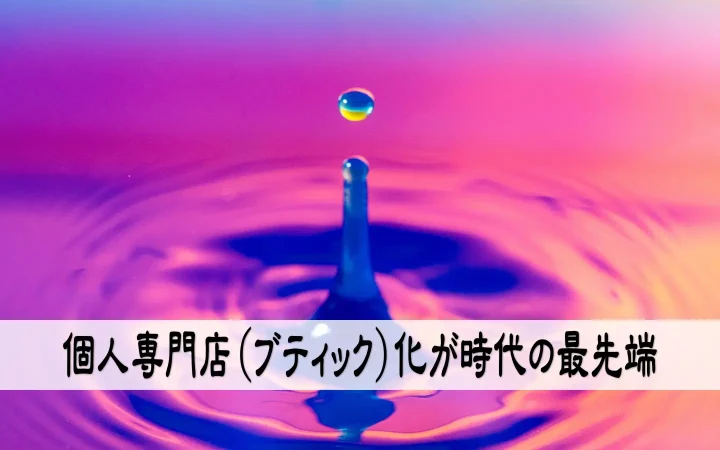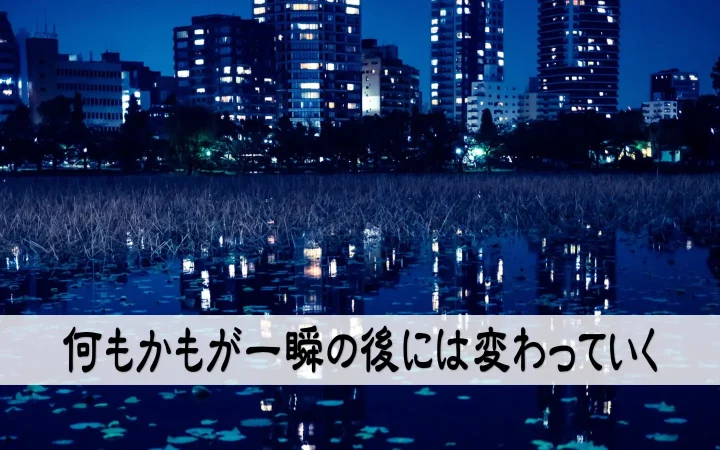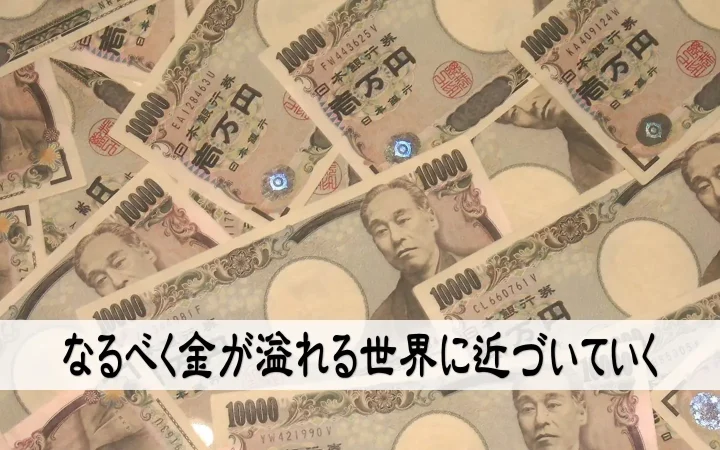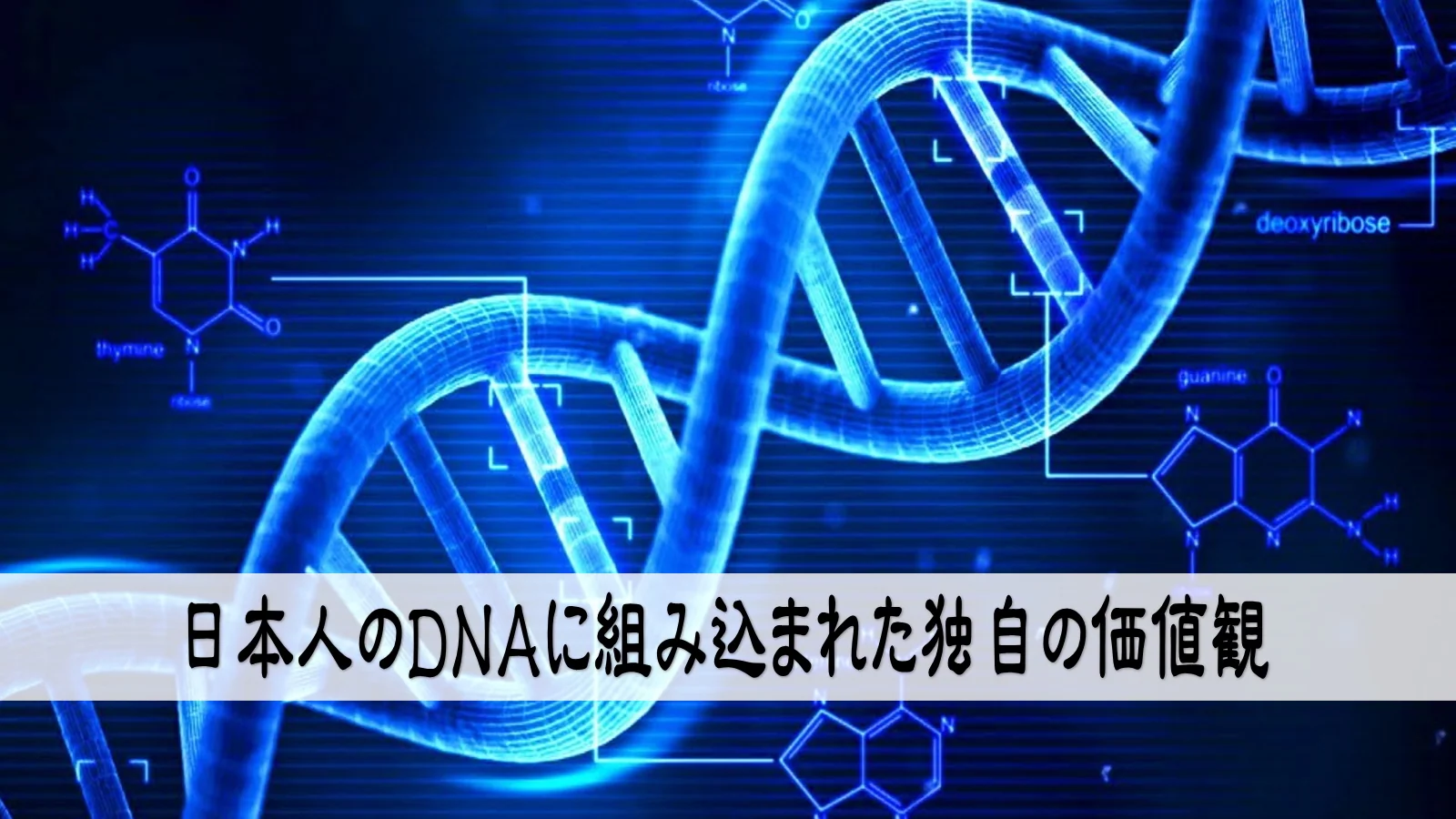
日本人は『ご恩と奉公』の古い価値観に縛られ、会社中心主義が崩壊する現代、グローバリズムの影響で実質賃金が低下する現実に直面する。「はたらけど はたらけど猶わが生活楽にならざり ぢっと手を見る」状況下、50代経営者は資本主義の伝統を捨て、自らの生きがいと独自のお金の稼ぎ方で人間中心の働き方を実現すべきだ。(内田游雲)
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
私たち日本人の多くは、どこかで「滅私奉公が美徳」という価値観を背負ってきた。鎌倉時代の「ご恩と奉公」に始まり、戦国時代の主君、江戸時代の藩主と武士の関係を経て、現代では会社が「主人」役を担うようになった。敗戦後の混乱期には、まさにこのDNAが大きな威力を発揮し、「会社のために犠牲を惜しまない」という意識が日本経済の成長を支えたことは否定できない。だが、今はどうだろうか。
「滅私奉公」が人生を貧しくする
かつては「終身雇用」というシステムが社員を守り、「会社に尽くせばいつか恩返しがある」と信じられてきた。しかし現代では、会社の都合で簡単にリストラが行われる。忠誠心を尽くしても、「ある日突然切られた」という話は珍しくもない。つまり、「会社中心主義」がすでに揺らいでいるのだ。
それにもかかわらず、「自分のために働くなんてわがままだ」という空気はまだ根強い。いわゆる「滅私奉公の呪縛」が、「生きがいを仕事にする」ことを邪魔している。会社に忠誠を誓うことが最優先で、自分のやりたいことや価値観は後回し。これでは、せっかくのスモールビジネスでも自由度を生かしきれない。50歳を超えた経営者こそ、「自分のために働く」覚悟を持つべきではないだろうか。
時代は大きく移り変わる。いつまでも昔の「滅私奉公」に縛られていると、人生はどんどん窮屈になる。思い切って古い価値観を手放すことが、これからの生きがいを得るための第一歩だ。自分がやりたいこと、自分が得意なことを仕事にしてこそ、「お金の稼ぎ方」だけではなく、人生そのものが充実してくる。会社のためにではなく、自分のために働く――それが「もう古い」とされる滅私奉公から抜け出す鍵になるのだ。
会社中心主義が崩壊し続けている
日本の高度成長期を支えた「会社中心主義」は、終身雇用や年功序列を土台としてきた。上司に尽くし、組織に尽くせば、定年まで面倒を見てもらえる。これが「ご恩と奉公」の現代版として機能し、多くのサラリーマンが安心して働ける環境をつくりだした。
ところが、資本主義が本来抱える「利益最大化」の論理が表面化し始めたとき、それまでの日本型経営と噛み合わなくなった。企業側は効率やコスト削減を第一に考え、従業員を「経費」の一部としてしか捉えなくなり、成長が鈍化すればリストラで人件費を削り、グローバル化が進めば安価な労働力を海外に求める。こうして、従業員への「ご恩」はどこかへ消え、「奉公」しても報われない状況が当たり前になった。

その結果、多くのベテラン社員が突然切り捨てられ、忠誠を尽くしたはずの会社から出ていく羽目になった。会社にとっては都合の良い経営判断であっても、個人の人生は大きなダメージを受ける。50歳以上で起業を考える人の中には、このような「会社からの放逐」をきっかけに独立するケースも多い。
ならば最初から、自分のために仕事をする選択を考えてもいいのではないか。会社中心主義が崩壊した現代、スモールビジネス経営者は「いい会社員」になる必要などない。むしろ自らの意志で未来を切り拓く「強い経営者」になるチャンスである。「会社に尽くす」という発想から、「自分と顧客の幸せ」を追求する発想へ切り替えるだけで、仕事観も人生観も大きく変わるはずだ。
グローバリズムの進化と落とし穴
日本の会社主義が薄れる一方、世界はグローバリズムへ突き進んだ。資本が国境を越えて行き交い、人材もモノも自由に動かそうという発想は、表向きは「国際協調」のように聞こえる。しかし、実態は「株主=資本家」の自己利益最大化の仕組みだ。
「はたらけど はたらけど猶わが生活楽にならざり ぢっと手を見る」という嘆きは、まさにグローバリズムが進んだ先の姿を映し出している。大量に働いたとしても、実質賃金が上がらない。むしろ競争が激化し、労働者同士の取り合いが起きた結果、多くの人の収入が押し下げられてしまう。これは「実質賃金が下がり続ける社会」の構造ともいえる。
グローバル資本主義の世界は、「人々の実質賃金を引き下げる」方向に常に動こうとする。なぜならば、「そうしなければ、我々(グローバリスト)の自己利益最大化が達成されない!」という話だからだ。
グローバリストが「移民を入れて人手不足を解消しよう」と叫ぶのも、要するに労働力のコストをさらに下げたいだけだ。経済がデフレで失業率が高まれば、「非正規雇用を増やせ」と言い、景気が持ち直して人手不足になれば「移民を受け入れろ」と言う。いずれにせよ、労働者側には厳しい結果が待っているのがグローバリズムの落とし穴だ。
「会社中心主義」が崩れたうえに、「グローバリズム」の波にさらされた日本の労働環境は、不安定さを増すばかり。特にスモールビジネスの経営者にとっては、コスト競争に巻き込まれやすい状況が続く。そこで重要になるのが、資本家に振り回されない独自の「お金の稼ぎ方」を見つけること。極端な値下げ競争に巻き込まれるより、自分の強みを活かして「生きがい」を前面に打ち出す方が、長期的な安定と幸福につながるのではないだろうか。
日本型技術者魂の危機と消失
日本はかつて「ものづくり大国」として世界に名を馳せた。そこにあったのは、職人やエンジニアが技術を磨き上げ、一つひとつの商品に魂を込める文化だ。ところが、グローバリズムの中では、安価な労働力や大量生産を追い求める流れが強く、日本の「職人精神」は置き去りにされ始めた。
そもそも、この職人精神の根底には、会社や組織への忠誠心が強く影響していた面もある。昔は「会社が成功すれば、自分も引き上げてもらえる」という期待があったため、一生懸命に技術を磨き、ノウハウを会社に捧げることが当たり前だった。しかし、資本主義が加速する中で、会社は株主を優先し、技術者への待遇を引き下げるケースが増えた。結果として、職人は他社や海外に流出し、技術だけを引き抜かれる状況になった。
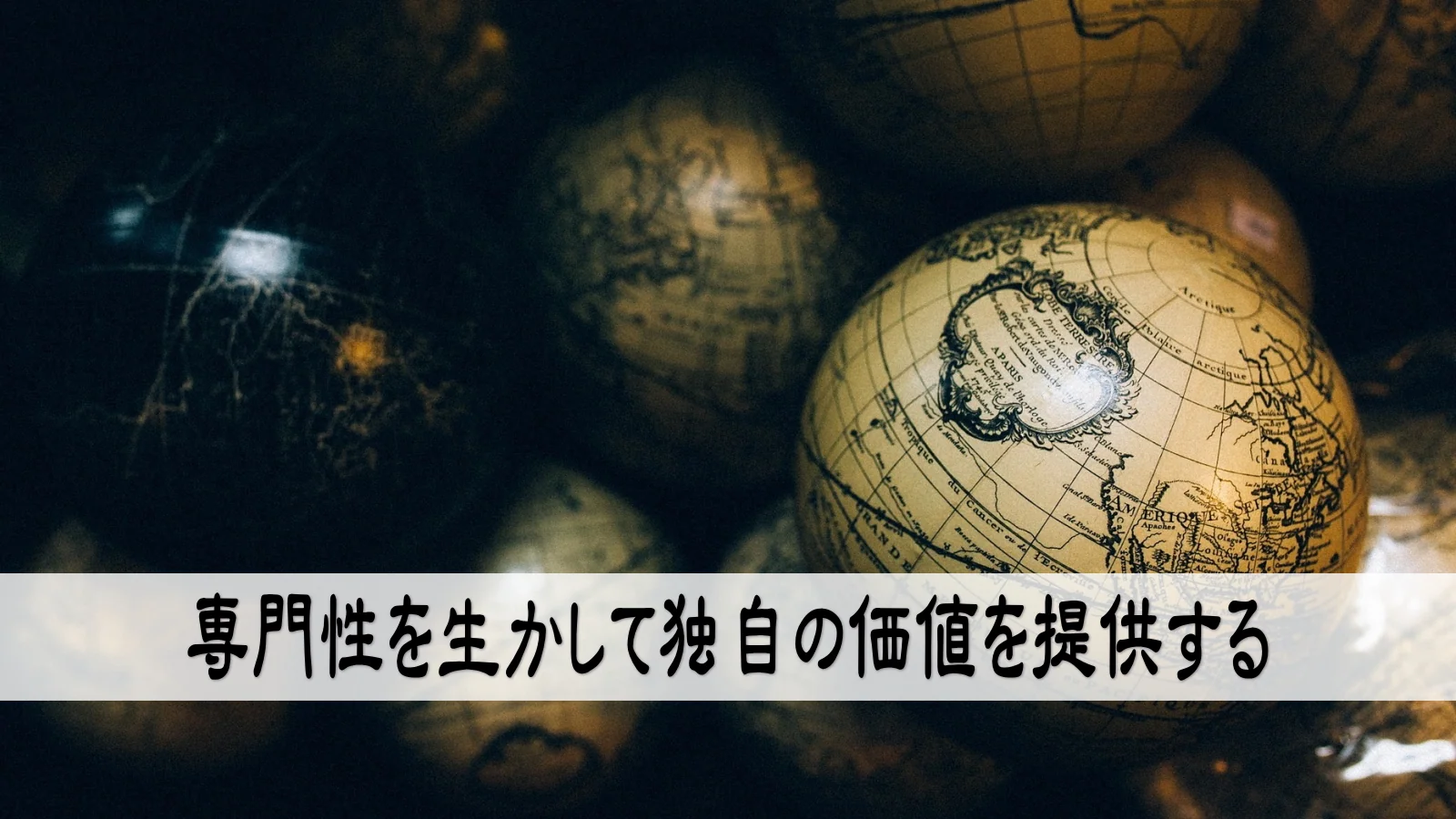
こうして「ものづくり」の根幹を支えていた日本型技術者魂は大きな危機に瀕している。非正規や派遣に置き換えられることで、じっくり技術を培う場が失われるのだ。スモールビジネスの経営者であればこそ、こうした流れを嘆いている人は多いだろう。だが、嘆いてばかりでは始まらない。ここにこそチャンスがある。大量生産に対抗しようとするのではなく、自分のこだわりや専門性を生かして、独自の価値を提供できれば、グローバル企業にはまねできないポジションを築ける。
「会社中心」ではなく「自分の信念」を中心に据え、それを顧客に共有していく。そうすることで、職人精神が再評価される未来を創ることができるはずだ。
人間中心への揺り戻しが始まる
世の中の振り子は、極端な方向まで行ききると、必ず反対方向へ戻り始める。現代の資本主義は「グローバル資本主義」という極端な形になり、多くの人々がそのひずみを感じ始めている。リーマンショックを契機に、アメリカですら「お金至上主義」に疑問を投げかける動きが顕著になってきた。
この揺り戻しは、人間の幸福度を重視する「人間中心主義」へのシフトといえる。資本は大切だが、それが全てではない。むしろ、資本を手段として活用し、人間がより自由に、より豊かに生きるために使おうという発想が世界的に広まりつつある。
日本でも、徐々にではあるが、「自分らしく働く」「生きがいを仕事にする」という流れが生まれつつある。これまでのように企業の利益を最優先するのではなく、働く側の幸せややりがいを重視する。お金の稼ぎ方そのものも、「不当なコストカット」や「安易な労働搾取」ではなく、「価値を創造して正当な対価を得る」方向へシフトしはじめている。
もちろん、社会の変化はゆっくりで、一朝一夕に進むものではない。それでも「資本中心主義」の行き詰まりを肌で感じている人は多いはずだ。スモールビジネス経営者としては、この潮流を先取りし、「人間中心」の視点で事業を進めることこそが大きな武器になるだろう。
50代からの生きがいと仕事
では、具体的にどのように「生きがいを仕事にする」か。50歳を超えたスモールビジネス経営者だからこそ、これまでの経験や人脈、技術を存分に活かすチャンスがある。拡大路線を追いかけるのではなく、自分らしさを発揮できる規模で仕事を楽しむ。その結果として収益が上がれば最高だ。
「好きなこと」や「得意なこと」に集中すれば、時間を忘れて没頭できる。そこから生まれるアイデアは自分の本心に根ざしているから、新たな顧客をも魅了する力を持つ。大きな企業のように安価な製品を大量に売るスタイルを目指すよりも、自分のこだわりに共感してくれる人とのつながりを大切にしたほうが、結果的に長く愛されるビジネスになりやすい。
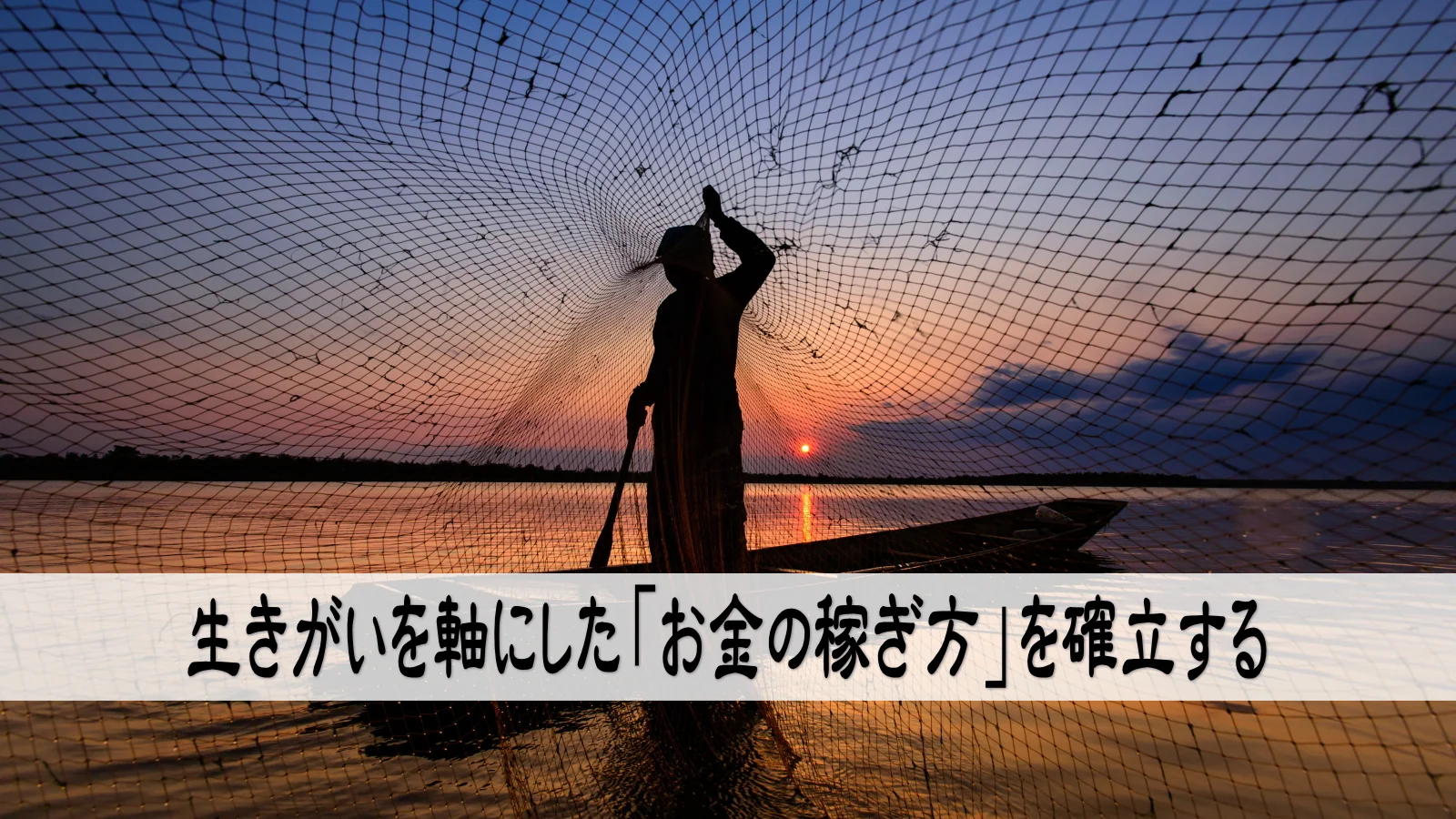
会社中心主義やグローバリズムに振り回されることなく、自分の生きがいを軸にした「お金の稼ぎ方」を確立すれば、実質賃金や景気動向に神経をすり減らす必要も少なくなる。顧客と共に成長しながら、生活の質を高めていくというスタイルこそ、これからの時代に求められるのではないだろうか。
最終的に大事なのは、自分が楽しめるかどうかだ。これまで苦労を重ねてきた50代以上の経営者にこそ、その余裕と胆力がある。「時間を切り売りする世界から、自分のために仕事をし、自分の生きがいとして仕事をする」という新しい時代が目の前に広がっている。