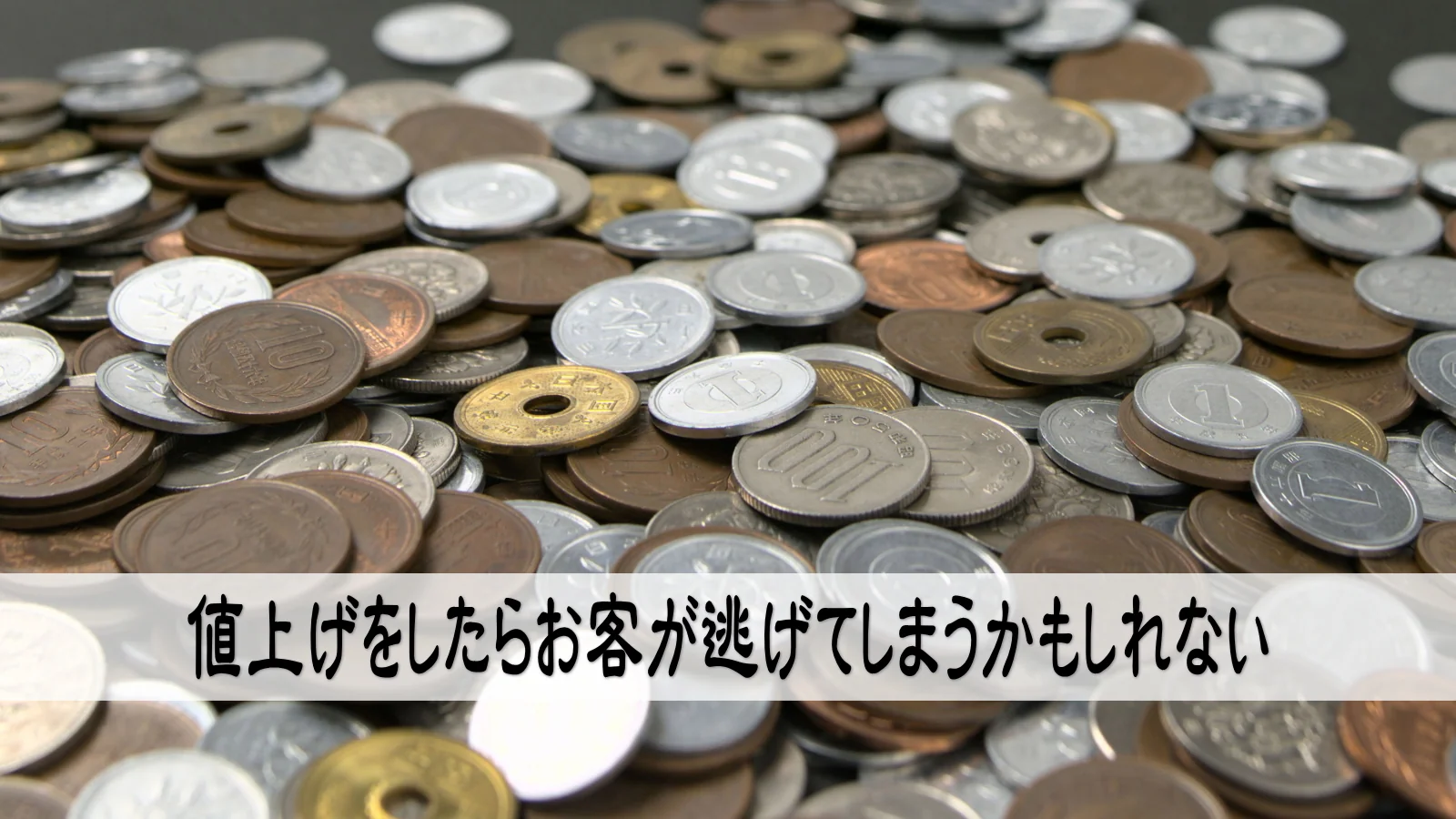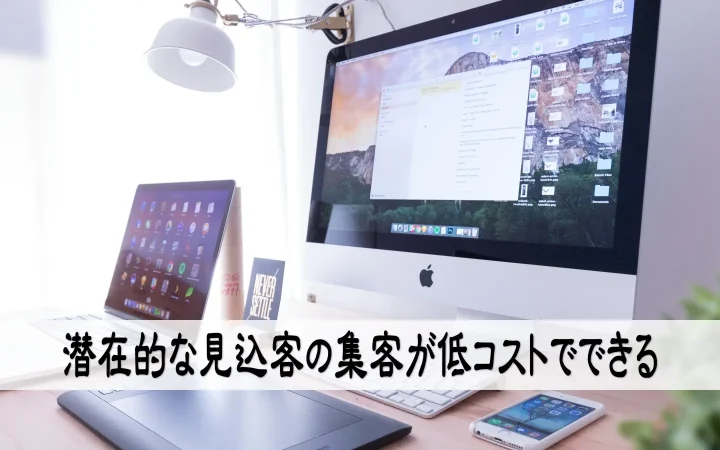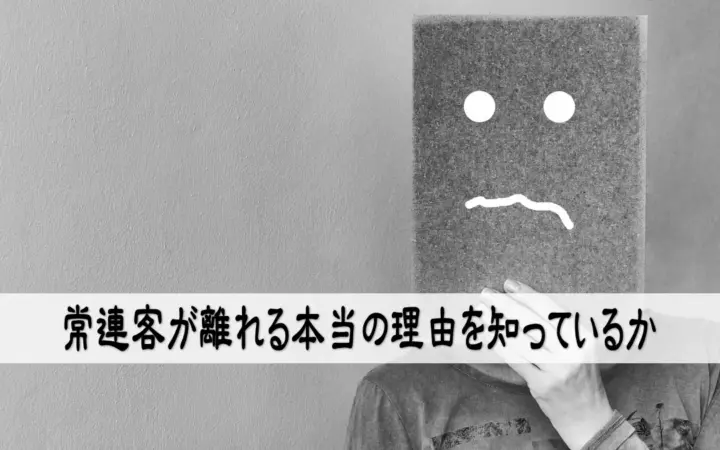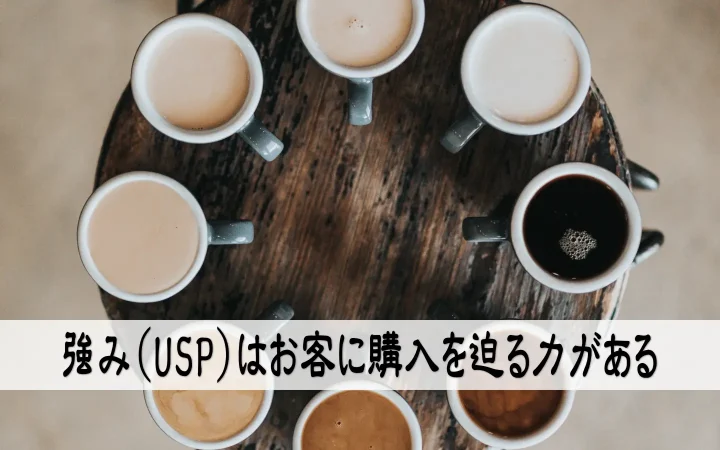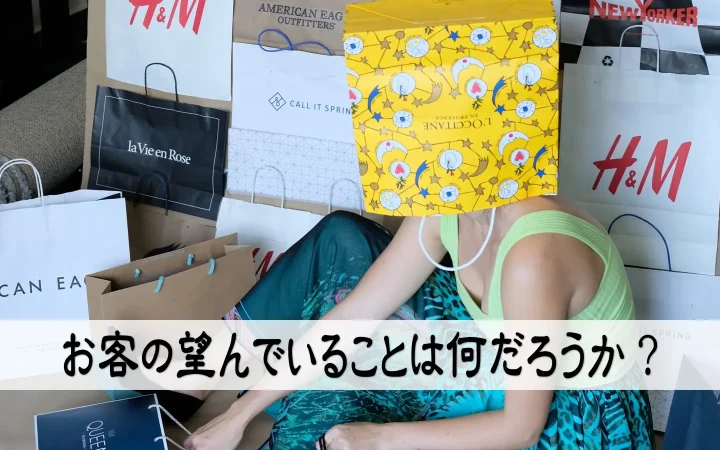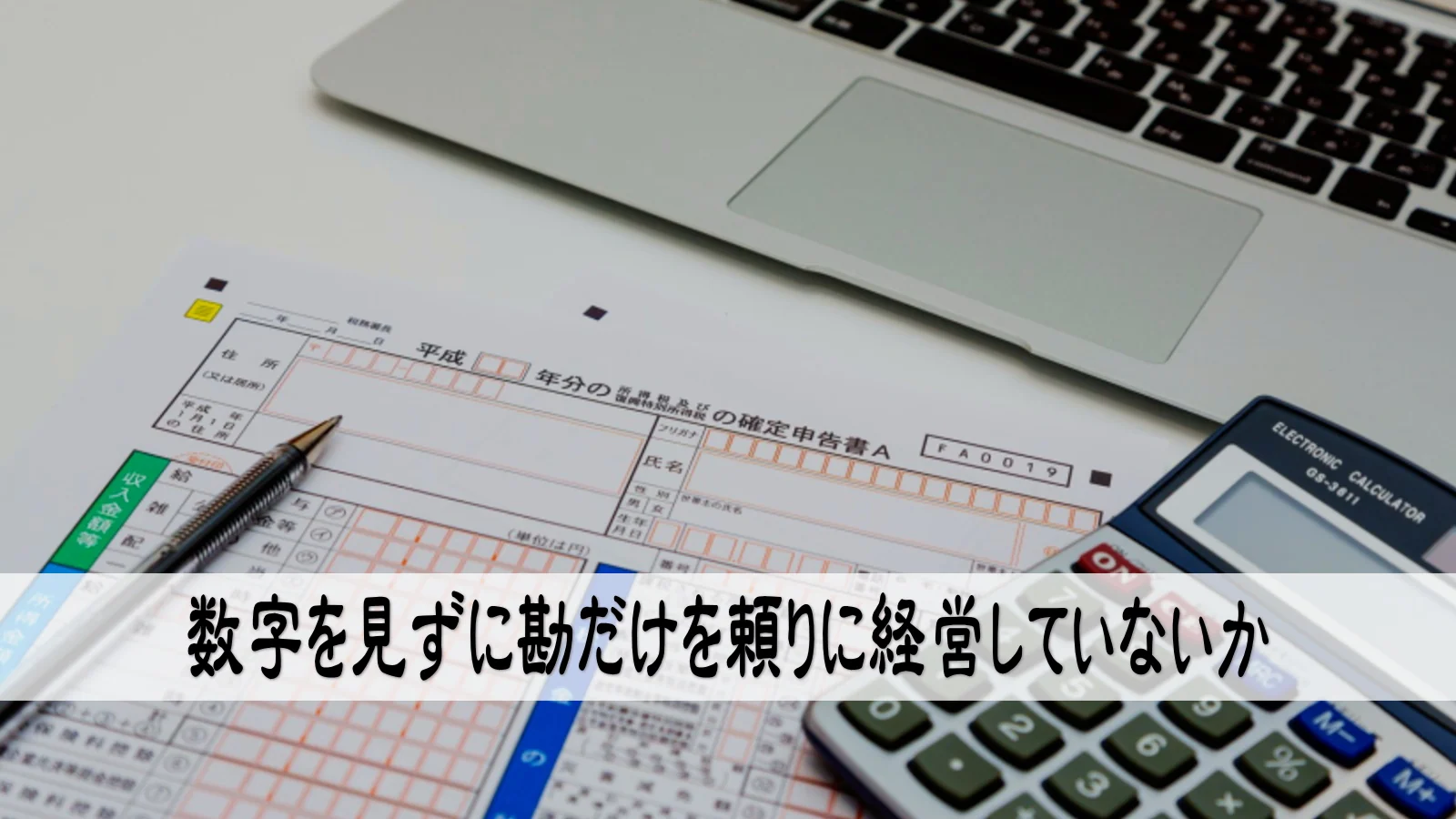
社長が数字に強くならなければ、経営は感覚任せとなり、ビジネスの未来を危うくする。決算書は企業の通信簿であり、財務状況の把握は経営判断の基本だ。「経理は全部女房にまかせてあるから!」では済まされず、少なくとも月に一度は収支やキャッシュフローを確認すべきだ。安売りは利益を圧迫し、適正価格を維持するためには数字を根拠に価格戦略を立てる必要がある。経営判断を勘に頼らず、データを活用することで、会社の未来が明確に見えてくる。(内田游雲)
profile:
内田游雲(うちだ ゆううん)
ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)
さな会社の社長業をしていると、日々の業務に追われて
「とにかく忙しい」
という状況に陥りがちだ。
だが、忙しさと会社の繁盛ぶりは比例しない。
いくら汗を流して働いたところで、売上や利益が伸びるとは限らないからだ。
そこには
「ビジネスは勘ではなく数字で動く」
という鉄則がある。
社長が数字に強くなるべき理由
そもそも経営とは、会社がどれだけのコストをかけ、どれくらいの利益を生み出しているのかを正確につかむことから始まる。
収支のバランスを把握しなければ、どんな優秀な商品やサービスがあっても、いずれは経営難に陥る恐れがある。
数字を見ずに頑張るだけでは、まるで暗闇の中を歩くようなものだ。
行き先がわからず、手探り状態が続くのはリスクが大きい。
会社の決算書は、いわば「企業の通信簿」。
現状の通信簿を見ずに、感覚だけで
「うちは儲かっているはず」
「まだまだ大丈夫」
などと思いこむのは非常に危険だ。
特に中小企業や個人事業などの小さな会社の場合、少しの誤算が経営全体を大きく左右する。
だからこそ社長が自ら数字に目を通し、どの部分で利益を上げ、どこにコストがかかっているかをしっかりつかむ必要がある。
数字がわかるようになると、経営にはさまざまな選択肢が生まれる。
例えば、追加投資を行うかどうかの判断や、新たなサービスを打ち出すタイミングなど、すべて数字に基づいて決めることができる。
勘任せではなく、データを踏まえた説得力のある戦略が打てるのだ。
一方、
「数字に強くなる」
といっても難しい専門用語を覚える必要はない。
基本的な会計用語と計算方法がわかれば、日常の経営判断には十分活かせる。
自分が経営している会社の体力を知り、その上でどのような方向に舵を切るか。
そこを間違えなければ、小さな会社でも大きなチャンスをつかめる可能性はぐんと高くなる。
数字を見て経営するのと、ただ働き続けるのとでは、未来の展望が大きく変わる。
「忙しい=成功」
ではなく、
「数字を理解している社長=賢い経営者」
まずはここを押さえることから、あなたの社長学が始まる。
会社の財務状況を正しく把握する
「経理は全部女房にまかせてあるから!」
という社長の言葉を耳にすることがある。
経理や会計の作業をパートナーやスタッフに任せるのは、時間を有効に使ううえで悪いことではない。
ただ、丸投げ状態で数字をまったく追っていないとしたら、それはかなり危ない。
なぜなら財務状況を把握していない限り、社長は会社の健康状態を確認できないからだ。
まずチェックすべきは、毎月・毎年どれだけの経費がかかり、どれだけの売上があり、最終的にどのくらいの利益が出ているかという基本的な数値。
特に中小企業にとっては、キャッシュフローが命綱といっても過言ではない。
たとえ売上があったとしても、入金と支出のタイミングがズレて資金繰りが苦しくなるケースは少なくない。
自社のキャッシュフローを定期的にチェックしていれば、近い将来の資金不足を予測し、早めに金融機関と相談したり、コスト削減策を打ち出したりできる。
逆に把握していないと、銀行口座の残高が思ったよりも早く底をつき、慌てて高金利の融資に飛びつくはめになる。
これでは経営リスクを高める要因になってしまう。
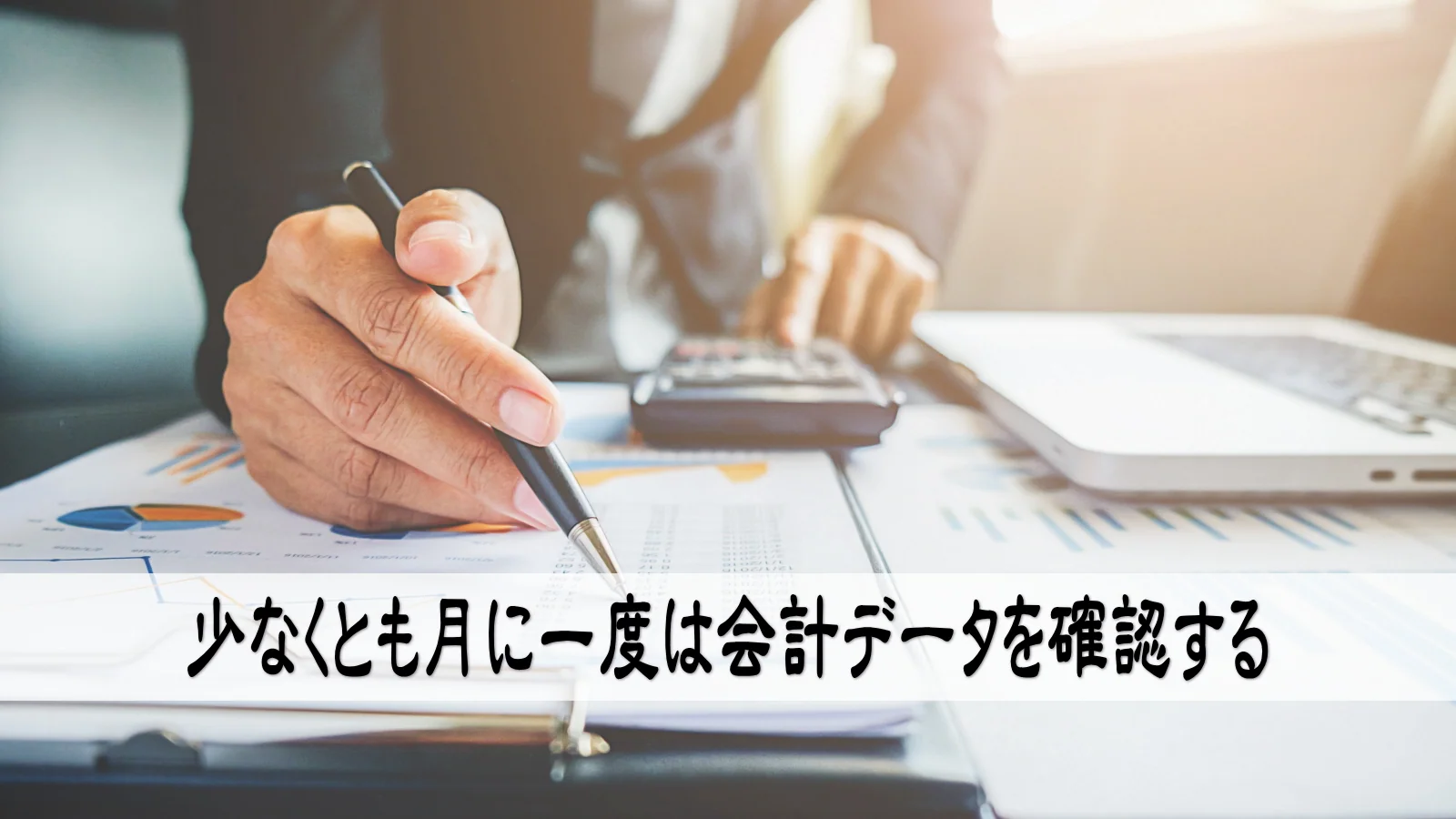
だからこそ、少なくとも月に一度は財務データを確認したい。
エクセルやクラウド会計ソフトなどを用いれば、売上や経費の推移を簡単にグラフ化できる。
グラフ化された数字を見る習慣がつくと、ビジネスの流れが可視化され、次に手を打つべきポイントが見えてくる。
さらに年に一度はすべての年間経費と利益を洗い出し、予実(予定と実績)の差を検証するのも大事なステップ。
ここで会社の全体像がつかめれば、
「あの事業は意外にコストがかかっていた」
「もっと利益が出せる分野がある」
といった発見があるはずだ。
そうした小さな発見が次の価格戦略や新規サービス開発につながる。
「自分は数字が苦手だから」
と避けていては、いつまでも会社のかじ取りが勘頼みになってしまう。
財務状況を正しく把握することこそ、賢く経営するための一丁目一番地なのだ。
安売りが経営を圧迫する理由
中小企業や個人事業でありがちなのが、
「とにかく売上を上げるために安売りする」
という戦略だ。
しかし、安売りに走ると薄利多売になりがちで、利益が残らないばかりか、会社の体力を削ってしまう。
特に
「数字をあまり見ていない社長」
は、安売りによって本当に利益が出ているのかどうかを把握できていないケースが多い。
ビジネスにおいては、商品やサービスを安く提供すれば最初はお客が増えるかもしれない。
しかし一方で、コストが下がらないまま売上単価だけが落ちると、利益率が急激に低下する。
固定費や人件費、原材料費はそのままなのに、単価が低い商品ばかりが動けば、最終的には赤字スレスレで回しているということになりかねない。
また、安売りが常態化すると
「その価格が当たり前」
という認識が顧客の中に根付く。
そうなると、値上げをしようとしたときに大きな抵抗に遭うだけでなく、ビジネスそのものの価値が低く見られてしまうリスクがある。
安い商品には価格相応のイメージがつきまとうため、長期的に見てブランド力を損なうことにもつながる。
さらに、安売り路線には体力勝負の側面がある。
資金力や規模の大きい企業が市場を席巻している場合、小さな会社が同じやり方で戦うのは無謀に等しい。
むしろ生き残るためには、自分の会社の強みを見極め、適正価格で勝負していく道を探るほうが健全だ。
数字を理解していれば、
「ここまで下げると利益が出ない」
「ここまでは値段を保てる」
というラインが明確にわかる。
要するに、安売りで一時的に売上を増やすよりも、しっかり利益を確保することが経営においては重要。
値段をただ下げるのは誰でもできるが、それではビジネスを長く続けるのは難しい。
利益がしっかり残る形で成長を目指すためにも、数字を冷静に見る姿勢が必要になる。
適正価格で販売するための戦略
それでは具体的に、どうやって適正価格を設定し、値上げを行えばいいのか。
まず大前提として、自社の原価と利益率を正確に把握することが欠かせない。
会計ソフトやエクセルを使って、商品やサービスごとにコストと売上を分けて計算するのがおすすめだ。
「どの分野が儲かっていて、どこが赤字を生んでいるのか」
を数値でクリアにするだけでも、価格戦略のヒントが得られる。
もし
「どうやら安すぎる」
と感じたなら、思い切って値上げを検討してみよう。
値上げと聞くと顧客離れが怖いと思うかもしれないが、そこをスムーズに進めるコツは
「追加価値を提供すること」
たとえば、サポート体制を手厚くするとか、新しいオプションを付けるなど、値段分の価値を感じてもらう仕掛けを作るのだ。
相手が納得できる形で値上げを行うと、価格へのクレームも大幅に減る。

値上げの手順としては、事前に顧客へアナウンスし、心の準備をしてもらうことも大切だ。
いきなり上げると
「なんだそれ!」
と反感を買いかねない。
あらかじめ
「○月から価格が変わります」
と告知しておくだけでも、印象はずいぶん違う。
また値上げに対するクレームや不安の声が出ることも想定して、いくつかの対応策をあらかじめ準備しておくと安心だ。
「値上げ=悪」ではない。
むしろ適正価格に近づけることは、小さな会社が健全に成長するためのステップといえる。
安売りから抜け出せずに経営が行き詰まるより、価値に見合った価格でじっくり勝負したほうが長い目で見て有利だ。
社長学のセオリーとしても、安易な価格ダンピングより、正当な利益を得る仕組みづくりが推奨される。
値上げの成功体験は会社にとって大きな糧になる。
そこには
「数字を正しく把握した上で経営戦略を立てる」
という学びが詰まっているからだ。
数字が裏付ける価格で勝負することで、ビジネスは腰の据わった安定感を手に入れる。
利益を最大化する数字の見方
数字を見るときに重要なのは、単に売上高や経費の合計だけを眺めるのではなく、細かい内訳まで踏み込むことだ。
どの商品がどれだけ利益を生んでいるのか、どのサービスに無駄が多いのかを分析すれば、効率よく利益を上げる道が見えてくる。
例えば、人件費や在庫管理費、広告費などを細分化してチェックすると、
「この部門にコストをかけ過ぎているかも」
「このキャンペーンは費用対効果が低い」
という気づきが得られる。
また、どの顧客層が一番リピートしてくれるかを数字で把握すれば、そこへ注力することで売上アップと同時に無駄な出費を減らせる。
ポイントは
「自社のビジネスモデルのどこで粗利が最大化できるか」
を常に意識すること。
売上が高くても、原価率が高ければ利益が残りにくい。
逆に売上がそれほど大きくなくても、原価率を抑えられる仕組みがあれば高い利益を生み出せる。
つまり、経営の数字をしっかりと見極めれば、自分の会社がどの強みを伸ばせば一番効率的に稼げるのかがはっきりする。
さらに、長期的な視点で
「価格戦略」
を考えることも大切だ。
一時的に利益を伸ばそうと無理な拡大やコストカットをしてしまうと、サービスや商品の品質が下がり、かえってリピーターが離れる場合がある。
あくまでも適正なバランスを保ち、継続的に利益を生み出す体制を整えることが、結果的に会社の資産を増やすことにつながる。
数字を活用した利益最大化のプロセスは、決してとっつきにくいものではない。
専門家の知識を借りるのも一つの手だし、会計ソフトの分析ツールを使うだけでも、かなりのヒントを得られる。
大事なのは、社長自身が数字に興味を持ち、分析の結果を会社の具体的なアクションに落とし込むこと。
ここをサボっていては、いつまでたっても勘に頼る経営から脱却できない。
数字を活用して賢く経営する
数字に強くなることは、会社の将来を守るための必須条件といっても過言ではない。
勘や経験も大事だが、それを裏付けるデータがあってこそ説得力のある戦略が立てられる。
小さな会社こそ、きめ細かな数字の管理によって大企業とは違った強みを発揮できるのだ。
数字を踏まえた経営判断は、たとえば
「どのタイミングで新規事業に参入すべきか」
「いつ値上げを行うか」
「新しいサービスのターゲットは誰か」
という問いに対して、明確な答えを導きやすくしてくれる。
目標と現実のギャップを客観的に把握できるので、
「やみくもに動いていたら結果オーライ」
という博打的アプローチから脱却できる。
決算書や月次レポートをチェックし、
「今期はどんな投資をする余裕があるか」
「どんな費用を削減できるか」
「新たな売上チャネルは見込めるか」
といった具体的な検討をすることで、経営の舵取りがぐっと楽になる。
そこでは、会計や値上げ、価格戦略といったキーワードが直接的に結びつき、会社の成長に寄与していく。

数字を嫌って逃げるのではなく、自ら進んで味方につける。
そうすることで、無駄を省きつつ効率的に稼ぐ仕組みを構築し、強い企業体質を築ける。
数字を見る習慣こそが
「勘違いによるミス」
を最小化し、愚かな決断から自分自身を守ってくれるのだ。
小さな会社でも、社長が数字を理解すれば未来への選択肢が広がる。
経営に迷いが少なくなり、ビジョンを実現するための行動に集中できる。
結果として、社長自身もストレスを減らし、より楽しくビジネスに打ち込めるはずだ。
最終的には
「経理は全部女房にまかせてあるから!」
ではなく、
「自分も数字をしっかり把握しているからこそ、女房やスタッフが安心して働ける」
という姿勢が大切になる。
勘任せではなく、データを根拠にした社長学を身につける。
これが、会社の未来を明るいものに変える最良のカギである。